
救急・集中治療 最新ガイドライン 2024-’25
国内外のガイドラインから、救急・集中治療領域110項目に関する最新の情報をまとめました。救急・集中治療領域で働く医師(専門医、当直医、研修医)必携の一冊です。
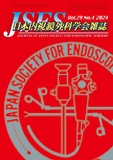
日本内視鏡外科学会雑誌 Vol.29 No.4
2024年 07月号
日本内視鏡外科学会の機関誌。1万5千人を超える学会員から寄せられた投稿論文を、厳正な審査を経て掲載している。2023年より、教育的な症例や独自の手技の工夫、術中合併症への対応症例、困難症例などを動画で紹介することを主眼として、「video articles」欄を新設。 (ISSN 1344-6703)
隔月刊(奇数月)、年6冊、電子版のみ

精神医学 Vol.66 No.7
2024年 07月号
特集 アディクション コロナ禍で変わったこと,変わらないこと
特集 アディクション コロナ禍で変わったこと,変わらないこと 精神医学領域のさまざまなテーマを毎号特集形式で取り上げ、第一線の執筆陣による解説をお届けする。5月号は増大号として領域横断的なテーマや、1つのテーマを幅広い視点から掘り下げる充実の内容。日々の臨床から生まれた「研究と報告」「短報」など原著論文も掲載している。 (ISSN 0488-1281)
月刊、増大号を含む年12冊

総合診療 Vol.34 No.7
2024年 07月号
特集 どうする! 健診異常 これってホントに異常なの? どう説明する?
特集 どうする! 健診異常 これってホントに異常なの? どう説明する? ①独自の切り口が好評の「特集」と、②第一線の執筆者による幅広いテーマの「連載」、そして③お得な年間定期購読が魅力! 実症例に基づく症候からのアプローチを中心に、診断から治療まで、ジェネラルな日常診療に真に役立つ知識とスキルを選りすぐる。「総合診療専門医」関連企画も。 (ISSN 2188-8051)
月刊、年12冊

医学のあゆみ290巻3号
気候変動と医療
気候変動と医療
企画:橋爪 真弘(東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学,Planetary Health Alliance日本ハブ)
・IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)において,気候変動による大きな健康影響がすでに生じており,今後,気温の上昇に伴ってその影響は大幅に増加するという予想が報告された.
・健康影響の回避,軽減に向けて,医療システムの気候変動耐性強化,水・大気・食料システムなど環境的決定要因の健全保持,健康コベネフィット,医療分野のカーボンニュートラル化などの重要性が示されている.
・本特集では,気候変動による健康影響とその対策についてわが国の状況を概観する.人新世の時代における医療従事者の使命と役割を新たな次元で捉え直す機会となることを期待したい.

社会保険旬報 №2934
2024年7月21日
《論評》 『令和初頭における診療報酬改定の変質:「経済学的」アプローチ』尾形裕也
《論評》 『令和初頭における診療報酬改定の変質:「経済学的」アプローチ』尾形裕也
令和に入ってからこれまで3回の診療報酬改定が実施され、直近の令和6年度改定は、6年ぶりの介護報酬等との同時改定であった。診療報酬改定の具体的な内容については、(筆者を含め)すでにその都度さまざまな論評が公表されてきている。令和4年度及び令和6年度改定については、特に医療従事者の賃上げが大きな課題であったことは間違いない。これは岸田内閣における「成長と分配の好循環」という基本的な政策路線の、医療政策における反映であったと考えてよいだろう。
本稿の目的は、そうした具体的な改定内容について論評することではない。私見では、診療報酬改定というわが国の医療政策における重要な政策ツールのあり方について、近年大きな2つの変更(改定プロセスの変質及び診療報酬の基本的性格の変質)が行われてきているが、こうした問題についてはあまり意識的に取り上げられ、論じられることはなかったように思われる。本稿は、そうした診療報酬改定のあり方の変貌について、「経済学的」な視点から考察することを目的としており、その点に論文として多少の新規性が見込めるものと考えている。なお、筆者は現在、中央社会保険医療協議会(中医協)の分科会(入院・外来医療等の調査・評価分科会)会長を務めているが、以下の論考はまったく筆者の私見であり、中医協分科会等の見解ではないことは言うまでもない。

エキスパートナース Vol.40 No.10
2024年8月臨時増刊号
『患者さんの訴えを受け止めて、アセスメントするときに、あなたが知っておくべき解剖生理』
学生時代に習ったけれど、それっきりになりがちな解剖学や生理学。忙しい勤務のかたわらに教科書を引っ張り出さずとも、ヤンデル先生が日常の看護業務に直結する解剖生理学だけを、ピンポイントで解説します。
[ポイント]
・臓器を暗記するのではなく「使える知識」にするための解説
・読み切って集中的にやりなおせる、読みやすい誌面構成
『患者さんの訴えを受け止めて、アセスメントするときに、あなたが知っておくべき解剖生理』
学生時代に習ったけれど、それっきりになりがちな解剖学や生理学。忙しい勤務のかたわらに教科書を引っ張り出さずとも、ヤンデル先生が日常の看護業務に直結する解剖生理学だけを、ピンポイントで解説します。
[ポイント]
・臓器を暗記するのではなく「使える知識」にするための解説
・読み切って集中的にやりなおせる、読みやすい誌面構成

エキスパートナース Vol.40 No.9
2024年8月号
◆腎臓病・透析患者を受け持ったナースが最初に受けたい 腎臓病の授業
◆知ってお得な委員会活動活用術
◆腎臓病・透析患者を受け持ったナースが最初に受けたい 腎臓病の授業
◆知ってお得な委員会活動活用術

理学療法41巻6号
2024年6月号
疾患別・病期別の心臓リハビリテーションにおける理学療法の進め方
疾患別・病期別の心臓リハビリテーションにおける理学療法の進め方 心臓リハビリテーション(以下,心リハ)の効果として、施行後の身体機能や最高酸素摂取量の改善が、その後の生命予後、生活の質の向上、そして再入院抑制などに寄与することが報告されています。
心リハにおける理学療法士の役割として、疾患特性に応じた評価、運動療法の組み立て、リスク管理、患者教育、生活指導が重要となります。また、対象者に対するシームレスなサポートという観点から、150日間の保険期間である急性期・回復期以降の維持期までを視野に入れた継続的な取り組みが重要となることが指摘されています。
そこで本特集は,心リハにおける疾患別・病期別の理学療法の実際について理解を深めていただくことを目的としました。

小児科 Vol.65 No.7
2024年7月号
炎症性腸疾患と類縁疾患
炎症性腸疾患と類縁疾患
小児の発生が増えている「炎症性腸疾患」が今号のテーマ.早期発症ほど診断が難しく,潰瘍性大腸炎とクローン病との鑑別が成人の場合より難しいことがよくあります.また,初発時に非特異的症状でクリニックをおとずれた場合,どの段階で紹介すべきか迷う場合もあると思います.こうしたケースを想定し,病院勤務の先生にとっても,クリニックの先生にとっても役立つ内容にまとめました.

産婦人科の実際 Vol.73 No.7
2024年7月号
産婦人科医が知っておくべき新生児マススクリーニング
産婦人科医が知っておくべき新生児マススクリーニング
臨床に役立つ知識や技術をわかりやすく丁寧に紹介する産婦人科医のための専門誌です。面白くてためになる,産婦人科の“実際”をお届けします。今号のテーマは「新生児マススクリーニング」。検査によって先天性疾患の子どもを発病前に見つけ出して治療し,その子どもの未来を変えることができるかもしれない,夢のある分野です。出生直後から児を診察する産婦人科医にとって,新生児マススクリーニングの十分な理解は欠かせません。本特集では,診療科の枠を飛び越えて各分野のエキスパートの先生がたにご執筆いただきました。

皮膚科の臨床 Vol.66 No. 8
2024年7月号
熱傷
熱傷
今月号の特集は「熱傷」です。自家培養表皮を用いた治療のコツなど,明日からの診療に役立つ情報が満載です。豊富な臨床写真とともにお届けします。エッセイ『憧鉄雑感』などの人気連載も好評掲載中!

整形・災害外科 Vol.67 No.8
2024年7月号
大腿骨近位部骨折における二次性骨折の予防
大腿骨近位部骨折における二次性骨折の予防
2022年春の診療報酬改定で,大腿骨近位部骨折術後患者に対する二次性骨折予防継続管理料が新設されたことで,大腿骨近位部骨折の早期手術や二次性骨折予防に向けた積極的な取り組みへの機運がますます高まっている。本特集を読むことで,大腿骨近位部骨折の二次骨折予防の取り組みの実際や,その課題などについて網羅的に理解できる。

小児神経の画像診断 改訂第2版
―脳脊髄から頭頸部・骨軟部まで―
発生・病理から先天代謝・腫瘍、脊髄・頭頸部・骨軟部の疾患まで日常診療に役立つ様々な疾患を・豊富な画像とあわせて丁寧に解説.
改訂版では疾患概念の変化・遺伝子バリアントの関わりなど新しい知見を取り入れた.
小児神経領域の画像診断に必携の1冊.

妊娠合併子宮頸癌診療マニュアル
本邦の叡智が結集した妊娠合併子宮頸癌診療のバイブル
本邦の叡智が結集した妊娠合併子宮頸癌診療のバイブル.妊娠時に発見される固形腫瘍で最多の子宮頸癌を正しく診断・治療するための1冊.妊娠中の細胞診・コルポスコピー・病理組織診断の留意点,MRI/PET-MRIによる画像診断,妊娠中の広汎子宮頸部摘出術の麻酔・手技の実際・周産期管理をエキスパートが解説.治療法の選択にも実際の治療にも難渋する妊娠合併子宮頸癌診療を習得し,患者と子を救う!編者と著者が何度も話し合いと書き直しを重ね,国内外のエビデンスや症例を徹底的に精査しまとめた精度・濃度の高い内容となっております.

ICUとCCU 2024年7月号
2024年7月号
特集:ヘモグロビンをめぐる最近の話題
特集:ヘモグロビンをめぐる最近の話題

臨牀消化器内科 Vol.39 No.8
2024年8月号
これからの胃癌診療
これからの胃癌診療
最近では喜ばしいことに胃癌は減少傾向で技術認定を取得するための症例数獲得に困るようなことも耳にする.一方で,内視鏡技術・機械の進歩,多数の臨床試験によるエビデンスの構築にもとづき,胃癌の診断・治療戦略は複雑化している.このように変化・進歩しつつある胃癌診療の検診から内視鏡診断・治療,外科手術,薬物療法,ゲノム医療そして人工知能による診療支援の現況を解説し,一冊で胃癌診療のすべてを網羅できるような本特集を企画した.(編集後記より)
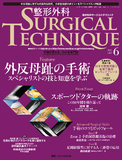
整形外科 SURGICAL TECHNIQUE(サージカルテクニック) 2017年6号
2017年6号
特集: 外反母趾の手術 スペシャリストの技と知恵を学ぶ
特集: 外反母趾の手術 スペシャリストの技と知恵を学ぶ 整形外科領域の「手術」を徹底して取り上げる専門誌『整形外科サージカルテクニック』
教科書には載っていない手術のコツ、ピットフォール、リカバリー法が満載。各手術のエキスパートの技と知恵を凝縮した「手術が見える・わかる専門誌」です。
本誌で取り上げた手術動画を専用WEBページでチェックでき、誌面と動画でしっかり確認できます。
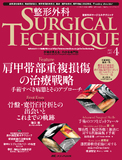
整形外科 SURGICAL TECHNIQUE(サージカルテクニック) 2017年4号
2017年4号
特集: 肩甲帯部重複損傷の治療戦略
特集: 肩甲帯部重複損傷の治療戦略 整形外科領域の「手術」を徹底して取り上げる専門誌『整形外科サージカルテクニック』
教科書には載っていない手術のコツ、ピットフォール、リカバリー法が満載。各手術のエキスパートの技と知恵を凝縮した「手術が見える・わかる専門誌」です。
本誌で取り上げた手術動画を専用WEBページでチェックでき、誌面と動画でしっかり確認できます。
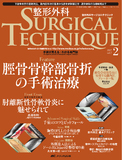
整形外科 SURGICAL TECHNIQUE(サージカルテクニック) 2017年2号
2017年2号
特集: 脛骨骨幹部骨折の手術治療
特集: 脛骨骨幹部骨折の手術治療 整形外科領域の「手術」を徹底して取り上げる専門誌『整形外科サージカルテクニック』
教科書には載っていない手術のコツ、ピットフォール、リカバリー法が満載。各手術のエキスパートの技と知恵を凝縮した「手術が見える・わかる専門誌」です。
本誌で取り上げた手術動画を専用WEBページでチェックでき、誌面と動画でしっかり確認できます。
