
エキスパートナース Vol.40 No.7
2024年6月号
◆診療報酬改定 ナースがおさえるべき8つのこと
◆入退院にかかわるお金の悩みを相談されたときナースとしてどう対応したらよいか
◆診療報酬改定 ナースがおさえるべき8つのこと
◆入退院にかかわるお金の悩みを相談されたときナースとしてどう対応したらよいか

皮膚科の臨床 Vol.66 No.5
2024年5月号
乾癬
乾癬
今月の特集は「乾癬」です。生物学的製剤使用中に乾癬を発症した症例やCOVID-19ワクチン接種後に発症した膿疱性乾癬の症例など,貴重な報告が盛りだくさんです。メトトレキサートによる乾癬治療のまとめも掲載。豊富な写真とともにお届けします!エッセイ『憧鉄雑感』などの人気連載も好評掲載中!

整形・災害外科 Vol.67 No.6
2024年5月号
脆弱性骨盤輪骨折―診断・治療と予後
脆弱性骨盤輪骨折―診断・治療と予後
高齢者の低エネルギー外傷により生じる脆弱性骨盤輪骨折は,超高齢社会の日本においてますます患者数が増えることが予想され,椎体骨折,大腿骨近位部骨折,橈骨遠位端骨折などと同様に適切な治療方針の決定が重要となってくる。本特集では脆弱性骨盤輪骨折の分類,評価,治療方針,予後までを網羅し,最新の知見をわかりやすく解説した。

パーキンソン病治療Controversy
パーキンソン病における議論が分かれる状況をエキスパートが解説した実践書.
世界中で増加傾向のあるパーキンソン病は,超高齢化を迎える本邦では社会的にも大きな問題となっている.専門家だけでは対応が追い付かない状況に加え,多岐に渡る症状に専門の医師でさえ苦慮することが少なくない.そこで本書では,ガイドラインには載っていないが日常診療で比較的よく遭遇し,議論が分かれる状況をピックアップして解説した.エキスパートならどう対応するのか,経験を踏まえた実践的な方法が詰まった1冊だ.

BeyondER Vol.2 No.4 2023
2023年4号
特集1:救急部門:使命と収益のハザマ/特集2:敗血症 GLやエビデンスをふまえた実臨床でのアクションとは
特集1:救急部門:使命と収益のハザマ/特集2:敗血症 GLやエビデンスをふまえた実臨床でのアクションとは

手術 Vol.78 No.6
2024年5月号
後腹膜アプローチを活用した消化器内視鏡外科手術
後腹膜アプローチを活用した消化器内視鏡外科手術
手術がうまくなりたい消化器・一般外科医のための専門誌。マニアックなほど深堀りした特集内容やビジュアルでわかりやすい手術手技の解説を特長とする。今回の特集では,消化器内視鏡外科手術における新たなアプローチとして「後腹膜」に注目した。定型的な腹腔内からのアプローチでは対応困難な症例に対し,後腹膜領域を活用した手術は絶大な効果を発揮し得る。手術の引き出しを増やす,きわめてユニークな内容となっている。

≪最新美容皮膚科学大系 3≫
アンチエイジングとスキンケア
アンチエイジングでは,予防的ケアである運動・栄養・精神・環境について説き,加齢による変化が反映される「見た目」を認識させるとともに,それに対する身体各部位へのケアや美容医療における注射・点滴療法,再生医療について解説する.
スキンケアでは,化粧品や具体的な皮膚ケアに関連する基礎知識とともに,皮膚トラブルへの対処法,毛髪や爪,口腔などのケアについて解説する.

≪15レクチャーシリーズ 理学療法テキスト≫
スポーツ理学療法学
スポーツ理学療法は,スポーツ選手をより早く安全に競技復帰させることを目的とした理学療法である.スポーツ理学療法に必要な評価や徒手療法をはじめ,再発予防に向けた身体操作の修正方法を学習する.また,走行,投球,ジャンプ・着地などのスポーツ動作の特徴を踏まえたうえで,スポーツによる内科的障害や重篤な外傷への対処法,上肢・体幹・下肢の代表的なスポーツ傷害に対する理学療法を学ぶ.

小児看護2024年6月号
多職種とともに子どもと家族をささえるグリーフケア;診断時からの継続した支援
多職種とともに子どもと家族をささえるグリーフケア;診断時からの継続した支援 子どもとの死別はその親やきょうだいに加えて、同じ病棟の友人、治療に携わった医療者にも影響を与える。また、子どもの年齢や病状、過ごした環境や施設によっても状況はさまざまである。それらの悲嘆(グリーフ)に対する支援は死別直後だけではなく、診断時から始まり子どもが退院した後も続いていく。グリーフケアにかかわっている現在の多職種の活動について紹介していく。

杏林大学ICIBD直伝!IBD腸管エコーマニュアル[Web動画付]
IBDの病勢・治療効果モニタリングを行う上で近年有用性が再評価されている腸管超音波検査(腸管エコー)について,前処置・事前準備といった検査の実際や基本操作手順など機器の扱い方を簡潔に解説した入門書.潰瘍性大腸炎やクローン病の代表的な画像・動画を豊富に掲載したほか,評価・スコアリングについても解説.さらに豊富な症例も提示している.IBD腸管エコーを日常臨床に導入するために必携の一冊.

産科麻酔に必要な知識と手技が図とチャートでわかる本
難解な産科麻酔を“見える化”
●複雑な産科麻酔の手技と知識の要点を,コンパクトに,わかりやすく提示。
●視覚的に理解できる図表とチャートを豊富に掲載。
●産科関連疾患の病態,産科麻酔に関連した手技・手順に関する情報を一目で把握できる。
●実臨床で,瞬時に,スムーズに,自信を持って行動できる!
●ポケット麻酔シリーズ第4弾。好評既刊『胸部手術の麻酔』,『神経麻酔と神経集中治療の基礎と実践』,『麻酔における気道管理の手技と知識を知る』もぜひ。
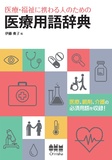
医療・福祉に携わる人のための 医療用語辞典
教育現場、実務の現場でも使える用語集!
医療従事者等が現場で職務を遂行するために必須の専門用語を厳選して掲載した用語集です。
特に近年は、証明書等の作成が医師の多大な負担になっており、医師に代わって文書を作成する医師事務作業補助者の役割が増しています。また、チーム医療という概念から、コ・メディカルスタッフの医療業務に関わる姿勢、位置づけも重要性を増しています。
こうした背景から本書は、実際に医療または福祉の現場で使用される用語を「医療」「調剤」「介護」に分けて解説しました。教育分野での活用はもとより、実務でも役立つ必携の書となっています。
[このような方におすすめ]
コ・メディカルスタッフ
医師事務作業補助者
介護支援専門員,介護福祉士
看護師

≪jmedmook 90≫
jmedmook90 ガイドライン改訂で変わる糖尿病関連腎臓病(DKD)診療
◆ 糖尿病性腎症は生活習慣病のCommon Diseaseの1つとなっており、多くの先生方が遭遇する疾患となっています。また近年、アルブミン尿や蛋白尿を呈さずに腎機能障害となる例が増えたことから、従来の糖尿病性腎症を包括する糖尿病関連腎臓病(DKD)という新しい疾患概念が登場しました。
◆ 本書は、新薬の承認や治療の進歩などの動きをふまえたDKDの最新の診断と治療をはじめ、DKDに関して知っておきたい知識を網羅した一冊です。特に、「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」やKDIGOガイドライン2022など、各種ガイドラインの改訂にあたって変更となった部分の解説に重点をおいています。
◆ 一般医家の先生方はもちろん、初期研修医、内科専攻医、将来腎臓専門医や糖尿病専門医をめざす若手の先生方にも幅広くお役に立つ内容となっています!

産科と婦人科 Vol.91 No.6
2024年6月号
【特集】周産期メンタルヘルスを深掘り!
【特集】周産期メンタルヘルスを深掘り!
母体死亡原因の第1位は自殺であり,うつを含む心の不調への対策が急務となっています.また様々な精神疾患を合併した妊婦を診療する機会も増えており,産婦人科医も精神疾患に関する理解を深める必要があります.
しかし,心の問題は非常にデリケートな領域で,知識がないためかえって状況が悪化することもあり,また連携体制の構築は経験が少ないと大変困難です.
現況や連携に関する知識,妊産婦にみられる精神疾患に関する知識のアップデートにお役立てください!

医学のあゆみ289巻7号
皮膚の悪性腫瘍――研究と診療の進歩
皮膚の悪性腫瘍――研究と診療の進歩
企画:奥山隆平(信州大学医学部皮膚科)
・皮膚疾患の診療で苦慮するのは多くの医師が経験することであるが,特に皮膚がんはQOLを大きく障害することから,診断と治療に慎重を期す必要があろう.
・しかし,皮膚がんといっても有棘細胞癌,基底細胞癌,悪性黒色種,乳房外パジェット病など,異なる性質の有するがんの集合体である.形状や性質はさまざまであり,治療も一様ではない.
・好むと好まざるとにかかわらず,医師は皮膚がんへの対応を求められる状況であり,その機会は今後ますます高まるであろう.

わかる! できる! 歯科麻酔実践ガイド
教育でも臨床でも“即戦力”!
歯科麻酔のエッセンスを凝縮した実践ガイド
●教育現場では実習書として,臨床現場に出た後は若手向けの手引き書として,長くお使いいただける歯科麻酔の実践ガイドブック.全身管理,局所麻酔,鎮静法,全身麻酔,救急蘇生,ペインクリニックまで,歯科麻酔全般にわたって“本当に必要なポイントだけ”を厳選して,知識・技術をコンパクトにまとめました.
●身につけておきたいテクニックは,一連の写真を用いてビジュアルに解説.重要事項は「ワンポイントアドバイス」,補足知識は「一口メモ」,コラム的な内容は気軽に読める「コーヒーブレイク」としてまとめるなど,わかりやすさを重視して編集しました.

臨床栄養 144巻5号
健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023
健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023
●厚生労働省は健康日本21(第三次)における身体活動・運動分野の取り組みを推進するため,「健康づくりのための身体活動基準2013」を改訂して「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」を公表しました.このガイドは,健康づくりにかかわる専門家,政策立案者,職場管理者,健康・医療・介護分野における身体活動を支援する関係者を対象者に,健康づくりのための身体活動や運動に関する推奨事項や参考情報をまとめたものです.
●栄養・食生活の分野には「日本人の食事摂取基準」があり,これには数種類の指標が存在しますが,「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」では定量的な推奨値と全体の方向性を示す定性的な推奨事項の2種類のみであり,食事摂取基準とは異なる特徴をもっています.
●今回の特集を通じて,健康づくりのための身体活動や運動に関する推奨値や推奨事項に対する理解を深め,栄養・食生活の指導に活用するだけでなく,ご自身の健康づくりにも役立てていただきたいです.

J. of Clinical Rehabilitation 33巻5号
神経難病患者の在宅生活におけるリハビリテーション医療の役割
神経難病患者の在宅生活におけるリハビリテーション医療の役割
●神経難病疾患は進行性であり,他疾患と同様,適切な時期にリハビリテーション治療・教育指導を行いながらの在宅生活が主体となってきている.そのため,生活期リハビリテーションの充実は早急に検討すべき課題である.
●本特集では、在宅の神経難病患者のリハビリテーション治療の実態とその課題に関する調査結果が示された後、4人のトップランナーが具体的な現場での状況や指導内容について解説.リハビリテーション治療の標準化から在宅での支援、就労の課題についても取り上げた.
●さらにはリハビリテーション医療だけでなく,臨床心理士や運動教室の役割についても触れ,さまざまな視点から在宅での神経難病患者のサポートについて考えた一冊である.

Medical Technology 52巻5号
知っておきたい 体型による影響と解剖学的バリエーション―心電図・超音波検査編
知っておきたい 体型による影響と解剖学的バリエーション―心電図・超音波検査編
●日常の生理機能検査を行うなかで,右胸心や馬蹄腎など,さまざまな解剖学的バリエーションに遭遇することがある.こうしたバリエーションに出合った時に通常とは異なると認識できることは,正しい検査結果を出すうえで重要である.
●本特集では,心電図検査と超音波検査を行う際に比較的遭遇する可能性が高い解剖学的バリエーションや体型による影響について,検査を行う際のコツや画像の特徴,注意点などをご紹介いただく.

訪問看護と介護 Vol.29 No.3
2024年 05月号
特集 心不全増悪の生活要因を解消する68のアイデア
特集 心不全増悪の生活要因を解消する68のアイデア 「在宅」の時代、暮らしを支える訪問看護師に、情報とパワーをお届けします。
ケアに関わる情報はもちろん、「気になるあの人/あのステーションがやっていること」を皆さんに代わって編集室が取材。明日の仕事に活かせるヒントが見つかります。 (ISSN 1341-7045)
隔月刊(奇数月)、年6冊
