
呼吸器ジャーナル Vol.72 No.2
2024年 05月号
特集 気管支拡張症 温故知新 注目され始めた一大カテゴリー
特集 気管支拡張症 温故知新 注目され始めた一大カテゴリー 2017年1号から「呼吸と循環」誌を全面的にリニューアルし、呼吸器領域に特化した季刊誌として刊行。呼吸器専門医、および専門医を目指す呼吸器科医・研修医を対象に、臨床の現場で必要とされている情報を的確に提供する。特集では、呼吸器領域の重要なテーマを最新の知見に基づいてプラクティカルに解説。 (ISSN 2432-3268)
年4冊刊(2月・5月・8月・11月)

生体の科学 Vol.75 No.2
2024年 04月号
特集 生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開
特集 生命現象を駆動する生体内金属動態の理解と展開 生命科学・生物科学領域における最先端の研究を、毎号特集形式により紹介。神経科学はもとより分子生物学・酵素科学・栄養科学にいたる領域も含め、注目されるトピックテーマの最新情報を提供する。 (ISSN 0370-9531)
隔月刊(偶数月)、増大号を含む年6冊

歯科診療報酬点数表 令和6年6月版
歯科診療報酬に的をしぼって収録したライトな一冊
歯科窓口での算定に必要な情報を網羅した実践的な内容
歯科固有の施設基準について通知も抄録
左欄には点数表および該当する保険医療材料の点数を、右欄には項目ごとに算定上の要点・留意事項を掲載しています。視覚的に捉えやすい構成で、算定に必要な情報はひと目で確認できます。
巻頭には区分番号レベルまで収載した詳細目次を掲載して利便性の向上を図るとともに、点数表部分右欄の区分番号、見出しや加算対象の記載等をゴシック体にすることでメリハリのある表記を目指して編集しています。
他にも巻末に点数表の項目から区分番号を検索できる「50音索引」を収載しており、初めて算定にかかわる方にもわかりやすく、入門書としても最適の一冊です。

医科診療報酬点数表 令和6年6月版
本文2色による構成、改定による変更箇所には下線を表示し使いやすさ抜群の『医科点数表 実務書』の決定版
本文2色、変更箇所への下線表示等の工夫により理解しやすく、初めて点数表を使う方やまだ点数表を使い慣れていない方にもおすすめの一冊です。
独自の編集によるフルカラーの早見表や別紙様式も掲載
左欄に点数表、右欄には算定上の留意事項等を掲載するといった、長年親しまれてきた伝統的な構成に加えて、注に規定する加算の名称や、算定単位・回数などの書体を強調するなど、見やすさ・使いやすさにこだわった工夫をしています。
巻頭にはオリジナル編集によるフルカラーのわかりやすい早見表、区分番号レベルまで収載した詳細目次、巻末には区分番号・掲載ページを素早く検索できる50音索引を掲載しています。
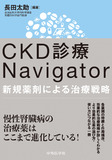
CKD診療Navigator 新規薬剤による治療戦略
CKD治療における1番効果的な薬の選び方・使い方につながる1冊
CKD治療は薬剤の選び方・使い方で効果が変わります.SGLT2阻害薬や,HIF-PH阻害薬など,腎保護作用やeGFRの改善がエビデンスとして出始め,CKD診療は大きな変革を迎えました.
各薬剤の特徴と作用機序,効果的な治療戦略が詳しくわかるだけでなく,CKDの治療効果だけでなく,貧血改善や心血管ベネフィットなど患者の合併症ごとに望ましい効果のある薬を選ぶことで,最適な治療戦略をできるようになる必読書.

感染対策の手引き
院内感染対策のために,何が必要か,どう行動すればいいのかパッとわかる!
感染対策を知り尽くしたプロからのアドバイス,各種のガイドラインや指針をまとめ,最適で正確な対応をすべて網羅できる必携書.ネット検索をするよりも素早く信頼できる答えがわかる,ポケットの相棒.ひと目でわかるフローチャートや表をふんだんに使い,時間が無い現場でもパッと開いてサッと必要な情報が確認できる便利なマニュアル.施設内のすべてのスタッフと患者の安心・安全のための1冊!

賛否両論の病気 こころとからだのはざまで
誰も教えてくれなかった“contested diseases”
「検査所見に異常はみられない」「自覚症状が非常に強い」「心理的な要因の関与が考えられる」といった疾患を目の前にしたとき,一方では「精神疾患であることの証明はない」「患者は身体疾患と考えている」「身体疾患を示唆する診断名も用意されている」とも考えられる余地があるのかもしれない.このように身体疾患と精神疾患のはざまでは,医学界の中で疾患単位やコンセンサスが十分に形成されていないものも少なくない.これらの曖昧な概念に対する解決策は未来に委ねられるが,その議論の萌芽は,我々が賛否両論の病気(contested diseases)を認識することから始まるのかもしれない.
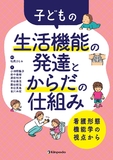
子どもの生活機能の発達とからだの仕組み
看護形態機能学の視点から
看護学校では,「看護師は生活を援助する係」という観点から,小児の生理学・解剖学に関しても教えるようになり,また「形態機能学」を取り入れて教育する学校が増えてきています.しかし成書には,小児の形態機能学の書籍はない状態です.そこで本書は小児に特化した看護の観点から,患者さんの日常生活行動を切り口とし解説しました.またイラストもあるため理解の助けとなる一冊.

社会保険旬報 №2924
2024年4月11日
《論評》 『韓国の公共病院の現状と新型コロナウイルスへの対応』伊関友伸(城西大学経営学部マネジメント総合学科教授)
《論評》 『韓国の公共病院の現状と新型コロナウイルスへの対応』伊関友伸(城西大学経営学部マネジメント総合学科教授)
本論文は2023年6月28日・29日の2日間、韓国国立中央医療院の招待を受け、ソウル市内で講演を行った1ことを契機として、韓国公共病院の現状に関し調査した内容について報告を行うものである。韓国にも各地域に公共病院と呼ばれる地方医療院や赤十字病院が設置されている。新型コロナウイルスの蔓延により地方医療院はコロナ専担病院となり、感染患者を多数受け入れてきた。新型コロナの蔓延が落ち着きを見せたものの、地方医療院は医師不足、患者流出による収益減などによる経営悪化に苦しんでいる。さらに、2024年2月には、尹錫悦(ユン・ソンニョル)政権による大学医学部定員の大幅拡大方針に反発した専攻医が大量に退職。公共病院は韓国医療の混乱に対して、非常診療体制を取るなど新たな対応を求められている。
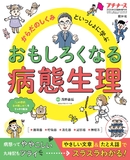
プチナース Vol.33 No.6
2024年5月臨時増刊号
■直感的に伝わる“たとえ話”と図表・イラスト・写真で、病気のしくみを無理なく理解できます。
■低学年では解剖生理の理解を助け、高学年では実習で出合う疾患の疑問を解消できます。
■各章の最後には「国家試験に挑戦」のコーナーも!(解説つき)
■直感的に伝わる“たとえ話”と図表・イラスト・写真で、病気のしくみを無理なく理解できます。
■低学年では解剖生理の理解を助け、高学年では実習で出合う疾患の疑問を解消できます。
■各章の最後には「国家試験に挑戦」のコーナーも!(解説つき)

ペイン・リハビリテーションを生きて
セラピストと患者の共著による、疼痛(CRPS type1)に対する4年半のリハビリテーションの記録。
患者の経験、セラピストの学術、両者の対話という3つの視点を重ね合わせたドキュメントであると同時に、ペイン・リハビリテーションの実践に有効な知識と具体的な技術、そして治療を患者とセラピストとの二人三脚という協業作業に高めていくための感性にまで及ぶ提言を行う実践書。

リハビリテーションのための発達科学入門
身体をもった心の発達
小児リハビリテーションに長く取り組んできた著者が、子どもたちの発達支援に欠かすことのできない発達科学の知識を、科学的な知見、自らの臨床経験をもとに紹介。
これからの小児リハビリテーションを背負っていくすべての若いセラピストたちに向けて書かれた、発達科学の入門書。

≪産業保健と看護2024年春季増刊≫
産業保健現場のデータ活用術
【データのまとめや報告、発表が楽しくなる!】労働者の健康に関するさまざまなデータを分析し、日々の産業保健活動や健康経営につなげたい産業保健スタッフのためのガイドです。読みながら段階を踏んでデータを分析し、報告・発表できる形にして実践活動へ活かすところまで持っていけるようになりましょう。

≪眼科ケア2024年春季増刊≫
めめ子と学ぶ まるごと点眼薬
【点眼薬が基礎から楽しく学べる!】点眼薬の種類と特徴に加えて、点眼指導にも焦点を当て、患者さんごとに正しい指導方法を習得できる構成。主要な眼疾患の概要とともに処方すべき点眼薬の紹介もしているので、まんがやイラストを交えながら楽しく学べ「明日からの仕事のお供」になる一冊である。

プチナース Vol.33 No.5
2024年5月号
◆キホンが身につく! 看護師ななえるの実習記録テンプレート
◆最新国試からわかった! 第114回看護師国試勉強アドバイス
◆キホンが身につく! 看護師ななえるの実習記録テンプレート
◆最新国試からわかった! 第114回看護師国試勉強アドバイス

腎臓病診療がわかる現場の教科書
診るロジックと薬の使い方
●腎臓病の診断・検査・治療、薬の使い方が丸ごとわかる!
●CKD診療ガイドライン2023を踏まえた新しい内容!
●研修医、薬剤師、非専門医にやさしい解説!
日本で慢性腎臓病(CKD)患者は1,000万人以上、透析患者は34万人以上と、腎臓病で苦しむ患者は多数います。薬剤性腎障害や脱水で急性腎臓病(AKI)に陥るケースも少なくありません。そんな腎臓病のメカニズム、診断・治療、薬の使い方を丸ごと1冊にまとめたのが本書です。研修医などの初学者を意識して書かれた解説はわかりやすく、具体的です。この1冊があれば基礎体力は十分身につき、いろんな場面に役立つはず。研修医、薬剤師問わず、臨床現場で使える内容が詰まっています!

だれでもわかる臨床試験のモニタリング
JSCTRモニタリング担当者テキストブック
●研究者主導臨床試験におけるモニタリング担当者の知識・スキルの研鑽のために
リソースが限られている研究者主導臨床試験は、研究者、CRC、治験事務局員、医局秘書など、日頃からモニタリングを専任としてない人がモニタリング業務を担当することも珍しくありません。
本書は、臨床研究法・人指針に基づき実施するモニタリングについて、その概要や臨床試験に関連する基本的知識の取得方法をはじめ、文書モニタリングや症例モニタリングの実践方法など、基礎から応用まで網羅的に解説。日本臨床試験学会が実施するモニタリング担当者検定試験・認定モニタリング担当者試験を受験する方、モニタリング担当者を目指す方、臨床試験、モニタリングに関する知見を広げてスキルアップしたい方におすすめです。

ICUが変わる!PICS診療実践マニュアル
入院時から退院後まで、予後改善のためのスタンダード
PICSを最小限にするための実践書.基礎知識から評価・予防・介入の具体的な進め方までを,根拠とともにクリアに解説.ICU退室後フォローの事例や,ダウンロードして使える各種資材データなどの特典も必見!
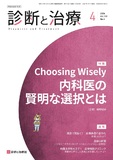
診断と治療 Vol.112 No.4
2024年4月号
【特集】Choosing Wisely 内科医の賢明な選択とは
【特集】Choosing Wisely 内科医の賢明な選択とは
患者との対話のなかで最適な診断と治療を選択するために,「Choosing Wisely」という国際的なキャンペーンが注目を集めています.Choosing Wiselyの概念から,内科領域における重要なトピック,臨床現場での問いについて紹介します.

救急医学2024年4月号
鎮痛・鎮静 今昔未来物語
鎮痛・鎮静 今昔未来物語 安全で安心な鎮痛・鎮静のために、単なるノウハウだけでは満足できないあなたに。救急・集中治療とは切っても切り離せない鎮痛・鎮静だからこそ、今では“当たり前”な薬剤やガイドライン、スケールの導入・作成の歴史も、新たな鎮痛薬・鎮静薬の可能性も、貪欲に学ぼう。
