
臨床栄養 144巻3号
フレイル最新動向2024 ―多彩に広がるアプローチに学ぶ
フレイル最新動向2024 ―多彩に広がるアプローチに学ぶ
●フレイルは,2014年に日本老年医学会から提唱された概念です.加齢や慢性疾患,老年症候群が積み重なることにより脆弱となり,ストレスや疾患により要介護や死亡などに陥りやすい状態である一方,適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像とされます.
●フレイルの要素は,身体的フレイル,精神・心理的フレイル,社会的フレイルが広く知られていますが,オーラルフレイル,ウロフレイル,アイフレイル,スキンフレイルといった概念も近年,提唱されています.フレイルをきたしやすい疾患や老年症候群が個人に同時に複数存在し,互いに悪影響を及ぼし,要介護や死亡のリスクの増加させていることが明らかになってきています.
●本特集では,このように近年広がりをみせているフレイルの多面性に着目し,老年期に起こりやすいさまざまな機能の低下や症状からフレイルをとらえるアプローチについて,各領域の専門家よりご解説をいただきます.

Medical Technology 52巻3号
臨床医は一般検査に何を求めているのか
臨床医は一般検査に何を求めているのか
●一般検査の実施にあたり,対象患者の検査目的や依頼内容の把握の困難さや検体情報などが少なさから,検査結果の解釈に自信をもない読者もいるだろう.しかし,臨床検査技師が検査を実施するには,検査依頼から結果報告までの過程を可能な限り理解していないと,思わぬピットフォールに落ちることや,安易なlaboratory diagnosis に陥ることがある.
●そこで,本特集では,臨床医の先生方が何を求めて臨床検査技師に検査を依頼するのか,また,結果報告に何を求めているのかなどについて詳細にご解説いただいた.
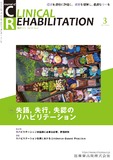
J. of Clinical Rehabilitation 33巻3号
失語,失行,失認のリハビリテーション
失語,失行,失認のリハビリテーション
●失語,失行,失認はその症状の多様性から,誤って認知症と一括りにされるなど,適切な評価が行われないままリハビリテーションが実施される可能性が懸念されている.
●本特集では,失語,発語失行,半側空間無視に加え,見逃されがちな失行や視覚性失認,稀な症状である聴覚性失認に焦点を当て,臨床で遭遇しやすいこれらの症状を評価し理解することを目的とし,確立されていない症状に対するリハビリテーションの方法や将来的な展望も含め,最新の情報を提供している.
エキスパートナース年間購読2024年度(増刊号あり)
エキスパートナース年間購読2024年度(増刊号なし)

≪腫瘍病理鑑別診断アトラス≫
卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌 改訂・改題第2版
卵巣腫瘍・卵管癌・腹膜癌取扱い規約第2版やWHO分類第5版が発行されたほか,初版刊行から12年が経ち,分類や疾患概念が変わった.今改訂では,新たに卵管腫瘍や腹膜腫瘍の項を設け,また代表的な変更点のひとつである漿液性腫瘍については頁を割き,精選された写真とともに丁寧に解説した.婦人科腫瘍の診断に欠くことができない肉眼観察や適切なサンプリング,分子標的治療についても項目を設け,その基本を解説した.

医学のあゆみ288巻11号
アナフィラキシー up to date 2024
アナフィラキシー up to date 2024
企画:海老澤元宏(国立病院機構相模原病院臨床研究センター)
・日本アレルギー学会(JSA)では,2022年8月末に世界アレルギー機構(WAO)の「アナフィラキシーガイダンス2020」をベースに,アナフィラキシーガイドラインを8年ぶりに改訂した.
・診断基準が3つから2つに簡素化され,アレルゲンの曝露や曝露が疑われる場合には,単独の呼吸器症状(気管支攣縮・喉頭症状)でもアドレナリンの筋肉注射を躊躇わないでより積極的に行っていく方針が示された.
・本特集では,原因別のアナフィラキシーの詳細,場面別(学校,周術期)などに関して第一人者の先生方に執筆していただく.アナフィラキシーのへの対応が改善することを期待したい.

検査と技術 Vol.52 No.4
2024年 04月号
若手臨床検査技師、臨床検査技師をめざす学生を対象に、臨床検査技師の「知りたい!」にこたえる総合誌。日常検査業務のスキルアップや知識の向上に役立つ情報が満載! 国試問題、解答と解説を年1回掲載。年10冊の通常号に加え増大号を年2回(3月・9月)発行。 (ISSN 0301-2611)
月刊、増大号2冊(3月・9月)を含む年12冊

≪循環器診療コンプリートシリーズ≫
循環器診療コンプリート 心不全
心・腎・脳の視点でとらえる循環器疾患
若手循環器内科医に必須な心不全診療の知識を網羅し,図表や画像を多用しビジュアルに解説.
腎臓内科専門医・脳卒中専門医のアドバイスを全項目で載せ,心・腎・脳連関を意識した新しいタイプの循環器診療テキストシリーズ.
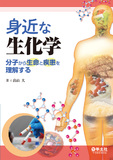
身近な生化学 分子から生命と疾患を理解する
生化学反応を日常生活にある身近な生命現象と関連づけながら,実際の講義で話しているような語り口で解説することにより,学生さんが親しみをもって学べるテキストとなっています.好評書『身近な生物学』の姉妹編.

理学療法37巻10号
2020年10月号
高齢者における転倒予防─この10年の成果と次の10年に向けての課題
高齢者における転倒予防─この10年の成果と次の10年に向けての課題 高齢者は転倒を経験すると,転倒後に外傷がなくても転倒への恐怖感を示し,歩行障害を来すという転倒後症候群に陥る危険性があることが指摘されています.
高齢者のQOLの維持・向上や,自分らしい生活に向けての自己効力感の高揚を促進していくために理学療法士にとっての重要な課題は,トレーニングを通して「転倒予防」に努めていくこと,また,歩行動作中のつまずきやバランスのくずれに対する“とっさの一歩” の能力の評価であると考えられます.
本特集では,本誌の2010年(27巻5号)の特集「高齢者の転倒予防─この10年の成果」からの10年間における成果や,これからの10年における理学療法としての課題を浮き彫りにすることにより,「転倒予防」を目的とした,より安全で効果的な理学療法のあり方について述べていただきます

理学療法37巻12号
2020年12月号
膝関節周辺の外傷・障害に対する理学療法診断の進め方
膝関節周辺の外傷・障害に対する理学療法診断の進め方 37巻8号の特集「股関節周辺の外傷・障害に対する理学療法診断の進め方」に続き,「膝関節周辺の外傷・障害」を取り上げます.
「理学療法診断」の定義は,「疾病の同定ではなく,さまざまな要因によって生じた障害を同定し,その関連因子や予後を予測し,理学療法の効果を判断するプロセス」と提起されており,具体的には,『理学療法士の知識と経験に加え,理学療法検査の標準値 と 対象者の測定値 を比較することにより,科学的根拠に基づいた治療の選択 と 運動機能障害の予後予測 を可能にするため,臨床推論の妥当性を可視化する』とされています.
この考え方は理学療法のさらなる発展を視野に入れる時,多くの考え方が提示され深化されていくべきものと考えられ,本特集ではこの「理学療法診断」の定義に沿って述べていただきます.
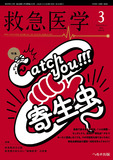
救急医学2024年3月号
Catch you!!! 寄生虫
Catch you!!! 寄生虫 救急で遭遇するこんな症候、あんな病態、もしかして原因は“寄生虫”かも!? めったに遭遇しなくても、救急医としてあらゆる可能性を捨てないために、寄生虫の基礎的知識と、寄生虫感染症の特徴や診断のポイントを学んでみよう!

循環器の検査 基本とドリル
心電図・心エコーなどの適切な検査の選び方・考え方
循環器診療で使う「検査」の選び方や組合せ方,結果の考え方を「循環器薬ドリル」のメンバーが研修医向けに解説!基本を学ぶ「基礎編」とドリル形式で症例を考える「実践編」の2部構成で,しっかり実力が身につく.

物理・化学・数理から理解する生命科学
基本トピックを7章にわけ,法則・理論を重視したミニマムな解説と,具体的な問いから構成.厳選された45の問いと生物学的な意義を「少しずつ学ぶ」ことを通して,可能性や広がりに気づく教養としての生命科学

精神看護学 第3版 学生-患者のストーリーで綴る実習展開
14の事例で精神看護学実習のリアリティが体験できる好評書の第3版.
●精神看護学の基本的な考え方や技術・技法について復習でき,実習の流れに沿って,「看護計画のための情報の整理」,「看護計画の実際」,「カンファレンスと実習の振り返り」という順序で構成.「看護計画の実際」では,各精神障害別に,それぞれの障害に関する基本的な知識と看護のポイントを押さえつつ,学生と患者とのストーリー展開を通して,看護計画の立案が学べるよう工夫した.
●実践に即した形で必要なときに必要な知識が取り出せるよう「コラム」,「復習のための資料」として随所に記載.
●第3版では,診断基準をDSM-5-TRに準拠するとともに,一部法制度を見直した.

臨床検査技師 臨地実習ハンドブック
すべての検査領域を一冊で学習できる
臨地実習のカリキュラム改訂に対応した新テキスト!
●臨地実習において実施/見学することが定められた検査業務の流れ・手技を解説.検査の実際をイメージできるイラスト・画像や,患者に対する声かけの具体例など,実践に活かせるポイントが充実.
●検査手技だけではなく,実習関連書類の書き方から接遇,感染対策,情報管理まで,臨地実習で必要となる知識をこの一冊で完全マスター.
●臨地実習指導者の着眼点・アドバイスなど,検査現場の声も多数掲載.

PT・OT・STのためのリハビリテーション薬剤 生活機能をより高める“リハ薬剤”
さあ,今日から“リハ薬剤”をはじめよう!
●疾患やサルコペニアによる生活機能低下のリスクが高い高齢患者が増加する昨今,多職種でリハ環境の薬剤管理に取り組めば,リハビリテーションのアウトカムを向上し,生活機能をより高めることが可能になる.
●本書は医師や薬剤師に限らず,PT・OT・STをはじめとするスタッフが知っておくべき薬剤管理について,各領域の第一人者が解説.多職種でリハビリテーションにおける薬剤管理に取り組むきっかけとして最適な一冊.

麻酔Vol.73No.2
2024年2月号
投稿論文掲載号

形成外科 Vol.67 No.2
2024年2月号
動静脈奇形症例集(3)―躯幹―
