
臨床皮膚科 Vol.77 No.13
2023年 12月号
さまざまな症例や治療成績が全国から寄せられる原著系皮膚科専門誌。写真はオールカラーで、『臨床皮膚科』ならではのクオリティ。注目の論文は「今月の症例」として、編集委員が読み処のアドバイスを添えて掲載する。増刊号「最近のトピックス」は、知識を毎年アップデートできる定番シリーズ。 (ISSN 0021-4973)
月刊、増刊号を含む年13冊

教育担当者・指導者のための“気づき”で導く 新人・後輩・部下 看護教育リフレクション入門
【自ら気づく新人が育つ】教育は一方通行に指導するのではなく、学ぶ側が自ら気づくことで学習効果・育成スピードが格段に向上する。自ら気づき学びを概念化するリフレクションを新人育成に活用するための方策を、具体例を紹介しながら解説する。
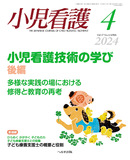
小児看護2024年4月号
小児看護技術の学び 後編;多様な実践の場における修得と教育の再考
小児看護技術の学び 後編;多様な実践の場における修得と教育の再考 小児看護技術は小児期の解剖生理学的特徴から、緻密さと正確性、丁寧さと臨機応変な対応が求められ、まさに小児看護の専門性が発揮される。実践や教育経験が豊富な執筆者による、小児医療の多様な場における看護技術に必要な要素、専門性の高い技術の修得と実践、これに対応する教育方法を再考していこう。

エキスパートナース Vol.40 No.4
2024年4月号
◆観察、アセスメント、対応をランクアップさせる ナースの教科書
◆新人ナースと先輩ナース 新生活の不安を聞いてみよう!
◆観察、アセスメント、対応をランクアップさせる ナースの教科書
◆新人ナースと先輩ナース 新生活の不安を聞いてみよう!

新訂第2版 写真でわかる高齢者ケア アドバンス
高齢者の心と体を理解し、フレイルを予防し生活の営みを支える
これからの高齢者ケアに欠かせないフレイル対策、エンド・オブ・ライフケアの視点を盛り込み、大幅改訂!!
東京都健康長寿医療センターが長年培ってきた高齢者看護のノウハウをまとめた『新訂版 写真でわかる高齢者ケア アドバンス』を、高齢者が健康で生き生きと過ごすために欠かせない要素である、フレイル予防を新たな柱として加筆改訂しました。
新訂第2版では新たな章として「高齢者におけるフレイル対策の重要性」を追加しました。また、高齢者が、最期までその人らしい人生を過ごせるように支援する重要性を鑑みて「エンド・オブ・ライフケア」についてや、清潔のケアでは「スキン-テア(皮膚裂傷)の予防とケア」についても加筆しました。
超高齢化の進行と看護職の役割拡大のもと、ナース、看護学生、高齢者看護・介護に関わる方々など幅広い方々にご活用いただきたい一冊です。

臨牀消化器内科 Vol.39 No.4
2024年4月号
内科医が知っておくべき,肛門疾患の基礎知識
内科医が知っておくべき,肛門疾患の基礎知識
今回の特集は,非常に読みやすい論文となっている.「検査・診かた」では問診のポイントや診察の実際が詳しく述べられており,肛門診察の際の手引きとなる.「痔核」「痔瘻」「裂肛」の3大肛門疾患や「直腸脱」では疾患の写真がふんだんに盛り込まれており,すぐに診断に役立つ内容である.

ICUとCCU 2024年3月号
2024年3月号
特集:集中治療と漢方薬
特集:集中治療と漢方薬

理学療法37巻7号
2020年7月号
足の障害と靴
足の障害と靴 靴の提供は,患者個々への靴の処方を踏まえて,チームによって行われます.
そこでまず医師の立場から,足の機能・構造障害に対する靴の処方について,理学療法士に対する要望も含めて述べていただきます.
より良い靴を患者に提供するにあたって靴の形状と足圧分布特性を把握し参考にすることは有意義であり,その最新知見,足の機能・構造障害と靴との関連性,さらに医師との連携のあり方についても述べていただき,加えて,それぞれの足の障害を理学療法の視点からどのような点を補正した靴を提供すべきかについて,症例を交えて述べていただきます.

小児科 Vol.65 No.3
2024年3月号
日常診療に活かせる専門外来の知識とテクニックⅡ
日常診療に活かせる専門外来の知識とテクニックⅡ
専門外来に紹介できれば助かるが、なかなかそうもいかない――前号に引き続き、日常診療にありふれたそんな症状・病態がテーマ。「食物アレルギー」「アトピー性皮膚炎・スキンケア」「神経発達症(発達障害)」「睡眠関連疾患」「摂食障害」「母乳・乳児期の栄養」という、小児科医であれば避けては通れない話題について、一般小児科医が診療に活かせる知識と技術をまとめました。

皮膚科の臨床 Vol.66 No. 3
2024年3月号
悪性黒色腫
悪性黒色腫
「悪性黒色腫」の症例報告をまとめました。鑑別診断や治療の選択など,明日からの診療に役立つ情報が満載です。臨床講義欄では悪性黒色腫の“治療”にフォーカスをあてて解説。この10年で大きく変化した悪性黒色腫の治療を一挙に学べます。エッセイ『憧鉄雑感』などの人気連載も好評掲載中!

整形・災害外科 Vol.67 No.3
2024年3月号
変形性足関節症の最新の治療
変形性足関節症の最新の治療
超高齢社会,人生100年時代を迎え,変形性足関節症の患者数が増加しており,有効な治療法がこれまで以上に求められている。本特集ではエキスパートが病態・病態から保存治療,各種骨切り術,鏡視下手術,人工足関節全置換術を詳細に解説しており,変形性足関節症の最新治療の全容を把握できる。

産婦人科の実際 Vol.73 No.3
2024年3月号
帝王切開のネガティブ・インパクトの克服と新たな取り組み
帝王切開のネガティブ・インパクトの克服と新たな取り組み
臨床に役立つ知識や技術をわかりやすく丁寧に紹介する産婦人科医のための専門誌です。面白くてためになる,産婦人科の“実際”をお届けします。今回は帝王切開におけるネガティブ・インパクトについて深堀りします。妊産婦の高齢化や生殖補助医療による妊娠の増加に伴い,帝王切開分娩率も増加の一途をたどっています。今回の特集では,帝王切開がもたらす「負の側面」に向き合い,それらを克服する様々な取り組みに焦点を当てました。

訪問看護、介護・福祉施設のケアに携わる人へ
コミュニティケア Vol.26 No.4
2024年4月号
特集:服薬自己管理に向けた支援
特集:服薬自己管理に向けた支援
現在、在宅療養者の多くが慢性疾患を有し、薬物療法によってその症状をコントロールしています。
しかし、薬剤数が多かったり、服用のタイミングが複雑だったり、認知機能が低下していたりとさまざまな理由から服薬自己管理に困難が生じるケースも少なくありません。
服薬管理が適切になされていないと薬剤の効果が十分に発揮されず、症状のコントロールも難しくなるため、在宅においては、利用者自身の服薬に対する意欲を高めながら、利用者の状態や生活に合わせた支援が求められます。
そこで本特集では、服薬状況の情報収集や服薬行動の改善に向けた支援のポイントを整理した上で、服薬支援を行うに当たってのよくある困り事を薬剤師がQ&A形式で解説。報告では、飲み忘れ等により有害事象が発現していた利用者に対して、お薬カレンダーなどのツールの使用や多職種による連携など、生活に合わせた支援を行い、改善に導いた事例を紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
なお、本特集では薬剤の名称を一般名、もしくは「商品名(一般名)」で表記しています。

眼科 Vol.66 No.3
2024年3月号
屈折異常の進行評価
屈折異常の進行評価
トピックス、診療のコツ、症例報告、どこから読んでもすぐ診療に役立つ、気軽な眼科の専門誌です。今月の特集は「屈折異常の進行評価」と題し、近年患者数の増大がみられる近視ならびに円錐角膜の進行とその評価に関する最新の話題を、4本の論文に凝縮して掲載しました。高齢者の斜視ならびにステロイドと骨粗鬆症の関係を取り上げた2本の綜説や連載、4本の投稿論文ともども、ご一読のうえ明日からの診療にご用立てください。

小児科診療 Vol.87 No.4
2024年4月号
【特集】新生児・乳児の感覚に寄り添う
【特集】新生児・乳児の感覚に寄り添う
小さい子どもほど五感(視覚,聴覚,味覚,嗅覚,触覚)を使って生きており,接する際は五感を用いた寄り添いが求められます.
感覚器官の発達やその養い方,適切な環境調整を解説したかつてない特集です.

理学療法37巻9号
2020年9月号
慢性腎臓病患者に対する運動療法の関わり
慢性腎臓病患者に対する運動療法の関わり 慢性腎臓病患者にとって透析療法に移行することは言うまでもなく,できる限り避けたいことです.
現在,わが国の慢性腎臓病の患者数は約1,300万人とされており,確実に増える一方で,進行して腎不全となり透析療法に移行する患者も確実に増加しており,その人数は35万人を超えているものと予想されます.
そのような状況の中で,慢性腎臓病患者に対する運動療法に効果が認められることが指摘されており,透析患者の減少に向けて理学療法士に対する期待が高まっています.
そこで本特集では,慢性腎臓病患者が透析療法に移行する人数を減少させるために,運動療法(理学療法)が寄与するための取り組みについて,その具体的な内容と効果について述べていただきます.
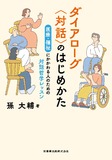
ダイアローグ〈対話〉のはじめかた 医療・福祉にかかわる人のための対話哲学レッスン
日々の「現場」が圧倒的に面白くなる!
“家庭医そんそん”による〈対話〉哲学講義.
●ソクラテス,ブーバー,レヴィナスらによる対話をめぐる哲学を手がかりに,
〈対話〉をはじめるための基本と原則(大事にすること)をやさしく解説.
●医療・福祉・ケアの現場で活躍する対人支援職のための,
臨床場面や地域において〈対話〉を実践したセッションを収載.
・さまざまな訴えのある患者とのダイアローグ
・慢性的な痛みと不安を抱える患者とのダイアローグ
・アドバンス・ケア・プランニングに関するダイアローグ
・多職種カンファレンスでのダイアローグ
・近しい人の死による悲嘆をめぐるダイアローグ
・障害をもつ男性の困りごとをめぐるダイアローグ
・介護をテーマにしたダイアローグ
●不確実性の耐性,エンパシー,リフレクティング,健康生成論……
対話実践を深めるため健康・医療と対話をめぐるキーワードをコラムで解説した.

最新言語聴覚学講座 臨床歯科医学・口腔外科学
言語聴覚士を目指す学生のための新しいテキスト
●口腔・顎・顔面の形態,機能を理解しながら,各部位の疾患についても学べるように多くの図表を収載.
●口腔に現れる症状・障害の特徴を理解し,歯科医学的な治療の概念,対応法を学ぶことができ,言語聴覚士の臨床にも有用な1冊.
●令和5年4月版の「言語聴覚士国家試験出題基準」に準拠し,中枢性疾患による口腔機能障害,加齢による口腔機能障害の章も設けた.

≪15レクチャーシリーズリハビリテーションテキスト≫
リハビリテーション統計学 第2版
疾病を患った人の集団を治療や研究の対象とする医学では,経験や実験を繰り返すことで生まれた経験則を,数値で表す工夫をしてデータにし,統計学の力を借りて効果があった/なかったという客観的な判断を行う.こうして活用される統計学について,リハビリテーションの臨床に役立つ基本的な内容で構成されているため,必要なときに独学の資料としても多用できるテキストである.第2版では,記載を見直すとともに,全4色とした.

教育心理学
教職課程「教育心理学」のテキスト.文科省から示されたコアカリキュラムに準拠し,「発達」と「学習」に関する内容で構成されている.イラストや図表類を多用し,初学者にも学びやすいよう配慮した.また各章に事例も配し,学びの方法にも工夫されている.教職採用試験の出題領域にも考慮して試験対策用のテキストとしても利用できるテキストの決定版.
