
VisualDermatology Vol.23 No.3(2024年3月号)
【特集】新しい検査,慣れない検査Q&A
【特集】新しい検査,慣れない検査Q&A 新しい検査や慣れない検査など30項目選定し4つのPartに分けて解説。他の診療科で行っている検査では、診療科視点からの解説もあり、新たな気づきも!検査の実施法や、難しい解釈についての解釈方法などをQ&A形式で紹介。

医師×看護師×臨床心理士 緩和医療コミュニケーション相談室
正解なき問題を「構造化」.医療コミュニケーションの新しいバイブル.
厳しい状況の患者や患者家族と関わる医療者は,日々「正解なき難題」にぶつかる.本書では実際に寄せられた難題に,緩和ケア専門医,がん看護専門看護師,臨床心理士が会話を重ね,迷いながら答えにたどり着こうとする様子が書かれている.彼らの思考の流れや問題をとらえる視点が,一つとして同じものはない難題を解決するヒントとなるだろう.特に,対人関係を「構造化」した図は必見.コミュニケーションの新バイブルだ.

パワーアップ問題演習微生物学 第2版
変化する感染症の最新情報を掲載。これからの国家試験に役に立つ内容。

画像診断 Vol.44 No.3(2024年3月号)
【特集】押さえておきたい呼吸器疾患の画像診断 Case-based review
【特集】押さえておきたい呼吸器疾患の画像診断 Case-based review 人気のCase-based review胸部特集! 比較的特徴的な所見を呈する疾患や,稀だが知っておくと鑑別を挙げる際に役立つような疾患を,クイズ形式で楽しみながら学習し,呼吸器疾患に対する知識をブラッシュアップできる特集とした.

女性の更年期症状緩和のための認知行動療法 第1版
更年期障害に悩む女性たちのための認知行動療法テキスト。

脊椎手術パーフェクト
術前準備から展開、除圧、固定、閉創まで術中写真・シェーマでわかる基本手技
手術の手順を1ステップずつ,画像とシェーマで簡潔に解説.切除や固定のコツから使用する器具まで具体的にわかり,合併症対策もおさえられる.基本的な手技習得にはもちろん,執刀前夜の確認にこの1冊

理学療法38巻9号
2021年9月号
成長期のスポーツ障害と理学療法
成長期のスポーツ障害と理学療法 「成長期の身体は,大人の身体とは異なる」と言われるように,成長期の骨には成長軟骨板(骨端線)が存在し,特に男子では13歳頃,女子では11歳頃に成長軟骨の代謝が活発になり急速に成長します.
軟骨や筋,靱帯などにも成長期特有の生体力学的特性があるため,成長期のスポーツ活動による過剰な運動負荷(オーバーユース)は障害発生を招き,それに伴う不適切な処置や治療はさらに障害を助長するなどのリスクとなりえます.
そのため成長期のスポーツ障害に対する理学療法を進めるには,成長期の運動器および心身機能の特性,スポーツ障害の特徴について正確に理解することが必要です.また,特有の傾向性もある点も踏まえ治療に取り組むとともに,スポーツ障害発生予防も含めたスポーツ指導に取り組むことが重要です.
本特集は,成長期のスポーツ外傷と障害のうち「障害」に絞った内容を述べていただきます.

OCP・OFP・OBPで学ぶ 作業療法実践の教科書
面接,観察,スクリーニングなどの場面で,「なぜそのような思考に至ったのか?」「どのようなときにこの会話を行うのか?」など,作業を中心とした実践において大切なことや考慮すべきことについて,事例を紹介しながら丁寧に解説。これらをお手本にアプローチすれば,クライエントに対して効果的な実践が身につきます。
ベストセラー『5W1Hでわかりやすく学べる 作業療法理論の教科書』,『5つの臨床推論で整理して学ぶ 作業療法リーズニングの教科書』に続く第3弾登場!

理学療法38巻7号
2021年7月号
エビデンスを参照した呼吸器疾患に対する理学療法の考え方と進め方
エビデンスを参照した呼吸器疾患に対する理学療法の考え方と進め方 好評の「エビデンスシリーズ」の呼吸器疾患編です.
「根拠に基づく実践(Evidence-based Practice:EBP)」
における臨床判断要素としては,臨床研究の実証結果である狭義のエビデンスだけでなく,臨床家の臨床能力,施設の設備や環境,そして,患者の意向や価値観を含めた広義のエビデンスを踏まえた,患者中心型の総合的な判断が重要となります.
したがって,担当患者に関連したエビデンスがヒットしても,患者の意向や価値観との折り合いがつかなかったり,施設の設備・環境の関係で対応できない等,場合によっては他の選択肢を選択するという臨床判断を行うことも必要となります.
本特集では,エビデンス “を” 判断の中心に置くのではなく,エビデンス “も” 含めた患者中心型の包括的な臨床判断を行う考え方を「エビデンスを参照した」と記すこととし,このような実際的なEBPの概念と行動様式に基づいた呼吸器疾患患者に対する理学療法の考え方と進め方に焦点を当てるべく述べていただきます.

がん看護 Vol.29 No.2
2024年3-4月号
がん医療における「家族ケアの課題」 ~困難事例への解決アプローチ~
がん医療における「家族ケアの課題」 ~困難事例への解決アプローチ~ がんの医学・医療的知識から経過別看護、症状別看護、検査・治療・処置別看護、さらにはサイコオンコロジーにいたるまで、臨床に役立つさまざまなテーマをわかりやすく解説し、最新の知見を提供。施設内看護から訪問・在宅・地域看護まで、看護の場と領域に特有な問題をとりあげ、検討・解説。告知、インフォームド・コンセント、生命倫理、グリーフワークといった、患者・家族をとりまく今日の諸課題についても積極的にアプローチし、問題の深化をはかるべく、意見交流の場としての役割も果たす。

理学療法38巻8号
2021年8月号
骨粗鬆症予防と理学療法の取り組み
骨粗鬆症予防と理学療法の取り組み 「2015年度版骨粗鬆症ガイドライン」によると,国内の患者数は,女性980万人,男性300万人と報告されています.
加齢に伴い骨が脆くなり骨粗鬆症が進行することが知られており,特に女性では閉経後に骨粗鬆症が急速に進行し,腰椎や大腿骨の骨折をもたらし,それが腰痛や寝たきりを招き,廃用症候群につながります.
そのため骨粗鬆症に対して予防的観点から取り組むことが重要な課題となっています.
そこで本特集では,骨粗鬆症に対し理学療法がどのような取り組みを展開することができるかを述べていただきます.

Medical Practice 2024年3月号
頭痛~頭痛難民を救う,頭痛診療の実践
頭痛~頭痛難民を救う,頭痛診療の実践 特集テーマは「頭痛~頭痛難民を救う,頭痛診療の実践」.記事として,[座談会]頭痛難民はどのようにしたら減るのか:実地医家の役割とは,[総説]頭痛の診療ガイドライン2021を紐解く,[セミナー]あらためて学ぶ片頭痛の病態,[治療]薬剤の使用過多による頭痛への対処.連載では,[One Point Advice]障害者の健康管理,[今月の話題]「肥満症診療ガイドライン2022」改訂のポイント,[知っておきたいこと ア・ラ・カルト] 他を掲載.

臨床スポーツ医学 2024年3月号
一流を目指す小児アスリート~スポーツ医学ができること
一流を目指す小児アスリート~スポーツ医学ができること 「一流を目指す小児アスリート~スポーツ医学ができること」特集として,一流のサッカー選手になるためには何が必要か?/一流の野球選手になるためには何が必要か?/一流の水泳選手になるためには何が必要か?/筋肉づくりとたんぱく質補給/柔軟性獲得の基本/心肺機能を鍛える/メンタルを鍛える/一流の女性アスリートになるために などを取り上げる.また,[スポーツ関連脳振盪-アムステルダム声明-]他を掲載.

心エコー 2024年3月号
シン・エコーで冠動脈疾患に迫る
シン・エコーで冠動脈疾患に迫る 特集は「シン・エコーで冠動脈疾患に迫る」.動脈硬化リスクに迫る─subclinical atherosclerosisを診断する/胸痛患者のトリアージとしての心エコーを活用する/診断に負荷心エコーを活用する/INOCAに心エコーで迫る/心筋viabilityに迫る/陳旧性心筋梗塞患者の予後を予測する/心筋梗塞に合併する虚血性僧帽弁逆流に迫る/あえて問う,冠動脈血流速を計測する意義/preclinical heart failureに心エコーで迫る 他を取り上げる.連載として症例問題[Web動画連動企画],[COLUMN]を掲載.

≪腫瘍病理鑑別診断アトラス≫
脳腫瘍 第2版
分類の理解の上で欠かせない遺伝学的な異常をわかりやすく解説しつつ,診断現場の実際を考慮して形態学的診断にも重きを置き,精選された写真とともにその組織像を解説した.さらには分子分類に即した免疫染色の応用や腫瘍と鑑別を要する非腫瘍性病変も取り上げている.そして,臨床との連携を目指して,治療に伴う病理所見の解釈と報告書の記載法についても解説した.難しいとされる脳腫瘍の病理診断もまずはこの1冊から.
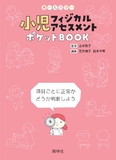
小児フィジカルアセスメント ポケットBOOK
子どもの身体は発達段階にあり、成人と同じようにみることはできません。また、子どもは言葉で伝える以外に、その表情や顔色、姿勢、息づかいなど、多様な表現で自らの状態を訴えます。本書は、このような子どもの特徴を理解して、看護師が“何か変だな?”と思ったときに、「なにを」「どのように」みて、それが「正常」また「異常」なのかを判断できる1冊です。
●豊富なイラスト・写真・図でポイントがわかりやすく、新人・若手・学生さんも使いやすい
●「見て、聴いて、触れて」、ポケットで持ち歩き、いつでも全身のフィジカルアセスメントができる

改正感染症法ガイドブック
改正のポイント&施行日別条文
令和4年12月の感染症法等の改正の全体像がわかるガイドブック。条文は施行日別に改正箇所を明記し、委任事項がある箇所は対応する政省令の条文も収載。重要な改正には「改正のポイント」として改正要旨を明記した。新型コロナ5類移行にも対応した感染症対策業務の必携書。

会話分析でわかる看護師のコミュニケーション技術
ナースに必要なコミュニケーションについて、会話のレベルや意図、言語的・非言語的な技術を40以上紹介。事例を用いた技術の活用法も解説する。その中で様々な会話分析でコミュニケーション技術のエビデンスを「見える化」した。新人からベテランまで役立つ技術書。

ICUとCCU 2024年2月号
2024年2月号
特集:重症患者の腸内細菌叢は制御できるか?:腸管内治療の現況と展望
特集:重症患者の腸内細菌叢は制御できるか?:腸管内治療の現況と展望

小児泌尿器科学
日本小児泌尿器科学会の編集となる本書では,充実した基礎領域とともに,小児泌尿器科の最前線で活躍する精鋭執筆陣が重要疾患や必須事項についての最新知見を惜しみなく紹介.
忙しい日々の診療業務のなかで役立つよう,どの項目からでも読み進められる独立した頁構成とした.さらに図表やカラー写真を適宜用いて「見やすく,読みやすく」表現することを心がけた.
小児泌尿器科のみならず,多くの近接領域で手許に置いて役立てたい1冊.
