
日本看護協会機関誌『看護』年間購読(2024年1月号~12月号:臨時増刊号含まない計12冊)
日本看護協会出版会発行の日本看護協会機関誌『看護』の2024年の年間購読(電子版・12冊発行予定)になります。日本看護協会機関誌『看護』の内容は下記をご覧ください。 日本看護協会の重点政策・重点事業、全国各地の優れた看護実践等を紹介 特徴: 〇日本看護協会の重点政策・重点事業をわかりやすく解説 〇あらゆる場所で活躍する優れた看護の取り組みを紹介 〇経営・管理・教育にヒントが得られる事例報告

日本看護協会機関誌『看護』年間購読(2024年1月号~12月号:臨時増刊号含む計15冊)
日本看護協会出版会発行の日本看護協会機関誌『看護』の2024年の年間購読(電子版・12冊発行予定)になります。日本看護協会機関誌『看護』の内容は下記をご覧ください。 日本看護協会の重点政策・重点事業、全国各地の優れた看護実践等を紹介 特徴: 〇日本看護協会の重点政策・重点事業をわかりやすく解説 〇あらゆる場所で活躍する優れた看護の取り組みを紹介 〇経営・管理・教育にヒントが得られる事例報告

臨牀消化器内科 Vol.39 No.2
2024年2月号
IBD 診療-ますます増えた薬剤の選択とさらなる進化の展望
IBD 診療-ますます増えた薬剤の選択とさらなる進化の展望
これまでも,本誌においてIBD の特集を編纂し,そのときそのときのIBD診療の最新の一断面についてお伝えしようとしてきました.ただ,毎年のように新たな薬剤が登場し,ちょっと前にupdate した知識は今はもう少し古くなっているというような状況には,編集するものとして少し困っておりました.しかしながら,新たな薬剤による新たな治療ということも当然大切ですので,本号でもしっかり解説していただいています.

消化器クリニカルアップデート Vol.5 No.2
2023年(Vol.5 No.2)
特集: 潰瘍性大腸炎について基本から最新まで改めて学んでみよう
特集: 潰瘍性大腸炎について基本から最新まで改めて学んでみよう

ICUとCCU 2024年1月号
2024年1月号
特集:経皮的補助循環 update
特集:経皮的補助循環 update

『産婦人科の実際』年間購読(2024年)
毎号充実した内容を提供し、産婦人科医の「あれ知りたい!」「これ知りたい!」「いま知りたい!」にお応えします。明日からの診療に即役立つプラクティカルな知識が満載です。

『小児科』年間購読(2024年)
日常診療のコツから、今知るべき他科の知識・時事的課題まで。査読をクリアした信頼度の高い論文が、豊富な話題をやさしく解説。診療の質を上げる、子どもを診るすべての医師のための専門誌です。

『眼科』年間購読(2024年)
学界のトピックス、診療のコツ、臨床現場からの症例報告。どこから紐解いても日々の診療に役立つ内容満載の、気軽に読める眼科専門誌です。

『皮膚科の臨床』年間購読(2024年)
全国の臨床現場から寄せられる症例報告を毎月20編以上掲載。研究発表、論文執筆に必読と好評。さまざまな症例経験があなたの診断の目を確実に養います。エッセイ憧鉄雑感、臨時増刊号も人気。

看護 Vol.76 No.1
2024年1月号
特集1 期待高まるクリティカルケア認定看護師
特集1 期待高まるクリティカルケア認定看護師
国は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」等により災害や新興感染症に対する医療提供体制の強化をはかっています。
新興感染症等への速やかかつ着実な対応体制の整備には、感染管理および急性期を担う看護の質の確保が必要であるため、日本看護協会では、感染管理認定看護師・クリティカルケア認定看護師の養成等を行っています。
本特集では、健康危機管理体制の強化など、今、クリティカルケア認定看護師が求められる背景を説明した上で、日本看護協会の養成推進事業や教育の実際を解説。さらに、コロナ禍におけるクリティカルケア認定看護師の取り組みを振り返り、その必要性を確認します。
特集2:
回復期・慢性期看護実態調査 解説
急性期入院医療における在院日数の短縮などにより、回復期・慢性期入院医療において医療依存度の高い患者が増加し、看護職員の負担が増加しています。
そのため回復期・慢性期の各病棟では、患者像の特徴に応じた看護ケアを提供するために診療報酬上の配置基準を上回る配置がなされています。
本特集では、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料、療養病棟入院基本料、緩和ケア病棟入院料を算定する病棟の概要や、患者像、患者の状態とアウトカム、提供している看護とその提供体制、早朝・夜間の看護提供体制に関する調査結果を解説します。

周産期医療にかかわる人のための
やさしくわかる胎盤のみかた・調べかた 第2版
胎児・新生児や妊産婦に異常があった時,分娩経過に異常があった時,母児に影響を与えずに原因を調べられるのが胎盤ですが,その診断は難しい!本書は,大きく見やすい症例写真,検査・診断のフローチャート,病理診断の申込例など豊富な図表とともに,検査の目的や手順,用語解説などの基本的事項,単胎・多胎胎盤の調べかた,臨床で問題となる病態など,日常診療で役立つ内容をわかりやすく解説.
また,APWGCSによる用語統一やCOVID-19などのトピックスも盛り込み,FAQも充実させた,胎盤病理診断の第一人者による集大成です.

診断と治療 Vol.112 No.1
2024年1月号
【特集】フレッシャーズからベテランまで いま知りたい心房細動治療
【特集】フレッシャーズからベテランまで いま知りたい心房細動治療
プライマリ・ケアの医師はまず何を行うべきなのか,どのような患者を専門医に紹介すればよいか,新しい診断法や治療までわかりやすく解説しました.
リニューアル第1号です!ぜひお手にとってご覧ください.
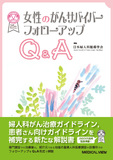
女性のがんサバイバー フォローアップQ&A
⻑期生存率の改善に伴い増加しつつある婦人科がんサバイバーのフォローアップを解説する一般産婦人科医/かかりつけ医向けのテキスト。
見開き2ページ単位のQ&A形式で患者から頻繁に聞かれるような質問を中心に,写真や図表を多用して外来で患者説明に利用できる形式の回答例を紹介し,またフォローアップで直面することが多い二次がん・再発,心理的・社会的問題への対応等も記載。医師向けの解説も別に掲載しており,一般の産婦人科医・内科医が実際に患者のフォローアップに当たることができる内容となっている。
日本婦人科腫瘍学会の創立25周年を記念する公式テキスト。

シンプル理学療法学・作業療法学シリーズ
リハビリテーション英語テキスト
リハビリテーションのリアルな現場を描き出した英文を用いることで、医療専門職を目指す学生が「英語を学習する」のではなく、「英語で学習する」ことを実現した教科書。英文と問題で構成された第I部と、医学用語の基礎を習得することを目的とした第II部の2部構成。特に、難解な医学用語については、構造と語形成のルールをわかりやすく説明した画期的な構成により効率的に学習できるようになっている。

看護学テキストNiCE
災害看護 改訂第4版
看護の専門知識を統合して実践につなげる
災害看護の知識や考え方を学ぶ「総論」と,専門領域別に災害看護の実際を学ぶ「各論」の2部構成が好評のテキスト.今改訂では,全面的なアップデートに加え,災害現場における看護活動を紹介するコラム「現場発」では最新の事例を多数追加し,「各論」に「在宅看護と災害」の項を新設.「感染看護と災害」の項では新型コロナウイルス感染症対策を追加し,巻末付録に「災害看護関連用語集」を新たに収載.いっそう充実した.

≪看護学テキストNiCE≫
看護学テキストNiCE
ヘルスアセスメント[Web動画付] 改訂第2版
臨床実践能力を高める
「ヘルスアセスメント」は看護過程の要であり、個々に合った看護ケアに欠かせない。人体の構造・機能といった基礎的知識や診査手順・方法を、図表や写真を多数用いて根拠をもって解説。フィジカルアセスメントの実演動画を新たにWeb掲載とし、再生・視聴が容易に。心理社会的側面のアセスメントについても、必要な中範囲理論を含めてわかりやすく解説し、看護実践能力を高める一冊。

周産期医学53巻7号
周産期医療のヒヤリ・ハット―医療事故・医療紛争を防ぐために 新生児編
周産期医療のヒヤリ・ハット―医療事故・医療紛争を防ぐために 新生児編

手術 Vol.78 No.1
2024年1月号
外科医の働き方改革を考える
外科医の働き方改革を考える
わが国の医療は長年,医師の献身性により支えられてきた。しかし,2024年4月からは医師に対しても,労働時間短縮および健康確保のための措置を講じることが義務化される。5年の猶予期間が遂に終了するわけで,皆,対応に必死であるが,なかでも“過酷”とされる外科領域での働き方改革実現は本当に可能なのか……。先進施設の担当者や先駆者が,5つのテーマからその実態を語る“いま読みたい”待望の総特集である。

小児内科55巻7号
腎・泌尿器疾患―血尿から移植まで
腎・泌尿器疾患―血尿から移植まで

レジオネラ感染症総まとめ
新設入浴施設での集団発生が報告されているレジオネラ症について、感染経路、疫学から画像診断、検査、治療まで総まとめ!
◆全国の専門家がレジオネラ感染症の最新情報を解説。症例を挙げ、非定型的な症状なども紹介しながらレジオネラ感染症診療を詳述しました。
◆画像診断では、レジオネラの特徴と肺の解剖構造、肺炎の画像パターンを踏まえ、レジオネラ肺炎の鑑別に有用な所見を提示。
◆検査では、塗抹検査、培養検査、尿中抗原検査など各検査の特徴、手順、ピットフォールをまとめています。
◆治療では、各治療薬の使い方を解説。2剤併用療法の有効性や、腎機能障害時の用量調節が不要なラスクフロキサシンについても言及しています。
◆医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師をはじめ、保健所関係者、衛生管理者、安全衛生推進者などにもお勧めです。
