
臨床婦人科産科 Vol.78 No.1
2024年 01月号(合併増大号)
今月の臨床 産婦人科医のための感染症最新レクチャー
今月の臨床 産婦人科医のための感染症最新レクチャー 産婦人科臨床のハイレベルな知識を、わかりやすく読みやすい誌面でお届けする。最新ガイドラインの要点やいま注目の診断・治療手技など、すぐに診療に役立つ知識をまとめた特集、もう一歩踏み込んで詳しく解説する「FOCUS」欄、そのほか連載も充実。書籍規模の増刊号は、必携の臨床マニュアルとして好評。 (ISSN 0386-9865)
月刊、合併増大号と増刊号を含む年12冊

脳神経外科 Vol.52 No.1
2024年 01月号
特集 脳神経圧迫症候群のすべて 診断・治療・手術のポイント〔特別付録Web動画〕
特集 脳神経圧迫症候群のすべて 診断・治療・手術のポイント〔特別付録Web動画〕 「教科書の先を行く実践的知識」を切り口に、脳血管障害、脳腫瘍、脊椎脊髄、頭部外傷、機能外科、小児神経外科など各サブスペシャリティはもちろん、その枠を超えた横断テーマも広く特集します。専門分野・教育に精通し第一線で活躍する脳神経外科医を企画者・執筆者に迎え、診断・治療に不可欠な知識、手術に生きる手技や解剖を、豊富な図と写真を用いて解説します。さらに、脳神経外科領域の最新の話題を取り上げる「総説」、手術のトレンドを修得できる「解剖を中心とした脳神経手術手技」も掲載します。 (ISSN 0301-2603)
隔月刊(奇数月)、年6冊

公衆衛生 Vol.88 No.2
2024年 02月号
特集 健康日本21の20年間の評価と次期プラン
特集 健康日本21の20年間の評価と次期プラン 地域住民の健康の保持・向上のための活動に携わっている公衆衛生関係者のための専門誌。毎月の特集テーマでは、さまざまな角度から今日的課題をとりあげ、現場に役立つ情報と活動指針について解説する。 (ISSN 0368-5187)
月刊、年12冊
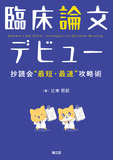
臨床論文デビュー 抄読会“最短・最速”攻略術
臨床論文を初めて読む・読むのに苦手意識のある研修医や医学生などのための“最短・最速”攻略本.論文の読み方・臨床論文を初めて読む機会である「抄読会」の乗り切り方を,ポイントをおさえてサクッと解説.抄読会での論文の選び方や自動翻訳による時短術など,コスパ/タイパよく論文を読むための実践的な知識も身に付けられる!臨床論文へのハードルを下げ,自信をもって抄読会に臨むことができる一冊.

『臨床放射線』年間購読(2024年)
「画像診断」と「放射線治療」の両面から臨床に役立つ情報が充実。多数の診療例・症例を毎号掲載。特集・連載も勉強になると大好評。放射線に関わる幅広い層に愛され続ける老舗雑誌!

理学療法40巻12号
2023年12月号
地域リハビリテーションにおける理学療法士の役割
地域リハビリテーションにおける理学療法士の役割 現在では地域包括ケアシステムの枠組みの中で、理学療法士が地域リハビリテーションの重要な役割を担うようになっています。
これからも加速する少子高齢化や疾病および障害の多様化などによって、地域でのリハビリテーションの需要が増し、対象者の心身機能の維持・改善、介護予防、生活支援、また多職種連携や組織マネージメントなどにおいて、理学療法士の役割はますます重要になっています。
また、2024年からは、通所と訪問の連携型新サービスが始まります。
本特集では、地域リハビリテーションにおける理学療法に関する基本的な知識・技能、対象者に接する態度、
および多職種連携やマネージメントのあり方を、今後の役割発揮に向けて述べていただきます。

理学療法40巻11号
2023年11月号
協調運動障害患者に対する理学療法
協調運動障害患者に対する理学療法 協調運動障害をもたらすのは主に小脳の病変であり、その病態は複雑で、患者個々に応じた理学療法を展開する必要があります。
しかしながら、協調運動障害の理学療法に関するエビデンスが少ないため、理学療法の展開や日常生活活動指導でも苦慮することが多いものと思われます。
近年、その機序が画像診断、計算理論などによって解明されつつあることから、その機序の理解は理学療法における評価や治療に重要な示唆を与えてくれることが期待されています。
経験豊かな先生方にアプローチ考案の実例を自験例を挙げて述べていただき、効果的な理学療法展開の参考を目指します。

理学療法40巻10号
2023年10月号
がん患者の病期別緩和ケアにおける理学療法士の役割
がん患者の病期別緩和ケアにおける理学療法士の役割 日本での緩和ケアの対象者は「末期の悪性腫瘍または後天性免疫不全症候群に罹患した者」と疾患が限定されています。
がん患者の緩和ケアの課題は、①診断時、②治療期、③終末期の3期に分けられ、早期から維持期・末期までを対象に積極的に行われるようになり、
その中で緩和ケアチームの一員である理学療法士に対する期待は大きいと考えられています。
そこで本特集では、がん患者の緩和ケアにおける理学療法士の役割について、病期別に整理し、
理学療法士の関わり方の要点と具体的な理学療法のプログラムについて、事例を交えるなどして述べていただきました。

訪問看護、介護・福祉施設のケアに携わる人へ
コミュニティケア Vol.26 No.2
2024年2月号
特集:新任訪問看護師の研修プログラム
特集:新任訪問看護師の研修プログラム
新任訪問看護師の定着には、計画的な研修の実施や学習支援が重要です。しかし多忙ゆえに、研修プログラムや教育体制の整備ができていない訪問看護ステーションも少なくないのではないでしょうか。
新任訪問看護師はキャリアが多彩であることから、経験の浅い分野について実践で学べるOJT(On the Job Training)が有用です。しかし、外部での集合研修やeラーニング等によるOff-JT(Off-The-Job Training)も欠かせません。
Off-JTで業務に必要な知識や技術を身につけた上でOJTを実施し、振り返りを行うなど、OJTとOff-JTを計画的に連動させることで、より効果的な学びとなります。
本特集では、〈総論〉でOJTとOff-JTを進めるに当たってのポイントなどを解説し、〈論考〉で既存の研修プログラムの活用法や、実際の導入の仕方などを紹介します。
また、既存のプログラムを自ステーションの特徴を踏まえてカスタマイズした研修プログラムや、独自の研修プログラムを用いて、研修・学習支援を行う4つの訪問看護ステーションから、その実際について述べます。

臨床画像 Vol.40 No.2
2024年2月号
【特集】特集1:FDG–PET検査におけるピットフォール集/特集2:遠隔画像診断の最新動向と未来予測
【特集】特集1:FDG–PET検査におけるピットフォール集/特集2:遠隔画像診断の最新動向と未来予測

耳科学アトラス ―形態と計測値― 第5版
初版刊行から半世紀を目前に「耳科学分野の古典」が6年ぶりに大改訂!1974年の初版以来約50年続く、耳科学分野に携わる医学生、研修医、専門医、言語聴覚士に読み継がれてきた「座右の書」。著者の野村恭也医師監修による精緻な線描画と計測値で耳の構造をひも解いていく。次の50年を見据えて80点の新規イラスト追加、解説も大幅に加筆し、耳科学分野の英知を集めるアトラスとなった。

≪看護をひとつひとつわかりやすく。≫
検査値をひとつひとつわかりやすく。
好評シリーズ「看護をひとつひとつわかりやすく。」の第四弾として,「検査値」をひとつひとつわかりやすく解説!
検査値がなぜか苦手なアナタに読んでほしい,看護技術と検査値がひとつになった本当に使える「検査手技」の入門テキストです!

哲学入門 第3版
身体・表現・世界というキーワードで,人間理解に必要な哲学と身体・世界,時間と他者,言葉と世界とのかかわり,自然と人間が生み出した科学と世界とのかかわりから,哲学への世界にいざなう,
不変かつ変化の激しい今に必要な自身の哲学の柱となる名著.

日本看護協会機関誌『看護』年間購読(2025年1月号~12月号:臨時増刊号含む計15冊)
日本看護協会出版会発行の日本看護協会機関誌『看護』の2025年の年間購読(電子版・12冊発行予定)になります。日本看護協会機関誌『看護』の内容は下記をご覧ください。 日本看護協会の重点政策・重点事業、全国各地の優れた看護実践等を紹介 特徴: 〇日本看護協会の重点政策・重点事業をわかりやすく解説 〇あらゆる場所で活躍する優れた看護の取り組みを紹介 〇経営・管理・教育にヒントが得られる事例報告

実験医学 Vol.42 No.3
2024年2月号
【特集】不妊の原因解明に挑む生殖細胞研究
【特集】不妊の原因解明に挑む生殖細胞研究 体細胞とは大きく異なる卵子や精子の形成・維持メカニズムの解明と,それらの人工的な制御への挑戦の最前線をご紹介.未来の生殖医療の礎がここに/スパコン「富岳」版のAlphaFoldで大規模タンパク質構造予測
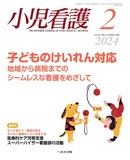
小児看護2024年2月号
⼦どものけいれん対応;地域から病院までのシームレスな看護をめざして
⼦どものけいれん対応;地域から病院までのシームレスな看護をめざして 看護師への社会的な期待は病院やクリニックだけではなく、地域においても多くの場所で必要とされ、保育所、児童発達支援事業所、学校、放課後等デイサービス、病児保育など地域のさまざまな施設に広がり、各施設で看護師の役割への期待が高まっている。本特集では、2023年に改訂された『熱性けいれん(熱性発作)診療ガイドライン2023』の最新の知識を解説しブラッシュアップするとともに、地域から病院までのさまざまな看護師の実践を紹介する。

小児科診療 Vol.87 No.2
2024年2月号
【特集】米国の小児医療・卒後教育の現状と臨床留学への手引き
【特集】米国の小児医療・卒後教育の現状と臨床留学への手引き
米国で活躍する小児科医が米国の小児医療,医学教育から留学準備,現地での生活までお伝えします.
留学希望者はもちろん,日本の小児医療をより良くするため尽力される先生方に役立つ一冊です.
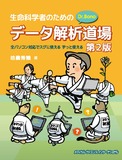
生命科学者のためのDr.Bonoデータ解析道場 第2版
全パソコン対応でスグに使える ずっと使える
データ解析をはじめようか迷っているあなたへ
環境設定からコマンドライン操作まで本書でイチからマスターしよう!
ビッグデータの解析に欠かせないコマンドラインの実践書、待望の改訂。今版はMacのみならず、Windows、Linuxの各OSに対応。「実際に解析ができるようになる」ために、解析ソフトウェアのインストールから、解析用に用意されたダミーデータを使用したコマンドの打ち込みを行い、データ解析を丸ごと体験できる。よくある疑問や陥りがちな誤りにも言及された初学者からベテランまで必携の一冊。

内視鏡下縫合・結紮手技トレーニング[Web動画付] 改訂第2版
日本内視鏡外科学会主催の講習会の内容をベースとして,縫合・結紮手技の基本を学べる実践書の改訂版.トレーニング法から,消化器外科を中心に,泌尿器科,婦人科,呼吸器外科領域の手術実践における縫合・結紮の方法や注意点まで網羅.さらに 講習会のWeb開催移行や新たな自主トレーニング法 ,ロボット手術における縫合・結紮など最近の変化も反映して内容を大幅に拡充.内視鏡外科手術を始めたい助手・術者のみならず,技術認定取得やさらなる上達をめざす読者に最適の一冊である.

医学のあゆみ288巻3号
CAR-T細胞療法の最前線――現状と残された課題
CAR-T細胞療法の最前線――現状と残された課題
企画:赤塚美樹(名古屋大学大学院医学系研究科分子細胞免疫学)
・世界初のCD19 CAR-T細胞が米国で承認され, T細胞が主要組織適合抗原非依存性に,抗体の特異性によってがん細胞上の抗原に結合し,直接傷害することが可能になり,抗体製剤の反復投与も不要となった.
・CAR-T細胞療法は,抗原を喪失した腫瘍細胞の出現により再燃をきたす.腫瘍微小環境を有するソリッドキャンサーに対する効果は限定的であり,CAR-T細胞調製の成否や所要時間の長さの課題もある.
・本特集では,CAR-T細胞開発の歴史から最新動向,CAR-T細胞療法の現状と課題,バイオマーカー,高品質のCAR-T細胞を供給するための体制構築などについてエキスパートが最新知見を紹介している.
