
Evidence Update 2024
最新の薬物治療のエビデンスを付加的に利用する
情報は減ることなく,毎年積み重なっていきます.この新しく追加された情報から重要なものを厳選し,整理し,わかりやすくまとめ,現場で役立てていただくことをコンセプトとして,2012年に"Evidence Update"シリーズが登場しました.2024年版では,漢方薬などの4つの治療薬と「押さえておきたいホットトピックス」の項も追加しました.各領域のエキスパートが厳選して執筆した"Evidence Update" 本年も多くのみなさまにお役立ていただければ幸いです.

分子細胞生物学 第9版
分子細胞生物学の基準的教科書として世界的に広く使われている“Molecular Cell Biology”の日本語最新版(原著第9版).

研修医1年目の教科書
不安や緊張が期待に変わる!
研修医から医師のキャリア生活が始まります.研修医は,学習者,医療従事者,労働者の3つの顔があり,それぞれの役割をバランス良く保ち過ごすことで研修医生活を乗り切ることができます.本書は,研修生活は何かという基本的事項から紹介し,研修生活をうまく乗り切るコツ,研修生活を迎えるにあたって抱えている様々な不安を払拭するにはどうすればいいのかなどを紹介.本書を読んでその不安や緊張を期待に変えてみませんか?

訪問看護ステーションの顧客管理と人材管理・育成
好評既刊書『新版 訪問看護ステーション開設・運営・評価マニュアル』の姉妹編
利用者・家族や関係職種・関係機関と訪問看護師等のマネジメントに関する最新知識を一冊に凝縮!
本書は主に訪問看護管理者を読者対象としています。
訪問看護において、マネジメントが難しいとされる「顧客(利用者・家族や関係職種・関係機関)」と「人材(訪問看護師等のスタッフ)」にフォーカスした最新知識を一冊に凝縮しました。
専門看護師・認定看護師を含む経験豊富な第一線の管理者を中心とした充実の執筆陣により、多職種連携や人材育成、最近課題となっているカスタマーハラスメントへの対応や職場内ハラスメント対策、またスタッフだけでなく管理者自身のメンタルヘルスも含むストレスマネジメントについても解説しています。

Medical Practice 2024年1月号
気管支喘息~古くて新しい疾患
気管支喘息~古くて新しい疾患 特集テーマは「気管支喘息~古くて新しい疾患」.記事として,[座談会]エキスパートに聞く喘息診療のコツとピットフォール,[総説]喘息病態Up-To-Date─気道炎症制御の重要性─,[セミナー]喘息診療のポイントと考え方,[治療]気管支拡張薬の選択と使い方.連載として,[One Point Advice]外国人患者のeGFRに注意!,[今月の話題]HPVワクチン,[知っておきたいこと ア・ラ・カルト]もやもや病の臨床像と遺伝的背景他を掲載.

臨床スポーツ医学 2024年1月号
膝関節のスポーツ障害
膝関節のスポーツ障害 「膝関節のスポーツ障害」特集として,膝関節のスポーツ障害を理解するための解剖学的知識/ジャンパー膝の病態と治療/Osgood-Schlatter病の病態と治療/膝周囲の腱症の病態と治療/膝周囲の腱症予防のためのコンディショニング/離断性骨軟骨炎の病態と治療・リハビリテーション/外側円板状半月板の病態と治療/膝蓋骨脱臼・亜脱臼の病態と治療/PRP療法 などを取り上げる.また,【スポーツ関連脳振盪-アムステルダム声明-】他を掲載.

がん看護 Vol.29 No.1
2024年1-2月号
いま知っておきたい! がん治療薬&支持療法薬13
いま知っておきたい! がん治療薬&支持療法薬13 がんの医学・医療的知識から経過別看護、症状別看護、検査・治療・処置別看護、さらにはサイコオンコロジーにいたるまで、臨床に役立つさまざまなテーマをわかりやすく解説し、最新の知見を提供。施設内看護から訪問・在宅・地域看護まで、看護の場と領域に特有な問題をとりあげ、検討・解説。告知、インフォームド・コンセント、生命倫理、グリーフワークといった、患者・家族をとりまく今日の諸課題についても積極的にアプローチし、問題の深化をはかるべく、意見交流の場としての役割も果たす。

産婦人科の実際 Vol.72 No.13
2023年12月号
動画で理解する婦人科悪性腫瘍手術の外科解剖―腔の展開と切断ラインの決定―
動画で理解する婦人科悪性腫瘍手術の外科解剖―腔の展開と切断ラインの決定―
臨床に役立つ知識や技術をわかりやすく丁寧に紹介する産婦人科医のための専門誌です。面白くてためになる,産婦人科の“実際”をお届けします。今回の特集では,骨盤内解剖に精通した先生方に,婦人科悪性腫瘍手術の外科解剖についてご解説いただき,さらに手術動画をご提供いただきました。最前線で活躍中のプロフェッショナルによる美しい手術動画は,産婦人科医必見です! (合計45本の動画を見ながら本誌を読み進めることで,婦人科悪性腫瘍手術の外科解剖を深く理解できる内容となっています。)

皮膚科の臨床 Vol.65 No.13
2023年12月号
膠原病
膠原病
全身性強皮症,皮膚筋炎を中心に「膠原病」の症例報告をまとめました。鑑別診断や各種検査方法,治療の選択など,明日からの診療に役立つ情報が満載です。エッセイ『憧鉄雑感』などの人気連載も好評掲載中!

≪ニュートリションケア2023年冬季増刊≫
イラストで楽しくまなぶ 転ばぬ先の生化学
【疾患の栄養管理と栄養素をつなげて考える!】栄養の素となる「栄養素」は多種類あり、ヒトの生命維持に重要な役割を担っているが、その消化・吸収・代謝の過程は互いが関係し合い、複雑である。よりよい治療の実践のために、栄養学の基本である生化学をわかりやすいイラストと楽しいキャラクターで学べる一冊。

苦手にサヨナラ!モニター心電図
【イラストで正常・異常を最速イメージ】心電図モニター装着患者の受け持ちを、慣れないナースが不安に思うことは多い。本書では、刺激伝導系や波形の異常がひとめでわかるイラストとともに、専門知識をやさしく解説。理解に必要な12誘導の基本もおさえて“ニガテ”を“これならわかる!”に変える。
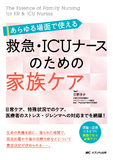
あらゆる場面で使える 救急・ICUナースのための家族ケア
【家族の心のケア、精神的支援が実践でわかる】救急・ICUという特殊な環境下での家族への対応は悩ましく、難しい。生命の危機を前に短時間で意思決定が求められるなど、ナースには、さまざまな状況や場面に応じた適切な対応や振る舞いが求められる。日々いのちの危機と向き合う中で、しっかり家族に寄り添い、医療者自身のこころも大切にできる、家族ケアの実践と理論が結びついた渾身の1冊。

看護 Vol.75 No.15
2023年12月号
特集1 看護管理者が注目すべき「看護師等確保基本指針」
特集1 看護管理者が注目すべき「看護師等確保基本指針」
日本看護協会と日本看護連盟が「看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」について改定を要望。厚生労働省において医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師等確保基本指針検討部会が設置され、10月26日に改定された指針が告示されました。
同指針は、「看護師等の人材確保の促進に関する法律」第3条の規定に基づき定められたもので、1992年の制定以来30年ぶりの改定となります。
特集1では、まず指針改定の意義を述べた上で、看護管理者が知っておくべき改定のポイントを解説。さらに、指針を政策的視点から読み解きます。座談会では、看護管理者は指針改定を受け、どのように認識をあらため、どのように活用すべきかを語り合いました。
特集2:
副看護師長が活躍する病院へ
「医療職俸給表(三)」で評価された役割
2023年4月に国家公務員の給与体系である「医療職俸給表(三)」が改正され、新たに「医療機関の副看護師長の職務」が3級に規定されました。
特集2では、まず副看護師長のポストを設置し、看護師長を補佐する職員を役割に応じて処遇することは、本人のモチベーション向上だけでなく、魅力ある病棟づくりにつながることを説明。さらに、変化の激しい今の医療現場において副看護師長に求められる役割や能力について解説します。また2つの病院から、ポストを設定し適切に処遇することの意義や、次世代の看護管理者を育成するための取り組みを報告します。

小児科 Vol.64 No.12
2023年12月号
細菌だけじゃないクリニックで注意すべき食中毒
細菌だけじゃないクリニックで注意すべき食中毒
クリニックでもよくみるものの、一般的な感染性胃腸炎との鑑別が難しいこともよくある「子どもの食中毒」がテーマ。細菌に限定せず、アニサキスや馬肉を介したサルコシスティス・フェアリーなどの寄生虫によるもの、食用キノコによく似た毒キノコの中毒、ギンナンやジャガイモを含めた植物性自然毒のほか、化学物質の混入や食品の経時的変化によるものなど、数は少なくても診る可能性がある食中毒に幅広くスポットを当てました。

整形・災害外科 Vol.66 No.13
2023年12月号
整形外科疾患における性差
整形外科疾患における性差
近年,様々な領域で性差に基づいた個別化医療への関心が高まっており,性差への理解を深めることで,より効果的で適切なケアを患者に提供できることが期待されている。
本特集では性差医療・医学の総論に加え,骨粗鬆症,変形性関節症,関節リウマチ,側弯症,スポーツ損傷,疼痛,サルコペニア,ロコモ,小児整形外科疾患について,性差のエビデンスとその背景を第一線の執筆者が解説した。

眼科 Vol.65 No.13
2023年12月号
私の経験集 珍しい真菌の角結膜感染への対応
私の経験集 珍しい真菌の角結膜感染への対応
トピックス、診療のコツ、症例報告、どこから読んでもすぐ診療に役立つ、気軽な眼科の専門誌です。今月の特集は、治療に難渋しがちな珍しい眼感染症をみた際の対応力や病診連携意識を深めようと、珍しい真菌感染症について論文を4本お寄せいただき、情報の集約を試みました。難治性アカントアメーバ角膜炎への角膜移植、ならびにMRIを用いて緑内障と脳構造・脳機能の関係を論じた綜説2本や連載、投稿論文も是非ご一読ください。

小児看護2024年1月号
カンファレンス再考;みんなで考えるこの子の最善のケア
カンファレンス再考;みんなで考えるこの子の最善のケア 多職種で医療が行われる昨今、目の前の子どもに最善のケアを行うため、カンファレンスでケアの目標や方向性を見出していくことが日常になりました。本特集では、医療施設内でのカンファレンス、医療施設と地域が交わるカンファレンス、そして地域の訪問看護ステーションや福祉・教育施設で行われているカンファレンスなど、多様なシチュエーションで実践されているカンファレンスを紹介する。
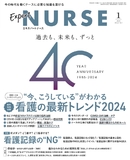
エキスパートナース Vol.40 No.1
2024年1月号
◆看護の“今、こうしている”がわかる看護の最新トレンド2024
◆何がダメ?どう直す?どう指導する?看護記録の“NG”
◆看護の“今、こうしている”がわかる看護の最新トレンド2024
◆何がダメ?どう直す?どう指導する?看護記録の“NG”

臨牀消化器内科 Vol.39 No.1
2024年1月号
消化器内視鏡診療における鎮静
消化器内視鏡診療における鎮静
本邦においても内視鏡検診の時代にもなり,苦痛なく内視鏡検査・治療を行うことで,コンプライアスの向上による早期診断,さらには予後改善,また治療内視鏡の成績向上につなげていくか,ということを考える時代になっている.2020 年には,巻頭言をご寄稿いただいた後藤田卓志先生が委員長として発刊された「内視鏡診療における鎮静に関するガイドライン(第2版)」とともに,本特集が日々の内視鏡診療における鎮静手技の向上につながり,内視鏡医・患者の両者の益となることを願っている.

整形外科 Vol.74 No.13
2023年12月号
1950年創刊。整形外科領域でいちばんの伝統と読者を持つ専門誌。読者と常に対話しながら企画・編集していくという編集方針のもと、年間約180篇にのぼる論文を掲載。その内容は、オリジナル論文、教育研修講座、基礎領域の知識、肩の凝らない読み物、学会関連記事まで幅広く、整形外科医の日常に密着したさまざまな情報が、これ1冊で得られる。
