
感染管理・感染症看護テキスト
●診断・治療から看護まで、感染症に関する必須テーマを網羅
●感染分野の第一線で活躍している専門職種が、最新の知見をもとに執筆
●ICT(感染対策チーム)必携の1冊

周術期超音波ガイド下神経ブロック 改訂第 2 版
区域麻酔の更なる普及に呼応して!
周術期の鎮痛法として、末梢神経ブロックが果たす役割が、より重要視されています。
本改訂第2版では―
(1)この3年間に出版された重要な論文からのエビデンス
(2)それを基に、自信を持って紹介できる方法や使用法の実際
(3)自らの臨床体験、国内外の一線で活躍している医師から得
た情報に基づいたティップスやピットフォールなどを分か
り易く組み入れています。
患者の満足度の向上に、周術期疼痛管理に携わる医療従事者の必読・必携の書!!

こういうことだったのか!! 一般医療者の生き残りの気管挿管
どんなケースにも対応できるための「リスキリング」
わかりやすくてマニアックな大好評シリーズの第10弾.気管挿管というハードルが高いテクニックには,守るべきさまざまなルールやコツがある,これまで誰も教えてくれなかった考え方とノウハウを読み込めば,どんな症例にも対応できる応用力を手に入れることができる.新しい知識を学び直して常識をアップデートし,気管挿管のリスキリングをするためのサバイバルブック.著者のメッセージ「気管挿管・気道管理で足をすくわれて欲しくない。生き残ろうぜ!!」をぜひとも体感していただきたい。

ER・ICU診療を深める2 リアル血液浄化 Ver.2
「シンプルに考える.イージーに考えない」を信条に,血液浄化のリアルを軽妙な語り口と絶妙な例えでひもといた,急性期血液浄化の新スタンダード.Ver.2では,新たに血漿交換,バスキュラーアクセスなどの重要課題が加わり,全面的に大幅改訂を行った.難解な数式が並び,決して分かりやすいとは言えない血液浄化の背景や問題点などを理解し,本質を理解することを目指す.日々の診療・治療が劇的に変化するお薦めの1冊.

小児エコー 検査直前チェックポイント
小児科医でもしっかり超音波検査を活用するために!小児科医が疑問に持ちやすいポイントは?見落としがちなポイントはどこ?見るべきポイントを検査直前に手早くチェック.

産婦人科レジデントの教科書
「産婦人科レジデントに初めに手に取ってもらう教科書」をコンセプトに,人気オンラインセミナー『SSS online』で講師を務める気鋭の医師が執筆。
産科婦人科領域の癌や不妊,内分泌,女性医学などの各分野を網羅した「知識編」から,明日の外来診療に活かせる「臨床編」,キャリア形成や認定医・専門医取得を解説した「特別編」まで,産婦人科レジデントが学んでおきたい内容を,幅広く,わかりやすくまとめました。
若手医師が医局で先輩に教えてもらうような読書体験ができる一冊です。
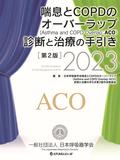
喘息とCOPDのオーバーラップ(Asthma and COPD Overlap:ACO)診断と治療の手引き 第2版 2023
今回の改訂版においては,2018年の初版以降に集積した観察研究の結果や,新たに上市された治療薬(single inhaler triple therapy,生物学的製剤など)を喘息-COPDの合併例でどのように位置付けるかを念頭に,できるだけ具体的な診療指針となるように改訂を行った。前版の“ACOの重症度”では,GOLD 4期COPD+軽症喘息が最重症と判定され,増悪頻度が低く本来は低用量ICS治療で十分な症例に中~高用量ICSを推奨してしまう齟齬が生じていたが,本版の“タイプ分類”による治療指針ではそのような齟齬は解消されている。
本改訂版が呼吸器専門医・非専門医の診療の一助となることを祈念している。
(一般社団法人 日本呼吸器学会 喘息とCOPDのオーバーラップ(Asthma and COPD Overlap:ACO)診断と治療の手引き第2版作成委員会「序」より抜粋)

手の外科―私のアプローチ 第3版
手の外科におけるマイクロサージャリーの手術手技の全てが詰まった一冊!
手の外科全般や整形外科領域で扱うマイクロサージャリー手術手技を網羅したビジュアルテキストを大幅改定.整形外科領域のエキスパートとして長年のキャリアを持つ著者による各疾患,病態,手術解剖,手術適応,手術治療を丁寧に紹介.今回は著者のライフワークである手根不安定症の記載を新たに追加した.症例供覧やコツ,疾患に対する複数のアプローチなどもさらに充実させ,手外科・マイクロサージャリーを実践するエキスパートの「技」と「考え方」をより広く深く学べる一冊となった.

研修医のための輸液・水電解質・酸塩基平衡 改訂2版
輸液・水電解質が1冊で基本から実際の治療までよくわかる
輸液・水電解質・酸塩基平衡が1冊で基本から実際の治療までよくわかる.臨床で役立つ水電解質・酸塩基平衡の基本を本格的にわかりやすく解説する決定版入門書が待望の大改訂!知っておくといい症例や経験的知見を大幅に増やし,まるで指導医が横にいるような充実感にパワーアップ.病態生理から治療まで,最新のエビデンスと経験的知見を伝授!急いでいるときはこれだけ見れば対応できる「電解質異常クイックリファレンス」つきでいざというときに頼りになる,研修医はもちろん救急外来や入院病棟でも大活躍の必携書.

美しい画像で見る内視鏡アトラス 上部消化管
腫瘍から感染性・炎症性疾患まで、典型例とピットフォール画像で鑑別点を理解する
高精細かつ高情報量の「美しい内視鏡画像」が満載で,疾患の本質を理解して診断ができるようになる!腫瘍性病変だけでなく,遭遇率の低い疾患まで幅広い上部消化管疾患を扱った,日常の内視鏡診療に必携の大図鑑!

排液の正常・異常が見てわかるカラー図鑑
ドレーンの色いろ
12診療科での術後ドレーンの症例写真200点をまとめた「ドレーンの写真集」
“淡血性”の言葉だけじゃわからない!外科ナースが目で見てわかるカラー図鑑
<本書の特徴>
・外科系病棟で観察する「ドレーン排液の色・性状」の正常・異常を、外科医による豊富な症例写真で展開するドレーンの写真集。
・縫合不全や再出血、感染など術後合併症の早期発見を行うために、ナースの観察・アセスメントに役立つ1冊です。
・調べやすくて見やすい、ベッドサイドでも使えるA5サイズ。

薬局 Vol.76 No.4
2025年3月増刊号
みえる!わかる!婦人科・産科・女性医療のくすり
みえる!わかる!婦人科・産科・女性医療のくすり 月経や妊娠・出産に関連する,女性ならではの疾患や状態に対する薬物治療.その多くで性ホルモンに関する薬剤が使用され,薬剤師・看護師やその他の医療スタッフによる丁寧な薬学管理・フォローアップが必要です.しかし,「患者さんにどこまで踏み込んで聞き取りや情報提供をしてよいのか迷う」という不安や,「ホルモン製剤」への苦手意識をお持ちの医療スタッフも少なくないでしょう. そこで,患者さんの不安や懸念に寄り添い,治療継続の一助になりたい薬剤師・看護師・医療スタッフに向けて,婦人科・産科領域で使われるくすりの知識を,①整理して,②活用できて,③迷ったときにすぐに参照できる書籍をつくりました.経験豊富な先生がたに,やさしくすっきりご解説いただいています.第1部では,婦人科・産科領域でよく使われる薬剤を製剤写真つきでまとめました.第2部では,婦人科の疾患や症状の解説とともによく使われる薬剤について理解を深めましょう.「よく聞くこの言葉や疾患,どんなものだっけ」と思ったときには,第3部を参照してください.婦人科・産科領域の薬物治療の学習と実践を“ここから”始めるための力になる1冊です!
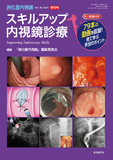
消化器内視鏡2024年36巻増刊号
スキルアップ内視鏡診療
スキルアップ内視鏡診療

臨床に直結する血栓止血学 改訂3版
血栓止血学の最高の入門書かつ最強の実践書 待望の改訂3版
前版(2018年)からのアップデートや最新のホットトピックを完全網羅.血栓止血学を専門としない読者にもわかりやすく,すぐに役立つ知識を中心に解説した入門書の改訂3版。内容はボリュームアップしながらも,「ポイント」「ここがコンサルトされやすい!」「症例紹介」「ピットフォール」「お役立ち情報」の記載などにより,「臨床に直結」した内容をコンパクトに網羅しました.血液専門医はもちろん,一般臨床医,他科専門医,研修医,臨床検査技師,薬剤師,医学生,保健学科学生の方々にも役立つ一冊です.

≪画像診断別冊 KEY BOOKシリーズ≫
困ったときの胸部の画像診断
胸部画像診断の新たな決定版!
肺病変を中心にカテゴリー別に分け,さらに縦隔と胸膜・胸壁病変を掲載.
各疾患ではバリエーションや鑑別すべき参考症例も提示し,理解が深められる.
人気シリーズの疾患別アプローチで,困ったときに役立つ必携の一冊.

ジェネラリストが知りたい 膠原病のホントのところ
わからないから面白い!議論があるからこそ楽しい!
リウマチ膠原病のみかた・考え方をワクワクしながら学ぼう
ジェネラリストと気鋭の膠原病専門家の熱い対談を通して、診療の本質に迫りつつ、非専門家向けのプラクティスを提示する。症状や検査、コモンな疾患、ステロイドの使い方について、つまづきやすい部分や現場でよくある悩ましいテーマ、議論のあるトピックも収載。対話の合間に臨床知識や手技のポイントをまとめ、知識の整理や振り返りにも役立つ。膠原病領域に苦手意識をもつ初期研修医・内科系専攻医から一般内科医におすすめ。
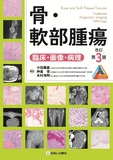
骨・軟部腫瘍 改訂第3版
臨床・画像・病理
2020年に改訂されたWHO分類をもとに新しい動向を反映して疾患構成を再構築し,最先端の治療法や分子遺伝学的病理診断などを詳細に解説した第3版.日常診療に役立つ実践的な情報を新たに加え,前版よりさらにパワーアップしました.
骨・軟部腫瘍診療の第一線の専門家が総力を結集し,整形外科医・放射線科医・病理医が診療現場で必要とする最新の知識を網羅した一冊であり,これから学ぶ方や専門ではない方にも最適の教科書です.

医師1年目からの 100倍わかる! 胸部X線の読み方
解剖の基本 画像の見え方 絶対に見逃せない頻出所見まで 臨床で本当に必要な知識を放射線診断専門医が厳選してまとめました
豊富な画像とシェーマから胸部X線読影の必須知識を学ぶ総論,頻出疾患・病態の見え方を学ぶ各論で,異常所見を見落とさないための読み「型」が身につく!「これで胸部X線が読める!」と自信を持てる必読書!

≪画像診断別冊 KEY BOOKシリーズ≫
すぐわかる小児の画像診断改訂第2版
小児の画像診断のすべてがこの1冊に!
初版より全面改訂し,最新の情報を盛り込みました.
部位別の成長に伴う正常像の変化と,疾患別画像全440症例を収録し,正常と疾患の両方で全身を網羅.
より充実した内容で,自信を持って小児画像の読影に当たれます!

脳神経内科 改訂 5版
神経学の魅力を余すところなく伝える,進化し続けるスタンダードテキスト,改訂第5版.
神経系は美しい論理に貫かれた臓器だ.本書は,長きにわたり神経学に真摯に向き合ってきた著者が独自の視点で説き起こし,その魅力を余すところなく伝えている.全篇フルカラーで,重要度によって強弱をつけた紙面は視覚的にも見やすく,理解が進む.前版からの進歩を踏まえ,内容をアップデートした改訂第5版.脳神経内科指導医や一般内科医にとっても有用な内容となるよう工夫された,進化し続けるスタンダードテキストである.
