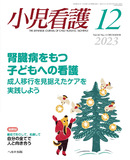
小児看護2023年12月号
腎臓病をもつ子どもへの看護;成人移行を見据えたケアを実践しよう
腎臓病をもつ子どもへの看護;成人移行を見据えたケアを実践しよう 子どもの腎臓病は、先天的なもの、後天的なもの、学校検尿、または発熱などの症状からみつかることもあり、発症年齢、病院に来るまでの経過はさまざまである。また、子どもの腎臓病は、急性発症して完治するものから、慢性腎臓病に移行して成人に至ってもうまく付き合っていく可能性も含んでいる。本特集は、腎臓病の基本を学び、成人移行を見据えた看護に生かすことを目指した一冊。

形成外科 Vol.66 No.11
2023年11月号
動静脈奇形症例集(1)―手足―
動静脈奇形症例集(1)―手足― 動静脈奇形は治療に難渋する疾患の代表の1つだが,発症頻度は高くないため扱いに苦悩することになる。本特集では,その第一弾として「手足の動静脈奇形の症例」を集めた。全国の各施設から,良い経過をたどっている症例ばかりでなく難渋例も提示し,一施設一専門家の経験を多くの読者で共有・蓄積して,次の突破口を開くことにつなげたい。

泌尿器外科 2023年10月号
2023年10月号
特集:バイプレーヤーズ! 転移性癌治療における外科治療の役割,徹底解明
特集:バイプレーヤーズ! 転移性癌治療における外科治療の役割,徹底解明

肝臓クリニカルアップデート 2023年10月号
2023年10月号
特集:進行・再発肝細胞癌に対する集学的治療update
特集:進行・再発肝細胞癌に対する集学的治療update
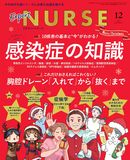
エキスパートナース Vol.39 No.15
2023年12月号
◆10疾患の基本と“今”がわかる!感染症の知識
◆これだけおさえればこわくない!胸腔ドレーン入れてから抜くまで
◆10疾患の基本と“今”がわかる!感染症の知識
◆これだけおさえればこわくない!胸腔ドレーン入れてから抜くまで

標準食品学総論 第4版
食品学のロングセラーテキストが,待望の改訂!
●食品成分表とその理解,食品化学・食品物理の基礎知識をできるだけ平易に記述した,初学者にも学びやすいロングセラー好評書.
●日本食品標準成分表2020年版(八訂)に対応.
●法令や各種データを最新版に更新.
●学問の進歩に伴い記述内容もアップデート.
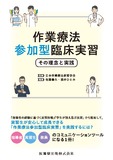
作業療法参加型臨床実習 その理念と実践
臨床実習教育者,実習生,教員のコミュニケーションツールになる1冊!
●改正指定規則で推奨されている作業療法参加型臨床実習を実践したいけれど,疑問や悩みが多い―.そんな声に,日本作業療法教育学会監修の本書が応えます.
●理念を理解したうえで,「指導者の経験に基づく実習指導」「学生が耐え忍ぶ実習」から脱却し,実習生が安心して成長できる「作業療法参加型臨床実習」を実践するには?

看護微生物学 第4版
看護学生向けに微生物学の基本をわかりやすく解説した,四半世紀にわたるロングセラーテキストが待望の改訂!
●院内感染・起因微生物・感染症を三本柱として,微生物学の基本原則をわかりやすく解説した看護学生向けテキスト.
●「看護にとって必要な微生物学とは何か」という視点で,多くの情報のなかから必要なもののみをピックアップし収載.臨床的問題となっている主要な微生物に起因する疾患とその対策などについて,最新の情報にアップデート!
●2章では自然免疫の追加や腫瘍免疫療法,特に免疫チェックポイント阻害薬など最新トピックを追加.4章では,最近の抗ウイルス薬についての追加と修正や麻疹,風疹の最近の流行などについて説明を追加,5章では,微生物の分類の変更,6章では最新のデータやトピックを収載.

セラピストのキャリアデザイン
「あるべき姿」から、それぞれの「ありたい姿」を見つめたキャリアデザインを!
いま、キャリアデザインの考え方は大きなパラダイムシフトを迎えています。「キャリアはより高く積み上げるもの」、「学位,職位が高ければ高いほど良いキャリア」というこれまでの考え方にこだわっていては、これからの社会では通用しないかも? あなたのありたい姿に近づくための「あなたらしい」キャリアの作り方を、気鋭の著者がお届けします。
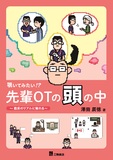
覗いてみたい!?先輩OTの頭の中 ― 臨床のリアルに触れる
人気シリーズ「覗いてみたい!?先輩OTの頭の中」最新刊
リハビリテーションの難しさを感じたとき、いつの間にか後輩を指導する立場になっていたとき、養成校から実習を受けてほしいと依頼されたとき、逆に教え子を実習先に送り出すとき……。そんな場面で著者は何を考え、どう行動したのか。いつも気の置けない友人や職場の仲間と一緒だった著者の“リアル”をお届け。

発達が気になる子の偏食の見方と対応―口腔・認知・感覚・環境面からのアプローチ
子どもの好き嫌いには理由がある!ー子ども一人ひとりの好き嫌いの理由に応じた対応をするために
発達が気になる子では偏食(好き嫌い)に困っている家庭もあり、栄養・発達面から介入が望まれるケースもある。
本書では一人ひとり異なる好き嫌いの理由を口腔面・認知面・感覚面・環境面、また手の不器用さの面から解説するとともに、理由に応じた具体的な対応50項目を詳述。子どもの食行動の傾向や好き嫌い、またその理由を知るのに役立つチェックリスト付き。
リハスタッフ、栄養士、調理員、保育士、保護者、学校の先生、療育スタッフの連携に便利な資料や保護者支援のポイントも記述。

日本の現代麻酔科学の歩み
日本における1950年以降の現代麻酔科学の歴史を立体的視点でとらえる。“山村秀夫東京大学名誉教授との対談”“山村秀夫の‘麻酔標榜医の認可'における業績”などを収載。
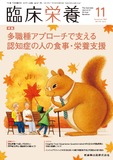
臨床栄養 143巻6号
多職種アプローチで支える 認知症の人の食事・栄養支援
多職種アプローチで支える 認知症の人の食事・栄養支援
●日本は他の先進諸国に類を見ない速さで超高齢社会に突入し,認知症を有する高齢者の方が増加している.認知症の方にとっても食事は他者とのコミュニケーションを図るなど,おいしさや満足感を介して心の充足を感じる機会であり,栄養専門職による専門的な支援が求められています.
●また,認知機能の低下した方が食事をおいしく食べられる環境づくりや周囲のサポートは,認知症だけでなく介護予防や健康寿命延伸にも重要となるため,早期の栄養介入が認知症の進行予防にどのような効果を示すのかについてはエビデンスを構築する必要もあります.
●本特集では,認知症の方への食支援や研究を第一線で推進する専門家を執筆陣に迎え,それぞれの立場から食支援をわかりやすく解説.
●認知症高齢者における嚥下造影検査と臨床所見,4大認知症における食の特徴,看護師による食事ケア,口腔衛生,作業療法支援,精神病院や地域包括ケア病棟における栄養ケア,離島における支援,認知症基本法についてなど,「多職種アプローチで支える認知症の人の食事・栄養支援」について広く掲載しています.
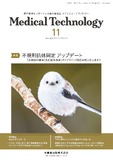
Medical Technology 51巻11号
不規則抗体同定アップデート―『赤血球型検査(赤血球系検査)ガイドライン(改訂4版)』をふまえて
不規則抗体同定アップデート―『赤血球型検査(赤血球系検査)ガイドライン(改訂4版)』をふまえて
●不規則抗体同定は大変重要な検査であり,現場からも「複数の抗体の存在が疑われる場合の対応方法」や「実際のパネル結果から推測していく手順」について,わかりやすい解説を求める声が多数あります.
●本特集では,日本輸血・細胞治療学会より『赤血球型検査(赤血球系検査)ガイドライン(改訂4版)』が発表されたことを受けて,ガイドライン改訂をふまえた不規則抗体検査の同定手順から,不規則抗体検出時の考え方,輸血副反応に至るまで,本領域のエキスパートが詳しく解説しています.
●後半には,手を動かしながらチャレンジできるパートも用意しているため,ぜひ本書を活用して実際に取り組んでみてください.
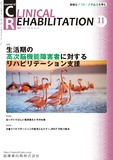
J. of Clinical Rehabilitation 32巻12号
生活期の高次脳機能障害者に対するリハビリテーション支援
生活期の高次脳機能障害者に対するリハビリテーション支援
●高次脳機能障害の患者は,ADL(日常生活動作)においては自立していても,記憶障害や注意障害,遂行機能障害,感情障害の影響で学業や職業,再就職などの社会的な復帰が困難となるケースがある.
●本特集では,こうした高次脳機能障害に関連する社会生活上の課題に対処するために,外来と他機関との連携や,就労継続支援,自動車運転支援,スポーツへの参加支援などさまざまな支援やアプローチを紹介.
●高次脳機能障害への多面的な方法を知ることで,認識拡大や各施設の活用増加に寄与することを期待した一冊.

≪眼科診療エクレール 1巻≫
最新 緑内障診療パーフェクトガイド
患者教育から最新の手術治療まで
我が国の緑内障診療の第一人者の編集によって,緑内障のエキスパートである執筆陣が,診断や薬物治療はもとより,疫学,患者教育,病診連携,疾患管理,そして手術療法に至るまで,最新の緑内障診療のすべて網羅し,詳細かつ分かりやすく解説した決定版.カラーの図版を豊富に用いたビジュアルな構成で,診療上疑問に思ったことを直ちに参照できる臨床に即したハンドブック.

感染対策60のQ&A
問題解決のための理論と実践をQ&A形式で具体的に解説
医療関連感染対策の現場で起こる複雑で多様な問題を解決する情報が満載。押さえておきたい60テーマを8カテゴリーに分類し、Q&A形式で具体的に解説(①標準予防策、②感染経路別予防策、③医療器具関連感染予防、④職業感染予防、⑤洗浄・消毒・滅菌、⑥医療環境管理、⑦サーベイランス、⑧新興感染症のパンデミック)。姉妹書の『感染対策40の鉄則』とともにIPC(医療関連感染の予防と管理)に取り組む人の心強い相棒!

検査と技術 Vol.51 No.12
2023年 12月号
若手臨床検査技師、臨床検査技師をめざす学生を対象に、臨床検査技師の「知りたい!」にこたえる総合誌。日常検査業務のスキルアップや知識の向上に役立つ情報が満載! 国試問題、解答と解説を年1回掲載。年10冊の通常号に加え増大号を年2回(3月・9月)発行。 (ISSN 0301-2611)
月刊、増大号2冊(3月・9月)を含む年12冊

総合リハビリテーション Vol.51 No.11
2023年 11月号
特集 障害児の成人移行支援の課題とトランジション
特集 障害児の成人移行支援の課題とトランジション リハビリテーション領域をリードする総合誌。リハビリテーションに携わるあらゆる職種に向け特集形式で注目の話題を解説。充実した連載ではリハビリテーションをめぐる最新知識や技術を簡潔に紹介。投稿論文の審査、掲載にも力を入れている。5年に一度の増大号は手元に置いて活用したい保存版。
雑誌電子版(MedicalFinder)は創刊号から閲覧できる。 (ISSN 0386-9822)
月刊、年12冊

臨床婦人科産科 Vol.77 No.11
2023年 11月号
今月の臨床 胎児心臓を診る この超音波所見を見逃すな!
今月の臨床 胎児心臓を診る この超音波所見を見逃すな! 産婦人科臨床のハイレベルな知識を、わかりやすく読みやすい誌面でお届けする。最新ガイドラインの要点やいま注目の診断・治療手技など、すぐに診療に役立つ知識をまとめた特集、もう一歩踏み込んで詳しく解説する「FOCUS」欄、そのほか連載も充実。書籍規模の増刊号は、必携の臨床マニュアルとして好評。 (ISSN 0386-9865)
月刊、合併増大号と増刊号を含む年12冊
