
エビデンスに基づく
臨床査定メソッド
質の高い心理支援の基礎と実践
臨床判断を研ぎ澄ますための手引書.
査定の基礎から一連のプロセスを一挙網羅.臨床現場でよく遭遇する精神疾患に使われる標準的尺度を紹介するとともに,示唆に富む複数の事例から細かなニュアンスを汲み取ってもらえるように工夫した.
筆者らが実施した介入研究におけるランダム化比較試験の事例では,実証的な介入研究によるエビデンス構築の方法や手順を学ぶことができる.質の高い心理支援を行うためのノウハウが満載!

胆と膵 2023年11月号
2023年11月号
特集:胆道癌,膵癌の薬物療法・集学的治療最前線
特集:胆道癌,膵癌の薬物療法・集学的治療最前線

レジデントノート Vol.25 No.15
2024年1月号
【特集】透析患者の診かたで絶対に知っておきたい8つのこと
【特集】透析患者の診かたで絶対に知っておきたい8つのこと 研修医が透析患者を診る際に「これだけは絶対知っておくべき」基本を8つのテーマに絞って解説!透析記録の見かたから薬剤投与の注意点,救急での具体的対応まで,日常診療で役立つ実践的知識とスキルが身につく.

救急医学2023年12月号
気になりませんか? 漢方の可能性
気になりませんか? 漢方の可能性 漢方の可能性、気になりませんか? 救急現場を想定した漢方の実践とエビデンスを解説。漢方って…ホントに効果あるの?作用が遅いのでは?エビデンスあるの? そんな“疑問”が、これを読めば“可能性”に変わるはず。

消化器外科2023年12月号
IPMN診療の新知見
IPMN診療の新知見 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)はもっとも頻度が高い膵嚢胞性腫瘍であり、近年の画像診断の進歩により、早期に診断されることが多くなってきた。本特集では、IPMN診療のエキスパートの先生方に、IPMNの悪性診断に関する新知見や治療戦略について、わかりやすくご解説していただいた。

脊椎脊髄ジャーナル Vol.36 No.10
2023年10月号
■特集
わかればみえる!脊椎手術術野へのアプローチ

作業療法ジャーナル Vol.57 No.13
2023年12月号
■特集
精神科作業療法最前線

リハベーシック 心理学・臨床心理学 第2版
リハ学生のために「心理学」「臨床心理学」の専門家がやさしくレクチャー!
●教養・基礎科目から専門科目へつなげるPT・OT・ST向けの好評テキストシリーズ,待望の改訂!
●リハ学生のために「心理学」「臨床心理学」の専門家がわかりやすく書き下ろした入門テキスト!
●【講義1コマで学ぶテーマ4つ】×【各テーマ見開き2頁】=【1コマ合計8頁】
●授業に適したコンパクトなボリュームにまとめて解説し,要点をしっかり学習できる!
●巻末にはPT・OT・ST国家試験過去問も掲載.
●高いレベルの対人技法を習得するための理論的基盤となる心理学・臨床心理学.その基礎(心理学)と応用(臨床心理学)の関係を理解することで,課題解決能力を習得する!

≪15レクチャーシリーズ 作業療法テキスト≫
作業療法概論
人の生活を支え,生活を科学的に分析する専門職としての作業療法の役割を理解する.また,作業療法に必要な医療についての社会学的な役割や障がい者の生活の実態を理解し,関連知識や主対象(疾患,病期,職域別)などを概略的に学習する.1年次に作業療法の全体像をつかむだけでなく,作業療法のおもしろさややりがいを見出し,各自が「理想の作業療法士像」をイメージし,今後の学習に向けて意欲を高めることができるようにまとめた.

≪眼科診療エクレール 第2巻≫
最新 眼科画像診断パワーアップ
検査の基本から最新機器の撮影法まで
眼科画像診断の基本から応用を,エキスパートの執筆陣が具体的に解説.部位・疾患別の画像診断の種類と目的,検査の実際,検査結果の解釈と診療への活かし方がよくわかる.広角眼底撮影,造影検査(FA,ICGA),超音波断層撮影,CT,MRI,MRA,そしてOCTをはじめとして,OCTAやSS-OCT,SD-OCT,UBM,SLOなど,最新機器を用いた画像診断のコツも満載.

レジデントノート増刊 Vol.25 No.14
【特集】処方の「なぜ?」がわかる 臨床現場の薬理学
【特集】処方の「なぜ?」がわかる 臨床現場の薬理学 薬理学の知識,臨床現場でどう使う?本書では基礎から各診療領域まで,薬理学の必携知識をわかりやすく解説.診療に欠かせない「くすり」についての理解と処方スキルがアップする,研修医と薬理学をつなぐ一冊!
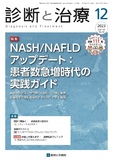
診断と治療 Vol.111 No.12
2023年12月号
【特集】NASH/NAFLDアップデート:患者数急増時代の実践ガイド
【特集】NASH/NAFLDアップデート:患者数急増時代の実践ガイド
NASHやNAFLDの患者を診たときの対応方法や,治療・管理方法,さらには最近欧米主導でNAFLDの疾患名が「MASLD」に変更になった経緯や,新薬の開発状況などをわかりやすく解説しました.ぜひ日常診療にお役立てください.

JOHNS39巻6号
漢方治療のエビデンス構築
漢方治療のエビデンス構築

周産期医学53巻6号
周産期医療のヒヤリ・ハット―医療事故・医療紛争を防ぐために 産科編
周産期医療のヒヤリ・ハット―医療事故・医療紛争を防ぐために 産科編

小児内科55巻6号
小児の心身症~いま改めて心身相関を考える~
小児の心身症~いま改めて心身相関を考える~

小児外科55巻6号
今日の小児肝移植
今日の小児肝移植

助産雑誌 Vol.77 No.6
2023年 12月号
特集 新世代がつくるお産の場 わたしたちの助産院
特集 新世代がつくるお産の場 わたしたちの助産院 助産師は、妊産褥婦と児のケアはもちろんのこと、思春期や更年期の女性からも期待される、女性の一生に寄り添う職業です。加えて、医療技術が進歩した現代では、より高度で専門的な知識が求められています。『助産雑誌』では、そのような臨床現場で欠くことのできない最新の知識と情報を発信しています。助産学生から新人、ベテランまで、幅広い年代の助産師に向けた雑誌です。 (ISSN 1347-8168)
隔月刊(偶数月)、年6冊
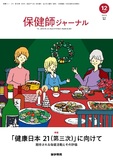
保健師ジャーナル Vol.79 No.6
2023年 12月号
特集 「健康日本21(第三次)」に向けて 期待される保健活動とその評価
特集 「健康日本21(第三次)」に向けて 期待される保健活動とその評価 公衆衛生活動の現場で働く保健師に向けた、「保健師」と名の付く唯一の専門誌。保健活動の「いま」と「これから」を、確かな情報と具体的な実践を伝えることで描きます。 (ISSN 1348-8333)
隔月刊(偶数月)、年6冊

看護教育 Vol.64 No.6
2023年 12月号
特集1 実践にいきるフィジカルアセスメント/特集2 受験生はこんな教育を受けている! 小論文・面接では何を評価すべきか
特集1 実践にいきるフィジカルアセスメント/特集2 受験生はこんな教育を受けている! 小論文・面接では何を評価すべきか 変わりゆく医療の構造、そして教育界全体の動きをみすえ、今求められる看護教育を、みなさんとともに考えていきます。ベテランの先生方はもちろん、学生への指導に不安を感じていらっしゃる新人教員の方々にも役立つ内容をお届けします。 (ISSN 0047-1895)
隔月刊(偶数月)、年6冊

病院 Vol.82 No.12
2023年 12月号
特集 人を活かす病院経営 地域で病院の存在意義を発揮するために
特集 人を活かす病院経営 地域で病院の存在意義を発揮するために 「よい病院はどうあるべきかを研究する」をコンセプトに掲げ、病院運営の指針を提供する。特集では、病院を取り巻く制度改正や社会情勢の読み解き方、変革に対応するための組織づくりなど、病院の今後の姿について考える視点と先駆的な事例を紹介する。 (ISSN 0385-2377)
月刊、年12冊
