
腎と透析94巻5号増大号
高齢化社会の腎泌尿器疾患診療UpToDate【増大号】
高齢化社会の腎泌尿器疾患診療UpToDate【増大号】

小児内科55巻5号
小児の移植医療
小児の移植医療

小児外科55巻5号
ロボット支援手術
ロボット支援手術

周産期医学53巻5号
今,改めて考える,流産,死産,新生児死亡
今,改めて考える,流産,死産,新生児死亡

JOHNS39巻5号
手術をしない音声・構音・言語の治療
手術をしない音声・構音・言語の治療

看護管理 Vol.33 No.12
2023年 12月号
特集 ジョブ・クラフティング入門 仕事の自律的再創造によって組織を変える
特集 ジョブ・クラフティング入門 仕事の自律的再創造によって組織を変える 社会の変化を的確にとらえながら、看護管理者として直面するさまざまな問題について解決策を探る月刊誌。看護師長を中心に主任から部長まで幅広い読者層に役立つ情報をお届けします。 (ISSN 0917-1355)
月刊、年12冊

理学療法ジャーナル Vol.57 No.12
2023年 12月号
特集 疾病・介護予防のための運動療法
特集 疾病・介護予防のための運動療法 理学療法の歴史とともに歩む本誌は、『PTジャーナル』として幅広い世代に親しまれている。特集では日々の臨床に生きるテーマを取り上げ、わかりやすく解説する。「Close-up」欄では実践的内容から最新トピックスまでをコンパクトにお届けし、その他各種連載も充実。ブラッシュアップにもステップアップにも役立つ総合誌。 (ISSN 0915-0552)
月刊、年12冊

臨床泌尿器科 Vol.77 No.13
2023年 12月号
特集 落ち着け,慌てるな! 泌尿器外傷マネジメント
特集 落ち着け,慌てるな! 泌尿器外傷マネジメント 泌尿器科診療にすぐに使えるヒントを集めた「特集」、自施設での手術テクニックを紹介する「手術手技」、話題のテーマを掘り下げる「綜説」、そして、全国から寄せられた投稿論文を厳選して紹介する。春に発行する書籍規模の増刊号は、「外来」「処方」「検査」「手術」などを網羅的に解説しており、好評を博している。 (ISSN 0385-2393)
月刊、増刊号を含む年13冊

臨床眼科 Vol.77 No.13
2023年 12月号
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報
特集 知って得する白内障と屈折矯正の最新情報 読者からの厚い信頼に支えられた原著系眼科専門誌。厳選された投稿論文のほか、眼科領域では最大規模の日本臨床眼科学会の学会原著論文を掲載。「今月の話題」では、気鋭の学究や臨床家、斯界のエキスパートに、話題性の高いテーマをじっくり掘り下げていただく。最新知識が網羅された好評の増刊号も例年通り秋に発行。 (ISSN 0370-5579)
月刊、増刊号を含む年13冊

臨床婦人科産科 Vol.77 No.12
2023年 12月号
今月の臨床 AIがもたらす産婦人科医療の変革
今月の臨床 AIがもたらす産婦人科医療の変革 産婦人科臨床のハイレベルな知識を、わかりやすく読みやすい誌面でお届けする。最新ガイドラインの要点やいま注目の診断・治療手技など、すぐに診療に役立つ知識をまとめた特集、もう一歩踏み込んで詳しく解説する「FOCUS」欄、そのほか連載も充実。書籍規模の増刊号は、必携の臨床マニュアルとして好評。 (ISSN 0386-9865)
月刊、合併増大号と増刊号を含む年12冊

≪シリーズ ケアをひらく≫
わたしが誰かわからない
ヤングケアラーを探す旅
自他の境界線をめぐる冒険的セルフドキュメント!
「ヤングケアラー」について取材をはじめた著者は、度重なる困難の果てに中断を余儀なくされた。一体ヤングケアラーとは誰なのか。世界をどのように感受していて、具体的に何に困っていているのか。取材はいつの間にか、自らの記憶をたぐり寄せる旅に変わっていた。ケアを成就できる主体とは、あらかじめ固まることを禁じられ、自他の境界を横断してしまう人ではないか──。著者はふたたび祈るように書きはじめた。

脳卒中の機能回復
動画で学ぶ自主トレーニング
当事者のニーズを個別に解決!自主トレーニングの新しいカタチ
脳卒中患者のリハビリに携わる療法士に向けた革新的なガイドブックが誕生。本書は30時間に及ぶYouTube動画と連携し、療法士が患者に対して、より個別化された自主トレーニングの提供や実践的な説明、指導を行うための手引き書となっている。機能回復に必要な情報や評価手順、家族でも実施可能なトレーニングなど、療法士や患者家族が知りたい情報も豊富に収載。学生の臨床実習から現場の療法士まで幅広い層に最適な一冊。

医学のあゆみ287巻9号
第1土曜特集
質量分析イメージング法を用いた創薬・医学研究――時空間マルチオミクスの力
質量分析イメージング法を用いた創薬・医学研究――時空間マルチオミクスの力
企画:池川雅哉(同志社大学生命医科学部医生命システム学科)
・質量分析イメージング法を主題とした医学・創薬研究について,質量分析イメージング法の基礎から応用,海外動向に至るまでを俯瞰し,同技術の可能性と課題について,専門家が最新の成果と将来展望を紹介している.
・工学,理学,薬学,農学,医学分野から,質量分析イメージング法の基礎理論,対象分子のイメージングの可能性,栄養素の吸収・代謝機構,臨床応用例やリアルワールドデータにおける本技術の役割と可能性を解説.
・質量分析技術および画像統計解析の進展についても,機器開発の現場から国内外の動向を含め各分野のエキスパートが解説している.本特集が,わが国における本解析技術の進展の一助となれば本望である.
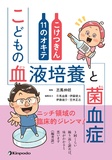
こどもの血液培養と菌血症 こけつきん11のオキテ
「こどもの血液培養と菌血症カレッジ」(略称:こけつきん)を主催するメンバーが執筆.重症化しやすい菌血症の確定診断のための血液培養から診断と治療について,検査をする基準から治療方針,患者マネジメントの方法まで記した内容.「こどもの血液培養と菌血症カレッジ」で聞かれてきた、よくある質問に関するQ&Aが満載.菌血症を疑ったとき,何をしたらいいのか,何を考えたらいいのかがわかる一冊.

産婦人科の実際 Vol.72 No.12
2023年11月臨時増刊号
婦人科悪性腫瘍手術―トラブルシューティングとその予防法―
合併症はなぜ起こる?どう防ぐ?起こったらどう対処する? 現時点の「最適解」を伝授!
婦人科悪性腫瘍手術―トラブルシューティングとその予防法―
合併症はなぜ起こる?どう防ぐ?起こったらどう対処する? 現時点の「最適解」を伝授!
今回の臨時増刊号では,婦人科手術のエキスパートの先生がたに,術中・術後合併症の予防法や,術中に発生したトラブルへの対処方法をわかりやすく解説いただきました。手術の達人たちが長年の経験をもとに術中偶発症や術後合併症の要因を検証し,試行錯誤してたどり着いた対策法は,現時点での「最適解」です。その「最適解」を身につけ,患者さんにとっても術者にとっても安心で安全な手術を行うことを目指す,婦人科医必携の一冊です。

ナースのためのレポートの書き方 第2版
看護の実践・教育に長く携わってきた著者が、現場で求められる、伝わる文章のルールと知識を伝授。会議録や研修報告書等の書き方を、例示等を用いて解説する。第2版では、学会発表等で必須のPower Pointによるスライド作成のコツも収載。自己学習や研修会・勉強会に最適。

チャイルドヘルス Vol.26 No.12
2023年12月号
【特集】小さく生まれた赤ちゃん〜NICUを退院したあと〜
【特集】小さく生まれた赤ちゃん〜NICUを退院したあと〜
NICU退院後の赤ちゃんには,どんなことが必要でしょう?
エキスパートの先生方に解説いただいた本特集で,ぜひ日本の新生児医療のいまを知ってください!

看護にいかす文献検索入門
学び続けるための情報探索スキル
看護に必要な学術情報を効率的に検索・入手するための考え方とノウハウを、看護学生、大学院生、臨床看護師それぞれのケースで紹介。実際の文献データベースの検索画面を使いわかりやすく解説した。看護情報学のテキスト、またはレポートや学会発表の参考書として活用できる。

CLINICAL NEUROSCIENCE Vol.41 No.12
2023年12月号
【特集】脳の進化―多様性と可能性
【特集】脳の進化―多様性と可能性 ヒトの脳は極めてよく発達して高次の精神機能を実現しています.一方で動物界の脳の多様性を視野に入れると,進化がヒトの脳という頂点を目指して進んできたかのような単純化した見方がそぐわないことは明らかです.我々の脳が進化の過程でどのように形成されてきたか,遺伝子研究から化石研究まで幅広い基盤に立って脳を多様性の観点から捉え直し,異なるタイプの脳が生む機能の可能性やヒトの特殊性について探求する特集です.

≪PT・OTビジュアルテキスト専門基礎≫
解剖学 第2版
運動器系を中心とした解剖学をPT・OT目線で丁寧に解説.第2版では令和6年版の国家試験出題基準に対応.筋触察や章末問題も追加し,さらに学びやすく.解剖学の基礎を学び直したい医療従事者にもオススメ.
