
臨床雑誌外科 Vol.85 No.11
2023年10月号
肝門部胆管癌の治療戦略update
肝門部胆管癌の治療戦略update 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨床作業療法NOVA Vol.20 No.2
2023年夏号
【特集】脳卒中人生を生ききる勇者たちと作業療法
【特集】脳卒中人生を生ききる勇者たちと作業療法
脳卒中を受症したら、どういう経過をたどり、どのように身体・生活は変わるのか。長いスパンで明らかにしておくことは、当事者、家族、作業療法士をはじめとするセラピストにとって重要な意味をもつ。
本書は、脳卒中の疫学と予防を解説し、脳卒中者とともにつくりあげてきた地域リハの歴史と実践が語られる。また、退院後、長期にわたる心身機能・活動&参加・環境・個人の変化と推移にも言及される。臨床経験のから得られた経験知、文献知、そして調査のなかから得られたエビデンスなどが理解できる。
臨床に関わるリハスタッフは、「身体は今後、よくなるのか」「どのような生き方ができるのか」など、脳卒中者からよく尋ねられる。それに対して、適切な受け答えができる内容が盛り込まれている。

臨床画像 Vol.39 No.10
2023年10月号
【特集】特集1:まれに出会うと悩ましい 膝・足の疾患/特集2:顔面骨骨折の画像診断
【特集】特集1:まれに出会うと悩ましい 膝・足の疾患/特集2:顔面骨骨折の画像診断

≪作業療法学 ゴールド・マスター・テキスト≫
地域作業療法学 改訂第2版
作業療法学専門分野の講義用テキスト・シリーズ。これからの学生に役立つ内容を意識し,能動学習の手助けとなる課題の提示,新しい実習形式である「作業療法参加型臨床実習」への対策となるような解説を追加し,また国家試験対策を充実させ,さらに巻末付録として事例集も追加。
本巻では,改訂にあたって全体を精査して掲載情報をアップデートした上で,地域での小児ケアの内容を充実させ,また昨今注目を集める就労支援について追加を行った。

消化器内視鏡35巻2号
上部消化管内視鏡のトラブルシューティング
上部消化管内視鏡のトラブルシューティング

腎と透析94巻2号
バスキュラーアクセスUpToDate
バスキュラーアクセスUpToDate

動画&イラスト&写真でわかる眼瞼手術の極意
【眼科・形成外科・美容外科の視点と技を伝授】眼瞼手術を受ける患者は視機能の改善だけでなく「きれいに美しく治してほしい」という整容的な要望も強い。そのため、術者には患者満足度の高い手術が求められる。眼瞼下垂手術を中心に主要な眼瞼手術を取り上げ、基本やコツ、トラブル時の対処、患者説明のポイントを解説!

≪眼科グラフィック 2023年増刊≫
外来処置・小手術で求められる手技のコツとこだわり
【より確実で効果的な処置&小手術がわかる!】日々の外来における処置や小手術を徹底解説した眼科医必携の一冊。前置レンズの使い方など知っておきたい基本知識はもちろん眼瞼、結膜、角膜、涙道、緑内障、外眼部、斜視、外傷における手技&こだわりも押さえられる!

≪脳神経外科速報 2023年増刊≫
二刀流術者のための脳血管障害手術テキスト
【ハイブリッド手術を支える知識と技術を解説】脳血管障害手術の二刀流術者となるための必要なトレーニング、解剖、機器・デバイスの知識や手術のテクニックを解説。また、二刀流術者を育てるチーム運営や教育についても紹介。エキスパートが求めるベースライン・指標を知ることで、実践につなげる。
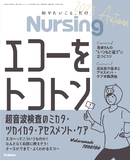
Nursing Vol.43 No.6(2023年秋号)
【特集】【1】エコーをトコトン! 超音波検査の見方・使い方・アセスメント&ケア【2】患者さんの「いつもと違う?」に気づくコツ
【特集】【1】エコーをトコトン! 超音波検査の見方・使い方・アセスメント&ケア【2】患者さんの「いつもと違う?」に気づくコツ 臨床現場でのさまざまな疑問や困ったことに、根拠と実践的な視点を織り込みながら、よりよい方法を示す看護総合雑誌!いま知りたい臨床の課題など今日から床現場で使える基本・ワザ・コツを網羅!

産業保健看護職・産業医・衛生管理者のための職場診断マニュアル
【職場が具体的に分析できる&変えていける!】行政保健師においては地域診断モデルが確立され一般化されているのに対し、産業保健分野においては職場診断モデルが確立されておらず、体系的には実施されていない。そこで、企業全体あるいは各部署のアセスメントを適切に行うことができる職場診断方法を作成した。本書を活用することで、職場の課題やウェルネスが「見える化」し、より具体的なアプローチにつなげることができる。

主訴から攻める初期対応
【適切なコールと対応が音声で学べる!】急変時には、見逃してはいけない疾患を示唆する症状・所見を評価し、最悪の病態を予測して行動することが大切。本書では主訴ごとに、急変時の観察項目をリスト化して解説。急変コール音声付きのシナリオで、初期対応のポイントや適切なコンサルトを学べる。病棟ナースの急変トレーニングがこれ1冊でばっちり!
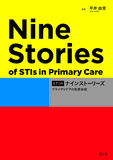
STIのナインストーリーズ
プライマリケアの性感染症
プライマリケアで遭遇しうる梅毒,HIV,淋菌・クラミジアといった9つの代表的な性感染症について,問診から診察,検査,診断,治療,フォローアップ,医療費の目安,専門施設への紹介のタイミング,本人への説明まで,実践的な内容を具体的な症例を提示しながら解説.初めて性感染症の診療を行う医師でも慌てることがないよう,Minimal EssentialsとTimelineも提供.近年増加傾向にある性感染症の慢性化・難治化やさらなる蔓延を防ぐために,プライマリで臨床を行う医師にとって必携の一冊.
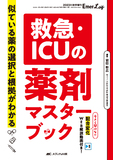
≪Emer Log2023年秋季増刊≫
救急・ ICUの薬剤マスターブック
【薬剤の“知ってるつもり”から脱却!】救急・ICUの症例を挙げ、複数の候補からどの薬剤をチョイスするかを、根拠にもとづき解説。臨床をイメージしながら、組み合わせの禁忌や、副作用などを学べる。薬物動態など、薬剤の基礎知識もしっかり収載。自信を持って患者さんを看たい、後輩を教えたいナースに向けた1冊。

院内医療事故調査の指針 第3版
【医療事故調査制度を改めて正しく理解する】2015年に施行された医療事故調査制度だが、今なお、本制度を正しく解釈しない、不適切な対応をしている病院が多い。今改訂では、参考として編著者施設における死亡症例管理システムを紹介、医療法改正に伴う制度改正や、定義が混乱している用語を整理した。

フットケアはじめてBOOK
【基本・手技・在宅ケアが写真でよくわかる!】フットケアにかかわる解剖やさまざまな病変、診療報酬、チーム医療にはじまり、問診、視診、触診、評価方法などのポイントまで、フットケアの基本を1冊に凝縮。病診連携、在宅ケアなどで求められる退院準備・セルフケア指導の内容をさらに充実させている。

妊産婦の生活と育児に寄りそうメンタルヘルスケア
【セルフケア看護モデルで10の事例を解説】妊産婦の生活と育児のセルフケア評価項目をまとめた「ひとめでわかるアセスメント表」を用いて、精神的問題を持つ妊産婦の支援に役立つ観察の視点、介入方法をわかりやすく解説する。看護職が「これでいいんだ!」と自信を持って支援できるようになるための一冊。
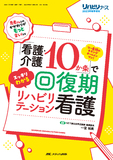
≪リハビリナース 2023年秋季増刊≫
「看護・介護 10 か条」でスッキリわかる 回復期リハビリテーション看護
【回復期リハ病棟で目指すケアがこの1冊に!】回復期リハビリテーション病棟協会が掲げる「看護・介護10か条」に沿って、必要な支援の実際と、支援の評価方法を解説する。本書の狙いは、退院後に患者さんが望みどおりの生活を送ることを目標に、リハ看護師が患者・家族を支援できるようにすることである。

改訂2版 リウマチケア入門
【リウマチ患者さんと共に歩むケアガイド】国内外のガイドライン改訂に合わせて内容を大幅にアップデート。新薬の登場など進歩の著しい関節リウマチ診断治療の基本知識、共有意思決定(SDM)がもたらした患者支援の変化、病院から地域へと広がる多職種連携のあり方など、近年のリウマチケアの潮流がこの一冊ですべてわかる。
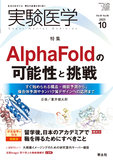
実験医学 Vol.41 No.16
2023年10月号
【特集】AlphaFoldの可能性と挑戦
【特集】AlphaFoldの可能性と挑戦 構造生物学に革命をもたらしたAI「AlphaFold」は何ができて何ができないのか?Webですぐに活用する方法や,AI時代の研究戦略を解説/膨大な研究データを保管するためのラボ内サーバー構築ノウハウ
