
薬剤師力がぐんぐん伸びる 専門医がやさしく教える 慢性腎臓病フォローアップの勘所
腎障害を示す所見や腎機能低下が慢性的に続く状態である慢性腎臓病(CKD)。我が国には約1330万人のCKD患者がいるとされ(2011年時点)、中でも80歳台では2人に1人と、超高齢社会を迎え患者数は右肩上がりに増えています。CKD患者は末期腎不全や心血管疾患のリスクが高く、放置すれば人工透析の導入や心筋梗塞・脳卒中を来し得ることから、発症・進展を防ぐことが欠かせません。早期発見には定期的な健診が重要だが、加えて進展予防には、糖尿病や高血圧など生活習慣病の管理が重要になります。
本書は、こうしたCKD患者に外来で日々対応している薬局薬剤師向けに、患者フォローアップに必要な知識をまとめた解説本です。
現状、薬局薬剤師は「腎機能が低下している患者」と聞くと、腎機能に応じて投与量の変更を要する薬剤が多いことから、薬(処方内容)のチェックに注力しがちです。しかし、患者の重症化予防を考えた時、それだけでは不十分であり、腎機能が低下した患者の薬物療法を、食事・運動などの生活習慣も含めて適切に管理していく視点が求められます。
折しも、2019年の医薬品医療機器等法(薬機法)改正により、薬剤師による服薬後フォローアップおよび医師への情報提供が義務化されました。薬を手渡すまででなく、薬を交付した後も、さらにもう一歩踏み込んで患者をサポートする役割が求められ、そのための知識習得が欠かせなくなっています。
本書は、CKD患者に対応する上で必要な知識を、「基礎編」「管理・指導編」「カンファレンス編」に分けて解説。腎臓専門医が最新の知見を基に、難しい話をやさしく解説します。2023年6月に改訂された日本腎臓学会「エビデンスに基づくCKD診療ガイドライン2023」にも対応しており、読みやすく、明日からの業務にすぐ役立つ内容となっています。「腎機能をこれ以上悪くさせないためには」「透析導入の期間を遅らせるには」「CKD患者の心血管イベントリスクを減らすには」――。目の前の腎臓が悪い患者に何ができるか、どう関わっていけばいいかを考える、現場の第一線で働く薬剤師必携の1冊です。

看護ケアのための便秘時の大腸便貯留アセスメントに関する診療ガイドライン
看護研究成果を臨床実践に還元することを目的に作成された日本看護科学学会によるガイドライン.Minds診療ガイドライン作成マニュアル2020に準拠.病院・療養施設・在宅の場で重要な,大腸便貯留による排便障害に伴う苦痛のアセスメントや看護ケアについて,臨床上の疑問をCQ(clinical question)で表し,それぞれのエビデンスと推奨度の強さを提示した.排便に関するニードを適切に訴えられない成人・高齢者において,早期に適切な排便ケアを行うことを導く1冊.
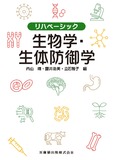
リハベーシック 生物学・生体防御学
リハ学生のために「生物学」「生体防御学」の専門家がやさしくレクチャー!
●教養・基礎科目から専門科目へつなげるPT・OT・ST向けの新しいテキストシリーズ!
●リハ学生のために「生物学」「生体防御学」の専門家がわかりやすく書き下ろした入門テキスト!
●生物学に苦手意識をもつ学生さんでも,国家試験や臨床へのつながりを感じながらポイント図解で楽しく学べる1冊.
●2~8章では生物学の概要を,9~14章では生体防御学の概要を解説している.
●【講義1コマで学ぶテーマ4つ】×【各テーマ見開き2頁】=【1コマ合計8頁】
●授業に適したコンパクトなボリュームで解説し,要点をしっかり学習できる!
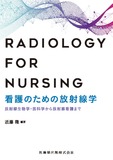
看護のための放射線学 放射線生物学・医科学から放射線看護まで
看護職にとって必要不可欠な放射線の知識を網羅した決定版テキスト!
●放射線医学の発展や原子力災害を背景に,放射線への正しい理解が看護職にもいっそう求められる中で,必要な知識を網羅した最新テキストです.
●第1章~第4章では,放射線の基礎知識から,細胞レベルの作用,各臓器への健康影響まで,基礎となる内容を噛み砕いて説明しています.
●第5章~第8章では,放射線防護の法令や原則とリスクコミュニケーション,診断・治療のそれぞれから見た放射線の医学利用,原子力災害まで,臨床的な内容を扱っています.ここでは章の前後半を知識編・看護編に設定し,特に看護職の役割が大きい核医学検査や小線源治療,内用療法などについては,治療の流れから患者説明の留意点まで,実際の看護を明らかにしています.
●理解を助けるコラムを随所に盛り込んだほか,章の冒頭には到達目標を明示し,末尾には要約内容を列挙した「本章のまとめ」を付すなど,教えやすく学びやすい内容を指向しました.

胃と腸 Vol.58 No.9
2023年 09月号
主題 知っておくべき口腔・咽喉頭病変
主題 知っておくべき口腔・咽喉頭病変 消化管の形態診断学を中心とした専門誌。毎月の特集では最新の知見を取り上げ、内科、外科、病理の連携により、治療につながる診断学の向上をめざす。症例報告も含め、消化管関連疾患の美麗なX線・内視鏡写真と病理写真を提示。希少疾患も最新の画像で深く学べる。 (ISSN 0536-2180)
月刊、増大号2冊を含む年12冊

総合リハビリテーション Vol.51 No.9
2023年 09月号
特集 これからの訪問リハビリテーションはどうあるべきか
特集 これからの訪問リハビリテーションはどうあるべきか リハビリテーション領域をリードする総合誌。リハビリテーションに携わるあらゆる職種に向け特集形式で注目の話題を解説。充実した連載ではリハビリテーションをめぐる最新知識や技術を簡潔に紹介。投稿論文の審査、掲載にも力を入れている。5年に一度の増大号は手元に置いて活用したい保存版。
雑誌電子版(MedicalFinder)は創刊号から閲覧できる。 (ISSN 0386-9822)
月刊、年12冊

臨床皮膚科 Vol.77 No.10
2023年 09月号
さまざまな症例や治療成績が全国から寄せられる原著系皮膚科専門誌。写真はオールカラーで、『臨床皮膚科』ならではのクオリティ。注目の論文は「今月の症例」として、編集委員が読み処のアドバイスを添えて掲載する。増刊号「最近のトピックス」は、知識を毎年アップデートできる定番シリーズ。 (ISSN 0021-4973)
月刊、増刊号を含む年13冊

医学のあゆみ286巻13号
美容医療の現状における問題点と解決への取り組み
美容医療の現状における問題点と解決への取り組み
企画:朝戸裕貴(獨協医科大学形成外科学教室)
・近年,美容医療は分野の拡大や新医療機器の出現により,一般への普及も進む一方で,未承認の機器や製剤を用いた治療による重篤な合併症の出現も後を絶たず,医療安全上の問題も種々指摘されている状況である.
・美容医療によって外見を改善することは心理的好影響をもたらし,人々の生活をより豊かにすることに寄与していることは事実で,美容医療がより安全で安心なものとなることは,医療界全体にとって重要な意義を持つ.
・本特集では美容医療の現状分析と課題解決に向けた取組を,各専門家および関連学協会の立場から歴史的経緯も含め解説いただく.本特集が美容医療への理解を深め,安全安心な美容医療の推進につながれば望ましい.

ST CHECK!
言語聴覚士国家試験必修チェック2024最新対策版
分野別要点マスター
20年以上にわたり養成校で国試後に改訂を重ねながら使われてきたチェックリストをベースに,内容を整理しコンパクトで覚えやすい構成にリニューアル.言語聴覚士を目指す全ての受験者に推薦したい一冊.■2024年版の特長 ・過去5年分(第21回~第25回)の頻出キーワードをマークで表示 ・「出題基準」の大項目に準じた項目立て ・養成校の教員による効果的な学習方法の紹介

産科と婦人科 Vol.90 No.10
2023年10月号
【特集】血栓に強くなる―産婦人科診療に活かす最新知識―
【特集】血栓に強くなる―産婦人科診療に活かす最新知識―
血栓は産婦人科診療に深く関わります.たとえば,妊娠はVirchowの3徴のうち血流うっ滞と血液凝固性亢進を満たし,静脈血栓症のリスク因子であったり,がんも血栓のリスクを孕んでいたり,OC・LEPの副作用としても要注意です.
本号では,血栓の形成機序や関連薬剤の薬理,血栓・凝固系の診断と評価,血栓性素因,血栓がかかわる病態の管理,関連薬剤を使用する際の留意点など,基礎から臨床まで幅広くご解説いただきました.

小児科 Vol.64 No.9
2023年9月号
PICU―小児集中治療室の今
PICU―小児集中治療室の今
小児科医であれば誰でも、何らかの“小児集中治療”の経験はあるのでしょうが、NICUやICUとの異同も含めて、PICUは、実はイメージの湧きにくいテーマかもしれません。時の流れとともに変化するPICUの使命や課題、呼吸器・循環器・神経系など個々の専門領域や、多様な背景を持つ医師のキャリアなど、PICUに直接携わらない小児科医に知っていただきたいことをまとめました。

看護学生のための精神看護技術 第1版
精神看護の基盤となる理論から、病院内で安定を促す看護、病院から社会への移行を整える看護、社会における自律を支える看護について、その援助に必要な理論と技術をまとめた。

わかるから楽しい解剖生理 テーマ50 第1版
「はたらく細胞」の細胞博士、鈴川茂先生が、「解剖生理は苦手です。」という看護学生のための救済書を発行。鈴川先生が普段行っている本当にわかりやすい講義を書面で再現。これで勉強すれば解剖生理が楽しくなる。
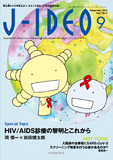
J-IDEO (ジェイ・イデオ) Vol.7 No.5
2023年9月号
【Special Topic】HIV/AIDS診療の黎明とこれから
【Special Topic】HIV/AIDS診療の黎明とこれから HIV/AIDS診療は新たな治療薬も登場し,いま,大きな変革期を迎えています.日本のHIV感染症診療・臨床研究を長年牽引してこられた岡 慎一先生をお招きし,HIV/AIDS診療の黎明期から現在までの道のり,今後の展望,ゼロエイズへの見通しについて,岩田健太郎先生と語っていただきました.HOT TOPICは「入院前の全患者にSARS-CoV-2スクリーニング検査を行う必要があるのか?」です.

皮膚科の臨床 Vol.65 No.10
2023年9月号
薬疹
薬疹
豊富な症例論文と多彩な連載記事で目と心を養う皮膚科の専門誌。今回の特集テーマは「薬疹」です。Stevens-Johnson症候群,中毒性表皮壊死症(TEN),薬剤性過敏症症候群など,さまざまな薬疹の症例報告をまとめました。薬疹の“動向”を捉える一冊になっています。エッセイ『憧鉄雑感』などの人気連載も掲載中!
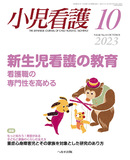
小児看護2023年10月号
新生児看護の教育;看護職の専門性を高める
新生児看護の教育;看護職の専門性を高める 新生児集中治療室(NICU)に入院する子どもたちは、誕生直後から集中治療・ケアを必要とし、長期間にわたって家族から離れた入院生活を送っている。子ども本人には予備力がないため、集中治療・ケアを必要とする時期は、看護職の感覚を研ぎ澄ます観察や技術に委ねられる。本特集は、新生児看護に関する教育の現状を紹介することで、小児看護に携わる人たちが自分の専門性を培う方略を考える機会を提供していく。

産婦人科の実際 Vol.72 No.9
2023年9月号
図解 産婦人科医のための臨床遺伝学必修知識Ⅱ
図解 産婦人科医のための臨床遺伝学必修知識Ⅱ
実臨床に役立つ知識や技術をわかりやすく丁寧に紹介する産婦人科医のための専門誌です。面白くてためになる,産婦人科の“実際”をお届けします。
今回の特集テーマは臨床遺伝学。臨床遺伝の分野は日進月歩に進化している一方で,産婦人科医が臨床遺伝に関する新しい知見を横断的に学ぶ機会は少ないのが現状です。本特集では,急速に進む遺伝情報の詳細化と分野の拡大に対応し,初学者でもすぐに診療につなげることができるよう図解でわかりやすく解説しました。

眼科 Vol.65 No.9
2023年9月号
変わりつつある網膜剥離の常識
変わりつつある網膜剥離の常識
トピックス、診療のコツ、症例報告、どこから読んでもすぐ診療に役立つ、気軽な眼科の専門誌です。今月の特集は「変わりつつある網膜剝離の常識」と題し、眼科医なら是非抑えておくべき網膜剝離の「常識」5つについて、基礎知識のおさらいと最新の知見の解説をいただきました。その他、角膜疾患の泰斗・西田輝夫先生からのメッセージや綜説3本、画像診断の連載に投稿論文2本、京都眼科学会の抄録も掲載。是非ご一読ください。

臨牀消化器内科 Vol.38 No.11
2023年10月号
消化管出血のマネジメントが変わっている?-最新情報と診療の実際
消化管出血のマネジメントが変わっている?-最新情報と診療の実際
本特集では、日常診療で遭遇することの多い「消化管出血」をテーマとして取り上げ、疫学から診断手順、疾患別の治療ストラテジーについて、最新情報と診療の実際を詳しく解説していただいた。

≪マスト&ベスト/ミニマム≫
フィジカルアセスメントで追いつめる!
リウマチ・膠原病診療マスト&ベスト
本書は,フィジカルアセスメントや病歴聴取をしっかり行って,関節の痛みや臓器障害から,➀リウマチ・膠原病を疑い,そして適切な検査をして,➁リウマチ・膠原病を診断することの2本柱で構成となっています.
また,リウマチ・膠原病疾患に苦手意識のある若手医師や非専門医がリウマチ・膠原病疾患の疑いのある患者を診る際に,スムーズに診断まで進められるアプローチの方法など,すぐに役立つ知識がちりばめられています.
