
ICUとCCU 2023年6月号
2023年6月号
特集:集中治療における診療報酬改定を読み解く
特集:集中治療における診療報酬改定を読み解く

泌尿器外科 2023年6月号
2023年6月号
特集:過活動膀胱 up to date 2023
特集:過活動膀胱 up to date 2023

虫垂炎を読み解く
たかがアッペン、されどアッペン
身近によくみる疾患でありながら,いまだわかっていないことも多い謎多き疾患でもある虫垂炎について,さまざまな見地より考察を加える本邦唯一の専門書.虫垂のはたらき,病因や疫学,治療選択や切除術の実際など,虫垂炎に関するあらゆる情報を盛り込んだ著者渾身の一冊です.

看護 Vol.75 No.9
2023年7月号
特集1 災害・新興感染症に対応する 新たな災害支援ナース
特集1 災害・新興感染症に対応する 新たな災害支援ナース
2022年12月、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取り組みを踏まえ改正感染症法が制定されました。
このうち最も大きな改正内容の1つが、災害発生時や感染症発生・まん延時における医療人材派遣等の調整の仕組みが設けられたこと。これを受けて、日本看護協会は、新たな災害支援ナースによる応援派遣体制の仕組みを構築することとなりました。
本特集では、わが国の自然災害や新興感染症発生時における医療体制の備えについて紹介した上で、過去の自然災害やコロナ感染拡大時に看護職がどのような役割を発揮してきたかを振り返り、新たな災害支援ナースによる応援派遣体制の仕組みを解説。さらに、2023年度より始まる「災害支援ナース養成研修」の概要を示します。
特集2:
看護職への役割移行支援
看護職にとって大きな困難を伴う役割移行としては、看護学生から看護職への移行、スタッフから管理職への移行があります。また、文部科学省がキャリア教育を推進し始めたころに初等中等教育を受けていたのが現在の20代後半であり、この2つの移行期にある看護職は、それ以前の世代の看護職とは異なるキャリア教育を受けてきたことになります。
特集2では、現在の看護学生や若手看護職員がどのようなキャリア教育を受けてきているかを概観した上で、そのような新人を迎えて1人前のナースに育成し、さらにジェネラリスト、スペシャリスト、管理職へと役割移行をしていく過程で生じる困難、それを乗り越えるために必要な支援を示します。

消化器外科腹腔鏡手術 免許皆伝
エキスパートから学ぶ技術認定取得のための3つのポイント
日本内視鏡外科学会(JSES)の技術認定医試験合格のための必読書!
技術認定審査で評価の対象となる手技・項目,各臓器別の審査のポイント,「不合格」となる手技について,実際の動画を使って臓器ごとにエキスパートがわかりやすく解説した1冊.試験が終わってからもスキルアップに役立つ,内視鏡・腹腔鏡手術のエキスパートを目指す若手消化器外科医のための最強の1冊.

臨牀透析 Vol.39 No.8
2023年7月号
腹膜透析の展開-生き残りをかけた在宅医療
腹膜透析の展開-生き残りをかけた在宅医療
本特集では,近年の腹膜透析の新たな展開- インクリメンタルPD,PD+HD併用療法,assisted PD などを紹介している.各論文には執筆者の,透析医療への熱い思いが溢れている.本誌を手にした方々,是非,本特集を一読し,新時代が到来していく事実を認識していただきたい.
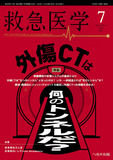
救急医学2023年7月号
外傷CTは“何のトンネル”だ?
外傷CTは“何のトンネル”だ? ハード・ソフト両面の進歩が著しい外傷診療におけるCT検査。でも、一歩間違えれば“死のトンネル”なのは変わらない。CTを“生へのトンネル”とするために必要な適応の考え方、撮影の工夫、診療体制などをじっくり考えよう。

消化器外科2023年7月号
ロボット大腸癌手術のすべて
ロボット大腸癌手術のすべて 2022年4月の診療報酬改定で、大腸癌に対するロボット支援下手術は今後さらなる広がりが期待される。本特集では大腸癌に対するロボット支援下手術を安全に行うためのKnack and Pitfallを先進施設の先生方にご解説していただいた。

ケースから学ぶ 高齢者ケアにおける介護倫理 第2版
高齢者ケアにおける倫理的問題について,倫理と法律の専門家がわかりやすく解説した好評書が改訂!
●高齢者ケアにおける倫理的問題に対して“気づき”をもつための基礎となる倫理的・法的基礎知識を,11の臨床事例を通してわかりやすく解説した好評書が改訂!
●第2版では,〈認知症ケアの倫理〉〈蘇生不要(DNAR)指示〉〈アドバンスケアプランニング(ACP)〉〈POLST(DNAR指示を含む)〉に関する項目をあらたに収載した.

診断と治療 Vol.111 No.7
2023年7月号
【特集】食道癌・胃癌・大腸癌,最近の診療を知る
【特集】食道癌・胃癌・大腸癌,最近の診療を知る
急速に進歩する消化管癌の診断と治療について,検診や画像診断,外科手術,化学療法,集学的治療,内視鏡AI診断などをわかりやすく解説しました.

脊椎脊髄ジャーナル Vol.36 No.5
2023年5月号
■特集
脊髄および末梢神経鞘腫瘍のすべて

医学のあゆみ286巻2号
オキシトシンの向精神作用と精神疾患治療応用への展望
オキシトシンの向精神作用と精神疾患治療応用への展望
企画:門司 晃(慈光会若久病院院長)
・近年,オキシトシンは下垂体後葉だけでなく脳内の他の部位でも分泌されることが判明し,分泌されたオキシトシンは扁桃体や大脳皮質などにおいて作用し,抗ストレス作用,摂食抑制作用などを示すことが明らかになった.
・オキシトシンをヒトに経鼻投与する実験により金銭取引で相手との信頼関係を高めることがわかり,精神科領域においては,自閉スペクトラム症(ASD)の社会行動障害を改善する効果が期待されている.
・本特集では,オキシトシンの神経機能解剖学,抗炎症作用,精神科領域(統合失調症,ASD,知的・発達障害,高齢者など)での向精神作用や課題に関して,各分野での第一人者にそれぞれの研究を紹介していただく.

精神看護 Vol.26 No.4
2023年 07月号
特集 ストレングスがあふれるアクティビティ プログラムの作り方&そのまま使える盛り上がりネタ集
特集 ストレングスがあふれるアクティビティ プログラムの作り方&そのまま使える盛り上がりネタ集 「地域」へ向けて、本格的な変革期に入る精神科領域。大きな時代の流れも見据えつつ、自分の仕事も楽しんでいきましょう。この雑誌にはワクワク情報がいっぱいです。 (ISSN 1343-2761)
隔月刊(奇数月)、年6冊

訪問看護と介護 Vol.28 No.4
2023年 07月号
特集 失敗する前に教えてほしかった……! 訪問看護に来ていきなり必要になる看護技術
特集 失敗する前に教えてほしかった……! 訪問看護に来ていきなり必要になる看護技術 「在宅」の時代、暮らしを支える訪問看護師に、情報とパワーをお届けします。制度改定の情報やケア技術はもちろん、「気になるあの人/あのステーションがやっていること」を取材。明日の仕事に活かせるヒントが見つかります。 (ISSN 1341-7045)
隔月刊(奇数月)、年6冊

病院 Vol.82 No.7
2023年 07月号
特集 病院リハビリテーションの進化
特集 病院リハビリテーションの進化 「よい病院はどうあるべきかを研究する」をコンセプトに掲げ、病院運営の指針を提供する。特集では、病院を取り巻く制度改正や社会情勢の読み解き方、変革に対応するための組織づくりなど、病院の今後の姿について考える視点と先駆的な事例を紹介する。 (ISSN 0385-2377)
月刊、年12冊

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.95 No.8
2023年 07月号
特集 真菌症 知っておきたい診療のポイント
特集 真菌症 知っておきたい診療のポイント 目のつけ処が一味違う耳鼻咽喉科・頭頸部外科専門誌。「こんなときどうする!?」などの臨床的なコツの紹介から、最新の疾患概念を解説した本格特集まで、硬軟とり混ぜた多彩な企画をお届けする。特集2本立ての号も。「Review Article」欄では研究の最前線の話題をわかりやすく解説。読み応えのある原著論文も多数掲載。 (ISSN 0914-3491)
月刊、増刊号を含む年13冊

臨床眼科 Vol.77 No.7
2023年 07月号
特集 第76回 日本臨床眼科学会講演集[5]
特集 第76回 日本臨床眼科学会講演集[5] 読者からの厚い信頼に支えられた原著系眼科専門誌。厳選された投稿論文のほか、眼科領域では最大規模の日本臨床眼科学会の学会原著論文を掲載。「今月の話題」では、気鋭の学究や臨床家、斯界のエキスパートに、話題性の高いテーマをじっくり掘り下げていただく。最新知識が網羅された好評の増刊号も例年通り秋に発行。 (ISSN 0370-5579)
月刊、増刊号を含む年13冊

臨床整形外科 Vol.58 No.7
2023年 07月号
特集 股関節鏡手術のエビデンス 治療成績の現状
特集 股関節鏡手術のエビデンス 治療成績の現状 整形外科医の臨床の質を高める情報を発信。一流の査読陣による厳正な審査を経た原著論文「論述」「臨床経験」「症例報告」などを収載。「特集」では話題のテーマを多面的に解説する。好評連載も。2020年から増大号がスタート! 運動器診療でいま知りたいことにフォーカスし、困った時の1冊、を目指します。 (ISSN 0557-0433)
月刊、増大号を含む年12冊

胃と腸 Vol.58 No.6
2023年 06月号
主題 分類不能腸炎(IBDU)の現状と将来展望
主題 分類不能腸炎(IBDU)の現状と将来展望 消化管の形態診断学を中心とした専門誌。毎月の特集では最新の知見を取り上げ、内科、外科、病理の連携により、治療につながる診断学の向上をめざす。症例報告も含め、消化管関連疾患の美麗なX線・内視鏡写真と病理写真を提示。希少疾患も最新の画像で深く学べる。 (ISSN 0536-2180)
月刊、増大号2冊を含む年12冊

総合診療 Vol.33 No.7
2023年 07月号
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー 広域に考え、狭域に始める
特集 “消去法”で考え直す「抗菌薬選択」のセオリー 広域に考え、狭域に始める ①独自の切り口が好評の「特集」と、②第一線の執筆者による幅広いテーマの「連載」、そして③お得な年間定期購読(医学生・初期研修医割引あり)が魅力! 実症例に基づく症候からのアプローチを中心に、診断から治療まで、ジェネラルな日常診療に真に役立つ知識とスキルを選りすぐる。「総合診療専門医」関連企画も。 (ISSN 2188-8051)
月刊、年12冊
