
最新理学療法学講座 小児理学療法学
授業づくりをアシスト!新テキストシリーズ始動
41本の付録動画で,学習をサポート.
●小児理学療法の現場を知る著者陣による,待望のスタンダートテキスト!
●スマホ・タブレットで視聴できる付録動画付き.これまで分かりにくかった反射・反応や子どもの動きが,ぱっと見て理解できる.
●これから理学療法士の関わりが期待されている発達性協調運動障害について,章をひとつ設けて詳述.
【シリーズコンセプト】
●4色カラー刷りのテキストで必要知識を視覚的に理解できる
●基本解説では理学療法士国家試験の出題内容をカバー
●実習や臨床に役立つ要素も充実
●15コマの授業で講義しやすい構成
●能動的に学べる課題を複数掲載

医師と患者は対等である
こんな時、患者とどう向き合えばよいのか。医師は患者の思いをどのように受け止め、どんな言葉を掛けるのか。対等な関係で共に歩むための医師・患者関係の処方箋。

看護研究 Vol.56 No.2
2023年 04月号
特集 若手研究者の活躍に向けて
特集 若手研究者の活躍に向けて 研究の充実がますます欠かせない時代。看護とは? 研究とは? という原点を見つめながら、変わらない知を再発見し、変わりゆく知を先取りしながら、すべての研究者に必要な情報をお届けします。誌面を通して、看護学の知と未来をともに築きたいと考えています。 (ISSN 0022-8370)
隔月刊(偶数月)、年6冊

検査と技術 Vol.51 No.6
2023年 06月号
若手臨床検査技師、臨床検査技師をめざす学生を対象に、臨床検査技師の「知りたい!」にこたえる総合誌。日常検査業務のスキルアップや知識の向上に役立つ情報が満載! 国試問題、解答と解説を年1回掲載。年10冊の通常号に加え増大号を年2回(3月・9月)発行。 (ISSN 0301-2611)
月刊、増大号2冊(3月・9月)を含む年12冊

臨床検査 Vol.67 No.5
2023年 05月号
今月の特集 脳脊髄液検査 その基礎と新しい展開
今月の特集 脳脊髄液検査 その基礎と新しい展開 「検査で医学をリードする」をキャッチフレーズに、特集形式で多領域をカバー。臨床検査にかかわる今知っておきたい知識・情報をわかりやすく解説する。連載企画も充実。年2回(4月・10月)、時宜を得たテーマで増大号を発行。 (ISSN 0485-1420)
月刊、増大号2冊(4月・10月)を含む年12冊

総合リハビリテーション Vol.51 No.5
2023年 05月号
特集 整形外科疾患の回復期リハビリテーション
特集 整形外科疾患の回復期リハビリテーション リハビリテーション領域をリードする総合誌。リハビリテーションに携わるあらゆる職種に向け特集形式で注目の話題を解説。充実した連載ではリハビリテーションをめぐる最新知識や技術を簡潔に紹介。投稿論文の審査、掲載にも力を入れている。5年に一度の増大号は手元に置いて活用したい保存版。
雑誌電子版(MedicalFinder)は創刊号から閲覧できる。 (ISSN 0386-9822)
月刊、年12冊

看護教育のためのオンライン活用エッセンス 【Web動画付】
授業・研修に使える仕掛け
オンライン教育は、もはや“トレンド”ではなく“メインストリーム”
今や対面と同じくらい重要になったオンラインでの教育。どちらが優れているかを議論する段階は終わり、いかに使いこなすかを先生方自身が検討し実践することが求められています。本書は、「知識を届ける」「思考・コミュニケーションを鍛える」「実践につなげる」「学びの効果(成果)を測る」という4つの教育のコアに焦点を当て、オンラインを使いこなすためのエッセンスを散りばめました。Web付録もお役立てください。

臨床皮膚科 Vol.77 No.5
2023年 04月号(増刊号)
最近のトピックス2023
最近のトピックス2023 さまざまな症例や治療成績が全国から寄せられる原著系皮膚科専門誌。写真はオールカラーで、『臨床皮膚科』ならではのクオリティ。注目の論文は「今月の症例」として、編集委員が読み処のアドバイスを添えて掲載する。増刊号「最近のトピックス」は、知識を毎年アップデートできる定番シリーズ。 (ISSN 0021-4973)
月刊、増刊号を含む年13冊

臨床婦人科産科 Vol.77 No.5
2023年 05月号
今月の臨床 産科救急 意識障害と危機的出血の初期対応
今月の臨床 産科救急 意識障害と危機的出血の初期対応 産婦人科臨床のハイレベルな知識を、わかりやすく読みやすい誌面でお届けする。最新ガイドラインの要点やいま注目の診断・治療手技など、すぐに診療に役立つ知識をまとめた特集、もう一歩踏み込んで詳しく解説する「FOCUS」欄、そのほか連載も充実。書籍規模の増刊号は、必携の臨床マニュアルとして好評。 (ISSN 0386-9865)
月刊、合併増大号と増刊号を含む年12冊
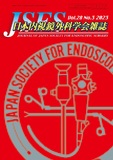
日本内視鏡外科学会雑誌 Vol.28 No.3
2023年 05月号
日本内視鏡外科学会の機関誌。1万4千人を超える学会員から寄せられた投稿論文を、厳正な審査を経て掲載する。隔年で全国の医療機関に対して実施されている「内視鏡外科手術に関するアンケート調査」の結果も掲載。掲載論文だけでなく、この調査のデータも多くのジャーナルで引用されている。 (ISSN 1344-6703)
隔月刊(奇数月)、年6冊、電子版のみ

胃と腸 Vol.58 No.5
2023年 05月号
主題 壁内局在からみた胃上皮下腫瘍の鑑別診断
主題 壁内局在からみた胃上皮下腫瘍の鑑別診断 消化管の形態診断学を中心とした専門誌。毎月の特集では最新の知見を取り上げ、内科、外科、病理の連携により、治療につながる診断学の向上をめざす。症例報告も含め、消化管関連疾患の美麗なX線・内視鏡写真と病理写真を提示。希少疾患も最新の画像で深く学べる。 (ISSN 0536-2180)
月刊、増大号2冊を含む年12冊

医学のあゆみ285巻8号
神経系リハビリテーションの新潮流――機能回復治療に革新をもたらす最新の知見
神経系リハビリテーションの新潮流――機能回復治療に革新をもたらす最新の知見
企画:川上 途行(慶應義塾大学 医学部 リハビリテーション医学教室)
・脳卒中などの中枢性疾患の後遺症に対する神経系リハは社会的なニーズも高く,身近なテーマであるが,この分野の最新の知見や未来への構想は,リハ科を専門とする者以外の医療者にとって理解を進めるのが難しい.
・本特集では,DX,AI,再生医療などリハ医療の仕組みや概念を変えうるテーマや,ロボティクス,BMI,磁気刺激などのニューロモデュレーションに関する最新知見をエキスパートがわかりやすく解説している.
・リハ治療は発症からの時期によって戦略を変えるものである.本特集の急性期と回復期という2 つの時期におけるリハのトピックスは,幅広い診療科の臨床の先生方にとって明日の診療に応用可能な内容となっている.

歴史から読み解く ワクチンのはなし
新たなパンデミックに備えて
私たちの命と健康を守るために欠かせないワクチンについて,ウイルス学の専門家がわかりやすく解説。〔内容〕感染症とは/ワクチンのメカニズム/ワクチンの礎を築いた先人たち/現在国内で用いられているワクチン/ワクチンの未来。
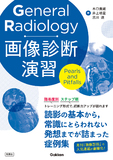
General Radiology画像診断演習
画像診断コンテスト世界チャンピオンなど,新進気鋭の著者らによる『画像診断』の人気連載から58症例を書籍化.
難易度別・ステップ別のトレーニング形式で,読者の読影力向上が図れる.
エキスパートの思考過程から学び,日常臨床に即した知識が身につく!
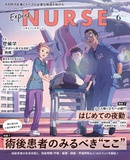
エキスパートナース Vol.39 No.7
2023年6月号
術後患者のみるべき“ここ” 術後患者の全身状態と術後管理(呼吸・循環・創部・疼痛管理など)のポイントを解説!
ナース独り立ちへの関門(患者観察、情報収集、報告・引継ぎ、夜勤後の過ごし方など)
術後患者のみるべき“ここ” 術後患者の全身状態と術後管理(呼吸・循環・創部・疼痛管理など)のポイントを解説!
ナース独り立ちへの関門(患者観察、情報収集、報告・引継ぎ、夜勤後の過ごし方など)

≪こころJOB Books≫
誰もが知っている「緊張」の、誰も知らないアセスメントとアプローチ
【身体と心の「緊張」を読みほぐす!】心の悩みはさまざまな形で身体や感情、対人関係に現れます。その1つが緊張です。緊張という1つの体の反応を中心に、BPSモデルをもとに、人(クライエントなど)の見立て・アセスメント、心理職による具体的なアプローチ法についてまとめました。日々のカウンセリングや援助に役立つ一冊です。
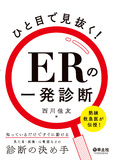
ひと目で見抜く!ERの一発診断
熟練救急医が伝授!知っているだけですぐに動ける、見た目・画像・心電図などの診断の決め手
救急外来でよく出会う『一発診断』症例を押さえて当直に備えよう!症状から見出すキーワード,注目すべき身体所見,画像所見など,熟練救急医が診断ポイントを伝授.初期対応や入院・帰宅の判断など次の一手も解説!

医学思想史―精神科の視点から
本書は医学思想(病気についての考え)の歴史をたどり、その変遷を通して現在の私たちがそれぞれ抱いている病気と治療についての考えを検証するとともに、現代医学が直面している諸問題−疾病観・治療観を考えようとするものである。
本書によって西洋近代に始まる身体医学中心の医学(思想)史は、精神医学の果たすべき役割を視野に入れて書き改められた。著者渾身の待望の書。

Quality Indicator 2022 [医療の質]を測り改善する
聖路加国際病院の先端的試み
18年にわたるQI活動の基盤は病院・管理者主導から現場主導へシフト。次世代の医療の質改善活動へ移行し始めた聖路加国際病院の試み、そしてこれから。
本書は、QIの測定・公表の先駆者たる聖路加国際病院における2004年から2021年までの18年間にわたるQIの経年変化、その間に行われた改善の試みを記した書籍の最新版です。
「医療の質」改善を目指す病院にとって手引きとなる一冊です。

産婦人科の実際 Vol.72 No.5
2023年5月号
生殖医療の保険適用の実際Ⅰ
生殖医療の保険適用の実際Ⅰ
2022年4月から生殖医療の健康保険適用が開始されました。この1年,臨床の現場では手探りで今回の制度改正に対応してきましたが,対応困難な事例や様々な問題点,疑問点が生じてきたことも事実です。本特集では,現段階での生殖医療にかかわる保険診療の実際についてわかりやすく解説しました。
