
生体の科学 Vol.74 No.2
2023年 04月号
特集 未病の科学
特集 未病の科学 生命科学・生物科学領域における最先端の研究を、毎号特集形式により紹介。神経科学はもとより分子生物学・酵素科学・栄養科学にいたる領域も含め、注目されるトピックテーマの最新情報を提供する。 (ISSN 0370-9531)
隔月刊(偶数月)、増大号を含む年6冊

理学療法ジャーナル Vol.57 No.4
2023年 04月号
特集 理学療法の2040年
特集 理学療法の2040年 理学療法の歴史とともに歩む本誌は、『PTジャーナル』として幅広い世代に親しまれている。特集では日々の臨床に生きるテーマを取り上げ、わかりやすく解説する。「Close-up」欄では実践的内容から最新トピックスまでをコンパクトにお届けし、その他各種連載も充実。ブラッシュアップにもステップアップにも役立つ総合誌。 (ISSN 0915-0552)
月刊、年12冊

精神医学 Vol.65 No.4
2023年 04月号
特集 わが国の若手による統合失調症研究最前線
特集 わが国の若手による統合失調症研究最前線 時宜にかなった特集、オピニオンを中心に掲載。また、臨床に密着した「研究と報告」「短報」など原著を掲載している。「展望」では、重要なトピックスを第一人者がわかりやすく解説。 (ISSN 0488-1281)
月刊、増大号を含む年12冊

BRAIN and NERVE Vol.75 No.4
2023年 04月号
特集 All About Epilepsy
特集 All About Epilepsy 脳・神経を基礎と臨床から追究する、MEDLINE 収載雑誌。『脳と神経』 『神経研究の進歩』 の統合誌として2007年に発刊。時宜をとらえたテーマを深く掘り下げる「特集」、新しい動向をキャッチアップする「総説」を中心に日々更新される神経学、神経科学の知見をわかりやすく紹介する。投稿論文も英語、日本語の両方で募集中。掲載論文はPubMedで検索が可能。 (ISSN 1881-6096)
月刊、増大号1冊を含む年12冊

医学のあゆみ285巻3号
頻尿に潜む病態を見破る
頻尿に潜む病態を見破る
企画:大家基嗣(慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室)
・泌尿器科の外来で最も多い主訴のひとつは頻尿である.典型的な膀胱炎症状を訴えられると診察は容易であるが,そうでない場合は患者の基礎疾患,内服薬,生活のスタイルなど問診すべきことは多岐にわたる.
・超高齢社会においてのcommon diseaseとして,前立腺肥大症と過活動膀胱があり,泌尿器科以外の医師が診療を行う機会が増えている.
・「たかが頻尿,と思うなかれ」が,本特集の大きなメッセージである.頻尿にはさまざまな病態が潜んでいるからである.悪性腫瘍が隠れていることもあり,膀胱癌と前立腺癌が代表である.

手術 Vol.77 No.4
2023年4月号
肥満症・糖尿病患者に対する減量・代謝改善手術
肥満症・糖尿病患者に対する減量・代謝改善手術
手術がうまくなりたい消化器・一般外科医のための専門誌。マニアックなほど深堀りした特集内容やビジュアルでわかりやすい手術手技の解説を特長とする。本号の特集テーマは減量・代謝改善手術。これまで“肥満外科手術”などと呼称されてきた領域であるが,その実施にあたっては,周術期(栄養)管理や合併症対応など,独自のノウハウをチーム医療として習得する必要があり,今回は手術手技以外の内容充実にも留意した構成とした。
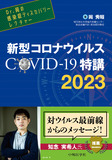
Dr.岡の感染症ディスカバリーレクチャー
新型コロナウイルス COVID-19特講 2023
大好評 新型コロナウイルス感染症特講の最新版!
5類にまもなく切り替わるが,現在の臨床像と診療はどのようになっているのか.ワクチン接種歴の有無で全く異なる重症化パターンに対応するために必要な知識,外来で多数みなければいけない軽症者診療で気を付けなければいけないことなど実際の症例を用いた誌上症例検討会で解説!現場で即使える活きた実践的知識がよくわかるCOVID-19診療のバイブル.

タイムマネジメントが病院を変える
―医療現場における働き方改革―
時間を慈しむ医師になろう
医療界においても働き方改革の機運が高まりつつある昨今,制度面の改革だけではなく,医療従事者側も「時間をコントロールし,時間に支配されない」というタイムマネジメントを身につけることが求められます.毎日時間に追われている,残業時間の多さが自慢,従来の評価制度に慣れきっている……そんな従来の価値観を刷新できる一冊です.巻末には元Googleのピョートル・フェリクス・グジバチ氏との対談を収録.

プライマリ・ケア看護学
小児期から成人期への移行支援
家族をケアユニットとした看護
近年の医療の進展に伴い,小児期発症の慢性疾患患者の入院期間は短縮傾向にあり,多くの子どもたちが外来通院を継続しながら地域社会で生活するようになった.本書は,小児期発症の慢性疾患に関する理解を深め,小児期から成人期への移行支援を実践できる能力を身につける,「プライマリ・ケア看護師」向けテキストである.

世界に飛びたて!命を救おう! グローバルヘルスを志す人 リーダーを目指す人のために
新型コロナパンデミック,戦争,地球温暖化,大規模災害など,世界が抱える保健医療上の課題は尽きません.本書はNGO,JICA,外務省,大学,UNICEF,グローバルファンドなどを通じて,世界130カ国以上を廻り,4大陸で生活しながらグローバルヘルスに従事してきた著者が,この分野で最初の一歩を踏み出す方法から,世界で活躍するリーダーになるための方法までを解説します.医療専門家はもとより,医療以外の分野でどのような活躍の場があるのか,どんなコンピテンシーが必要なのか,それをどのように獲得すればよいのか,どのようなコンパスを持ってライフデザインを作り航路を進めばよいのかなど,多くの方々からいただいた質問や相談を踏まえて多くの情報やアドバイスが含まれています.世界では活躍しているのに,日本では知られていない国際機関やNGO,シンクタンクなどの紹介もあります.著者本人やこの分野で活躍する友人・知人たちの実体験や知識に基づくリアルで役立つ情報満載の一冊です.

ひまはアスパーガール
発達障害母娘の15年
娘と母はタイプ違いの発達障害。悩みぶつかりながら互いに奮闘し成長する日常を、ちょっとコミカルに綴ったコミックエッセイ。
人はそれぞれ、親子もそれぞれ、家庭の事情もそれぞれ。でもこの娘と母の物語は、同じような子育て経験のある読者には共感を、子育て経験のない読者にも「普通」ではないことを否定しない大切さを、笑いを交えて伝えています。

愉しく食べる
食事に個別の配慮と援助を必要とするこどもさんとその家族の方へ
個別の配慮と援助が必要な子どもとその家族・援助者に向けて、愉しく食べるためのポイントをQ&Aで具体的に解説。
子どもの「自分で食べたいな」という気持ちを支援していくために、食事にまつわる注意点を「ミルクを飲んでいる頃」「食べること」「飲むこと」に分けてコンパクトにまとめた。
食べることを栄養学や医学的な観点からみるだけでなく、子どもが成長・発達する道筋を「学び」の過程として捉えるアプローチを提案する。

「日常言語」のリハビリテーションのために
失語症と人間の言語をめぐる基礎知識
これまで主として脳・神経科学的あるいは神経心理学的な機能研究によって理解が深められてきた失語症に対して、「日常言語」、すなわち人間のコミュニケーション行動を言語がどのような形で成立させているのかという観点から光を当てることによって、よりいっそうリハビリテーションの実践に近接した知識を提供。

言語機能系の再学習プロセスに向かって
失語症のリハビリテーションのために
コミュニケーション能力を支えている言語機能系の仕組みを解説し、言語の運用の仕組みを臨床に活用していく実践方法を紹介。
人間のコミュニケーション能力を支えている仕組みそのものに対するリハビリテーション治療のさらなる可能性を提言する画期的なテキスト。

食べることのリハビリテーション
摂食嚥下障害の多感覚的治療
脳-身体-道具の相互作用を考えながら、知覚・注意・記憶・判断・イメージ、それらのあり方を推測させてくれる言語との関連のなかで、食べることの多感覚性に目を向けて患者の病態を評価し、また治療に用いていく考え方と実際を紹介し、提案。
摂食嚥下治療の新しい可能性を探るセラピストにとって、見逃せない一冊。

この道のりが楽しみ
《訪問》言語聴覚士の仕事
自身も失語症当事者としての経験を持ち、地域密着で《訪問》言語聴覚士として在宅ケアを展開してきた著者が、これから訪問活動をめざす言語聴覚士へその意義と実際を伝える。
プロのカメラマンが著者の一日を追ったフォトドキュメント「今日もこの道を」も所収。

これだけは知っておきたい 糖質制限食のエビデンス
その糖質制限食、ちょっと待った!
糖質制限食に関する情報が氾濫しています.一見多大な効果をもたらすようにも見えますが、それらの情報は全て正しいといえるでしょうか? 医学論文をキャッチアップし続けている臨床医・研究者を除けば,たとえ医療従事者であってもそれらの情報の真偽を見極めるのは実は至難の業です.本書は糖質制限食に関する多数の研究結果(エビデンス)を平易に解説し,健康を維持しながら食生活を改善する方法を再考します.
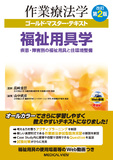
≪作業療法学 ゴールド・マスター・テキスト≫
福祉用具学(改訂第2版)[Web動画付] 改訂第2版
疾患・障害別の福祉用具と住環境整備
作業療法学専門分野の講義用テキスト・シリーズ。これからの学生に役立つ内容を意識し,能動学習の手助けとなる課題の提示,新しい実習形式である「作業療法参加型臨床実習」への対策となるような解説を追加し,また国家試験対策を充実させ,さらに巻末付録として症例集も追加した。
本巻では,改訂にあたって全体を精査して掲載情報をアップデートした上で,新たに「4章 住環境整備」「5章 トピックス」を追加。また「トピックス」では,作業療法の現場で広がる「情報通信技術(ICT)」「自動車運転補助装置」「3Dプリンター」「介護ロボット」などの新動向について項目を立てて追加した。近年の潮流および養成校指定規則改正によるアップデートを反映させた充実の改訂版。

ICUとCCU 2023年2月号
2023年2月号
特集:循環器集中治療と非心血管疾患
特集:循環器集中治療と非心血管疾患

そうだったのか! この1冊でスッキリわかる! リウマチ・膠原病の薬物療法の考え方・選び方・使い方
本書では、研修医や内科専攻医をはじめとした初学者や、日常的にリウマチ診療を行っている整形外科医を対象として、リウマチ膠原病の治療について解説しました。これからリウマチ膠原病内科の道を志す医師、ローテーションや内科専門医試験対策で勉強する医師にも有用な内容です。非専門医でも専門医へ紹介するにあたって、リウマチ膠原病の治療の知識を持っておくと役立ちます。
関節リウマチだけでなく、その他のリウマチ類縁疾患や一部膠原病まで含めたリウマチ膠原病の薬物療法に関する正しい知識(考え方・使い方)、そして疾患ごとの選択肢(メリット・デメリット)などをまとめました。
リウマチ膠原病に対する誤った知識、偏見、誤解、苦手意識が払拭され、正しい道筋をつかむことができるでしょう。
