
高齢女性診療Q&A 患者さんからの質問に答えるためのエッセンス
高齢女性診療でよくある質問について、相手を安心させ、スムーズに診療をすすめるための回答がQ&A形式で分かります!
◆ポスト更年期(=更年期を過ぎた50代後半以降)の高齢女性には、高齢者特有の悩み、女性特有の悩みが存在します。
◆外来で高齢女性特有の悩み・不安を相談されたとき、どう答えれば分かりやすいか、その答えの根拠は何かを、最新のエビデンスを交えて解説しました。
◆高齢女性の診療、看護、介護、ケアの日常現場で役に立つ1冊です。

診断と治療 Vol.111 No.4
2023年4月号
【特集】虚血性心疾患:日常診療から専門医による治療まで
【特集】虚血性心疾患:日常診療から専門医による治療まで 胸部症状を訴える初診患者や心筋梗塞の既往がある患者など,一般内科医の先生方も遭遇する虚血性心疾患の特集です.
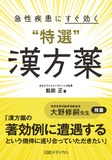
急性疾患にすぐ効く “特選”漢方薬
プライマリ・ケア医が日々の診療に役立つ漢方薬の使い方やコツを紹介。急性期に漢方薬を短期間処方することで、西洋薬では十分な効果が得られない愁訴を素早く緩和している。
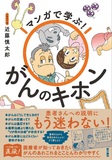
マンガで学ぶ!
がんのキホン
医療者が知っておきたいがんのキホン知識を、マンガ家ドクターがわかりやすく解説!
「がんはどうして生じるの?」「がんの定義って?」「がんは遺伝する?」「標準治療よりも“スゴい治療”があるの?」「がん検診ってどれくらい意味があるの?」――患者さんからこれらの質問を受けたときに、皆さんは自信をもって説明できるでしょうか? 私たちにとって最も身近な病気の1つであるがん。医療者が知っておきたいその基本知識を60のトピックスにまとめ、マンガや図表とともにとことんわかりやすく学べる1冊!

医学のあゆみ285巻2号
環境化学物質が人体へ与える影響
環境化学物質が人体へ与える影響
企画:市原佐保子(自治医科大学医学部環境予防医学講座)
・先進国では,大気汚染や水質汚濁,典型的な産業中毒症例は減り,低濃度の環境化学物質などによる環境ストレスの長期曝露による影響が深刻化しているが,発展途上国では,環境汚染は喫緊の課題となっている.
・人体に影響を及ぼす環境要因は,われわれの健康を脅かすのみならず,次世代への影響も危惧される.社会の持続的な発展を目指すためにも,環境の健康への影響を科学的に明らかにすることが重要である.
・本特集では,現時点で問題となっている環境化学物質を中心に,そのヒトへの影響に関する話題や職業がんについて専門家に解説いただくほか,近年,立て続けに発生し問題となっている職業がんについても紹介する.

高齢者の薬物療法の勘所
マルモ・リハ薬剤・サルコペニアを一刀両断
高齢者の薬剤の飲み合わせ・処方変更・薬の優先度など処方の勘所がよくわかる!
高齢者をみるすべての医師と薬剤師のためのハンディな1冊.疾患ごとにガイドライン通りにすべて処方したらポリファーマシーになってしまう…….疾患ごとにエキスパートが薬剤管理(導入,中止)のコツや注意すべき副作用などを解説.実際の症例を用いて処方の問題点・モニタリングのポイント・処方介入のコツを実践的に学べる!

看護 Vol.75 No.5
2023年4月号
特集1 看護職員の処遇改善 新たな展開 医療職俸給表(三)改正をキャリアアップに連動させる
特集1 看護職員の処遇改善 新たな展開 医療職俸給表(三)改正をキャリアアップに連動させる
「国家公務員医療職俸給表(三)」は、歴史的な経緯によって、公的・民間を問わず、病院看護職員の賃金制度や賃金水準に影響を及ぼしてきました。この「医療職俸給表(三)」の改正が、2023年4月から施行されます。このたび日本看護協会は「看護職員の処遇改善キャンペーン」を展開し、この機にキャリアアップに伴う処遇改善に取り組んでほしい、と強いメッセージを発信しています。
本特集では、新たな展開を迎えた看護職員の処遇改善に向けて、日本看護協会の福井トシ子会長からの提言を〈総論〉で、「医療職俸給表(三)」改正の意義や処遇改善に向けた取り組みを〈解説1、2〉〈載録〉で紹介します。さらに、「複線型等級制度」を基盤とする賃金制度を導入した3つの施設からの〈報告〉をお届けします。
特集2:患者を守る水害対策
近年、国内における水害被害は頻発しており、かつ激甚化の様相を呈しています。2018年の西日本豪雨、2019年の台風15号・19号、2020年7月の豪雨により、多くの医療機関で浸水被害が起きています。
本特集では、まず、近年の大規模水害被害の特徴と、過去に国内で発生した水害による医療機関の被災状況ならびに対応に見られる共通点・課題を整理した上で、京都大学防災研究所が策定した水害対策タイムライン等を紹介。次に医療機関における平時の防災訓練、BCP検証のポイントをまとめるとともに、災害時において看護管理者に求められる役割を示します。さらに、浸水被害のあった被災地域への派遣活動を実施した医療機関の経験・教訓による防災対策を報告。最後に水害時の感染症対策の留意点を解説します。

日本看護協会機関誌『看護』年間購読(2023年4月号~2024年3月号:臨時増刊号含まない計12冊)
日本看護協会出版会発行の日本看護協会機関誌『看護』の2023年4月号から2024年3月号までの年間購読(電子版・12冊発行予定)になります。日本看護協会機関誌『看護』の内容は下記をご覧ください。 日本看護協会の重点政策・重点事業、全国各地の優れた看護実践等を紹介 特徴: 〇日本看護協会の重点政策・重点事業をわかりやすく解説 〇あらゆる場所で活躍する優れた看護の取り組みを紹介 〇経営・管理・教育にヒントが得られる事例報告

日本看護協会機関誌『看護』年間購読(2023年4月号~2024年3月号:臨時増刊号含む計15冊)
日本看護協会出版会発行の日本看護協会機関誌『看護』の2023年4月号から2024年3月号までの年間購読(電子版・12冊発行予定)になります。日本看護協会機関誌『看護』の内容は下記をご覧ください。 日本看護協会の重点政策・重点事業、全国各地の優れた看護実践等を紹介 特徴:〇日本看護協会の重点政策・重点事業をわかりやすく解説 〇あらゆる場所で活躍する優れた看護の取り組みを紹介 〇経営・管理・教育にヒントが得られる事例報告

Heart View Vol.27 No.5
2023年5月号
【特集】心臓リハビリテーション 遠隔医療保険適用を見据えて
【特集】心臓リハビリテーション 遠隔医療保険適用を見据えて

臨牀透析 Vol.39 No.4
2023年4月号
もっと知ろう透析患者の栄養と身体評価
もっと知ろう透析患者の栄養と身体評価
超高齢化する透析患者に,愁訴の少ない安寧な生活を送っていただくため,低栄養とサルコペニアについてスクリーニングし,これら合併リスクの高い患者群には早期から介入することが必要となる.

領域別ファイリングノート3 基礎看護学のノート
講義・基礎実習・臨地実習での学びを無駄にせず,国試合格につなげる!
ルーズリーフ型の穴あき設計で,取り外し自由!
各領域毎にまとめてファイルすることができる,一生使える“自分だけのオリジナルノート”!
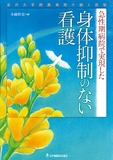
急性期病院で実現した 身体抑制のない看護
金沢大学附属病院で続く挑戦
「抑制=患者の安全」と誤解している人がいるが、患者が抑制された結果、身体状況が悪化したり、感情を暴発させる、不穏になるなどして、かえってケアの困難さが増すケースも多い。また患者を抑制することで、本当は必要な看護師の手、目、心が患者から遠ざかることを招いてしまう。高度急性期病院では難しいとされてきた身体抑制件数の減少に挑戦し、ゼロ化を達成した金沢大学附属病院の取り組みと成果を紹介した本書は、次に続こうとする挑戦者たちの精神的な拠り所になるだろう。
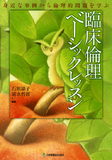
身近な事例から倫理的問題を学ぶ
臨床倫理ベーシックレッスン
「臨床倫理」というと難解もの、敬遠したいものと感じる人も多いようですが、医療者は日々、患者へのケアを行う中で倫理的問題に対応しています。本書では、臨床現場で倫理的問題になることの多い具体的な場面を取り上げ、医療者がどのように患者を尊重し、その人らしい生き方ができるようにサポートしていくべきかについて考えていきます。医療現場に長年携わってきた看護師・石垣教授と、哲学者・清水教授の異色コンビによる臨床倫理の本です。日々のケアの中で遭遇する倫理的問題について考える際の道標にしてください!
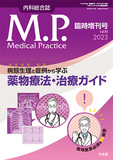
Medical Practice 2023年臨時増刊号
病態生理と症例から学ぶ薬物療法・治療ガイド~実地医家必須の54疾患
病態生理と症例から学ぶ薬物療法・治療ガイド~実地医家必須の54疾患 一般内科外来の診療で携わる機会の多い疾患,逆紹介で患者管理を行う機会の多い疾患を取り上げて,症例ベースで薬の使い方・治療の方法を解説した実践書.全54疾患の症例と処方内容を示し,なぜその処方・治療を行うか,病態生理を踏まえて解説した.臨床医としてさまざまな患者の診療に携わり,その後にあらためて病態生理を学ぶと,「あの症状はこのような病態で生じていたのか」「あの治療が効かなかった理由は,背景にこういう病態が潜んでいたからなのか」と,診療に則した知識として非常に興味深く,頭にすっと入っていくことがあります.そして,ここで得た知識が次の患者の診療に活かされていくことで,医師の診療能力が向上していきます.(本書序文より)【症例】を読んで薬の使い方・治療の方法を,【病態生理】を読んでその根拠を理解できる,応用の効く医師になるための一冊.

眼科 Vol.65 No.4
2023年4月号
わかりやすい オートファジーと眼疾患
わかりやすい オートファジーと眼疾患
トピックス、診療のコツ、症例報告、どこから読んでもすぐ診療に役立つ、気軽な眼科の専門誌です。本号は特集を「よくわかる オートファジーと眼疾患」と題し、とっつきにくいが眼の病態と密接に関係しているオートファジーについて5人の専門家の先生方に解説していただきました。その他、緑内障眼の黄斑手術や近視、COVID-19と視神経炎などトピックを取り上げた綜説や各種連載企画、投稿論文も掲載されております。是非ご一読ください。

泌尿器外科 2023年3月号
2023年3月号
特集:泌尿器科医必見! がんゲノム医療の基本と応用
特集:泌尿器科医必見! がんゲノム医療の基本と応用

大圃組はやっている!! 消化器内視鏡の機器・器具・デバイスはこう使え!
ますます増加、進歩していく消化器内視鏡の機器・器具・デバイス。その使い方を、カリスマ内視鏡医が率いる「大圃組」が親切丁寧に教えます。基本操作から使いこなすためのヒント・コツ・裏技まで、600点におよぶ写真・図表を駆使して、視覚的に解説。まさに最強の機器マニュアルが完成しました。さらに、各種デバイスのスペック表などを収録したポケットサイズのお役立ち冊子も付いています! 内視鏡技師、看護師から内視鏡医まで、消化器内視鏡に携わる全てのスタッフ必携!

超入門!スラスラわかる リアルワールドデータで臨床研究
リアルワールドデータと呼ばれる、医療ビッグデータ(NDB・DPCデータベースなど)を用いた臨床研究法の具体的・実践的な指南書。既存のデータベースを解析可能にするためのSQL操作法から、論文執筆にあたって抑えておくべきポイントまで、RWDを用いた臨床研究のまさに超入門書。
とくにRCT至上主義が跋扈する科学界で、論文をアクセプトまでもっていくためには、レフェリーとどのようにファイトするのかまで書いてあり、かゆいところに手が届く一冊。
本書で取り上げたURLを特設サイトにて公開中!

看護 Vol.75 No.4
2023年3月臨時増刊号
特集1 外来での在宅療養支援
特集1 外来での在宅療養支援
近年、医療が「病院完結型」から「地域完結型」へ変わりつつある中で、入院医療と在宅医療の間に位置する外来での患者への支援は重要性を増し、医療と生活の両面から支援を行える看護職の介入は必要不可欠です。しかし日々、多くの患者が来院する多忙な外来では、支援を要する患者の見極めや、効果的な支援を行うことは難しいという現状から、外来看護師が支援を実施するための外来看護提供体制の構築も求められています。
本特集では、まず1章の総論で、近年の外来医療に関する政策動向と日本看護協会の取り組みを説明した上で、2021 年の外来看護に関する2つの調査結果を基にこれから強化すべき外来看護の機能等について解説します。
2章の論考では、外来看護の重要性が増す中で、外来看護師が役割を発揮するためにはどのような仕組みを構築すべきなのかを述べます。
3章の報告では、外来での在宅療養支援に積極的に取り組んでいる病院やクリニックの、各病院の特色に合った仕組みづくりや取り組みを集めました。継続可能な体制づくりから支援の実際まで、事例を交えて紹介します。
さまざまな事情や病気を抱える外来患者が地域で暮らし続けるために必要な支援と、看護提供体制のあり方について、多種多様なヒントが詰め込まれています。ぜひ、ご活用ください。
