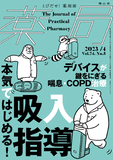
薬局 Vol.74 No.5
2023年4月号
本気ではじめる! 吸入指導
デバイスが鍵をにぎる喘息・COPD治療
本気ではじめる! 吸入指導
デバイスが鍵をにぎる喘息・COPD治療 喘息・COPDの治療に用いられる吸入薬には,それぞれ特有の使い方やピットフォールがあり,患者さんが適切に吸入できない背景も多岐にわたります.令和2年度には「吸入薬指導加算」が新設され,吸入指導が薬剤師のスキルの一つとして示されました.そこで今回は,巻頭カラー「デバイス別見ひらきトリセツ」を始めとして,診療ガイドラインを根拠とする薬学的介入のポイントや,適切な吸入デバイスを選択する際の考えかた,初回指導・再指導のコツなどをご解説いただきました.吸入指導を「本気ではじめる!」ために,おすすめの一冊です.

≪新篇眼科プラクティス 9≫
必読!コンタクトレンズ診療
本書は,コンタクトレンズ診療を始めたばかりの眼科医やスタッフが理解すべき知識を分かりやすくまとめた入門書である.レンズの種類や装用スケジュールなど基礎的なトピックから,近視抑制レンズのような,エキスパートにも役立つ最新情報を意欲的に盛り込んだ.また,巻末には,付録として【主要なコンタクトレンズデータ一覧表】も掲載.日々のコンタクトレンズ診療で参照したいエッセンスが網羅された,アイケアプロフェッショナル必携の書.【シリーズ概要】「日常臨床にすぐ役立つ」をコンセプトとした「眼科プラクティス」の最新シリーズ.今シリーズでは図版をより効果的に示すことで,さらにビジュアル面を大幅強化.直感的に理解できる「視る教科書」を目指した.

≪新篇眼科プラクティス 7≫
だれでもロービジョンケア
近年ますます注目が高まっているロービジョンケアについて,眼科医や視能訓練士だけでなく,歩行訓練士,公認心理師等様々な専門職種が解説した一冊.これからロービジョンケアを始めるために役立つ情報はもちろん,これまでロービジョンを行ってきた方々にとっても有用な情報を凝縮.【シリーズ概要】「日常臨床にすぐ役立つ」をコンセプトとした「眼科プラクティス」の最新シリーズ.今シリーズでは図版をより効果的に示すことで,さらにビジュアル面を大幅強化.直感的に理解できる「視る教科書」を目指した.
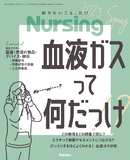
Nursing Vol.43 No.4(2023年春号)
【特集】血液ガスって何だっけ?!
【特集】血液ガスって何だっけ?! 臨床現場でのさまざまな疑問や困ったことに、根拠と実践的な視点を織り込みながら、よりよい方法を示す看護総合雑誌!いま知りたい臨床の課題など今日から床現場で使える基本・ワザ・コツを網羅!

診療所で働く人のための朝の1分間勉強会
ほーむけあクリニックと横林先生を成長させる『朝の1分間勉強会』ってなんだ?
医療チームとして「学び合える組織」をつくりあげるにはどうすればよいか悩む皆さんに,ほーむけあクリニックの横林賢一 先生が辿り着いた『朝の1分間勉強会』を紹介します.医師,看護師,作業療法士,介護士など,あらゆる職種のスタッフが施設内で共有したいテーマを厳選して掲載しました.そこでの回答,解説を参考にするもよし,新たなテーマを検討するもよし,もちろん医学知識の読み物として活用するもよしと,多種多様な実践方法をお楽しみください.

≪非腫瘍性疾患病理アトラス≫
消化管
炎症性疾患をはじめとした非腫瘍性消化管疾患は,多様な組織形態をとるうえに,病理診断では臨床情報も加味する必要があり,診断も一筋縄ではいかない.本書では実践を重視して,まず総論として「非腫瘍性」ならではの所見のみかたと鑑別診断の流れを解説.続く各論では,日常診断で遭遇しうる非腫瘍性消化管疾患のほとんどを網羅し,約800点の病理・内視鏡写真を提示して診断のポイントを解説.診断の方法論が獲得できる一冊.

臨床雑誌外科 Vol.85 No.4
2023年4月号
消化器外科における各種デバイスの使い方とピットフォール
消化器外科における各種デバイスの使い方とピットフォール 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

胸部外科 Vol.76 No.4
2023年4月号
活動期感染性心内膜炎の外科治療
活動期感染性心内膜炎の外科治療 1948年創刊。常に最近の話題を満載した、わが国で最も長い歴史と伝統を持つ専門誌。心、肺、食道3領域の外科を含む商業医学雑誌として好評を得ている。複数の編集委員(主幹)による厳正な査読を経た投稿論文を主体とした構成。巻頭の「胸部外科の指針」は、投稿原稿の中から話題性、あるいは問題性のある論文を選定し、2人の討論者による誌上討論を行っている。胸部外科医にとって必須の特集テーマを年4回設定。また、「まい・てくにっく」、「1枚のシェーマ」、読み物として「胸部外科医の散歩道」を連載。

脊椎脊髄ジャーナル Vol.35 No.11
2022年11月号
■特集
脊髄病理が診断や病態理解に重要な疾患

作業療法ジャーナル Vol.57 No.4
2023年4月号
■特集
「遊ぶ」は子どもの作業―「遊び」のチカラを考える

チャイルドヘルス Vol.26 No.4
2023年4月号
【特集】家庭内の事故予防を考える〜大きな怪我を防ぐために〜
【特集】家庭内の事故予防を考える〜大きな怪我を防ぐために〜 小さな子どもの事故の多くは,家庭内で起きていることをご存じですか?
子どもを守るために大切な予防策について,本特集で一緒に確認しましょう!

最新理学療法学講座 中枢神経系理学療法学
授業づくりをアシスト!新テキストシリーズ始動
●1、2年で学ぶ講義内容を統合しながら中枢神経系の理解を深め、その後の臨床実習にもいきるテキスト。
●豊富な図表で機能解剖から中枢神経系理学療法の重要ポイントをつかみやすい。
●臨床にいきる専門知識とともに、理学療法の醍醐味も伝わえる一冊。
【シリーズコンセプト】
●4色カラー刷りのテキストで必要知識を視覚的に理解できる
●基本解説では理学療法士国家試験の出題内容をカバー
●実習や臨床に役立つ要素も充実
●15コマの授業で講義しやすい構成
●能動的に学べる課題を複数掲載

脳卒中リハビリテーションポケットマニュアル 第2版
リハビリテーション医療者の必修事項をポケット版にぎゅっと詰めた最新マニュアル16年ぶりの大改訂!
●脳卒中リハビリテーションの知識と最新情報を詳しく解説
●豊富な脳画像や図をもとに,実践にいかすノウハウを紹介
●リハビリテーション医療者の共通書として最適な一冊
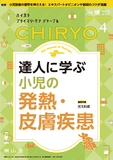
治療 Vol.105 No.4
2023年4月号
小児の発熱・皮膚疾患
小児の発熱・皮膚疾患 小児を診る機会はあるものの,成人と異なる見立てや治療に苦手意識を持たれる方も多いかと思います.本特集では,小児診療で最も頻度の高い「発熱」と「皮膚疾患」にフォーカスをしぼって,達人たちから小児診療の極意を解説していただきます.風邪と簡単に決めつけられない発熱の診かたや,経過観察でよい皮膚症状の見極め方など,保護者へのアドバイスも含めて1冊で小児診療が得意になれる内容となっておりますので,ぜひご確認ください.

看護管理 Vol.33 No.4
2023年 04月号
特集 病棟チームの関係性をつむぎ直す コロナ禍における「組織の安全感」とは
特集 病棟チームの関係性をつむぎ直す コロナ禍における「組織の安全感」とは 社会の変化を的確にとらえながら、看護管理者として直面するさまざまな問題について解決策を探る月刊誌。看護師長を中心に主任から部長まで幅広い読者層に役立つ情報をお届けします。 (ISSN 0917-1355)
月刊、年12冊
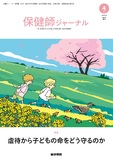
保健師ジャーナル Vol.79 No.2
2023年 04月号
特集 虐待から子どもの命をどう守るのか
特集 虐待から子どもの命をどう守るのか 公衆衛生活動の現場で働く保健師に向けた、「保健師」と名の付く唯一の専門誌。保健活動の「いま」と「これから」を、確かな情報と具体的な実践を伝えることで描きます。 (ISSN 1348-8333)
隔月刊(偶数月)、年6冊

看護教育 Vol.64 No.2
2023年 04月号
特集 EBPと看護教育
特集 EBPと看護教育 変わりゆく医療の構造、そして教育界全体の動きをみすえ、今求められる看護教育を、みなさんとともに考えていきます。ベテランの先生方はもちろん、学生への指導に不安を感じていらっしゃる新人教員の方々にも役立つ内容をお届けします。 (ISSN 0047-1895)
隔月刊(偶数月)、年6冊

病院 Vol.82 No.4
2023年 04月号
特集 DXでタスク・シフトせよ 働き方改革の打開策
特集 DXでタスク・シフトせよ 働き方改革の打開策 「よい病院はどうあるべきかを研究する」をコンセプトに掲げ、病院運営の指針を提供する。特集では、病院を取り巻く制度改正や社会情勢の読み解き方、変革に対応するための組織づくりなど、病院の今後の姿について考える視点と先駆的な事例を紹介する。 (ISSN 0385-2377)
月刊、年12冊

臨床皮膚科 Vol.77 No.4
2023年 04月号
さまざまな症例や治療成績が全国から寄せられる原著系皮膚科専門誌。写真はオールカラーで、『臨床皮膚科』ならではのクオリティ。注目の論文は「今月の症例」として、編集委員が読み処のアドバイスを添えて掲載する。増刊号「最近のトピックス」は、知識を毎年アップデートできる定番シリーズ。 (ISSN 0021-4973)
月刊、増刊号を含む年13冊

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.95 No.4
2023年 04月号
特集 睡眠時無呼吸症候群の診療エッセンシャル
特集 睡眠時無呼吸症候群の診療エッセンシャル 目のつけ処が一味違う耳鼻咽喉科・頭頸部外科専門誌。「こんなときどうする!?」などの臨床的なコツの紹介から、最新の疾患概念を解説した本格特集まで、硬軟とり混ぜた多彩な企画をお届けする。特集2本立ての号も。「Review Article」欄では研究の最前線の話題をわかりやすく解説。読み応えのある原著論文も多数掲載。 (ISSN 0914-3491)
月刊、増刊号を含む年13冊
