
プチナース Vol.32 No.3
2023年3月号
◆この視点を追加しよう! 高齢患者さんのアセスメントとケア
◆先輩たちはこんな1年を送りました 就職・進学1年目ストーリーズ
◆この視点を追加しよう! 高齢患者さんのアセスメントとケア
◆先輩たちはこんな1年を送りました 就職・進学1年目ストーリーズ

みてわかるできる事例で学ぶ看護過程精神看護学 Web動画付 1
臨場感のある映像つき!
看護過程を学ぶうえで欠かせない「患者と看護師」のコミュニケーションの様子をビジュアルに学べます.
映像でイメージがつかめたら,情報収集・看護計画・看護過程の展開を書籍で学んでいきましょう.

リハビリの心と力3rd ed.
かかわることで学んだ輝く命のStory
著者が理学療法士から医師になり,どのように人と向き合ってきたのか.
いかに年をとろうと,どのような病気になろうと,そして,いかなる障害をもとうと,最後まで自分らしく生きること.
この大切なテーマを皆さんにお伝えします.

みてわかるできる事例で学ぶ看護過程成人看護学 Web動画付
臨場感のある映像つき!
看護過程を学ぶうえで欠かせない「患者と看護師」のコミュニケーションの様子をビジュアルに学べます.
映像でイメージがつかめたら,情報収集・看護計画・看護過程の展開を書籍で学んでいきましょう.

エビデンスに基づく検査データ活用マニュアル改訂第3版
第2版発刊から5年以上が経過し,その間も新しい検査がいくつかアップデートされ続けている.
それらを反映・誌面刷新し,国際基準に分類をあわせ,検査項目分類の項目における統一,その精度管理の解説を追加など,新たに読者に提供する.
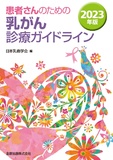
患者さんのための乳がん診療ガイドライン 2023年版
納得のいく医療を受けるためには、患者さんが標準治療(=最善の治療)や診療方法について正しく理解したうえで、医師と相談し、ご自身に合った治療を選択すること(=Shared Decision Making)が重要です。
本書では、乳がんの患者さんやそのご家族が、いま知りたいことについて、正しい情報をわかりやすく得られるよう、最新の情報をもとに、患者さんからの計65の質問(Q)に対する回答(A)と解説を掲載しています。

看護 Vol.75 No.2
2023年2月号
特集1 特定認定看護師の活躍
特集1 特定認定看護師の活躍
特定行為研修を組み込んだ認定看護師教育B課程を修了した特定認定看護師が誕生し、今、臨床現場で活躍を始めています。また、日本看護協会では認定看護師(A課程)で特定行為研修を修了した人の特定認定看護師への移行手続きも行っており、今後は、あらゆる場での活躍が期待されています。
特集1ではあらためて特定行為研修が組み込まれたB課程教育の内容を詳しく説明。さらに、現場で取り組みを始めた修了者の皆さんからその実践を報告、B課程の受講を推進する看護管理者からは人材育成の方針について述べていただきます。
特集2:看護師がつくる心理的安全性
近年、業務の連携強化や働きやすい職場づくりに役立つ考えとして、ビジネスやマネジメントの世界をはじめ、医療の場でも注目を集めている「心理的安全性」。心理的安全性が高まることにより、チームのパフォーマンスの向上や離職率の改善が期待できますが、さまざまな専門職が働く職場ではなかなか浸透しないのが現状です。
本特集では、心理的安全性のリーディングカンパニーであるGoogleの取り組み等をとおして基本的な知識を解説するとともに、心理的安全性をつくる上で管理職等が押さえておくべきポイントを示します。併せて、看護職が主導して取り組んだ職場やチームでの心理的安全性のある現場づくりの実践事例を紹介します。

説明できる検体検査・生体検査
アセスメント・ケアにつながる!
看護に必須な検体検査・生体検査について,「自分の言葉でわかりやすく説明できる」ことを目標にわかりやすく解説.
検査内容だけでなく,関連する病態や疾患の理解に加え,「論理的に考え,表現する力」がつく1冊!

領域別ファイリングノート2 疾病の成り立ちと回復の促進のノート
講義・基礎実習・臨地実習での学びを無駄にせず,国試合格につなげる!
ルーズリーフ型の穴あき設計で,取り外し自由!
各領域毎にまとめてファイルすることができる,一生使える“自分だけのオリジナルノート”!

≪Basic&Practice≫
看護・医療を学ぶ人のための よくわかる関係法規改訂第2版
難しそうな法律の話を,やさしく柔らかく学びませんか?
看護職・医療職を目指す学生の皆さんに身につけてほしい関係法規の知識を,ていねいな文章と豊富なイラストで解説します.
国試での出題も増え,現場での重要性が高まる今こそ必要とされる一冊.

領域別ファイリングノート1 人体の構造と機能のノート
看護師国家試験の出題基準をもとにまとめられ,図やイラストもたくさん!
取り外してファイルができる紙面に講義や演習などの学びの成果を書き加えて,自分だけのオリジナルのノートにしよう!

つなげてみたらドンドンわかる!病態生理学
イメージしやすくかわいいイラストと,親しみやすいやさしい語り口で,ちょっととっつきづらい病態生理学を徹底的に攻略しましょう!
暗記ではなく理解して知識をつなげられれば,実習でも国試でも自信をもって臨めます!

放射線技術学シリーズ CT撮影技術学(改訂4版)
定番テキストが最新の撮影法を採り入れて,充実の改訂!
診療放射線技師の国家試験対策、全国の大学・専門学校の放射線技術科の講義に対応した教科書シリーズの一巻です。本書は、多くの放射線技術科で講義がもたれているCT撮影技術学の定番教科書の改訂版です。
今回の改訂では、CT撮像の基本である画面再構成と画像表示に関する章を大幅に改訂するとともに、デュアルエネルギーCTなどの最新技術も盛り込み、さらに3Dモデルによる再構成のパートは4色刷として、より理解が深まる内容としています。

IT Text(一般教育シリーズ) 一般情報教育
●AI・データサイエンス時代に対応した、新しい一般情報教育の標準テキスト
●これからのカリキュラムに対応して、情報基礎からデータサイエンスまでを網羅
本書は、情報処理学会一般情報教育委員会で編纂した、これからの一般情報教育に対応した標準テキストです。情報ネットワークや情報機器の基礎知識から、プログラミングの考え方、情報倫理、データサイエンス等、社会生活で不可欠な教養ともいえる知識を幅広く網羅します。
半期2単位の授業で使用することを前提に、内容をコンパクトに、かつわかりやすく構成しています。各大学・高専で一般情報教育の見直しが行われている中で、まさに最適の教科書としてご利用いただけます。

臨牀透析 Vol.39 No.2
2023年2月号
血液透析導入の処方
血液透析導入の処方
日本透析医学会をはじめとする透析ガイドラインでは,透析導入の基準や維持透析処方,適正透析処方に関しての推奨は示されているが,透析導入時の処方について明示したものは少ない.

診断と治療 Vol.111 No.2
2023年2月号
【特集】外来通院患者に行う検査,計画的にきちんと実施できていますか?
【特集】外来通院患者に行う検査,計画的にきちんと実施できていますか? 様々な疾患,病態で通院中の患者へ,どのような検査をどのくらいの頻度で実施すべきかをわかりやすく特集しました.日常診療にぜひお役立てください.
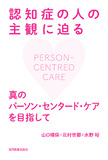
認知症の人の主観に迫る
真のパーソン・センタード・ケアを目指して
認知症ケアの現場では、たとえ認知症になってもその人らしく暮らすことを支える「パーソン・センタード・ケア」に基づくケアが求められている。
その実践にあたっては、「本人の気持ち(主観)」を正確に推測していくことが重要であり、本書を通して、認知症の本質をとらえるうえで必須の知識である「メタ認知」や「病識」について学び、ケアの際に求められる「認知的共感」のあり方を理解し、「サインの観察と推測」の具体的な方法を知ることで、真のパーソン・センタード・ケアについての理解を深めることができる。
認知症に関わるすべての医療・ケアスタッフ、学生にとって必須の知識と視点を提供。

新 知覚をみる・いかす
手の動きの滑らかさと巧みさを取り戻すために
運動機能には大きな問題がないのに、ものをつかむことができない。必要以上に強く握り込んでしまう。うまく道具を操作できない。
こうしたケースに遭遇したとき、手の巧みな動きを支えている知覚の障害をどのように診て、治療にいかしていけばよいのか。その考え方の流れがわかりやすくまとめられている。
知覚に関する基本的な知識の確認から、臨床への応用までを網羅した一冊。

片麻痺の作業療法
QOLの新しい次元へ
片麻痺の患者さんに対して、外から観察できる動きだけでなく、患者さん自身の身体感やまわりの世界の認識の仕方を治療的に解釈し、その特異的な動きを発現させる脳のはたらき方を変えていくことをめざす臨床を具体的に提案し、症例を通して観察のポイントや治療の展開の仕方を詳しく解説。
片麻痺の「治療」を模索している作業療法士、また学生にとっても明確な指針となりうる、実践的な臨床のテキスト。

基礎作業学実習ガイド
作業活動のポイントを学ぶ
作業活動(手工芸)の中から「木工」「革細工」「陶芸」を取り上げ、それぞれの活動を材料・道具・工程に分けて説明。その製作の過程を追いながら、作業活動に関する理解、その人の障害に関する理解、その人についての理解をもって、作業療法士がどのようにして治療に応用するのかを、作業活動という側面から考える力を養う。
作業療法士として必須の治療的観点、作業の工夫、段階づけとは何かを学べる格好のテキスト。
