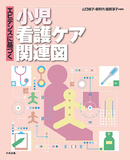
エビデンスに基づく小児看護ケア関連図
ダウン症候群、鎖肛、肺炎、麻疹、1型糖尿病、先天性股関節脱臼、ネフローゼ症候群、慢性腎不全、脳腫瘍、白血病、てんかん、脳性まひ等22疾患の病態生理・症状・検査・診断・治療・合併症について病態関連図を用いて詳解した。プレパレーション・生活援助についても紹介。

東邦大学医療センター大森病院間質性肺炎センターではこうしている 最新 間質性肺炎診療
東邦大学医療センター大森病院間質性肺炎センターの実践的な診療アプローチを余すところなく紹介。
ガイドラインには載っていない,日常診療で直面する疑問・ピットフォールへの具体的な解決策がここにあります。
■センターでの取組みの紹介や症例紹介で,プロフェッショナルの視点・考え方を学べます。巻末には現場の医師が聞きたいQ&Aも掲載。
■呼吸器内科医,看護師,理学療法士,管理栄養士の視点から,間質性肺炎診療に必須のチーム医療の実際がわかります。
■豊富な胸部HRCT画像,病理所見のほか,呼吸リハビリテーションの動画コンテンツを収録。間質性肺炎診療の基礎はもちろん,実践に役立つ情報が満載!

研修医が知りたい対応をチャートで整理!呼吸器診療エッセンシャル
好評書『循環器診療エッセンシャル』の呼吸器診療版が登場!症候・疾患別に「確認すべきポイント」,「必要な初期対応・検査」,「診療の手順」をフローチャートで図解し,チャートとリンクした解説文で理論と実践をスッキリ理解できる、実臨床で“使い倒せる一冊”.「押さえておきたい手技・対応・治療薬」のマニュアル,「診断に重要なCT所見」のアトラスも収載.“手際よく情報を得たい”,“診療の流れを知りたい”という研修医・若手医師にオススメ!
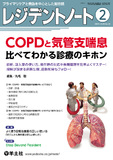
レジデントノート Vol.26 No.16
2025年2月号
【特集】COPDと気管支喘息 比べてわかる診療のキホン
【特集】COPDと気管支喘息 比べてわかる診療のキホン
類似した病態のCOPDと気管支喘息を併せて解説することで,それぞれの診断,発作時の対応や長期管理,薬物・非薬物療法がスッキリわかる!病棟・救急でよく出合う両疾患の,必ず身につけておきたい知識をまとめた1冊

関節外科 基礎と臨床 Vol.43 No.11
2024年11月号
【特集】人工股関節置換術のエキスパートを目指そう
【特集】人工股関節置換術のエキスパートを目指そう

≪新OS NEXUS No.6≫
脊椎固定術の基本手技[Web動画付]
「専攻医が経験すべき手術」を全20巻でほぼ網羅。メインの特集項目に加えて,手技の理解を深める解剖学的知識を示した「Anatomy Key Point」や,知っておくと有用な基本的手術・治療手技の紹介も毎号掲載し,専攻医として必要なスキルを漏れなくカバーできるシリーズ構成となっている。さらに前シリーズからの特徴である豊富な画像と精密なイラストに加えて今シーズンではストリーミング動画も配信し,静止画では伝わりづらい部分もよくわかる!
No. 6では脊椎に行われる2大手術の一つ「脊椎固定術」を取り上げており,No. 3の「脊椎除圧術」と併せて,マスターしておきたい基本手技を解説する。

レジデントノート増刊 Vol.24 No.8
【特集】人工呼吸管理 はじめの一歩
【特集】人工呼吸管理 はじめの一歩 「モードの使い分けがわからない…」「アラームが鳴ったけどどうすればいいの?」「人工呼吸器の早期離脱を目指したい!」そのお悩み,この1冊で全て解決できます!最低限知っておきたい基本をわかりやすく解説!

日めくり麻酔科エビデンス アップデート5
~1日1つ、3カ月で100の知見を得る~
好評書の第5弾。前作と同様、麻酔関連領域の新知見を楽しくアップデートできるようにした。「麻酔と環境」「覚醒と抜管」などの近年の重要なテーマも新たに組み入れた。

血液内科グリーンノート 第2版
最高水準の診療をめざし,現場で本当に必要な情報を凝縮したポケットマニュアル「グリーンノート」シリーズの血液内科編.改訂2版となる今版では,血液内科の臨床で必須とされる厳選知識をミニマムかつ網羅的に伝えつつ,全体を最先端の情報にアップデート.実臨床で活躍できる力がつく,新たな診療マニュアルである.

新訂第2版 写真でわかる母性看護技術 アドバンス
妊娠期から産後まで、切れ目のないケアを実践!
妊娠期・分娩期を新たに追加、周産期の一連のケアを取りあげ大幅改訂!!
今回の改訂では、妊娠期・分娩期パートを追加し、周産期を通しての母子の観察とケアを学べる内容に大リニューアル。妊娠期および産後の心理社会的支援、家族への支援などの内容も盛り込み、妊娠・分娩・育児期を通して切れ目なく、女性をとり巻く環境も含めて支援する視点で解説します。
また、新生児の清潔ケアは、新しい考え方に基づく手技に内容を刷新しました。

dAVF・AVM(硬膜動静脈瘻・脳動静脈奇形)のすべて
【dAVFとAVMのすべてがこの1冊で学べる!】好評を博した『硬膜動静脈瘻のすべて』を大幅改訂。臨床で遭遇し得るあらゆるタイプのdural AVF(硬膜動静脈瘻)とAVM(脳動静脈奇形)を完全網羅。疫学から病態、最新のデバイス、治療法まで学べ、血管内治療専門医試験の学習にも最適。治療の実際がよく分かるWEB動画●本付き!

NEWはじめての手術看護
【要点がパッとつかめる&根拠がわかる】豊富な写真やイラストで新人オペナースの必須知識をビジュアル解説。周術期におけるケアの根拠が明確にわかるだけでなく、先輩ナースの経験に根ざしたコツや注意点などもふんだんに紹介。手術看護の要点がギュッと詰まっているので、復習・指導用テキストとしてもおすすめ。理解度が確認できるWEBテスト付き。
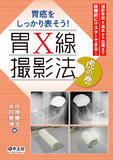
胃癌をしっかり表そう!
胃X線撮影法 虎の巻
撮影手技を基本から応用まで段階的にマスターできる!
胃癌の正確な診断には,精度の高い画像が必須!
5段階ステップアップ方式で,胃X線撮影技術の基本から応用までマスター!ビギナーからベテランまで役立つ,胃がんをきっちり撮影できるようになる本!

臨床検査ガイド2025年改訂版
これだけは必要な検査のすすめかた・データのよみかた
最新かつ信頼性の高い臨床検査ガイドブックとして医師,医療スタッフに長年愛用されるベストセラー.臨床現場をとりまく状況の変化と検査技術の進歩とをふまえて,項目を全面的に見直し,最新情報を盛り込んだ.「デシジョンレベル」「基準値」を示し,検査の意義,適応,注意点,異常値の解釈,フォローアップ方法,保険適用条件について見やすく整理して解説.臨床現場のニーズに応え,日常診療で瞬時に活用できる実践的な1冊.

ひとりでも書ける症例報告 クリニカルピクチャー論文のすすめ
クリピクが書けると日常診療も楽しくなる!
自身が経験した症例を100~300語程度で臨床画像を添えてまとめるクリニカルピクチャーは,「隙間時間で書ける」「症例の振り返り学習になる」「コツがわかれば量産できる」「学業業績にもなる」と良いことづくめですが,Acceptに至るにはCase reportとは異なるノウハウが必要です.本書では,症例選び, 同意書の取得やfigure編集, 型にはめた書き方やChatGPT有効活用法, revision/reject時の対応,頻出英語表現の紹介や秘伝資料の公開など,JAMAやBMJなどに約50本の掲載経験を持つ著者が培ったノウハウをもとに徹底解説します.
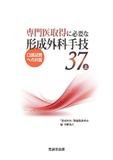
専門医取得に必要な形成外科手技 37 上
口頭試問への対策
形成外科の専門医試験、口頭試問の設問を想定した問題・解説集。加えて「概説」として、この設問を解くにあたって必要最低限の知識や学ぶべき内容を具体的に示されています。
雑誌『形成外科』に掲載された連載を単行本化した大好評の初版から、このたび8年ぶりに改訂されました。今回は実際に本試験の試験官を直近で経験した人を著者に迎え、より専門性の高い出題内容とされています。時代に即した充実の内容で、受験を予定している先生方には出題傾向を把握する意味で最適の本かと存じます。

甲状腺超音波診断ガイドブック 改訂第3版
甲状腺超音波検査の標準化のための,JABTS甲状腺用語診断基準委員会編集による手引き書.改訂第3版では,結節性病変に対する診断の進め方,超音波エラストグラフィなどの記載を充実させるとともに,新たに小児の甲状腺超音波解剖,福島県における小児超音波検診の項を設けた.甲状腺疾患の診療,頸部超音波検査に携わるすべての医療者にとって必携の書.

ECMO・PCPSバイブル
【Withコロナ時代のECMOチーム必携!】
心肺蘇生(ECPR)・呼吸補助(ECMO)・循環補助(PCPS)の各エキスパートが結集し、体外循環による救命治療の全領域を網羅した待望の1冊。COVID-19重症患者の管理にも言及し、withコロナ、postコロナ時代のECMO治療に携わる医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士などすべての人に贈る日本版ECMOの決定版“Blue Book”。
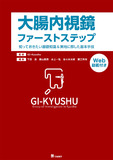
大腸内視鏡のファーストステップ 知っておきたい基礎知識&実地に即した基本手技
大腸内視鏡で、“この先ずっと” 役に立つ基本事項を1冊にまとめました。
研修医・専攻医の視点で、大腸内視鏡のことが“まるっと”わかります。
大腸内視鏡は、消化器内科専門医を志す医師にとって、習得すべき検査法の一つです。施設によっては初期研修の後半から修得をする機会はありますが、臨床現場で多くのことを学び始める時期と重なることから要点を押さえた習得法が望まれます。
本書では、実地において、まず指導医が最初に指導をする内容を中心に解説し、①限られた時間の中で押さえなければならない基本を身につけられる、②基本技術習得のみならず専門医以降も研鑽を積んでいくために必要となる臨床上の勘所を身につけられる、ことを大きな柱としています。実地手技の要点のみ、余すところなく披露されています。

胸部レントゲンを読みたいあなたへ
期待を確信に変える21話
典型例とその臨場感あふれるエピソードを皮切りに,日々の読影にすぐ活かせる読影スキルを解説.多くの症例写真を掲げて,様々な陰影パターンをふんだんに紹介.読影のポイントは図表を交えて,わかりやすくしっかり解説.はみ出しコラムでは,必ず役立つ読影の基本原則や実践スキルをイラストとともに楽しく学べる.初級者~上級者まで,すべてのステージであなたを完全フォロー.
