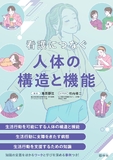
看護につなぐ人体の構造と機能
ふだん「人体の構造と機能」については、器官・器官系ごとに学ぶことが多いですが、本書では生活行動ごとにさまざまな器官・器官系を合わせて学ぶことができます。
生活行動を可能にしている器官・器官系のしくみとはたらきを理解したうえで、生活行動に支障をきたす病態を学習し、必要な援助へとつなげられるように展開しています。
ぜひ覚えるだけの知識から活用する知識へできるよう、本書をお役立てください。
この本の特徴
●看護が支援する生活行動の視点から人体の構造と機能を解説
●人体の構造と機能の知識が基礎看護技術の根拠や病態理解につながる
●単に暗記していた知識が看護に役立てられる知識に変わる

エキスパートナース Vol.40 No.10
2024年8月臨時増刊号
『患者さんの訴えを受け止めて、アセスメントするときに、あなたが知っておくべき解剖生理』
学生時代に習ったけれど、それっきりになりがちな解剖学や生理学。忙しい勤務のかたわらに教科書を引っ張り出さずとも、ヤンデル先生が日常の看護業務に直結する解剖生理学だけを、ピンポイントで解説します。
[ポイント]
・臓器を暗記するのではなく「使える知識」にするための解説
・読み切って集中的にやりなおせる、読みやすい誌面構成
『患者さんの訴えを受け止めて、アセスメントするときに、あなたが知っておくべき解剖生理』
学生時代に習ったけれど、それっきりになりがちな解剖学や生理学。忙しい勤務のかたわらに教科書を引っ張り出さずとも、ヤンデル先生が日常の看護業務に直結する解剖生理学だけを、ピンポイントで解説します。
[ポイント]
・臓器を暗記するのではなく「使える知識」にするための解説
・読み切って集中的にやりなおせる、読みやすい誌面構成

末梢神経障害
解剖生理から診断,治療,リハビリテーションまで
末梢神経障害の診断アプローチを双方向から徹底解説!
末梢神経障害の臨床に必須の情報を網羅した、明日の診療がレベルアップする1冊。commonからrareまで重要な末梢神経疾患の特徴を幅広く解説することに加え、症候の種類・出現場所、どの神経に障害があるかといった所見から何を疑うべきかを解説し、双方向から疾患に迫る。双方向からのアプローチに欠かせない解剖生理、生化学、神経病理の“真に役立つ”知識を厳選。最新の治療、リハビリテーションまで充実の内容。

麻酔への知的アプローチ スタートライン
ロングセラー『麻酔への知的アプローチ』の入門編!
●理論を踏まえながら、安全を第一に、麻酔管理や周術期管理のエッセンスをやさしく解説しました。
●医学生、初期研修医の方はもちろん、知識を整理したい専攻医や麻酔科特定行為研修を受けている看護師の方にもおすすめです。

≪実験医学別冊≫
大規模データで困ったときに、まず図を描くことからはじめる生命科学データ解析
解析のゴールドスタンダードを学び、生成AIとの対話でPython・Rを使いこなす
シングルセル,メタゲノムseq,プロテオームなどの膨大なデータは『図』として可視化してこそ,真価が引き出されます.UMAP,MAプロット,ヒートマップ…本書では生成AIの力を借りながら自分で思いのままに可視化する方法を解説します!作図プロセスを通してデータの核心を掴み,より本質的な研究に進みたいあなたへ

手・前腕・肘の外傷 解剖と手術手技
手の複雑な解剖と手術手技の難しさに直面したことがある整形外科医・形成外科医にオススメ.解剖編では献体写真・イラストを用いて肉眼解剖や機能解剖を示し,臨床編では手術手技をステップごとに丁寧に解説.エキスパートならではの知恵や経験に裏打ちされたポイントも随所に盛り込まれており,日々の臨床現場において即戦力となる1冊です.

臨床整形外科 Vol.60 No.6
2025年 06月号
特集 仙腸関節を科学する
特集 仙腸関節を科学する よりよい臨床・研究を目指す整形外科医の「うまくなりたい」「学びたい」に応える月刊誌。知らないままでいられないタイムリーなテーマに、トップランナーによる企画と多角的な解説で迫る「特集」。一流査読者による厳正審査を経た原著論文は「論述」「臨床経験」「症例報告」など、充実のラインナップ。2020年からスタートした大好評の増大号は選り抜いたテーマを通常号よりさらに深く掘り下げてお届け。毎号、整形外科医に “響く” 情報を多彩に発信する。 (ISSN 0557-0433)
月刊、増大号を含む年12冊

Dr.増井の神経救急セミナー 第2版
●著者の大人気セミナーの"公式"副読本!
●『脳卒中治療ガイドライン2015〔追補2019〕』『頭部外傷治療・管理のガイドライン』はじめ,神経救急領域の重要事項アップデートに対応。
●非専門医も知っておきたい「wake up strokeへの対応」「抗凝固薬の拮抗」「血管内治療の適応」もばっちりわかります!

直感で始める診断推論 ―向上のための誤診を恐れるな
◆“診断推論”の本って専門用語が多くてわかりにくい……。そう思って避けている先生も多いのではないでしょうか。
◆本書では生坂先生が医学生や研修医、一般家庭医向けにわかりやすく“診断推論”を解説いたします。まずは小難しい方略はおいておいて「直感」で診断推論を始めてみませんか?
◆実際に遭遇した症例を例に挙げ、どんな「直感」で生坂先生が診断をつけていくのか……?そのノウハウをぜひご覧ください!

血行動態ハンドブック
Step by Stepで理解する体内循環
循環は、液体・器・電線の「足し算」である!
動脈圧波形を「足し算」でイメージするところから始め、3ステップを踏んで血行動態に対する理解を深めていく。エコーなど非侵襲的検査でわかることと、カテーテル検査が真価を発揮するシチュエーションを判断できる力を養い、最後は熟練の循環器医にとっても最難関(最高峰)に位置する疾患群のそれぞれの「核」をつかむ。
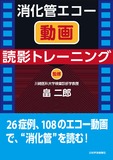
消化管エコー動画読影トレーニング
前処置が不要! 侵襲がない!簡便! 装置も小さく普及度も高い!そしてなんといっても他のモダリティを凌駕する高分解な画像とリアルタイム性!そんなエコーで“ガスが多く、曲がりくねった消化管”をどうやって診ればよいのか。「週刊 日本医事新報」で好評だった連載をコンテンツ化!
4歳から85歳まで、腹痛・嘔吐・下痢等を訴える26症例(26疾患)、108のエコー動画を収録しました! 消化管エコー研究会の「診断に役立つ10のポイント」:(1)部位と分布、(2)壁の厚み、(3)層構造、(4)エコーレベル、(5)壁の変形、(6)内腔の拡張・狭小化、(7)壁の硬さ、(8)蠕動、(9)壁外の変化、(10)血流評価、に沿った解説で、診断までの手順とポイントごとの分析・解析方法が身につきます。
監修者曰く「CT以上の診断だって可能!」〜消化器内科の医師はもちろん、エコーに興味のあるすべての医療従事者の方にオススメです!

腰痛のプライマリ・ケア
腰痛者と向き合う時の必携書
腰痛は人類の8割以上が経験する症候である.本書では,整形外科外来はもちろん,総合診療科や一般内科外来において患者数の多い腰痛,すなわち障害程度が低いものの日常の診療で診る機会が多い腰痛を中心に解説する.腰痛のプライマリ・ケアで求められる“震源地(=病態)と震度(=障害程度)”の適切な評価方法と最適な対処方法について,運動器を専門としない臨床家が理解・実践できるよう,平易な表現で紹介する.

わかる!身につく! 病原体・感染・免疫 改訂4版
病原体の分類・特徴,病原体感染とその防御のしくみについて,わかりやすく丁寧に解説した教科書です.記述内容について最新の知見を反映して情報の更新を行い,豊富な図表をカラー化して視覚的にもさらに理解しやすくリニューアルしました.医療従事者を目指す学生に最適の一冊です!

Dr.TT流 アクセプトされるケースレポート論文 9つの頻出パターンと攻略法
『無敵の腎臓内科』著者・Dr.TTによる,“アクセプトされる”ケースレポート論文の書き方解説本が登場!
『無敵の腎臓内科』著者・Dr.TTによる,“アクセプトされる”ケースレポート論文の書き方解説本が登場!
まだケースレポート論文を書いたことがない人から,何度か挑戦してみては挫折してしまった人にも使えるように,モチベーションの保ち方から,症例選びのコツ,投稿先の決め方,実際に書き上げる段階まで,この1冊に完全収録.著者の研究と経験から導き出された,アクセプトされるために必要な再現性の高い理論やノウハウを,優しく平易な言葉遣いと豊富な図表を用いて分かりやすく解説します.

消化器内視鏡37巻8号
動画で魅せる内視鏡的創閉鎖法のすべて
動画で魅せる内視鏡的創閉鎖法のすべて

臨床外科 Vol.78 No.11
2023年 10月号(増刊号)
特集 消化器・一般外科研修医・専攻医サバイバルブック 術者として経験すべき手技のすべて
特集 消化器・一般外科研修医・専攻医サバイバルブック 術者として経験すべき手技のすべて 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 (ISSN 0386-9857)
月刊、増刊号を含む年13冊
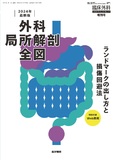
臨床外科 Vol.79 No.11
2024年 10月号(増刊号)
特集 2024年最新版 外科局所解剖全図 ランドマークの出し方と損傷回避法〔特別付録Web動画付き〕
特集 2024年最新版 外科局所解剖全図 ランドマークの出し方と損傷回避法〔特別付録Web動画付き〕 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 (ISSN 0386-9857)
月刊、増刊号を含む年13冊

嘱託産業医スタートアップマニュアル【改訂第2版】 2
これ一冊で産業医の仕事がわかる「未経験者のための業務マニュアル」
産業医講習会では教えてもらえない実務のハウツーを解説
◆これから嘱託産業医を始める人のために、必要最小限のノウハウをまとめた業務マニュアル。これ一冊あれば産業医として仕事をスタートできます。
◆健康診断、職場巡視、長時間労働者の面接指導、メンタルヘルス面談、ストレスチェック、就業配慮など、各種業務の流れとチェックポイント、報告書や意見書の書き方を解説しました。

症例を通して学ぶ年代別食物アレルギーのすべて 第3版
改訂3版では年代別の分け方を「乳幼児期」「学童・思春期」「移行期」「成人期」とし,乳幼児期発症の食物アレルギー患者の成人診療科への移行についても解説.学術論文やガイドライン等では埋められない細かい点(ヒントやコツ)を多くの症例から学べる実践書.さらに一歩進んだ「食物アレルギー」の診療が可能に!

我々の足の外科
手術手技アトラス
匠の技を継承する──奈良医大式・足の外科の真髄
奈良医大・足の外科診療班が長年にわたり築いてきた手術手技のエッセンスを余すことなく公開。前方アプローチによる前方移動骨移植術を用いた足関節固定術をはじめ、試行錯誤を重ねて磨き上げた術式について、豊富な写真とイラストで紹介。各々、手術適応や術式選択、手技のコツとピットフォールも漏れなく解説。「詳しい手術記録」のように参照しやすく、明日からの手術に活用できる、教科書を超えた、現場で本当に使える手技書。
