
≪非腫瘍性疾患病理アトラス≫
肺
非腫瘍性肺疾患には,感染症,間質性肺疾患,肺高血圧症等々,多岐にわたる疾患が含まれ,肺の構成要素を複合的に侵す.これらの疾患を理解するために「肺の解剖学的・組織学的所見に照らした病変分布」を意識しながら平易に解説.組織写真とともに,必要に応じてX線画像,肉眼写真やシェーマも用いる.総論では胎齢期の組織像が提示され,各論には剖検でしかみることがない疾患や,病理像から病因に迫るユニークな考察もある.

臨牀消化器内科 Vol.40 No.5
2025年5月号
膵・消化管 神経内分泌腫瘍の診療アップデート
膵・消化管 神経内分泌腫瘍の診療アップデート
神経内分泌腫瘍では的確な診断のもと治療戦略を決定しなければならない.本特集では,診断において最も重要な組織診断をはじめ,画像診断およびその病態についても詳細に解説し,内視鏡的治療,外科的治療および放射線治療を含む薬物療法の最新の情報を発信している.
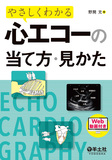
やさしくわかる心エコーの当て方・見かた
プローブの当て方と心エコー像の対比で,心臓を思い通りに見る方法がすぐわかる!プローブの持ち方から画像の計測・評価,報告レポートの書き方まで解説した,初学者にやさしい実践書!

股関節学 第2版
根拠にもとづく記述を基本に,基礎から臨床まで股関節に関連する専門的な知識を網羅し,詳しく解説.初版(2014年)出版後の新しい情報・エビデンスを盛り込み,さらに充実を図った.改訂のポイントはA4変形判からB5判にサイズを変更,誌面デザイン・書籍仕様を一新した.また各種ガイドラインの更新に合わせて内容をアップデートし,新たに,ロボット手術・リハビリテーション治療・データベース研究の項目を設けた.

「その」手術室外での鎮静・鎮痛 安全ですか
検査・処置や救急・集中治療の現場で欠かせない「鎮静と鎮痛」。適切な管理は患者の苦痛を和らげる一方、薬剤反応の差により重篤な合併症を招く危険を伴う。
本書は鎮静の基本概念から安全に行うための体制・機器・人員までを体系的に解説。さらに、各領域での安全な実践を専門家が解説するとともに、臨床で役立つチェックリストも巻末に収載した。
手術室外における鎮静の質と安全性を高めたい全ての医療者に必携の一冊!
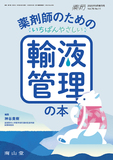
薬局 Vol.76 No.11
2025年9月増刊号
薬剤師のためのいちばんやさしい輸液管理の本
薬剤師のためのいちばんやさしい輸液管理の本 臨床現場では,患者の体液を適切に管理する「輸液療法」が欠かせません.輸液の目的は水・電解質の補給や血管の確保,疾患の治療など多岐にわたります.またほとんどの製剤が透明の液体で,外観も類似したものが多くあります.そのため,輸液療法や輸液製剤の複雑さやわかりづらさに直面し,薬学部で学んだ知識を臨床で活かしきれていない,と感じる薬剤師も少なくありません.そこで本書は“やさしく学ぶ”と“現場目線”を合言葉に,輸液の基礎から実践までを入門者に向けて図やイラストを多く掲載し解説しました.前半では輸液療法を理解するための基本的な知識や,輸液の種類について解説します.輸液管理を実践するためのデバイスや実際の管理方法についても紹介し,病棟や在宅の場面でどのように輸液投与が行われているかをイメージしながら知識を深めることができます.後半は,薬剤師として輸液処方をどのように考え,鑑査・疑義照会するかを解説し,病態の学習へ繋げます.輸液療法の位置づけや典型的な処方例,さらにはモニタリングのポイントまで掘り下げ,現場ですぐに活用・実践できるように解説しました. 執筆には,薬剤師に加え医師,看護師の先生方に携わっていただき,多角的な視点から,よりわかりやすくより実践的で役立つご解説をいただきました.輸液管理は静脈栄養に代表されるように栄養とも繋がりが深く,随所に栄養療法の知識がちりばめられています.本書が輸液に対する苦手意識の解消と,輸液管理や栄養療法の臨床業務に役立つ一冊となれば幸いです.

画像所見から絞り込む!頭部画像診断やさしくスッキリ教えます
“画像診断はできれば誰かに任せたい”と思っていませんか?本書で苦手意識を払拭!所見ごとの診断ステップを丁寧に解説.鑑別のフローチャートで救急・外来ですぐ調べられ,見落としなく適切な判断に繋げられる!

運動器の計測線・計測値ハンドブック
臨床の場で必要となる体表・X線・CT・MRIによる運動器の計測線・計測値を,明快なイラストと解説で示したデータブック.主要な計測線・計測値を網羅し,定義や基準値のほか,今日的な解釈や診断との結びつけなどの臨床的意義を解説.撮像のコツや最新のエビデンスを示す文献のサマリーも提示し,多忙な現場で役立つ一歩進んだ知識を習得できる.

プチナース Vol.35 No.2
2026年2月号
4号連続!第115回看護師国試対策号第4弾!
■必修問題でたとこまとめ
■頻出&得点源!見るだけ看護技術
4号連続!第115回看護師国試対策号第4弾!
■必修問題でたとこまとめ
■頻出&得点源!見るだけ看護技術

≪皮膚科サブスペシャリティーシリーズ≫
1冊でわかる皮膚病理 第2版
皮膚科医・病理医必携の大ヒット病理テキストが15年の時を経て大改訂.要点を絞った解説と,見開きの見やすい構成,わかりやすい写真説明は初版のままに,疾患数も写真も大幅に増やした.疾患解説には臨床像を提示.病理像と合わせてみることで疾患の理解も深まる.日常診療やカンファレンスはもちろん,初めての疾患に遭遇したときに,まず開く1冊.皮膚病理が苦手な医師もエキスパートも,皮膚病理を見る全ての医師の強い味方.
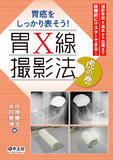
胃癌をしっかり表そう!
胃X線撮影法 虎の巻
撮影手技を基本から応用まで段階的にマスターできる!
胃癌の正確な診断には,精度の高い画像が必須!
5段階ステップアップ方式で,胃X線撮影技術の基本から応用までマスター!ビギナーからベテランまで役立つ,胃がんをきっちり撮影できるようになる本!

対症療法の強化書 頻用薬の使い方と非薬物療法
本書は病因に対応した根本治療のない病態に対して「患者さんに我慢をさせない」「とりあえず、漫然との対症療法を卒業する」ための知識とスキル向上に特化した、文字通り対症療法の強化本となります。
対症療法総論、風邪診療、作用機序から考える痛みへの対症療法、コモンな神経症状、メンタルヘルス不調、コモンな呼吸器・アレルギー症状、コモンな消化器系症状、泌尿器系症状、婦人科系症状、臓器を特定できない症候への対症療法など全10部で構成されており、それぞれ、エキスパートたちの実践智やプライマリ・ケア現場で役立つコンテンツが収録されています。
病因に対応した根本治療がないときでも、病態を正しく理解し、基礎的な薬理学(薬のメカニズム)を理解したうえで処方を行えるように、慢性疼痛に対する認知行動療法的アプローチの基礎など非薬物療法のエッセンス、東洋医学や漢方、リハビリ・運動療法処方など、対症療法の「引き出し」を可能な限り盛り込みました。ぜひ、「患者さんに我慢をさせない」「とりあえず、漫然との対症療法を卒業する」ための日常診療のレベルアップにご活用ください。

PCI・EVT・SHDインターベンションスペシャルハンドブック
冠動脈インターベンション(PCI)と末梢血管インターベンション(EVT)に関する総合的な知識を提供した好評書『PCI・EVTスペシャルハンドブック』がリニューアル.今回は新たにSHD(structural heart disease)インターベンションについても盛り込み,病態や診断の基本,各種デバイスの概説,手技のコツなど,臨床現場で必要な情報をギュッと凝縮.白衣のポケットに入るサイズで,若手医師の知識整理にも役立つ一冊.

≪整形外科SURGICAL TECHNIQUE BOOKS 14≫
膝の外傷
【膝の骨折、靱帯、半月板、軟骨損傷を網羅!】
「膝」の骨折、靱帯損傷、半月板損傷、軟骨損傷をまとめた整形外科医必携の手術テキスト。それぞれの外傷の診断、手術適応、手術手技について詳述。手技については、豊富な写真・イラスト・web動画でコツとピットフォールを確認できる。

薬剤師のためのクリニカル・パール
至言が生み出す臨床業務の新たな視座
医師の世界には、普遍性を備え短く洒脱で臨床判断に光を射す「クリニカル・パール」と呼ばれる格言が存在します。しかし、薬剤師の世界には、現場で輝くパールがあるにもかかわらず、それらをまとめた書籍はこれまで見当たりませんでした。本書は、薬剤師特有のパールを言語化した画期的な一冊です。単なる豆知識ではなく、経験豊富な臨床家の洞察や普遍性を宿した「言葉の結晶」を目指しました。制作過程ではAIのアイデアも取り入れつつ、短歌のように言葉を丁寧に練り上げ、あえて洗練さよりも執筆者の「思い」や「未完成の美しさ」を優先しています。臨床現場では静かなセーフティネットとなり、ここぞという場面では頼れる武器となる一冊です。

東洋療法学校協会編教科書 生理学 第3版【2025年1月10日 第3版第12刷】
本商品は2025年1月10日発行の「第12刷」となります.ご購入の際は刷りに間違いがないか再度ご確認いただきますようお願い申し上げます.
生理学の学習に必要な知識をわかりやすくまとめたテキスト.今改訂では複雑な人体の仕組みを理解しやすいよう,シェーマによる工夫を行い,簡潔な表現で解説した特徴をさらに進化させ,さらに授業で使いやすい工夫が盛り込まれるなど全面的に見直した.

静がんメソッド 消化器癌・頭頸部癌編<第3版>
静がん シリーズ「消化器癌・頭頸部癌編」、待望の改訂版!
◼ 大規模試験やガイドライン改訂に合わせて,レジメンを大幅追加。
◼ EBMを主軸にしながらも,臨床現場で培われた経験的ポイント・治療のこつを具体的にわかりやすく記載。
◼ 癌化学療法の実臨床で生じる「困った!」「悩む…」といった現場の声に,“静がん”(静岡県立静岡がんセンター)が惜しみなくメソッドを公開しています。

ラダーと事例から学ぶ家族志向のケア--家族療法の考え方とスキルをプライマリ・ケアに活用する
患者個人の問題は家族の問題でもある?!
「家族が絡む事例にどのように向き合うか?」「個別性の強い家族への対応をその場しのぎにしないためには?」など,患者の背景に存在する家族問題への介入は容易ではありません.家族は複数のメンバーがそれぞれの気持ちや考えをもち,相互に複雑な関係性をもち,また家族にはそれまでの歴史や文化があるためです.本書は家族をシステムとしてとらえ,家族療法の理論・スキルを応用し,さまざまな医療現場で実践できるように工夫しました.総合診療,家庭医療でトレーニング中の医師はもちろんのこと,家族問題に難しさを感じたことのある医療者であれば誰でも役に立つ内容となっています.
【家族志向のケアにおけるラダー式学習目標】
レベルごとの技術をマスターして,家族問題への適切な介入を目指そう.
レベル 1「医師主導で情報を扱う」,レベル 2「双方向に情報を扱う」,レベル 3「感情面を扱う」,レベル 4「家族関係を扱う」,レベル 5「困難事例を扱う」

胎児心エコーのすべて
スクリーニング・精査・治療・そして家族支援
心奇形の頻度は,生産児100人に対して1人の割合で発生するといわれているが,そのうちの1/3が重症心奇形であり,乳児死亡の最大の原因となっている。現在,胎児診断率は上昇し,その結果が救命率の上昇にとどまらず,合併症や後遺症のない救命,最終的には経済効率のよい医療に結びついている。さらに,出産後に診断される児に比べ,胎児診断された児は,出生後早期に状態が悪化するEbstein病,総肺静脈還流異常,肺動脈弁欠損などの超重症心疾患で出生後24時間以内の手術が必要な場合でも,手術に対応することができるようになり,救命率は著しく上昇している。また,出産時に病名が判明している場合は,分娩時にバルーン心房中隔切開術などの術式を用いることも可能となり,胎児診断が児の救命率に大きく関与しているといえる。この胎児診断の主軸を担っているのが「胎児心エコー」である。
本書では,豊富な画像を用い,スクリーニング,精査,治療を徹底解説。家族への告知についても,神奈川県立こども医療センターで長年培ってきたメソッドを,両親への説明図とともに公開。神奈川県立こども医療センターの胎児診断率も各疾患ごとにグラフ化されている。本分野の第一人者である川瀧元良先生の集大成本,ついに刊行!

基礎からわかる!若手整形外科医のための小児整形外科疾患
小児整形外科診療のニューバイブル誕生!
若手整形外科医を含む一般整形外科医のみならず、研修医やプライマリ・ケア医など子どもに関わるすべての人へメッセージが満載!
子どもに多い整形外科疾患を「基礎から・わかりやすく・丁寧に」解説!
本書の推しは、肘内障・「歩行障害」と「成長痛」の鑑別診断・股関節脱臼・内反足・筋性斜頚など紙面に対応した52本の動画。
肘内障の整復法や整復時のエコー動画なども繰り返しチェック可能です。
