
関節外科 基礎と臨床 Vol.40 No.12
2021年12月号
【特集】大腿骨頭壊死症の基礎と臨床Up to date
【特集】大腿骨頭壊死症の基礎と臨床Up to date

臨牀透析 Vol.37 No.12
2021年11月号
CKD・透析患者の栄養指導方法と実践
CKD・透析患者の栄養指導方法と実践 br> 本号では,最新の栄養情報とともに慢性腎臓病(CKD)における栄養・食事管理を行ううえで重責を担う管理栄養士の専門資格やその役割を示した.CKD は生活習慣病とも深い関係があり,保存期からの生活や食事・診療の管理が予後に大きく関与している.

救急医学2021年11月号
あつまれどうしょくぶつの毒
あつまれどうしょくぶつの毒 ‟万一のとき”の診察に役立つように、毒をもつ動植物とその毒に関して、その道のエキスパートや実際に症例を経験した先生方が詳しく解説。数年後・数十年後に「アレ読んでおいてよかった!」という瞬間が訪れることを信じて、まずは興味本位からでも、目を通してみてください。

消化器外科2021年11月号
メリットを最大限に活かそう!;消化器外科のロボット支援下手術
メリットを最大限に活かそう!;消化器外科のロボット支援下手術 ロボット支援下手術は多関節、モーションスケール、手振れ防止などの機能を有しており、腹腔鏡下手術の動作制限を克服し、より繊細な手術ができるものとして期待されている。消化器外科分野においては、今後さらに応用分野が広がっていくと考えられる。本特集では消化器外科分野のロボット支援下手術の現状と展望、さらに各分野の手技のコツや工夫について、第一線の先生に解説をいただいた。

肝臓クリニカルアップデート 2021年10月号
2021年10月号
特集:肝癌診療2021 アテゾリズマブ+ベバシズマブ登場後の展開
特集:肝癌診療2021 アテゾリズマブ+ベバシズマブ登場後の展開

Prostate Journal 2021年10月号
2021年10月号
特集:日本発の臨床研究からみた前立腺癌診療
特集:日本発の臨床研究からみた前立腺癌診療

アフターワクチンの新型コロナ感染対策
ワクチン接種後のモヤっとを解決!
● ワクチン接種後に変わること・変わらないこと,だれもが抱える「モヤっと」をDr. 矢野が大解決!!
● 経済活動も日常生活も,そしてコロナ対策も重要視した「アフターワクチン」生活について,最新の情報とエビデンスから解き明かします。
● ワクチン接種で新型コロナ感染対策はどうなるのか? これからの新型コロナ感染対策の道筋を示す1冊が登場。

≪腫瘍病理鑑別診断アトラス≫
卵巣腫瘍
本書は,種類がきわめて多く,それらの肉眼像も組織像もきわめて多彩である卵巣腫瘍について,初学者でも理解がしやすいように,『卵巣取扱い規約 第1部』(2009年)の腫瘍分類の底本ともなった2003年のWHO分類における定義を明確にすることからはじめ,わかりやすくかつ正確な言葉で所見や鑑別診断を解説した.また,執筆者自らの成績から得た経験的知見を加味することで,わが国の卵巣腫瘍の実状が浮き彫りになる構成とした.

≪腫瘍病理鑑別診断アトラス≫
甲状腺癌
甲状腺癌は,予後良好な乳頭癌・濾胞癌から,きわめて増殖スピードが速く,有効な治療のない未分化癌にいたるまで,さまざまな生物学的態度を示す病態がある.本書は,取扱い規約やWHO分類を読んだだけではわかりづらい実際の取り扱い,診断のポイントとコツをわかりやすく記載するほか,低分化癌やCASTLEなどの新しい疾患概念の解説,依然として重要な課題である濾胞癌と濾胞腺腫の鑑別,穿刺吸引細胞診についても盛り込んだ.

≪腫瘍病理鑑別診断アトラス≫
皮膚腫瘍II
メラノサイト系腫瘍とリンパ・組織球・造血系腫瘍
皮膚腫瘍は,組織学的に多彩であると同時に腫瘍概念も多彩で,WHO分類でもさまざまな問題点を内包している.そこで本書は,その矛盾点を整理し訂正した形で組織分類を提示し,アトラスとして明快に解説した.2分冊の1冊目となる『皮膚腫瘍II』では,メラノサイト系腫瘍とリンパ・組織球・造血系腫瘍を取り上げる.皮膚科医と病理医にとって皮膚腫瘍に関するひとつの「共通語」を提供し,相互理解を促進する病理学的ガイドライン.

≪腫瘍病理鑑別診断アトラス≫
皮膚腫瘍I
角化細胞性腫瘍,付属器系腫瘍と皮膚特有の間葉系腫瘍
皮膚腫瘍は,組織学的に多彩であると同時に腫瘍概念も多彩で,WHO分類でも様々な問題点を内包している.そこで本書は,その矛盾点を整理し訂正した形で組織分類を提示し,アトラスとして明快に解説した.2分冊の1冊目となる『皮膚腫瘍Ⅰ』では,角化細胞性腫瘍,付属器系腫瘍と皮膚特有の間葉系腫瘍を取り上げる.皮膚科医と病理医にとって皮膚腫瘍に関するひとつの「共通語」を提供し,相互理解を促進する病理学的ガイドライン.

Journal of Internet of Medical Things Vol.4 No.1
2021年10月号
特集 1 これからの医療・IoMT/特集2 コロナ時代のIoMT
特集 1 これからの医療・IoMT/特集2 コロナ時代のIoMT
本誌『Journal of IoMT』は医療におけるIoT(IoMT)、AI、ロボティクスやそこから収集されるビッグデータならびに新しいテクノロジーへの挑戦をキーワードとして新しい情報発信を行います。

≪脳神経外科診療プラクティス 7≫
グリオーマ治療のDecision Making
今般病理組織学と分子生物学の両面からグリオーマ病態診断が導入されつつあるが,これらの新たな診断によってグリオーマの標準治療が更新されるには少し時間がかかると予想されるので,まずは将来を見据えた視点を持ちながら今の標準治療とその根拠を整理するべきである.本書では,神経上皮性腫瘍全体をグリオーマと定義しているがそのすべてを網羅することはせず,特に標準治療として知っておくべき項目をピックアップした.

≪脳神経外科診療プラクティス 8≫
脳神経外科医が知っておきたい薬物治療の考え方と実際
わが国の脳神経外科医が欧米と大きく異なる特徴は,手術以外にも術前・術後管理はもちろん,リハビリテーションや外来などを含め,薬物療法にも日常的に関与する点である.これは、総合的に患者の診療を行えるという大きなメリットがある.本書では,多忙な脳神経外科医が診療業務の合間を利用して,日常使用する幅広い薬剤に関する基礎的・臨床的知識の確認ができることを目標に編集した.

必修 救急救命士国家試験対策問題集2022
これだけやれば大丈夫!
救急救命士国家試験問題の過去5年分(第40~44回)の問題を,救急救命士国家試験出題基準の掲載順に準じて分類することで,能率的なジャンル別学習ができる.掲載順はA・B・C・D問題別(一般問題,必修問題,症例問題別学習)とし,参照は【第10版】救急救命士標準テキストに準拠している.年々厳格化される国家試験を乗り切るだけでなく,より深く病態を理解する真の医療人を目指す全ての学生・研修生に推薦したい一冊.

≪BEAM(Bunkodo Essential & Advanced Mook)≫
患者を末期腎不全にしないための CKD診療のコツ
若手医師が求める日常診療のエッセンスをよりすぐり,かつ一歩進んだ知識を提供するムックシリーズ第11弾.レジデントがCKD患者を受け持った時,どうマネジメントしてゆけばよいか?CKDから末期腎不全へ進展させずに管理するための診療のコツを,『CKD診療ガイド2012』に準拠しわかりやすく解説.初期~後期研修医が自分のレベルに応じて理解していけるようステップを踏んで学べる目次構成となっている.
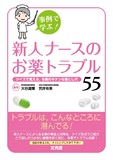
事例で学ぶ! 新人ナースのお薬トラブル55
クイズで覚える,与薬のキケンな落とし穴
新人看護師による薬がらみのトラブルの中でもとりわけ頻度・重要度の高いものを精選し,クイズ仕立てで紹介した一冊.55の各caseにはそれぞれ簡単な状況説明とそのイラストがあり,読者はまず「この状況のどこに落とし穴があるでしょう?」と問いかけられ,「何がいけなかったのか」「(ミスの結果)どうなってしまうのか」「ではどうすればよかったのか」というステップで解説.クイズ形式でよくわかる,与薬の危険な落とし穴!

理学療法士のための 在宅療養者の診かた
評価をプログラムに反映させる
症例を通して,在宅療養者に対する理学療法の評価からプログラムの立案まで,実際の流れに沿って解説した実践書.冒頭に症例を掲げて,理学療法評価を実施する順に記述.最後に初期評価の結果をまとめ,どのように理学療法プログラムへ反映させるか,根拠を示しながら解説した.用語や手技などの説明はMEMOとして,臨床の現場で役立つヒントや工夫はクリニカルヒントとしてまとめた.

臨床栄養 139巻6号
CGM/FGMを用いた糖尿病治療-血糖トレンドを栄養指導に活かす
CGM/FGMを用いた糖尿病治療-血糖トレンドを栄養指導に活かす
重症低血糖の予防や血糖値の日内変動を捕捉する方法としては従来,1日数回のスポットで行う血糖自己測定(SMBG)が用いられてきましたが,近年,これを補完する方法として,血糖トレンドを持続的に把握するCGM(continuous glucose monitoring)やFGM(flash glucose monitoring)の有用性に注目が集まっています.CGM/FGMでは,機器から得られる大量の血糖データを解析することでTIR(time in range)などの新たな評価指標が得られるようになり,また,スマートフォンなどのデジタル機器を用いて患者と医療者が情報を共有できるようになるなど,患者への指導・介入において大きな変化をもたらしています.
本特集では,本領域で先進的な取り組みをされている先生方に,現在使用できる機器の特性をはじめ,得られるデータおよび評価指標とその活用についての考え方,また薬剤ごとの血糖変動の特徴から考える治療薬の選択,チームで取り組むデータマネジメントシステム指導TMなど,CGM/FGMを臨床に取り入れるにあたっての基礎知識を整理していただき,さらに,管理栄養士にとって重要な栄養・食事指導への活かし方については,実際の症例を含めてご解説いただいています.
糖尿病の食事指導においては近年,ガイドラインなどで柔軟な個別化指導を重視する方向性が示されていますが,その潮流の中で,本特集が血糖トレンドを活かした新しい栄養業務につながる一助となれば幸いです. (編集部)

糖尿病プラクティス 38巻6号
GLP-1受容体作動薬への期待:新規創薬からの更なる飛翔-血糖値だけでない!その実力-
GLP-1受容体作動薬への期待:新規創薬からの更なる飛翔-血糖値だけでない!その実力-
