
保健・医療職のための生命倫理ワークブック
本当によいことなのか、もう一度考えてみよう!!
何が正しいことなのか、正しいことが本当によいことなのか ?
判断の難しい、さまざまな状況のシナリオに対して想像力を働かせ、自分の身近な例と結びつけて考えることで、日常生活の中に潜む倫理問題(虐げられた尊厳や不平等)に気がつくことができ、倫理的感受性が高まる一冊。
正しいこと、よいことをしようと思うのは大切なことです。ところが、何が正しいことなのか、あるいは正しいことが本当によいことなのか、判断が難しい場合があります。頭を悩ませ、心を苦しめる問題について、私たちはどのように考え、どのような態度をとったらよいのでしょうか。
本書は、まずシナリオを提示し、その状況を想像し質問に答えていくことで、生命倫理について考える練習ができるように作成しました。グループで話し合いながら使うと、自分では思いつかないような考えに出会うことができ、物事を広い範囲で考えることができます。一人で本書を使うときにも、他の人だったら、どんな意見を言うかを想像してみるとよいでしょう。大切なことは、早く正解を出すことではなく、できるだけ多くの異なる意見を出したうえで、その意見一つひとつを理解して、よりよい意見はどれだろうと考えていくことです。
本書で用いたシナリオはすべてフィクションですが、想像力を働かせ、自分が知っている実例を思い出し、結びつけて考えてみてください。自分の身近な例と結びつけることで、日常生活の中に潜む倫理問題(虐げられた尊厳や不平等)に気がつくことができ、倫理的感受性が高まります。リハスタッフ、看護職には是非ご一読いただきたい一冊です。

臨床眼科 Vol.76 No.4
2022年4月発行
特集 第75回 日本臨床眼科学会講演集[2]
特集 第75回 日本臨床眼科学会講演集[2] 読者からの厚い信頼に支えられた原著系眼科専門誌。厳選された投稿論文のほか、眼科領域では最大規模の日本臨床眼科学会の学会原著論文を掲載。「今月の話題」では、気鋭の学究や臨床家、斯界のエキスパートに、話題性の高いテーマをじっくり掘り下げていただく。最新知識が網羅された好評の増刊号も例年通り秋に発行。 (ISSN 0370-5579)

さあ! 事例研究に挑戦しよう
臨床看護の現場での看護者の体験や経験こそが,臨床における看護の知であり,埋もれさせてはいけない実践知である.
本書は臨床現場で働く看護者が楽しく取り組めるよう,ワークシート形式で事例研究のステップを示し,わかりやすく解説した.また,身近な具体的事例を使ってどのように事例研究に取り組めばよいのか,ステップを踏みながらポイントが理解できるよう工夫した.読者が事例研究への理解を深め,興味をもって事例研究に取り組み,臨床現場から発信する事例研究の第一歩となるよう解説した.

運動療法としてのピラティスメソッド
アスリートに対する実践的プログラミング
PARTIではピラティスの歴史,医療やコンディショニングの現場からピラティスに関わる研究などの各論を,PARTIIでは部位別の機能改善を目的としたピラティスアプローチを代表的なピラティスの器具を使用して解説している.PARTIIIでは大きなピラティス器具を設置できない様々なスポーツ現場において,持ち運びできるものや現場で用意できるものを使用して,同じ効果の出せるピラティスアプローチをどのようにしているかを解説している.

麻酔科で使う薬の疑問58
研修医,若手麻酔科医が麻酔を学び,用いる上でつきあたる薬の疑問を集めたQ&A形式のガイドブック.「揮発性吸入麻酔薬はどうして効くか?」「プロポフォールが持続投与で使われる理由は?」といった作用機序にまつわる質問から,「揮発性麻酔薬と静脈麻酔薬はどのように使い分けるか?」「高齢者での薬物使用の注意点は?」といった臨床上の問いに至るまで幅広く解説した.各項目の末尾には「まとめ」としてポイントを要約.

X線と内視鏡の比較で学ぶ
H.pylori胃炎診断
新時代の胃がん検診を目指して
本書は「ピロリ菌感染を考慮した胃がん検診研究会」編集による背景胃粘膜診断テキスト.読者には「1章 診断法」でピロリ菌感染診断の知識について学んだ上で,ぜひ「2章 症例提示」で「ピロ研」名物の参加型の演習コーナーを紙上体験していただきたい.「3章 今後の展開」では胃がん検診の課題と今後の方向性について詳細に解説される.胃がん診断・ピロリ菌感染診断に携わる,消化器内科医,検診医,放射線技師,必携の1冊.

膵癌早期診断実践ガイド
膵癌は極めて予後不良な悪性腫瘍で,死亡者数は年々増加しており,予後改善のためには,微小膵癌のうちに早期診断する必要がある.本書では,微小膵癌を発見するための,膵臓の精査を勧めるべき患者を見分けるポイント,画像診断のポイントについて,膵癌早期診断研究会の中心的メンバーが余すところなく解説.実際の早期診断例や各地での早期診断の取り組みも掲載しているので,早期診断の実践に向け,ぜひご活用いただきたい.

肝疾患診療に役立つ
肝線維化評価テキスト
肝生検から非侵襲的な検査の時代へ
B型・C型肝炎,脂肪肝などの肝疾患において,肝線維化は病気進行度や発癌リスク予測をする上で重要なファクターであるが,現在の肝線維化評価のゴールドスタンダードである肝生検は侵襲性やサンプリングエラーなどの問題がある.本書では,肝生検にかわり,非侵襲的に肝全体の線維化の程度を評価できる検査法として期待されるデバイスや線維化マーカー,スコアリングの概要から臨床への応用について,第一線の専門家が解説する.

ケースで学ぶ不明熱の診断学
エキスパートの頭の中を覗いてみよう
『この1冊で極める不明熱の診断学』の姉妹編.「症例から診断にいたる実例が知りたい」という読者の要望に応え,原因不明の発熱に対する診断の過程を①Review of Systems,②Problem List,③鑑別診断,④確定診断・除外診断,⑤最終診断,⑥不明熱エキスパートの診断・治療戦略,という構成で明快に解説,更に要所要所に「不明熱エキスパートの頭の中」を挟むことによって一層リアルに過程を追体験できるようにした.研修医,内科医必携の一冊.

検査データの「?」に答えます!
臨床検査で得られる結果は,測定や検体保存の際の行為によって影響を受けたり,患者の個体差や病態によって基準値が変わったりと,様々な「落とし穴」が存在する.本書は,第1章では検査時の体位による変動など,各検査に特有でない横断的な「落とし穴」を,第2章では,一般検査,血液検査,生化学検査,免疫検査,感染症検査それぞれに特有な「落とし穴」を,日々コンサルテーションに対応しているベテラン臨床検査医が解説.

すっきりフローチャートで学ぶ小児の麻酔
小児麻酔を敬遠している先生に少しでも積極的に取り組んでもらえるよう企画された入門書。基本的な疾患や病態を取り上げエキスパートの思考過程を簡便なフローチャートに。

たこつぼ症候群
これまでの歩みと未来へのメッセージ
「たこつぼ(takotsubo)」は、そのまま世界に通じる有名な心筋症となった。その名を広めた土橋・上嶋による総決算。日本発信の本疾患のこれまでとこれからとは?

読んでおきたい麻酔科学論文
編者が綺羅星の如くある論文から(citation indexの高いものを選択し、類似テーマを整理し)62編を選出し、各分野の一人者が解説。温故知新
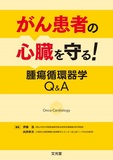
がん患者の心臓を守る!腫瘍循環器学Q&A
がん治療の進歩により,がん患者の生存率が大幅に改善され,さらに新しいがん治療法も次々と生み出されている一方で,がんサバイバーの心血管疾患による死亡や,がん治療による心毒性が話題となっている.これらの問題に取り組む新たな学際領域として「腫瘍循環器学(Onco-Cardiology/Cardio-Oncology)」が生まれた.本邦ではまだ数少ないエキスパートの先生方に主要なテーマをQ&A方式で執筆して頂き,1テーマ見開き2ページの簡潔なスタイルでまとめた.

呼吸器疾患の薬物療法を極める
呼吸器内科領域の薬物療法の進歩は近年,一層加速しており,専門医でも最新知識をアップデートすることは容易ではない.本書では,各専門領域の第一線のエキスパートが,ガイドラインでは記載しきれない薬物療法のポイントを解説する.最新の知見が,エキスパートオピニオンを交えて解説されており,実臨床に即した呼吸器疾患における薬物療法の「コツ」,「落とし穴」がふんだんに盛り込まれた1冊となった.
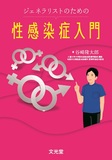
ジェネラリストのための性感染症入門
性感染症の診療には,医学的な知識があるだけでは不十分で,患者とそのパートナーの心情や社会的背景にも配慮が必要である.また,性器に関連した症状が出るとは限らず,産婦人科・泌尿器科・皮膚科・感染症内科をはじめ,複数の科にまたがる疾患であり,これまで系統だって学ぶことは難しかった.本書は,そんな性感染症の基本的知識から診断・治療,フォローアップ・予防までを一冊で学べるジェネラリストのための入門書である.

キャッスルマン病,TAFRO症候群
●ひょっとしたら,その患者さんは,キャッスルマン病かもしれません!
●年間発症数は100万人に1人,国内の患者総数1,500人と推定される希少難病「キャッスルマン病」が抱えている医療アクセスの悪さは,そのまま治療開発や研究の遅れにも結びついています。2018年に指定難病(331)に認定され,患者さんの経済的負担は軽減されたとはいえ,類縁疾患のTAFRO症候群は未だ指定対象に含まれていません。
●本書は,キャッスルマン病とTAFRO症候群の最新知見をまとめた初のテキストであり,希少難病の医療アクセス改善もその使命として掲げた成書です。
●医師には,本書をいつも臨床の傍に置いて,確実な診断と専門機関への紹介につなげていただきたい! 一般の方々にも,この希少難病について広く知っていただきたい!
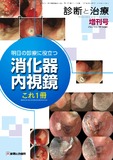
診断と治療 Vol.110 増刊号
2022年増刊号
【特集】明日の診療に役立つ 消化器内視鏡これ1冊
【特集】明日の診療に役立つ 消化器内視鏡これ1冊 消化器内視鏡の最新情報・基本を1冊にまとめました.各臓器・疾患・治療法の適応,全身管理の方法,手技の基本やコツ,最新技術,緊急事態の対応方法までを解説!

すべての診療科で役立つ 身体運動学と運動療法
運動器・運動生理学の基本から,臨床現場で必須の運動処方の流れ,各疾患の運動処方内容・中止基準までを体系的に解説.医師として知っておきたい身体運動学と運動療法の実践的知識が身につく一冊です.

ダメ例から学ぶ 実験レポートをうまくはやく書けるガイドブック
手つかず、山積み、徹夜続き そんなあなたを助けます!
はじめての実験レポートを徹底サポート!豊富な実例を示しながら,実験レポートの構成と作成のだんどりから各項目の書き方まで,わかりやすく解説します.大学生や高校生のレポート指導に携わる先生方にもおすすめ.
