
歯科国試パーフェクトマスター 全部床義歯補綴学 第2版
歯科医師国家試験合格にグッと近づくパーフェクトマスターシリーズ
出題基準改定(令和5年)に対応した改訂版,登場
歯科医師国家試験対策のために愛用されてきた『歯科国試パーフェクトマスター』シリーズが,国試の出題基準改定(令和5年)に対応して新しくなりました.最新の出題基準に対応した本書を活用して大切なポイントをしっかり抑え,歯科医師への道に進みましょう!
・直近の試験問題を精査して対策が記載されているので,各科目の大まかな出題傾向がつかめます!
・図や写真を多く用いているので,わかりやすく,覚えやすい!
・国試対策のほか,CBT対策や定期試験,各科目の授業の予習 ・復習にも活用できます!

脳血管内治療スタート&スタンダード[Web動画付] 改訂第2版
脳血管内治療の不朽の名著が7年ぶりの改訂。橈骨動脈アプローチなど最近の情報にアップデートされた「スタート編」,「脳腫瘍の塞栓」「慢性硬膜下血腫の塞栓」を加えてさらなる充実を図った「スタンダード編」,そして完全新規の「トレーニング編」ではガイディングやデバイス使用のトレーニング方法と上達のコツについて動画も交えて解説する。

徹底深掘り!蜂窩織炎 ジェネラリストのための皮膚軟部組織感染症診療ガイド
できる医師ほどコモンな疾患に手を抜かない
コモンだけど奥深い,皮膚軟部組織感染症診療の羅針盤.ガイドラインだけで解決できない困りごとをまとめて解決!
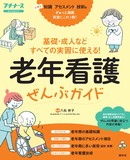
基礎・成人などすべての実習に使える!
老年看護ぜんぶガイド
基礎・成人・老年などすべての実習で求められる老年看護の知識を、これ1冊でおさえることができます。
Part1では高齢者を受け持つうえで欠かせない老年期の身体的変化、心理・社会的変化をはじめとする基礎知識がまとまっており、Part2では具体的なアセスメント項目を豊富に掲載。Part3では高齢者に特徴的な症状や疾患について、最新知識とともに学べます。Part4では、看護技術を写真入りで解説しており、高齢者に援助するときのポイントをおさえられます。

小児科医と内科医のための よくわかる経口補液療法・輸液療法〜体内の水と電解質の流れを極める理論と実践〜
輸液・電解質異常の“こんなことが整理されていたら良いな”がここにある
腎臓・輸液・チャネル・輸送体のエキスパートによる新感覚の輸液の教科書.「体内の水と電解質の流れ」を軸に,ミクロ(臓器の構造や生理機能)とマクロ(ヒトの体全体)の視点を使い分け,経口補液療法・輸液療法の本質に切り込みます.確立された理論体系やガイドラインの背景や意図を洞察することで実臨床に深みが増し,そして臨床で生じる疑問を理論的に解決したくなる,好循環が生まれる一冊です.

専門医を目指す 周産期診療ワークブック 第3版
日本周産期・新生児医学会専門医試験の実際の試験問題からオリジナルに設問を作成し,押さえるべき知識のポイントをまとめ,ポイントに沿ってコンパクトに解説をまとめた。○×式のExerciseで力試しができ,設問に答えていくことで専門医試験に役立つトレーニングにもなる。
専門医試験で押さえるべきポイントは専門医として押さえるべき知識の要点であり,試験対策のみならず,周産期医療の幅広い知識を整理した臨床に即した実践的教科書で,専門医試験対策として,専門医レベルの知識のアップデートとして,合理的に学べる内容となっている。

長野県立こども病院方式
超低出生体重児の管理マニュアル 改訂第2版
わが国の超低出生体重児出生において,高度な医療技術と救命率で知られる長野県立こども病院の新生児科。その管理法をもれなく記載した人気のマニュアルが5年ぶりに最新医学情報とファミリーセンタードケア(FCC)の内容を盛り込んで改訂。フィンランドで学んだ医療者たちが病院に持ち帰ったFCCの理念は長野で受け継がれ,実践を重ね,「家族と一緒に築く医療」として,現在進行形で進化を続けている。最新のNICU治療・チーム医療の詳細とともに,FCCの考え方から医療者のトレーニングの紹介,また,実践内容をFCC Pointとして随所にまとめるなど,ますます充実した内容をお届けする。

医療情報システム入門
『基礎知識から最新動向(医療DX,データヘルス,オンライン資格確認,PHR,HL7FHIR,etc.)まで,病院の情報システムがこの1冊でしっかりわかる!』
本書は、医療情報システムの現状分析と将来展望をまとめた入門書です。電子カルテをはじめとする医療情報システムの導入・活用に取り組む医療機関の方、医療分野を担当するシステム企業の方、特定健診に伴い医療情報システムの理解が求められる保険者の方、大学・専門学校で医療情報を学ぶ学生の方など、幅広い読者を対象としています。
内容は、JAHIS主催の「医療情報システム入門コース」をもとに構成しました。同コースでは、医療情報システムに初めて関わる方を対象に、各部門の専門委員が講師を務め、全体構成からオーダリング、電子カルテ、医事会計、地域連携まで、政策・業務・技術動向を交えて解説しています。
入門コースの蓄積を踏まえ、医療DXやデータヘルスなどの制度的な取り組み、PHRやHL7 FHIRといった新たな技術・仕組みに関する最新動向も現場目線で紹介。図表を活用し、ポイントをわかりやすく整理した実践的な入門書です。

これでわかる!
抗菌薬選択トレーニング
感受性検査を読み解けば処方が変わる
薬剤感受性検査結果の見かた、教えます! 抗菌薬を処方する際には、感染症と抗菌薬の知識はもちろんですが、薬剤感受性検査結果を読み解く力も大変重要です。ところが、今までこの部分にスポットをあてた書籍はほぼ皆無でした。本書では、約60問の精選問題に取り組んでいただくことで、実践で役立つ基礎力が身につくようにしました。抗菌薬適正処方とAMR対策に、医師のほか、ASTにかかわる薬剤師・臨床検査技師にもおすすめです。

脳神経内科 改訂 5版
神経学の魅力を余すところなく伝える,進化し続けるスタンダードテキスト,改訂第5版.
神経系は美しい論理に貫かれた臓器だ.本書は,長きにわたり神経学に真摯に向き合ってきた著者が独自の視点で説き起こし,その魅力を余すところなく伝えている.全篇フルカラーで,重要度によって強弱をつけた紙面は視覚的にも見やすく,理解が進む.前版からの進歩を踏まえ,内容をアップデートした改訂第5版.脳神経内科指導医や一般内科医にとっても有用な内容となるよう工夫された,進化し続けるスタンダードテキストである.
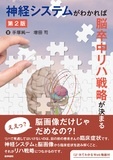
神経システムがわかれば脳卒中リハ戦略が決まる 第2版
神経システムと脳画像から臨床症状を読み解くこと、それがリハ戦略につながります
「神経システム+脳画像=リハ戦略」ではなかった?! リハで見逃してはいけないのは目の前の患者さんの臨床症状です。神経システムと脳画像所見から臨床症状を読み解くこと、それが効果的なリハ戦略につながるのです。本書によってアプローチの選択肢は確実に増えます。それは臨床現場で絶対的な武器となるでしょう。脳画像の見かたや運動療法がみてわかるWeb動画付き。

Onco-cardiologyガイドライン
がんと循環器疾患が重なる領域を扱う新しい臨床研究分野であるOnco-cardiologyに関する本邦初のガイドライン.CQ(clinical question)について,最新のエビデンスに基づく推奨を提示しつつ,エビデンスが不足しているが,今後の重要な課題と考える内容については,現状の考え方をFRQ(future research question)として記載し,さらに基本的な知識で臨床上広く行われている内容についてもBQ(background question)と位置づけ概説した.がんと循環器疾患を合併する患者の診療の指針となる一冊.

JOHNS41巻9号増大号
花粉症の疑問に答える
花粉症の疑問に答える

セラピストのための
機能解剖学的ストレッチング 上肢
関節機能解剖学に基づき,筋それぞれの起始と停止,そして走行を確実にとらえ,伸ばすためのストレッチング手技を解説。セラピストが意識すべき指のあて方・ポジショニングまで,多数のカラーイラストと写真で詳説。
2分冊のうち,本書『上肢』編には肩から手指までの内容を収載している。

褥瘡×嚥下障害×拘縮 ケアに活かすポジショニング技術
褥瘡ケア・嚥下障害ケア・拘縮ケアの現場ですぐに役立つポイントを専門的視点でコラボレーション。
・食事をする際のリクライニング角度は30~40度 これって、褥瘡ができやすい角度では?
・拘縮の強い患者さんが無理なく食事できるポジショニングは?
高齢者ケアの3大課題ともいえる「褥瘡」「摂食嚥下障害」「拘縮」。
発生要因や機序の面からみてもそれぞれ関連し合っていることがわかります。
重度の嚥下障害のある患者のベット上での食事姿勢は30°以上のヘッドアップです。
しかし、褥瘡予防の観点からは30°以上にしてほしくありません。
拘縮の強い患者の食事介助で、誤嚥を防いで、同時に褥瘡を作らないためのポジショニングはどうすればよいのでしょうか。
それぞれの領域のエキスパートが、「三方よし」のポジショニング技術と秘訣を伝授します。

Heart View Vol.30 No.1
2026年1月号
【特集】心不全診療 〜“で,結局どうする?”に効くガイドライン読解術〜
【特集】心不全診療 〜“で,結局どうする?”に効くガイドライン読解術〜

≪画像診断別冊 KEY BOOKシリーズ≫
知っておきたい顎・歯・口腔の画像診断
「顎・歯・口腔」領域についてCT、MRIを中心に口内法/パノラマX線写真も含め、基礎知識から代表的疾患を網羅.
最新の歯原性病変のWHO分類にも準拠しました.
大人気KEY BOOKシリーズの特長である見開き構成で、臨床にすぐ役立ちます!

肺癌診療虎の巻 WJOG肺がんグループのプラクティス
肺癌診療に携わる医師が汎用できるよう,臨床上必要と思われる箇所を強調し,判断に迷う際,参考になるよう,一歩踏み込んだ記載を行っており,このことが患者に説明されるときに役に立つことにもつながるという編集方針で構成されている。
また,すべての項目に対し,著者執筆後に,編者によるレビュー,加筆修正が施され,客観的な検証も行っている。

レジデントのための画像診断アトラス
必ず理解しておくべき全身200疾患
画像診断の知識は,臨床研修修了後に専門研修を放射線科で行う場合はもちろん,全ての診療科・領域で研修を行う際にも不可欠なものである.
研修医にとって重要な全身の疾患を取り上げ,その症例画像(X線,CT,MRI,PET,超音波,内視鏡など)をまとめた1冊.

高次脳機能障害の理解と診察
理学療法士や作業療法士などのメディカルスタッフに必要な神経内科学の知識をわかりやすく解説したテキスト.学校教育における専門基礎分野のテキストとして使用するにあたって反映せるべき2006年の初版以降の新しい知見や進歩,医学的見地などを盛り込むとともに,現状のガイドラインや教育カリキュラムなどを踏まえ,国試にも役立つよう内容を更新した待望の改訂2版
