
医学のあゆみ269巻8号
バーチャルリアリティ(仮想現実)機器の医療応用に向けて
バーチャルリアリティ(仮想現実)機器の医療応用に向けて
企画:住谷昌彦(東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部,同麻酔科・痛みセンター)
・バーチャルリアリティ(VR)とは,その使用者がビデオディスプレイを通じて提示される3D-CGで描画された仮想空間内で,視覚だけでなく聴覚や触覚など複数の感覚環境をリアルタイムで経験できる技術である.
・近年はVRの医学応用も進められ,とくに神経リハビリテーションの分野で活用されている.その治療領域は運動障害(脳卒中後麻痺)や感覚障害(幻肢痛)だけでなく,精神疾患領域にも広がってきている.
・本特集では,急速に医療界でも臨床応用が進んでいるVRの実例について紹介する.VRのさらなる進歩と,現実空間と3D-CGの組み合わせによる拡張現実(AR)の医療応用を考える礎としたい.

医学のあゆみ269巻6号
抗菌薬耐性(AMR)と闘う
抗菌薬耐性(AMR)と闘う
企画:舘田一博(東邦大学医学部微生物・感染症学講座)
・今日,150を超える抗菌薬が開発され,その応用範囲が広がり使用量が増加するなかで,人類はこれまでにない危機的局面に直面している.耐性菌の出現とその蔓延の問題である.
・耐性菌問題は病院内だけではなく,市中・環境・社会,そして地球規模で考えなければいけないグローバルな問題であり,アカデミア,企業,行政の連携に加えて,国家間での協調・協力がきわめて重要になる.
・本特集では,日本のAMR対策アクションプランの目標と戦略,グラム陽性薬剤耐性菌の最新動向,抗酸菌感染症,次世代感染症診断法など,注目のトピックを第一線で活躍される先生方に概説いただく.

精神科臨床 Legato Vol.6 No.2
2020年8月号
座談会 アスリートのメンタルヘルス
座談会 アスリートのメンタルヘルス
統合失調症や気分障害を中心に精神科領域全体を広く取り上げ,そのときのトレンドに沿った話題や読者が診療において役立つ情報を提供し,精神科臨床の向上に貢献することを目指したものである。

Frontiers in Alcoholism Vol.8 No.2
2020年7月号
特集 アルコール依存症と家族
特集 アルコール依存症と家族
アルコール依存症の心理社会的治療、薬物治療の現状と関連疾患をわかりやすく解説した学術誌。
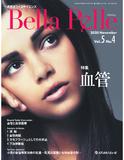
Bella Pelle Vol.5 No.4
2020年11月号
特集 血管
特集 血管
「美肌をつくるサイエンス」をテーマに,美容皮膚科領域における「科学的検証を経た正しい知識」を発信することにより,適正な診療のあり方を啓発する「日本初の美容皮膚科専門学術誌」。(「Bella Pelle」はイタリア語で「美しい肌」の意味)

医学のあゆみ268巻13号
第5土曜特集
制御性T細胞研究の現在
制御性T細胞研究の現在
企画:坂口志文(大阪大学免疫学フロンティア研究センター実験免疫学)
堀 昌平(東京大学大学院薬学系研究科免疫・微生物学教室)
・制御性T細胞(Treg)は,1980~1990年代にかけて,免疫自己寛容の導入・維持に必須のリンパ球として研究がはじまった.本特集では,Tregの基礎研究から臨床応用まで広く研究の現状を紹介する.
・近年,Tregの発生・分化,機能の分子的基礎,転写因子とのネットワークなどが明らかになりつつある.また,単なる免疫抑制だけでなく,組織の恒常性・再生にも重要な役割を担っている可能性も示されてきた.
・Tregの強化による自己免疫疾患の治療・予防,逆にTregの減弱によるがん免疫の惹起・強化なども期待されており,研究が進められている.本特集ではこれらの最新の知見についても解説いただく.

医学のあゆみ268巻12号
創薬インフォマティクス
創薬インフォマティクス
企画:広川貴次(産業技術総合研究所創薬分子プロファイリング研究センター分子シミュレーションチーム)
・近年のビッグデータ解析やAI技術,遺伝情報データの進歩に伴い,創薬インフォマティクスは今後の創薬研究を支える技術として注目されている.本特集では,本分野の第一人者の先生方に最新情報を紹介いただく.
・創薬インフォマティクスは,バイオインフォマティクス(生物情報科学)とケモインフォマティクス(化合物情報科学)を融合した横断的分野で,病態生理に関する情報管理に関する多様な領域が含まれている.
・近年では,PubChemやChEMBLを代表する膨大な化合物情報データが公開されるようになり,アカデミア創薬という選択肢が生まれるなど,創薬インフォマティクスはまさに学問として黎明期にあるといえる.

医学のあゆみ268巻11号
膵癌の予後改善に向けて
膵癌の予後改善に向けて
企画:古瀬純司(杏林大学医学部腫瘍内科学)
・「2018年のがん統計予測」において膵癌は,罹患数・死亡数ともに従来の五大がんの1つである肝癌を抜いてしまった.5年生存割合は切除例を含めても10%未満であり,主要ながん種のなかで最低の状況である.
・膵がんは早期の特徴的な症状に乏しいため早期診断・治療が困難である.また切除可能例は20~30%程度であり,根治切除後も再発が多い.最近の免疫チェックポイント阻害薬もなかなか効果が期待できない.
・これらの膵癌治療の困難なハードルを越えるべく,多くの専門家がさまざまな方面から工夫し努力している.本特集では,膵癌の診断から切除手術,薬物療法を中心に,予後改善に向けた最新情報を解説いただく.

医学のあゆみ268巻6号
細胞の極性化がもたらす生命現象
細胞の極性化がもたらす生命現象
企画:髙橋雅英(名古屋大学大学院医学系研究科分子病理・腫瘍病理学)
・細胞極性は,細胞内の成分が一つの軸に沿って空間的に偏りを持って配置される性質である.1細胞内に形態的・生理的な偏りを持つことで,細胞は方向性を持って分裂,移動,分化できる.
・従来は,モデル動物を用いた発生学の分野において細胞極性形成の機序が解析されてきた.最近では技術の進展により,哺乳類でも細胞極性の異常と先天性疾患などとの関連が解析できるようになってきた.
・今後は,マウス個体やオルガノイドでも細胞極性を解析・操作できる技術の進展が期待される.本特集では,形態形成,がんの進展,神経回路形成など,多様な生命現象をもたらす細胞極性に関する最新の知見を集めた.

医学のあゆみ268巻4号
カテーテルアブレーションの最近の進歩
カテーテルアブレーションの最近の進歩
企画:平尾見三(東京医科歯科大学医学部附属病院循環器内科)
・1990年初頭にわが国に臨床導入されたカテーテルアブレーション法は,この30年近い年月のなかで非薬物的な循環器治療法として確立されたばかりか,依然として日進月歩の技術革新が続いている.
・それに伴い,適応対象の不整脈は拡大し,2000年前後には心房細動のアブレーション治療が可能となった.その結果,わが国のアブレーション件数は10年前の約2.5万件/年から,現在9万件/年まで増加した.
・本特集では,実際にアブレーションや機器開発に第一線で取り組んでいる先生方に,診断機器・治療機器領域の技術革新の臨床応用法,また頻脈のアブレーション標的の特定方法の進歩について解説いただく.

医学のあゆみ268巻3号
自閉症学――自閉症・発達障害の病態解明に向けて
自閉症学――自閉症・発達障害の病態解明に向けて
企画:内匠 透(理化学研究所脳神経科学研究センター精神生物学チーム)
・自閉症は正式には自閉スペクトラム症(ASD)とよばれ,社会性の問題を主症状とする多彩な精神疾患で,脳の発達障害である.発症率は増加の一途のたどり,少子化に悩む先進国にとっては大きな社会問題でもある.
・自閉症の治療法には療育以外に確固たるものが存在しないが,臨床トピックスとして,オキシトシン療法の可能性のほか,注意欠如・多動症(ADHD)を例に発達障害において発達軌道を追う重要性を紹介いただく.
・“自閉症学”ともよべる新学術領域は,人文社会学・心理学から脳科学・人工知能(AI)まで幅広い分野をカバーするが,本特集では基礎・臨床医学両方の観点からの生物学的アプローチを中心に解説いただく.

医学のあゆみ268巻2号
Gorlin症候群――発生から治療法まで
Gorlin症候群――発生から治療法まで
企画:藤井克則(千葉大学大学院医学研究院小児病態学)
・Gorlin症候群は,1960年に報告された高発癌性の神経皮膚症候群である.日本国内ではまだよく知られていない疾患かもしれないが,疾患背景には多くの生物学的に興味ある事実がある.
・本症候群の責任遺伝子がヘッジホッグ蛋白の受容体PTCH1であることが報告され,シグナル異常症として脚光を浴びた.現在,vismodegibをはじめ,この経路を標的とした治療が期待されている.
・本特集では,Gorlin症候群をめぐる数多くの話題に触れ,研究と臨床の第一線で活躍される先生方に,ヘッジホッグシグナルが生体に果たす役割を解説していただく.

医学のあゆみ268巻1号
第1土曜特集
白血病UPDATE
白血病UPDATE
企画:黒川峰夫(東京大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科学)
・白血病は速やかな診断と治療の導入が重要な役割を果たす疾患である.古くから細胞形態に基づいた診断法が確立されてきたが,近年では遺伝子異常やゲノム解析が診断に大きく寄与するようになっている.
・最近ではAMLに対し,遺伝子変異を標的とした治療薬が臨床に導入されつつある.さらに,ALLの一部に対し,新たな抗体医薬や免疫細胞治療が有望な効果を持つものとして注目されている.
・白血病の治癒率の向上を目指した治療における進歩は目を見張るものがある.本特集では,特に注目を集めているトピックについて,各領域のエキスパートの先生方に最近の知見をわかりやすくまとめていただく.

医学のあゆみ268巻10号
顔面神経麻痺の形成外科的治療──最近の話題
顔面神経麻痺の形成外科的治療──最近の話題
企画:朝戸裕貴(獨協医科大学形成外科学教室)
・顔面神経に関する研究の進歩により,完全麻痺の状態で陳旧化する患者は減少したものの,麻痺の回復後に残存する異常共同運動や顔面拘縮に対する治療など,形成外科的治療は以前にも増して重要になってきている.
・マイクロサージャリーを用いた神経血管付き筋肉移植術の登場により,顔面神経麻痺に対する形成外科的治療は大きく発展し,陳旧性顔面神経麻痺の患者が閉瞼機能や“笑い”の表情を取り戻せるようになってきている.
・とくに神経端側縫合による神経再建術などは,形成外科的治療の幅を大きく広げるコンセプトとして最近注目を集めている.本特集では顔面神経麻痺治療のエキスパートの先生方に,各種治療法について解説いただく.

医学のあゆみ268巻9号
第1土曜特集
遺伝性心血管疾患のすべて
遺伝性心血管疾患のすべて
企画:小室一成(東京大学大学院医学系研究科循環器内科学)
・循環器疾患というと環境因子の影響が大きく,遺伝性疾患は心筋症などごく少数に限られると考えられていたが,解析技術の進歩により新事実が次々と明らかになり,遺伝子変異の同定は大きな意味を持つようになった.
・疾患の原因遺伝子が同定されることで,precision medicineの可能性が広がる.がんではすでにprecision medicineに基づいた診療が行われているが,循環器疾患でも重要となってこよう.
・2000年ヒトゲノム計画によりすべてのゲノムが明らかになり,医学の飛躍的な発展が期待されたが,その期待はいま現実化しつつある.本特集では20もの遺伝性心血管疾患を取り上げ,最新の知見を紹介いただく.

医学のあゆみ268巻7号
血糖管理の新展開──CGM・ポンプ・データマネジメントシステム指導から人工膵臓まで
血糖管理の新展開──CGM・ポンプ・データマネジメントシステム指導から人工膵臓まで
企画:渥美義仁(永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター)
・糖尿病の血糖コントロール目標はHbA1cで示されるが,低血糖や血糖変動を反映しない点が課題である.SMBGも一日数ポイントの測定に限られ持続的でないため,低血糖予防と血糖管理への寄与に限界がある.
・これらの課題に対し,血糖変動を持続的に把握することができるモニタリングシステムとして,持続グルコースモニタリング(CGM)とフラッシュグルコースモニタリング(FGM)などが注目を集めている.
・CGMとFGMはスマホアプリとの親和性が高く,家族や医療スタッフ間での即時共有が可能となる.しかしデータが膨大で解析が容易ではないため,データマネジメントシステム指導の充実も求められる.

医学のあゆみ268巻5号
第1土曜特集
動脈硬化UPDATE
動脈硬化UPDATE
企画:山下静也(りんくう総合医療センター病院長,大阪大学大学院医学系研究科総合地域医療学寄附講座)
・動脈硬化の分子機構は,細胞生物学的・分子生物学的レベルで詳細が明らかになってきた.一方,マクロファージ,炎症,脂肪酸代謝に関わる酵素群,脂肪酸結合蛋白との関係も明らかになっている.
・臨床的観点からは,糖尿病合併リポ蛋白代謝異常,高HDL血症の臨床的意義に関する最近の疫学研究,治療における性差,抗体医薬の開発による治療などについて,各領域の専門家に解説していただく.
・さらに,HDLをターゲットとした薬物療法,脂肪組織由来間葉系前駆細胞移植による血管再生療法のほか,動脈硬化性疾患予防ガイドラインや,スタチン不耐の診療ガイドなどについても最新の情報を紹介する.

医学のあゆみ268巻8号
睡眠呼吸障害の現状と治療・管理の進歩
睡眠呼吸障害の現状と治療・管理の進歩
企画:陳 和夫(京都大学大学院医学研究科呼吸管理睡眠制御学)
・成人,小児の睡眠呼吸障害,とくに閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)は頻度が高く,その理解はきわめて重要である.OSA発症の三大要因は肥満,男性,加齢であり,生活習慣病との関連も注目されている.
・平成30年度の診療報酬改定により,持続陽圧呼吸療法(CPAP)の遠隔モニタリング加算が認められた.また,6カ月以上の減量治療後の高度肥満OSA患者の肥満手術の保険適応も拡大された.
・本特集では,治療管理環境の大きな変化とCPAP治療患者の継続的な増加が認められているOSAを中心に,睡眠呼吸障害の頻度,治療と管理に関して,明日の実地診療に役立つ情報を解説いただく.
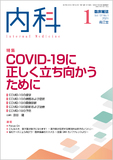
臨床雑誌内科 Vol.127 No.1
2021年1月号
COVID-19に正しく立ち向かうために
COVID-19に正しく立ち向かうために 1958年創刊。日常診療に直結したテーマを、毎号"特集"として掲載。特集の内容は、実地医家にすぐに役立つように構成。座談会では、特集で話題になっているものを取り上げ、かつわかりやすく解説。

臨床雑誌外科 Vol.83 No.1
2021年1月号
最先端の消化器外科クリニカルパス
最先端の消化器外科クリニカルパス 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。
