
臨床栄養 138巻1号
新型コロナウイルス感染症-栄養部門の対応 この1年,そしてこれから 前編
新型コロナウイルス感染症-栄養部門の対応 この1年,そしてこれから 前編

糖尿病プラクティス 38巻1号
糖尿病と感染症-新型コロナウイルスの時代を生き抜く-
糖尿病と感染症-新型コロナウイルスの時代を生き抜く-

Medical Technology 49巻1号
腹部エコー検査のステップアップ-エコーで悪性腫瘍を疑ったら
腹部エコー検査のステップアップ-エコーで悪性腫瘍を疑ったら
腹部エコーで悪性腫瘍を疑ったら,どのように検査を行い,どのような点を評価し,レポートには何を書いたらよいのか―病変の大きさや性状,質的評価に加え,周囲組織との関係・浸潤範囲などの評価,転移性腫瘍を疑った場合は原発巣の検索などを行い,加えて臨床に役立つポイントをおさえたレポートを作成することが重要となります.
そこで本特集では,代表的な悪性腫瘍について,そのエコー評価のポイント(着眼点・評価項目,検査の進め方,鑑別疾患,他の検査結果と併せた総合的評価など)をご解説いただきます.基本から一歩進み,腹部エコーの知識・スキルを向上させるために,ぜひ本特集をお役立てください.
(編集部)
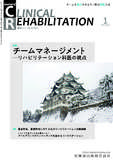
J. of Clinical Rehabilitation 30巻1号
チームマネージメント-リハビリテーション科医の視点
チームマネージメント-リハビリテーション科医の視点
リハビリテーション医療では,多くの職種がかかわりチームを形成して治療にあたる.リハビリテーション科医は,そのなかで舵取り役として,患者にとって最大・最良の力を発揮できるように調整をする.このチームマネージメントの必要性と重要性は,おそらく多くの人が理解をしているが,一方でその実際や具体的方策については十分な議論はなされていない.
リハビリテーション科医のかかわるマネージメントは,症例レベル:患者の担当チームとしてのチームマネージメント,多職種連携:リハビリテーション科医主導の多職種連携におけるチームマネージメント,リハビリテーション科レベル:診療科としてのマネージメント,病院レベル:リハビリテーション病院としてのマネージメント等,さまざまである.
本特集では,日頃第一線で試行錯誤しながらチーム医療を実践している先生に,チームマネージメントのあり方について執筆していただいた.リハビリテーションチームの概論(大高洋平氏)から始まり,重度障害のある困難症例のリハ医としての舵取りの実際(松浦大輔氏),多職種連携チームマネジメントの例として,骨転移キャンサーボード(石田由佳子氏・他)そしてCOVID-19流行下でのリハビリチームのマネージメント(森 直樹氏),リハビリテーション科としてのマネージメント(小口和代氏・他),最後にリハビリテーション病院全体のマネージメント(小川太郎氏・横串算敏氏)について,実践のなかで得られた貴重な経験とチームやマネージメントについての考え方を惜しみなく紹介していただいた.
これらの報告を読むと,リハビリテーション科医のマネージメントがいかに多様であるかということを再認識する.そして,マネージメントを行ううえでの課題を明確にし,1つひとつ地道に解決をし,適切にシステム化するということがいかに大切かということにも気づかされる.
本特集が,他人から見れば一見わかりにくく何をしているのかわからない,マネージメントという厄介な仕事に日々汗をかきながら取り組んでいる皆様の一助になれば幸いである.(編集委員会)

誰も教えてくれなかった糖尿病患者の感染症診療
感染症合併例はココに気をつけて!
糖尿病患者は免疫不全状態であり、感染症に罹患しやすいが、感染症診断が遅れがちである。また罹患すると感染症が重症化しやすいうえ、血糖コントロールも難しくなり高血糖が悪化する。新型コロナウイルス感染症においても、糖尿病患者は重症化しやすいと言われている。そこで糖尿病と関連の深い感染症を中心に、感染した糖尿病患者を診療する際に必要な情報を内科医向けにまとめた。
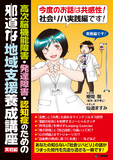
高次脳機能障害・発達障害・認知症のための邪道な地域支援養成講座 実戦編
「高次脳機能障害・発達障害・認知症のための邪道な地域支援養成講座」の”実戦編”
ADHDやASDといった発達障害のある当事者の困りごとの原因として、注意障害などがトピックとなってきた。問題の主体は、社会的コミュニケーションの問題、あるいは共感性の問題と呼ばれているものである。知能に問題がなくても、共感性、社会性に問題があれば、社会生活はできない。また、こうした社会性の問題は、知能の問題をも伴う高次脳機能障害でも認知症でもおきる。だからといって知能の問題だけに注目していていいだろうか?社会性の支援はどうしたらいいだろうか?
注意と感情を他者と共有することは、共感性の礎になる。そのため、本書では、まず共感性の基礎作りとなる注意の要素訓練(マインドフルネス瞑想)と感情を他者と共有する能力(情動の伝染)について紹介し、その応用段階である社会的な視点取得の解説へとすすみ、最終的には「当事者の視点に基づく支援」すなわち「ポジティブな行動支援」の具体的な話へと展開する。社会性の支援のためには、限りある当事者の「注意資源」を「社会性に割り振るためのコツ」が必要である。
あなたの知らない「社会リハビリテーション」がつまった新しい1冊である。

小児リハ評価ガイド
統合と解釈を理解するための道しるべ
理学療法・作業療法における小児のリハビリテーションに関連する約70点の評価法を紹介。イラストや写真により視覚的にイメージしながら学ぶことができる。さらに約40症例を通して現場での使用法を示し,実践にあたって必要な動作や認知の評価も学ぶことができる。

≪Emer-Log別冊2021≫
ウィズコロナ社会のnew normal医療の在り方
救急・ICUでの新型コロナウイルス感染症対応マニュアル
【COVID-19を踏まえた新しい救急医療】
防御に努めながら医療の新しい常態(new normal)をどのように構築し、救急医療体制をいかに保持するのか。外来体制、検査方法の選択、診断・治療のポイントから院内クラスター発生時の対応まで、現時点で蓄積されたエビデンスをもとに、COVID-19に対する医療の最前線である救急における診療の在り方を提案する。

医療・看護現場の成果が出るWeb会議術
【実践指導に基づくICT活用ノウハウを伝授】新型コロナ感染症対策で、会議や研修が一気にオンライン化している。初めて取り組む人にも理解しやすいZoomの使い方、Webを活用する会議や研修を実施する際のお作法、リアルとWebの使い分け方、準備・進め方、トラブル対応などを実践例を交えて紹介する。
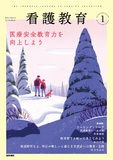
看護教育 Vol.62 No.1
2020年1月発売
特集 医療安全教育力を向上しよう
特集 医療安全教育力を向上しよう -

医学のあゆみ270巻1号
第1土曜特集
血管新生──基礎と臨床
血管新生──基礎と臨床
企画:望月直樹(国立循環器病研究センター研究所)
・発生学における臓器形成では,循環臓器としての心臓・血管・血球の形成が諸臓器の形成に先行することが必須である.また血管新生は発生時のみならず,虚血性血管疾患やがんにおいても認められる現象である.
・病態では発生時に機能する情報伝達系や血管構築シグナルだけではなく,炎症や細胞死に伴う特徴的な血管新生過程がみられる.加えて,組織や臓器に特徴的な血管形成過程も存在することから,血管構築の詳細が明らかにされてきている.
・本特集では,血管新生に共通する普遍的シグナルのアップデートのみならず,血管内皮細胞・血管平滑筋細胞の特徴的な情報伝達,臓器・組織特異的な血管新生過程,疾病に特徴的な血管新生誘導過程,発生・病態での血管新生過程を解析するための技術を紹介する.

医学のあゆみ270巻2号
飛行機・新幹線内での医療──医療従事者の方はいらっしゃいますか?
飛行機・新幹線内での医療──医療従事者の方はいらっしゃいますか?
企画:下畑享良(岐阜大学医学部脳神経内科学分野)
・航空機内での医師のよび出しが増加している.その理由は乗客数が指数関数的に増加し,疾患を抱える乗客数も増加しているためである.
・航空機内はさまざまな疾患を発症しやすい.頻度の高い症状は失神で,頭痛や痙攣など脳神経内科領域の症状が多い.次いで呼吸器症状や悪心・嘔吐がみられるが,循環器疾患や耳鼻咽喉科疾患も生じる.
・本特集では,航空機・新幹線における医療に関して各診療科の立場から注意すべき疾患とその対応,持病を持つ患者が搭乗する場合に注意すべきこと,法律問題や医師登録制度について最新情報を理解することをめざす.

医学のあゆみ270巻5号
第1土曜特集
メタボローム解析UPDATE
メタボローム解析UPDATE
企画:曽我朋義(慶應義塾大学先端生命科学研究所メタボローム研究グループ)
・メタボローム解析は,細胞や生体試料の代謝産物を網羅的に探索し,新規の代謝経路や不明であった代謝調節機構,未知遺伝子や蛋白質の機能,生体高分子と代謝産物の相互作用などを解き明かそうとする方法論である.
・近年,急速に進展したメタボロ-ム解析は,医薬分野における各種の疾患やがんの発症機序の解明,病体の診断,バイオマーカー探索などの分野にも普及し,すばらしい成果が数多く誕生している.
・本特集では,メタボローム解析を用いて老化,肥満,アレルギー,腸内細菌,がん,各種の疾患などの基礎研究での成果や,各種疾患の新たな機序の発見などの成果について解説していただく.

医学のあゆみ270巻8号
ファイトケミカルの最前線
ファイトケミカルの最前線
斉藤和季(千葉大学大学院薬学研究院遺伝子資源応用研究室,理化学研究所環境資源科学研究センター統合メタボロミクス研究グループ)
・ファイトケミカル(植物化学成分)は,長い進化の過程で動かないという選択をした植物がその生存戦略の結果として生産し,植物の種や属に特異的で大きな化学的多様性を有する.
・これらのファイトケミカルが持つ特異的な生物活性は,しばしば生薬や漢方の有効成分,医薬品のリード化合物,健康機能を有する食品の成分として,われわれ人間の疾病治療や予防,健康維持や増進に大きく貢献している.
・本特集では,このファイトケミカル研究の最前線について,基礎研究から開発研究,医薬品の規制,副作用,健康機能食品,臨床応用まで幅広いトピックスを取り上げる.

医学のあゆみ270巻4号
新しい高血圧ガイドライン(2017-2019)日米欧の比較
新しい高血圧ガイドライン(2017-2019)日米欧の比較
企画:田村功一(横浜市立大学医学部循環器・腎臓・高血圧内科学,同医学研究科病態制御内科学,同附属病院副病院長,同腎臓・高血圧内科)
・現代社会が求める健康寿命延伸の課題である,高血圧,脳心血管病,腎臓病の3つの病態は,互いに密接に連関し同一の患者に併存する場合も多い.その起点としての高血圧の克服はきわめて重要である.
・日本高血圧学会により2019年4月に改訂された「高血圧治療ガイドライン2019(JSH2019)」では,血圧値分類の名称も改訂されており,わが国の高血圧対策は非常に重要な局面であると考えられる.
・本特集では,世界的に厳格降圧が推奨されている状況下において,日本の「高血圧治療ガイドライン2019 」では何が重視され,どのように改訂されたのかについて,各領域の高血圧専門医に詳細に解説いただく.

医学のあゆみ270巻3号
医師の働き方改革――その目指すところ
医師の働き方改革――その目指すところ
企画:野原理子(東京家政大学家政学部栄養学科)
・医師が日々進歩している専門的な知識や技術を学び,つねに適切な医療を提供しつつ,人間らしい生活を送り自分らしく働くことを実現するために,さまざまな取り組みが推進されている.
・医療機関の勤務環境改善,臨床研究の推進,そして医師の働き方改革はそれぞれ議論されているが,それらはどのように結びつき,これからどのように推進されていくのであろうか.
・本特集では,医師の働き方改革,その目指すところについて,行政,医師会,学会,病院,組合などに加えて,ともに働く他職種,医療を受ける患者団体など,さまざまな角度からの見解を紹介する.

医学のあゆみ270巻11号
腸と健康:腸オルガノイドが挑む次世代バイオモデル
腸と健康:腸オルガノイドが挑む次世代バイオモデル
企画:阿久津英憲(国立成育医療研究センター研究所再生医療センター生殖医療研究部)
・小腸は栄養を取り込む代謝・吸収,さまざまな臓器へ影響を及ぼす内分泌機能,異物から身を守るための免疫機能など多様性のある生命維持に欠かせない臓器である.
・本特集では小腸の働きの実用的な観点から,経口医薬品開発の現状と課題,栄養と健康的な長寿社会の実現,腸内細菌叢と免疫,新たな小腸の現代病,難治性腸疾患に対する再生医療の取り組みを最先端の現場から報告する.
・幹細胞研究分野では,臓器疑似モデル(オルガノイド)が試験管内で可能となってきた.次世代バイオモデルとして,小腸の生理機能性を持つ小腸オルガノイド(ミニ腸)の可能性と,医薬応用への取り組みを紹介する.

医学のあゆみ270巻9号
第5土曜特集
脳機能イメージングの最前線
脳機能イメージングの最前線
企画:大久保 善朗(日本医科大学大学院医学研究科精神・行動医学)
・脳機能イメージングは,脳血流や脳代謝のような特定の生体機能情報を画像化する検査法で,MRI装置を用いた機能的MRI(fMRI)や,PETやSPECTなどの核医学検査法が含まれる.
・脳機能イメージングによって,脳の形態異常を伴わないために,これまでは評価することができなかった精神疾患でも,さまざまな脳機能の異常を評価することが可能になっている.
・総論では主にMRIとPETについて最近の技術進歩を紹介し,各論では脳血管障害,認知症などの器質性疾患や,統合失調症,発達障害など精神障害について,脳機能イメージングを用いた最新の研究成果を紹介する.

医学のあゆみ270巻10号
第1土曜特集
TRPチャネルのすべて
TRPチャネルのすべて
企画:富永真琴(自然科学研究機構生理学研究所細胞生理研究部門,同生命創成探究センター温度生物学研究グループ)
西田基宏(自然科学研究機構生理学研究所心循環シグナル研究部門,同生命創成探究センター心循環ダイナミズム創発研究グループ)
・transient receptor potential (TRP)チャネルは、1989年にショウジョウバエのtrp遺伝子が同定されて以来,世界で精力的に研究され,大きな機能的多様性を有するイオンチャネルファミリーを形成することが示されてきた.
・TRPチャネル機能異常は多くのチャネル病を引き起こし,多くの後天的疾患や癌の発生においてTRPチャネルが重要な役割を果たしていることが明らかにされ,阻害薬あるいは刺激薬の有用性が大いに期待されている.
・今後,原子レベルでの構造解明の上にTRPチャネルを標的とした薬剤が開発されることが期待される.TRPチャネルと疾患との関連ももっと研究されて行くであろう.現在までのTRPチャネル研究を本特集でまとめた.

医学のあゆみ270巻12号
がんの多様性を司るがん間質のバイオロジー──新たな診断・治療法の創生につなぐ
がんの多様性を司るがん間質のバイオロジー──新たな診断・治療法の創生につなぐ
企画:渡邉昌俊(三重大学大学院医学系研究科基礎医学系講座腫瘍病理学)
・日本では2019年6月から“がん遺伝子パネル検査”が公的医療保険の適用となり,いよいよがんゲノム医療の本格的開始となった.
がんは遺伝子病であり,その浸潤・転移能などの特性が知られている.
・がん組織では正常組織固有の“構造”が喪失し,その喪失具合と“がん”の悪性・進展具合は密接に関連している.がん細胞は種々の細胞や基質と相互作用し,自分に有利な環境を作り出していくと思われる.
・本特集では,がんの多様性をがん間質の視点から研究されている先生方に最新の研究データと考えをまとめていただく.がん間質の役割に興味を持つ機会になれば幸いである.
