
臨床整形外科 Vol.56 No.1
2021年1月発売
特集 パラスポーツ・メディシン入門
特集 パラスポーツ・メディシン入門 -

臨床外科 Vol.76 No.1
2021年1月発売
特集 徹底解説 術後後遺症をいかに防ぐか コツとポイント〔特別付録Web動画付き〕
特集 徹底解説 術後後遺症をいかに防ぐか コツとポイント〔特別付録Web動画付き〕 多くの癌手術において,臓器損失によるデメリットが発生してしまう.それは,癌根治とのバランスのうえで考えなければならず,患者さんにとって納得しうるものもあろうが,しかし特に早期癌の患者さんにとっては,多くは無症状の方が有症状になってしまう.その意味でも,術後後遺症は極力発生させてはならないものである.
達人は,その経験や知恵,工夫から多くの“技”を持っているものである.本特集では,代表的後遺症を取り上げ,若手向けに,特に術後QOLを落とすような後遺症を起こさないコツとポイント,発生した場合の対処法を解説いただいた.術後後遺症を防ぐための技を本特集から学びとっていただければ幸いである.
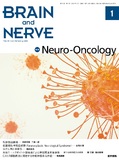
BRAIN and NERVE Vol.73 No.1
2021年1月発売
特集 Neuro-Oncology
特集 Neuro-Oncology -

循環器ジャーナル Vol.69 No.1
2021年1月発売
これからの高齢者診療——循環器医が人生100年時代にどう向き合うか?
これからの高齢者診療——循環器医が人生100年時代にどう向き合うか? -

総合診療 Vol.31 No.1
2021年1月発売
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック 今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来
特別増大特集 新型コロナウイルス・パンデミック 今こそ知っておきたいこと、そして考えるべき未来 -
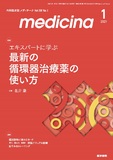
medicina Vol.58 No.1
2021年1月発売
特集 エキスパートに学ぶ 最新の循環器治療薬の使い方
特集 エキスパートに学ぶ 最新の循環器治療薬の使い方 -

公衆衛生 Vol.85 No.1
2021年1月発売
特集 病気の治療と仕事の両立支援 キャリアをあきらめないために
特集 病気の治療と仕事の両立支援 キャリアをあきらめないために -

医学のあゆみ275巻12・13号
ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)――臨床応用の展望
ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)――臨床応用の展望
企画:平田雅之(大阪大学大学院医学系研究科脳機能診断再建学共同研究講座,同脳神経外科学,大阪大学国際医工情報センター)
貴島晴彦(大阪大学大学院医学系研究科脳神経外科学,大阪大学国際医工情報センター)
・ブレイン・マシン・インターフェース(brain-machine interface:BMI)とは“脳と機械の間で直接信号をやりとりしてヒトの神経機能を代行,補完する技術”である.
・体内埋込を必要とする侵襲型のBMIはようやく治験が行われつつあるところで,臨床応用には時間がかかっている.企業の参入により,今後の加速が期待されるところである.
・非侵襲型のBMIは体内埋込が不要な分,一足先にリハビリテーション分野での治験が完了し,臨床応用にも目途が立った.

医学のあゆみ274巻6・7号
がんにおけるカヘキシア――とくにサルコペニアの問題を考える
がんにおけるカヘキシア――とくにサルコペニアの問題を考える
企画:葛谷雅文(名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅医療学・老年科学)
・カヘキシア(悪液質)の定義は明確に定まっているわけではないが,一般的には複合的な代謝異常により骨格筋量の低下ならびに体重減少を併せ持つ病態を指す.
・がんに伴うサルコペニア有病率に関しては,治療前の有病率に関して報告されたメタ解析によると38.6%(95%CI:37.4-39.8)で,術後の合併症,化学療法の副作用,さらには生命予後に関しても悪影響を及ぼしている.
・カヘキシアはがんのみならず進行した臓器不全などの消耗性疾患にも関与している.膨大な患者がカヘキシアならびにそれに伴うサルコペニア状態にあることが想定され,この分野の研究,治療法の開発が重要になる.

医学のあゆみ274巻13号
冠動脈疾患とステント治療
冠動脈疾患とステント治療
企画:中村 淳(医療法人社団誠馨会新東京病院院長)
・ステント治療により,経皮的冠動脈インターベンション(PCI)治療のクレディビリティは格段に上がることになった.理由は,急性冠閉塞が完全にコントロールでき,慢性期再狭窄は半分の30%になったからである.
・2002年のヨーロッパ心臓病学会で,薬剤溶出ステント(DES)が劇的に再狭窄を抑えたというエビデンスが発表され,冠動脈治療の大きな潮目が変わるときがきた.
・本特集では,冠動脈ステントを留置するに困難でかつ,最も注意が必要な病変に対してどのようにアプローチするべきかということに関して,日本を代表する循環器内科医師に詳説していただく.

医学のあゆみ274巻12号
多様な疾患の原因となるDNA損傷応答不全
多様な疾患の原因となるDNA損傷応答不全
企画:中西 真(東京大学医科学研究所癌防御シグナル分野)
・損傷を受けたDNAは損傷の種類に応じた多様な仕組みにより適切に修復されなければならない.これらの仕組みに異常が生じると,がんや発生異常などのさまざまな疾患の原因となる.
・DNA損傷応答機構の研究の歴史は非常に古く,1960年代の後半には大腸菌においてDNAの組換えに必要な遺伝子が同定されている.その後もさまざまな種類のDNA損傷に対応する修復機構が同定されている.
・今後,DNA損傷応答機構への理解がさらに深まることで,がんや老化をはじめとするDNA不安定症に対する新たな予防・治療薬の開発につながるものと期待できる.

医学のあゆみ274巻11号
形成外科の最前線
形成外科の最前線
企画:森本尚樹(京都大学大学院医学研究科形成外科学)
・形成外科分野では自家組織移植,自家細胞を用いた組織再生が実臨床として長年行われてきている.わが国ではじめて承認された細胞使用製品である自家培養表皮は600例以上の患者の皮膚再生に用いられている.
・また,脂肪細胞を併用した乳房再生,軟骨細胞を用いた耳介形成手術と,細胞を自家組織と組み合わせた組織再生も行われてきている.最近では,付属器まで含めた皮膚・皮下組織全体の再生も提唱されている.
・微小循環評価,ロボット手術など組織生着に必要な検査,手技も実臨床に基づいた評価が行われている.また,瘢痕・ケロイド治療,レーザー治療など,“きれいになおす”ためにはこれらすべての理解が必要である.

医学のあゆみ274巻10号
第1土曜特集
肥満――外科治療と基礎研究の最新情報
肥満――外科治療と基礎研究の最新情報
企画:戸邉一之(富山大学大学院医学薬学研究部(医学)内科学第一講座)
木村 穣(関西医科大学健康科学センター健康科学科)
・近年の肥満症分野での大きな発展は,肥満症の病態についての基礎研究と高度肥満症に対する外科的治療の進歩である.
・基礎研究の分野ではアディポネクチン受容体作動薬の開発,脂肪組織のリモデリングの分子的レベルでの解明,ベージュ脂肪細胞の研究の進歩,中枢を介したエネルギー代謝,肥満症に伴う諸臓器の障害のメカニズムについて次々と解明されてきた.
・肥満外科手術による減量はその急速かつ劇的な減量効果により,臨床的意義のみならず肥満症の病態生理にも新たな視点を与え,興味ある研究分野となっている.

医学のあゆみ275巻5号
第5土曜特集
がんゲノム医療――網羅的解析からの知見と臨床応用の展望
がんゲノム医療――網羅的解析からの知見と臨床応用の展望
企画:小川誠司(京都大学大学院医学研究科腫瘍生物学講座)
・がんはゲノムの異常に起因する疾患である.がんゲノムの異常を理解することは,がんの病態と治療戦略を考えるうえで不可欠であることは論を俟たない.
・次世代シーケンスのスループットは年々加速しており,これに伴うシーケンスコストの低下を背景として,がんゲノム異常の知見に基づいた医療はますます加速することは明らかである.
・本特集では,がんゲノム医療の展開を踏まえて,がんゲノム研究・がんゲノム医療の第一線で活躍されておられる専門家の方々に,近年のがんゲノム研究の最新の成果と,がんゲノム医療の現状について解説をいただく.

医学のあゆみ275巻3号
クローン性造血とは?――高齢化社会における新たな研究テーマ
クローン性造血とは?――高齢化社会における新たな研究テーマ
企画:北村俊雄(東京大学医科学研究所先端医療研究センター細胞療法分野,同幹細胞治療研究センター幹細胞シグナル制御分野)
・1996年に,BusqueらがX染色体不活化の偏りから同定した高齢者における血液クローンの偏りをARCHと命名したときに,“クローン性造血(CH)”という言葉がはじめて使われた.
・CHを有する人は造血器腫瘍を発症しやすいが,生命予後を悪化させるのは心筋梗塞,脳梗塞,癌であり,近年注目されている.本特集では,CHに関する8つの総説を専門家にご執筆いただいた.
・CHはこの超高齢者社会において社会的に重要な研究テーマであるが,数多くの疑問をかき立てられる研究対象として,基礎研究においても重要である.CHの研究はいまだ端緒についたばかりである.

医学のあゆみ275巻4号
ポリファーマシー――解消に向けた取り組み
ポリファーマシー――解消に向けた取り組み
企画:秋下雅弘(東京大学大学院医学系研究科老年病学)
・ポリファーマシー(polypharmacy)の背景にあるのは多病(multimorbidity)と複数医療機関・診療科の利用,つまり疾患ごとの専門医受診である.
・したがって,単純な薬減らしの話ではなく,総合的な視点から病状と生活機能を評価し,関係職種が協働して取り組まなければならない.
・本特集では,厚生労働省による“高齢者の医薬品適正使用の指針”でも取り上げられた病期や療養環境別の考え方,連携のモデルやツールをテーマにしたポリファーマシー解消に向けた最新の取り組みを紹介する.

医学のあゆみ275巻9号
子どもと環境――胎児期・幼少期の環境が与える影響
子どもと環境――胎児期・幼少期の環境が与える影響
森崎菜穂(国立成育医療研究センター社会医学研究部ライフコース疫学研究室)
・胎児期・幼少期の環境がさまざまな成人期慢性疾患の発症基盤と関連することが数多くの研究から徐々に明らかになり,より効果的な介入を行うために行動変容を促しやすい若年層への介入に期待が集まるようになった.
・また,子どもの貧困や格差の拡大,先進国で類を見ない低出生体重児の増加など,幼少期の問題が国の健康課題としてもあがってくるようになってきた.
・本特集では,胎児期・幼少期の環境曝露の健康への影響を動物モデル,疫学研究,脳画像など,さまざまな分野での最近の知見について紹介する.
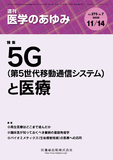
医学のあゆみ275巻7号
5G(第5世代移動通信システム)と医療
5G(第5世代移動通信システム)と医療
加藤浩晃(デジタルハリウッド大学大学院客員教授/アイリス株式会社共同創業・取締役副社長)
・現在,社会は“第4次産業革命”といわれる時代の大きな転換点に差し掛かっている.また2020年(令和2年:R2)は“リモートワーク&リモートライフ(R2)”を経験する時代となった.
・遠隔医療や医療AIなどが浸透していくことが予想されるこのような状況下で,基盤技術として注目されるのが,第5世代移動体通信システム“5G”である.5Gは高速・大容量,低遅延,多数同時接続といった特徴を持つ.
・Society5.0時代の基盤となる5Gの医療現場での取り組みは着実に進んでいる.本特集では,5G×医療の政策動向や医療機器としての展開,そして診断から手術に至るまでの取り組みを紹介する.

医学のあゆみ275巻6号
第1土曜特集
心血管イメージングの新時代
心血管イメージングの新時代
企画:伊藤 浩(岡山大学大学院医歯薬総合研究科循環器内科学)
・心血管イメージングは心血管疾患の診断,病態評価,リスク層別化から治療中のモニター,そして治療効果の判定に必須のモダリティーである.
・心血管イメージングといっても実に幅広い.心エコー図法,MDCT,心筋シンチ,MRI,PETなどの非侵襲的イメージングから,IVUS,OCT,血管内視鏡など治療ガイドに用いられる侵襲的イメージングまである.
・本特集の目的は冠動脈疾患,心不全,不整脈,成人先天性心疾患などの多くの分野における心血管イメージングの最前線と近未来をエキスパートに解説していただくことである.

医学のあゆみ275巻2号
在宅医療2020
在宅医療2020
企画:石垣泰則(悠輝会コーラルクリニック院長)
・高齢者医療から派生した在宅医療は,今やその対象は全世代であり,癌性疾患をはじめ認知症,障害者,病状が進行した慢性疾患患者,医療的ケア児まで広がる.
・2020年代は高齢化が進展するわが国にとってきわめて重要な10年であり,そのカギを握るのが在宅医療の充実である.
・これからは医療供給側が協力し,“治し支える医療”を提供するため有機的に機能分担することが重要で,地域差を踏まえたうえで標準的在宅医療をめざす必要がある.
