
医学のあゆみ275巻11号
心アミロイドーシスをどう診るか――最新の診断と治療
心アミロイドーシスをどう診るか――最新の診断と治療
企画:辻田賢一(熊本大学医学部循環器内科学)
・超高齢社会を突き進むわが国において,心アミロイドーシスが注目を集めている.加齢との関連が強く示唆され,健康長寿を考えるうえで避けては通れない21世紀の疾患である
・とくに野生型トランスサイレチンアミロイドーシスは想定されていたより頻度が高く,日常臨床において比較的遭遇することの多い疾患であることが明らかになってきた.
・本特集では,各エキスパートの先生方にわが国の最先端の心アミロイドーシス診断治療の現状を具体的に,そしてコンパクトにご解説いただく.

医学のあゆみ275巻10号
第1土曜特集
臓器線維症を科学する――病態解明と治療法開発への展望
臓器線維症を科学する――病態解明と治療法開発への展望
企画:稲垣 豊(東海大学医学部先端医療科学,同マトリックス医学生物学センター)
・現在,わが国において最も対応が急がれている生活習慣病は,医療費の3割,全死亡者数の6割を占め,急速に進む超高齢化を背景に,その対策は医学的また社会的にも一層重要となっている.
・これらの罹患臓器には線維化病変が共通して認められ,肺や肝臓ではがんの発生母地ともなるため,線維化の制御は生活習慣病の進展予防に直結する重要戦略と位置づけられる.
・本特集では多角的な視点と新たなツールを用いて臓器線維症の病態を掘り下げ,全身臓器の線維症にみられる共通性と臓器ごとの特異性を理解することで,新たな治療アプローチを模索することをめざす.

医学のあゆみ275巻1号
第1土曜特集
免疫リプログラミングと細胞デザイン
免疫リプログラミングと細胞デザイン
企画:吉村昭彦(慶應義塾大学医学部微生物学免疫学教室)
・免疫細胞は基本的に血液中を循環する細胞であり,標的に集積させたり,逐次補充することが可能である.免疫分野でもリプログラミングという言葉は最近よく使われるようになり,重要な研究要素となっている.
・免疫老化はさまざまな免疫細胞に現れるが,最もよく研究されているのはメモリーT細胞で,この存在比率や異常がヒトの寿命に大きく影響する.腫瘍免疫や感染免疫では“老化”に近い“疲弊”という現象が知られている.
・このような免疫老化やT細胞疲弊を解除する方法が見つかれば,がん治療のみならず健康寿命の延長におおいに貢献できるであろう.“免疫リプログラミング”や“細胞デザイン”はまさに今求められている研究テーマといえる.

医学のあゆみ274巻9号
第5土曜特集
AIが切り拓く未来の医療
AIが切り拓く未来の医療
企画:浜本隆二(国立研究開発法人国立がん研究センター研究所分野長,一般社団法人日本メディカルAI学会代表理事)
・近年,深層学習を中核とした機械学習技術の進歩,安価で高性能のGPUの登場を含む情報基盤技術の進歩,またパブリックデータベースの拡充などにより,大規模なデータを利活用することが容易になってきた.
・医療AIに対する期待および可能性は大きいものの,改正個人情報保護法の下で要配慮個人情報と定められた医療情報の取り扱い,また機械学習・深層学習技術に特有の問題点など,解決すべき課題も多いのが現状である.
・本特集は医学分野・情報科学分野のみならず,法律,生命倫理,プライバシー,医療機器の薬事規制など,さまざまな分野において国内第一線で活躍しておられる専門家に,医療AIの現状・期待・課題を論じていただく.

医学のあゆみ274巻8号
急速に変わる緩和ケア――薬物療法の進歩からアドバンスケアプランニングまで
急速に変わる緩和ケア――薬物療法の進歩からアドバンスケアプランニングまで
企画:森田達也(聖隷三方原病院副院長,同緩和支持治療科)
・症状緩和を越えて緩和ケアをとらえなおそうという試みとして意思決定過程,とくに,諸外国で制度化されたアドバンスディレクティブからの流れをくむアドバンスケアプランニングがある.
・がん患者での診断時早期から緩和ケアを提供しようという流れ,心不全患者に緩和ケアを提供しようという流れ,そして,安楽死や自殺幇助の枠組みのなかで緩和ケアの役割をどこに位置づけるかといった領域がある.
・本特集では,それぞれの領域のまさに先端を現場から紹介し,緩和ケアの多様な方向性を伝えることができれば幸いである.

医学のあゆみ274巻5号
第1土曜特集
細胞競合による生体制御とがん
細胞競合による生体制御とがん
企画:井垣達吏(京都大学大学院生命科学研究科)
・発生中の組織のなかで細胞同士が生存競争し,争いに勝った細胞が成体の一部を形成できるという“cell competition(細胞競合)”の概念は,1975年にMorataとRipollによってショウジョウバエではじめて示された.
・最近,異なる要因で起こる細胞競合で共通に機能するメカニズムが見えはじめ,細胞競合を特異的に制御する転写因子Xrp1が発見された.細胞競合研究は今,静かにフィナーレの第4楽章へと突入しつつある感がある.
・細胞競合は,遺伝的背景の異なるもの同士が限られた生息域(スペース)や資源(栄養)を奪い合う“適者生存”を想起させることから,地球上に存在するあらゆる生物を支配する根源的な生命原理に迫れるのではないか.

医学のあゆみ274巻4号
外国人診療
外国人診療
企画:鈴木敦詞(藤田医科大学医学部内分泌・代謝内科学)
・外国人診療を行ううえで最初の障壁になるのは外国語である.医療の専門教育について,どの程度英語を用いるべきかということは,一般教養としての英語教育とはまた異なった課題である.
・JCIのような国際的な病院機能評価システムや,JMIP,JIHのような外国人患者受け入れ体制に対する評価や推奨制度が広がりつつある.これは外国人患者が,より一層安心して医療を受けられるための仕組み作りである.
・本特集では現在,外国人患者受け入れのための体制づくりがどこまで進んでいるかと,医療スタッフの教育を含めた人的リソースの供給体制とを主眼におき,さらにスポーツ医学の観点からも執筆いただく.

医学のあゆみ274巻3号
HIFと疾患――ノーベル賞受賞と将来展望
HIFと疾患――ノーベル賞受賞と将来展望
企画:南学正臣(東京大学大学院医学系研究科腎臓・内分泌内科)
・2019年のノーベル医学・生理学賞は,低酸素誘導因子-プロリン水酸化酵素(HIF-PH)の酸素感知および応答経路を解明したGregg Semenza,Peter Ratcliffe,William Kaelin Jr.が受賞した.
・酸素生物学は生命の最も基本的な原理に密接に関連するものであり,さらに虚血性心血管疾患,脳卒中,腎臓病から癌に至る,さまざまな疾患の病態生理にも重要であり,そのことが評価されノーベル賞の受賞対象となった.
・本特集では,酸素生物学およびHIFとその関連する問題について,各分野のトップランナーの先生方をお招きし,解説をしていただく.

医学のあゆみ274巻2号
熱中症に立ち向かう――予防と応急処置
熱中症に立ち向かう――予防と応急処置
企画:三宅康史(帝京大学医学部附属病院高度救命救急センター,同救急医学講座)
・かつてはそれほど注目されていなかった“熱中症”だが,そういえば,いつから熱中症とよばれるようになったのか.筆者が学生のころには,熱射病や日射病という診断名で習った記憶もおぼろげながらある.
・今後,さらなる温暖化,高齢化,貧困化,孤立化による熱中症リスクが高まるなかで,夏期の気象の変化や熱中症の現状分析,的確な診断と有効な治療法について,最新の知見と見解をまとめていただく.
・今回の企画により,熱中症への理解が深まり,それぞれの立場で熱中症の予防・早期発見と発症時の適切な対策が進むことを切望する.

医学のあゆみ274巻1号
第1土曜特集
アルコール医学・医療の最前線2020 UPDATE
アルコール医学・医療の最前線2020 UPDATE
企画:竹井謙之(三重大学大学院医学系研究科消化器内科学)
・アルコール医科学・医療の諸分野の最近の進歩は瞠目するものがあり,また学際領域からも新たな知見が生まれ,他にも広く波及する新しい概念とアイデアを涵養している.
・一方,アルコール関連問題はますます社会的問題としての意義を増しており,飲酒運転や女性・若年者・高齢者の飲酒問題など,医療と社会・経済的問題とが不可分の関係にある.
・テーマの多様性を反映し,多彩な分野のエキスパートに“最新のエビデンスを最新の視点のもとに”執筆をお願いする.本特集がアルコール医学・医療の最先端を知るための導きになれば幸いである.

医学のあゆみ273巻9号
第5土曜特集
ゲノム編集の未来
ゲノム編集の未来
企画:山本 卓(広島大学大学院統合生命科学研究科,同ゲノム編集イノベーションセンター)
・ゲノム編集は,細胞内で標的の遺伝子を狙って改変する技術である.CRISPR-Cas9を使った方法が報告されて以来,その簡便性と効率性によって基礎研究から応用分野までさまざまな分野での利用が広がった.
・医学分野でのCRISPR-Cas9のインパクトはさらに大きく,遺伝性疾患の発症機構の研究や治療法の研究のため,モデル細胞・動物をゲノム編集によって作製することが可能となっている.
・本特集では,国内トップランナーのゲノム編集研究者に,ゲノム編集の基礎と医学分野の最新のゲノム編集技術について執筆いただく.

医学のあゆみ273巻8号
新しい臨床関連研究法の下での臨床研究の現況と課題
新しい臨床関連研究法の下での臨床研究の現況と課題
企画:笹野公伸(東北大学大学院医学系研究科医科学専攻病理病態学講座病理診断学)
・すべての臨床研究に関し,その手続の規制や手続自体の透明性を確保することで国民の臨床研究に対しての信頼確保をはかり,わが国における臨床研究を推進する目的で,2018年4月1日に,いわゆる臨床研究法が施行された.
・この施行後2年が経過したが,運用面での課題が少なからず提起されてきており,現場では混乱もみられている.
・本特集では,臨床研究法の仕組みや成立までの経緯,懸念されている課題などの総論的内容に加えて,それぞれの異なる立場からの議論していく.

医学のあゆみ273巻7号
未診断疾患イニシアチブ(IRUD)の成果
未診断疾患イニシアチブ(IRUD)の成果
企画:水澤英洋(国立精神・神経医療研究センター理事長・総長)
・未診断疾患を対象に,2015年からAMEDの基幹事業として開始されたのが未診断疾患イニシアチブ(IRUD)である.すでにわが国の難病診療とゲノム診療の体制のなかで重要な位置を占め,大きな貢献をしているといえる.
・一方,病的変異としてまだ確定せず,候補遺伝子の段階でも線虫やハエなどの小型モデル動物を活用して機能解析を行うことにより病態解明,治療法開発をめざす研究(J-MRDD)もはじまり,多くの成果が上がりつつある.
・本特集では,IRUDおよび関連するIRUD Beyondについて,それぞれ実際にご担当していただいている方々にご執筆いただく.本特集が未診断症例・疾患の解消と難病・ゲノム診療の発展に少しでもお役に立てば幸甚である.
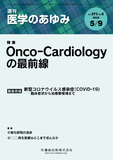
医学のあゆみ273巻6号
Onco-Cardiologyの最前線
Onco-Cardiologyの最前線
企画:佐瀬 一洋(順天堂大学大学院医学研究科臨床薬理学)
・がん医療の進歩に伴い,サバイバーの数が急増しつつある.そのなかで,心血管疾患は長期予後における主要な競合リスクであり,ハイリスクがん治療に伴う心血管疾患への対応が世界的な課題となっている.
・腫瘍循環器学(Onco-Cardiology/Cardio-Oncology)は,がん治療関連心血管疾患(CTRCD)の予防,診断,治療に関する学際領域の職種間連携である.
・本特集では,Onco-Cardiologyの最前線で活躍されているエキスパートの先生方に,教育・診療・研究の現状および今後の方向性についてご執筆をお願いする.

医学のあゆみ273巻5号
第1土曜特集
治療標的としてのがん幹細胞
治療標的としてのがん幹細胞
企画:伊藤貴浩(京都大学 ウイルス・再生医科学研究所がん・幹細胞シグナル分野)
・Dickらにより実験的にがん幹細胞の存在が証明されてから四半世紀が経過した.この間,多くの技術的進歩に伴ってがん幹細胞の性質やその作動原理が解明された.
・当初の骨髄性白血病での証明に続いて乳がんや脳腫瘍など,他のがん種にも幹細胞が存在することが示され,さらには遠隔転移や治療抵抗性における機能的重要性も明らかになった.
・本特集では,これまでのがん幹細胞研究を振り返ってその進歩を総括するとともに,次の四半世紀のがん研究の方向性を議論する基礎となるよう,多様な研究背景を持つ先生方に執筆いただく.

医学のあゆみ273巻4号
ヒトの分子進化からみた疾患の理解
ヒトの分子進化からみた疾患の理解
藤本明洋(東京大学大学院医学系研究科国際生物医科学講座人類遺伝学)
・ヒトゲノムの多様性は疾患の原因やリスクともなり,疾患の発症機序解明や治療法開発,リスク予測のために大規模研究が行われてきた.
・ありふれた疾患やメンデル遺伝病解析のための大規模シークエンス研究が世界中で行われている.また,がん研究や治療においても,ゲノム情報は必須になりつつある.
・ゲノムデータの解析研究のための基盤のひとつとして分子進化学,集団遺伝学は重要であると考えられる.本特集がゲノム解析を行う研究者の一助になると幸いである.

医学のあゆみ273巻3号
消化器疾患に対する内視鏡治療の最前線――機能性疾患から悪性腫瘍まで
消化器疾患に対する内視鏡治療の最前線――機能性疾患から悪性腫瘍まで
企画:矢作直久(慶應義塾大学医学部腫瘍センター)
・内視鏡は管腔内を観察してより正確に診断をつけるための機器であり,最初は組織をサンプリングする程度のことしか考えられなかったが,スネアが開発され高周波発生装置と組み合わせることで腫瘍の切除が可能となった.
・スネアしかなかった1990年代までは,切除できるサイズや部位が限られていたが,さまざまな処置具や新たな手技の開発により,現在では狙った範囲をほぼ確実に切除可能な,信頼性の高い治療法へと変貌を遂げている.
・従来は大きな侵襲を伴う外科手術しか選択肢がなかったものも,現在では内視鏡治療の普及により低侵襲治療へと大きくシフトしてきている.

医学のあゆみ273巻2号
糖尿病とスティグマ――Cure,CareからSalvation(救済)へ
糖尿病とスティグマ――Cure,CareからSalvation(救済)へ
企画:清野 裕(公益社団法人日本糖尿病協会理事長,関西電力病院総長)
・“スティグマ(stigma)”とは一般に“恥・不信用のしるし,不名誉な烙印”を意味し,ある特定の属性に所属する人に対して否定的な価値を付与することである.
・現在,糖尿病をめぐる医療環境は飛躍的に進歩しており,糖尿病があっても社会で活躍できる時代となっているが,おそらく社会のイメージは以前のままで固定されており,現在も糖尿病患者に不利益をもたらしている.
・糖尿病のスティグマのない社会をめざして,糖尿病医療に携わる医療従事者は,通常診療のみならず,患者の現状を認識し,患者に寄り添った立場から広く社会に訴えかけ,患者の権利を擁護する必要がある.

医学のあゆみ273巻13号
肝細胞癌治療のパラダイムシフト――分子標的薬,免疫チェックポイント阻害薬の登場を受けて
肝細胞癌治療のパラダイムシフト――分子標的薬,免疫チェックポイント阻害薬の登場を受けて
企画:工藤正俊(近畿大学医学部消化器内科)
・日本の肝細胞癌治療成績は,国単位では世界で最も優れている.サーベイランスは整備されており,また切除,局所治療,肝動脈化学塞栓療法(TACE)などの治療成績向上への取り組みが積極的に行われてきた.
・世界に先がけて日本で“TACE不応の概念”が提唱されたことは画期的である.TACE不応時点で分子標的薬に切り替えるほうが生存延長効果が得られることが明確に示され,ほぼグローバルコンセンサスとなっている.
・現在,肝細胞癌のすべてのステージで免疫チェックポイント阻害薬の臨床試験が進行中である.これらがもし成功すると本当の意味でのパラダイムチェンジが起こり,日本の肝癌治療の成績はさらに向上するであろう.

医学のあゆみ273巻12号
レトロトランスポゾンと内在性ウイルス――機能と疾患
レトロトランスポゾンと内在性ウイルス――機能と疾患
企画:朝長啓造(京都大学ウイルス・再生医科学研究所ウイルス感染研究部門RNAウイルス分野,同附属感染症モデル研究センター)
・ヒトのゲノムの約半分は,“動く遺伝子”あるいは“転移因子”とよばれるトランスポゾンで構成されている.
・ゲノムの大半を占めるレトロトランスポゾンと内在性レトロウイルスはその多くが機能を持たないと考えられてきたが,個体発生から疾患発症まで,さまざまな生命現象に関与していることが明らかとなってきている.
・本特集により,医学・生命科学領域におけるレトロトランスポゾンと内在性ウイルス研究の重要性がより深まることを期待する.
