
困ったウイルス肝炎パーフェクト対応ガイド
肝炎診療にあたる肝臓専門医、消化器科医を対象に、ウイルス肝炎の治療におけるDAA無効例、高齢者や臓器障害などspecial populationへの対応、ウイルス駆除後の肝硬変、発癌、緊急時や重症化などの“困ること・難しく感じること”を取り上げ、その対処法までを解説。各種ガイドラインには掲載されていない、現時点でのエキスパートの対応と知恵を結集し、明日からの診療に即役立つ一冊。

皮膚疾患全身療法薬Up-to-date
皮膚科で用いられる全身療法薬を解説。全身療法薬は高い効果が期待できる一方、外用薬とは異なり、使用にあたっては代謝状態、腎機能、肝機能、その他の副作用等に注意が必要である。前半では各全身療法薬の基本知識を解説し、後半では、著効例のほかに併存疾患を持つ症例などを題材にエキスパートの処方方法や注意点を解説した。

シンプルなロジックですぐできる
薬からの摂食嚥下臨床実践メソッド
●この1冊で誤嚥性肺炎の予防&治療、摂食嚥下リハ・薬物療法(認知症、パーキンソン病、COPD、気管支喘息、脳卒中、 etc.)・服薬管理のすべてがうまくいく!
●薬の視点からの摂食嚥下障害へのアプローチ方法を豊富な症例も含めて解説!
超高齢社会を迎えるわが国では、嚥下障害や誤嚥性肺炎患者が爆発的に増加しています。そのため、医療者は嚥下機能に影響を与える薬剤について評価し、嚥下機能の変化をチームでフォローしていく必要があります。
本書は、嚥下障害や食支援を薬剤の視点から実践的に解説しました。「嚥下や食を考慮した処方」という臨床的アドバンテージが身に付く1冊です。

ウィズコロナ時代の医療・介護経営
医療・介護の経営情報誌『日経ヘルスケア』の専門記者による総力取材で、コロナ後に「患者・利用者が減った」など、ニューノーマル時代の経営課題に適応するための取り組みをリポート。COVID-19陽性者が発生した際のリスクマネジメントや、普段からできる増収・増患策などを解説する。ピンチをチャンスに変え、より進化した組織に成長するためのノウハウや先進事例を盛り込んだ。

まんが 医学の歴史
医学の歴史は、人類の誕生とともにはじまり、いつの世もらせん状に続いてきた泣き笑いの人間ドラマがあった。世界初! 臨床医であり漫画家である著者による、まんがでみるわかりやすい医学の通史、堂々の刊行。古代の神々からクローン羊のドリーまで、『看護学雑誌』2003~2005年の連載に大幅描き下ろしを加えた。

歯界展望2018セット(131巻・132巻)
バラで買うよりお得!2018年に発行された歯界展望131巻1号~132巻6号までの12冊セットです. 高い信頼と定評のある誌面作り,最新情報も充実!ベーシックからアドバンスまで実際の臨床現場に即したケースプレゼンテーションを毎月多彩なコラムで数多くお届けします.臨床や医院運営など若手歯科医師が抱える日頃の悩みの解決のヒントとなる情報をまとめたコラムも充実!

看護研究 Vol.53 No.6
2020年12月発行
特集 ウィズ・コロナ時代の看護研究 COVID-19は研究にどのような影響をもたらしているか 2
特集 ウィズ・コロナ時代の看護研究 COVID-19は研究にどのような影響をもたらしているか 2 -

臨床検査 Vol.65 No.1
2021年 01月発行
特集 対比して学ぶ エコー所見で鑑別に悩む疾患
特集 対比して学ぶ エコー所見で鑑別に悩む疾患 -

臨床泌尿器科 Vol.74 No.13
2020年 12月発行
コロナ時代の泌尿器科領域における感染制御
コロナ時代の泌尿器科領域における感染制御 -
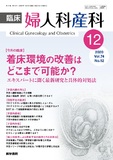
臨床婦人科産科 Vol.74 No.12
2020年 12月発行
今月の臨床 着床環境の改善はどこまで可能か? エキスパートに聞く最新研究と具体的対処法
今月の臨床 着床環境の改善はどこまで可能か? エキスパートに聞く最新研究と具体的対処法 -

精神医学 Vol.62 No.12
2020年 12月発行
特集 身体症状症の病態と治療 器質因がはっきりしない身体症状をどう扱うか?
特集 身体症状症の病態と治療 器質因がはっきりしない身体症状をどう扱うか? -

脳神経外科 Vol.48 No.12
2020年 12月発行
-

胃と腸 Vol.55 No.13
2020年 12月発行
主題 大腸鋸歯状病変の新展開
主題 大腸鋸歯状病変の新展開 -

がんのリハビリテーション診療ベストプラクティス 第2版
『がんのリハビリテーション診療ガイドライン』で示された最新のエビデンスを、「臨床での最良の実践方法」に落とし込み解説。「誰が、いつ、どこで行うのか」「どのような方法で行うのか」といった具体的な解説は、リハビリテーション専門職をはじめ多くの医療者の助けとなるだろう。患者への説明に重宝するパンフレット例など付録も充実し、診療ガイドラインに基づくリハビリテーション医療を実践するうえで必読の一冊となった。

関節外科 基礎と臨床 Vol.40 No.1
2021年1月号
【特集】日常よくある足疾患 保存治療を含めた治療法
【特集】日常よくある足疾患 保存治療を含めた治療法

人類は感染症とともに生きていく
学校では教えてくれないパンデミックとワクチンの現代史
CNNのジャーナリストであり公衆衛生の研究者でもある著者が、綿密な調査のもと綴った入門書。近年注目された感染症を広く解説すると共に、諸外国の驚くべき実情も紹介。未来に繋がる教訓と勇気を歴史から学ぼう!
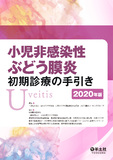
小児非感染性ぶどう膜炎初期診療の手引き 2020年版
小児では特に診断や治療が難しいとされる非感染性ぶどう膜炎の初期診療を,現状のエビデンスをもとに診断から評価や管理・治療に至るまで解説した,眼科だけでなく小児科やリウマチ科の先生にも役立つ1冊.

実験医学増刊 Vol.38 No.20
【特集】機械学習を生命科学に使う!
【特集】機械学習を生命科学に使う! 生命科学研究に機械学習のアプローチをどのように使うのか,それによって何ができるのかを解説します.初心者にも取り組みやすいGoogle ColaboratoryやImageJの入門記事もおすすめです.

歯界展望 133巻6号
誤嚥性肺炎予防は次のステージへ ~予防を具現化するための他職種連携,歯科医師・歯科衛生士の役割~
誤嚥性肺炎予防は次のステージへ ~予防を具現化するための他職種連携,歯科医師・歯科衛生士の役割~ 高い信頼と定評のある誌面作り,最新情報も充実!ベーシックからアドバンスまで実際の臨床現場に即したケースプレゼンテーションを毎月多彩なコラムで数多くお届けします.臨床や医院運営など若手歯科医師が抱える日頃の悩みの解決のヒントとなる情報をまとめたコラムも充実!
本特集は『誤嚥性肺炎予防は次のステージへ』です.1999 年,定期的な口腔ケアの実施により肺炎の発症・重症化が歴然と低下することを示す論文(Yoneyama T, et al. Lancet.1999)が発表され,国内外から大きな注目を集めました.本特集では論文発表後20 年となる本年,論文のFirst Author である米山氏の呼びかけでお集まりいただいた臨床家,研究者の方々により,「誤嚥性肺炎」の病因,病態,予防策を改めて整理・検証し,次のステージを見据えたストラテジーの展望について語っていただきました.

歯界展望 133巻5号
「難症例」を紐解く
「難症例」を紐解く
高い信頼と定評のある誌面作り,最新情報も充実!ベーシックからアドバンスまで実際の臨床現場に即したケースプレゼンテーションを毎月多彩なコラムで数多くお届けします.臨床や医院運営など若手歯科医師が抱える日頃の悩みの解決のヒントとなる情報をまとめたコラムも充実!
本特集は『「難症例」を紐解く』です.従来から難症例とされてきた「すれ違い咬合」は,今も変わらず難症例なのでしょうか.近年,抜歯原因として注目される歯根破折,また超高齢社会においては,治療時に想定しにくい問題の長期経過観察のなかでの顕在化など,「難症例」の意味は変化してきているようです.臨床家にとっての「難症例」の現代的な意味を,多くの長期経過症例からディスカッションいただきました.客観的な「難症例」のものさしを求める一つの試みとしてお読みいただければと思います.
