
J. of Clinical Rehabilitation 29巻3号
社会的行動障害へのアプローチ
社会的行動障害へのアプローチ
高次脳機能障害へのリハビリテーション(以下リハ)医療の取り組みとして,2001年より開始されたモデル事業時代の実態調査でも,社会的行動障害は高次脳機能障害の症状として頻度の多い4大症状の一つとして挙げられた.社会的行動障害と一言で表されるが,その状態は多岐にわたり,固執性,易怒性,意欲低下,病識欠如等多くの病態を含む「社会参加の制限につながる行動障害」の総称である.リハ医療がどのようにこの障害に取り組んでいけばよいのか,現場では日々苦慮している状況にある.
高次脳機能障害の支援が全国的に事業化され,10年余り経過する中で支援のうまくいかない困難事例の大部分が社会的行動障害の強い事例であると考えられ,2016年~2018年に厚生労働科学研究で社会的行動障害の実態調査が実施された.その詳細な報告およびその成果物として「社会的行動障害への対応と支援」というマニュアルが昨年7月に公開された.そのような動きの中,本誌で社会的行動障害にスポットライトを当てる特集を企画した次第である.
本特集では,まず社会的行動障害についての概説,さらに2016年度より実施された実態調査の結果について,高次脳機能障害支援事業の開始当初から中心的にご活躍された中島八十一先生に解説していただいた.次に,多くの精神症状・行動障害の中で頻度の多い「易怒性,感情コントロール障害」「意欲・発動性低下」にターゲットを絞り,それぞれ京都大学の上田敬太先生,埼玉総合リハビリテーションセンターの先崎 章先生に執筆いただいた.これらの精神科医療との狭間にある症状に対する薬物治療の実際と,リハ医療でも実践可能な非薬物的治療(心理療法,環境調整等)にも言及していただいている.また社会的行動障害は当事者の社会参加を制限するにとどまらず,介護者,特に家族に大きな負担感を与える障害であることから,家族支援をテーマに東京慈恵会医科大学の渡邉 修先生に執筆いただいた.最後に,社会的行動障害の一端ではあるが,起きてしまうと大きな問題となる「触法行為」を取り上げ,触法行為と精神障害の関係,鑑定書・意見書を求められたときの留意点等を弁護士の中井克洋先生に解説いただいた.
本特集では,「明日からの診療に役に立つ情報をお届けする」をテーマに企画したが,それぞれの領域の第一人者の先生方にご執筆いただくことができ,大変充実した内容になったと考えている.本特集が高次脳機能障害患者の社会的行動障害の対応に日々苦慮する先生方の診療の一助となればと期待している.(編集委員会)
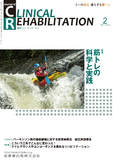
J. of Clinical Rehabilitation 29巻2号
筋トレの科学と実践
筋トレの科学と実践
近年,筋萎縮・筋力低下の問題は高齢者のサルコペニアに焦点が当てられるなか,栄養学を含めた学際的な領域へと発展してきている.単に食事を十分とって運動するというだけでは解決できない問題のようだ.先日,サルコペニア肥満の症例を診る機会があったが,外見では筋萎縮はわからないということを実感した.そもそも脂肪と筋組織が違うのは当然で,栄養補給もその視点で考えるのは同じく当然のことである.しかし,普通の食事をとって普通のsedentaryな生活を送っている高齢者のなかにもサルコペニアは存在するわけで,改めて筋萎縮の問題の深淵さを感じる.
リハビリテーション(以下リハ)以外の領域でサルコペニアやフレイル(frailty)が取り上げられる機会が増える一方,リハではどう対応するのかを問われることも増えている.筋トレはリハの原点の1つでもある.いろいろ要件はあるものの,この問いに対しては筋トレと答えるわけであるが,踏み込んだ話になると答えられないことも多い.そもそも筋肥大はどういうメカニズムで起こるのか,どうすれば効率的に筋肥大が起こるのか,筋肥大は筋力増強と同義なのか等,リハ従事者としては生化学,そして生理学的な基礎に立ち返って答えなければならないと考える.
高齢者のサルコペニアの話題から離れて,若い層の中でも筋トレがブーム化している.体育系の学問を修めた専門家が下支えして,スポーツジム文化が育っている.ボディビルとまでいかないまでも,ダイエットを意識した筋トレ人口は相当数あるのではないだろうか.その延長線上では電気刺激や加圧トレーニングといった技術を取り入れたものまで用意されている.治療としての電気刺激についてはリハ領域でも長い歴史があるが,商業ベースで使われる電気刺激装置に関する知識は乏しく,果たして効果はどの程度なのかと質問されても答えに窮する.一方,リハでは筋トレと電気刺激を組み合わせた新技術が研究され,既にシステム化されており,無重力での廃用性筋萎縮に学問的に取り組んだ報告もある.加圧トレーニングも医療界で取り組む例が出てきており,高齢者,種々の基礎疾患をもった患者にも安全に適用できることが報告されている.
本特集ではこのような社会背景に対して,筋トレを正面から扱い,生化学,生理学,栄養学,理学療法学,そして医学における当該領域の第一人者から執筆いただくことにした.高齢者,患者のためだけのテーマでなく,広く一般の筋トレブーマーにも役立つ内容になっているので,リハに携わる読者には自身の専門領域の知識の補充として役立てられたい.(編集委員会)
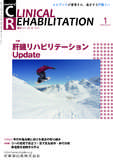
J. of Clinical Rehabilitation 29巻1号
肝臓リハビリテーション Update
肝臓リハビリテーション Update
肝臓は代謝中枢機能を持ち,また消化吸収に重要な胆汁分泌や生体に不要な物質を排泄する胆汁色素代謝・解毒等,身体のホメオスターシスや健康を維持するための多くの重要な役割を果たしている.しかし,肝臓は「沈黙の臓器」といわれるように,病気になっても当初は自覚症状に乏しく,肝硬変や肝がんといった重篤な事態になって初めて気づかれる場合も少なくない.重度の肝臓機能障害では,脱力感,掻痒感,筋肉痛,体重減少,腹水による腹部の膨満感,浮腫,消化管の静脈瘤の破綻による吐下血,脳症による意識障害・昏睡,食思不振・悪心・嘔吐等の症状により日常生活活動が制限される.
肝臓機能障害は2010年4月に新たに追加された内部障害である.CRでは2011年4月号で「見えない障害,肝臓のリハビリテーション」というわが国初の肝臓リハビリテーションの特集を組んだ.それから,8年が経過した.この間に,肝臓機能障害の身体障害認定基準が緩和され,肝臓リハビリテーションの運動療法のエビデンスが大きく進歩を遂げた.
そこで,本特集号では,肝臓機能障害の基礎疾患,身体障害認定基準の変更内容,障害の特徴,ADLや運動耐容能をレビューするとともに,慢性肝炎,肝硬変,肝がん,肝移植後の肝臓リハビリテーションの方法と効果について最新知見やエビデンスを交えながら解説いただくこととした.
執筆者はこの領域でトップランナーとしてご活躍されている先生方であり,極めて充実した内容にしていただいた.すなわち,上月正博先生からは総論として肝臓リハビリテーションの考え方を明快に示していただいた.また,NAFLD/NASH患者のリハビリテーションを小田耕平先生らに,肝硬変患者のリハビリテーションを筆保健一先生らに,肝がん患者のリハビリテーションを西田佳弘先生らに,小児の肝移植後患者のリハビリテーションを峯 耕太郎先生らに,肝移植術後患者に対する微弱電気刺激療法を花田匡利先生らに,それぞれ,病態,運動耐容能やADL,運動療法の効果,食事療法・薬物療法の効果,リハビリテーション普及の阻害因子と解決法等に関してわかりやすく解説していただいた.
肝臓機能障害は腎臓機能障害と並ぶリハビリテーション医学・医療のこれからの大きなターゲットである.本特集により肝臓機能障害を正しく理解するスタッフが増え,自信を持ってそのリハビリテーションの普及にますます貢献されることを期待する.(編集委員会)
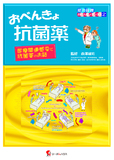
おべんきょ抗菌薬
医療関連感染と抗菌薬のお話
薬剤耐性菌(AMR)対策が世界的に深刻な問題となり,医師,看護師など職種を問わず,抗菌薬の知識が求められる昨今,本書は,医療関連感染と抗菌薬の関係性を中心に講義形式で読みやすく解説した抗菌薬入門書です!感染管理おべんきょブックスシリーズの第2弾。
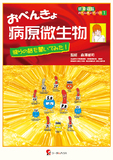
おべんきょ病原微生物
彼らの話も聞いてみた!
「感染」や「感染症」,「免疫」,「耐性菌」,「消毒」などについて病原微生物が微生物目線で語るスタイルの異色のテキスト。病原微生物の勉強が苦手な方々にも読みやすい内容です。感染管理おべんきょブックスシリーズの第1弾。

医療従事者のための 感染対策ルールブック
感染対策は感染防止のために必要なルールの集積です。本書は,エビデンスに基づいた227のルールを感染対策の第一人者である矢野邦夫先生がカテゴリー別に厳選し,ハンディーな新書判にまとめています。現場で感染対策を実践する医療従事者の方々,とりわけ研修医や新人看護師のみなさんにとって有益な情報を満載した手軽に使える実務重視のポケットルール集です。

皮膚病診療 Vol.42 No.13
2020年増刊号
【特集】形からみる皮膚疾患
【特集】形からみる皮膚疾患
皮膚症状の形に注目して7項目(線状、帯状、環状、網状、地図状、斑状、結節性)に分類し,その特徴から考えられる疾患をまとめた症例集です。

NAFLD/NASH診療ガイドライン2020 改訂第2版
日本消化器病学会・日本肝臓学会の共編による診療ガイドライン。Mindsの作成マニュアルに準拠し、臨床上の疑問をCQ(clinical question)、BQ(background question)、FRQ(future research question)に分けて記載。CQではエビデンスレベルと推奨の強さを提示。NAFLD/NASH診療における、疫学、病態、診断、治療、予後・発癌・フォローアップ等について、エビデンスに基づき現時点の標準的な指針を示す。

消化器外科2020年12月号
見直そう!;大腸がんに対する腹腔鏡・ロボット手術の基本手技
見直そう!;大腸がんに対する腹腔鏡・ロボット手術の基本手技 腹腔鏡・ロボット手術のような低侵襲手術は大腸癌に対する手術として適したアプローチであるといえる。本号では、大腸癌の部位別の基本術式について、術野展開方法を中心とした術式のポイントを写真・イラストを用いてわかりやすく解説した。

急性白血病診療テキスト エキスパートに学ぶ
抗がん剤治療が奏効しにくく,「不治の病」と見られがちだった急性白血病は近年,新薬などが承認され,その治療法は大きく進歩しつつある.本書では,急性骨髄性白血病・急性リンパ性白血病について,それぞれ前半部分で治療を安全に行うための血液学の基礎医学の知識,後半部分でそれぞれの疾患・病態に対する標準治療をエビデンスに基づき解説.より臨床の現場に即して使いやすいように,レジメンも記載した.

Heart View Vol.25 No.1
2021年1月号
【特集】抗血小板・抗凝固薬投与の問題は解決した?
【特集】抗血小板・抗凝固薬投与の問題は解決した?

古典的要点に学ぶ151生薬
センプク漢方セミナー長沢道寿「増補能毒」
現代につながる処方-古典に学ぶ漢方の知恵
長沢道寿の『増補能毒』は経験に基づいた、現代にも通じる漢方処方が記されている古典的名著です。読みにくいと思われる古典を著者がわかりやすく読み解いていきます。難しいと思われがちな漢方の古典ですが、漢方処方に対する道寿の熱い思いが伝わってくるような1冊です。ワンポイントアドバイスも面白い。

≪専門医のための精神科臨床リュミエール 21≫
前頭葉でわかる精神疾患の臨床
精神疾患の臨床症状と前頭葉機能の関連について,最新の知識をまとめた一冊.前半では前頭葉の構造と機能について,各部位ごとに最先端の研究を詳述し,後半ではそれを踏まえて,認知症,統合失調症,気分障害をはじめとするさまざまな精神疾患について明らかとなってきた前頭葉の構造と機能の特徴を解説.「精神の座」とされてきた前頭葉の機能から精神疾患を読み解く.

はじめての鍼灸マッサージ治療院 開業ベーシックマニュアル
「治療院を開業したい」と思ったら、まずこの1冊!
開業に必要な手順・手続きを、順を追って丁寧に解説
治療院の開業は治療家にとって大きなターニングポイント。治療の腕を磨かなければならないのはもちろんですが、それと同じくらい大切なのが、治療院経営について学ぶことです。
本書は、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師が治療院を開業する際に、必ず知っておかなければならない準備や手続き、そして経営の考え方について、イラストや図解を交えながら、分かりやすく解説。「開業資金が足りない」「どこで開業するか決められない」「そもそもどんな治療院にしたいか分からない・・・・・・」といった基本的な悩みに対して、治療家に役立つ内容にしぼって解説しています。

血管インパクト イラストと雑学で楽しく学ぶ解剖学
「血管」のことが楽しく学べるテキストです!
イラストで楽しく学べるテキスト「インパクト」シリーズ最新作。今回は「血管」がテーマです。主な血管ごとに、身体のどこを通るのか、どう枝分かれするのかを、わかりやすく図示しました。シリーズの特徴である雑学は今作でも盛りだくさん。既刊の『マッスルインパクト』『ボーンインパクト』『神経インパクト』と合わせて読めば、よりいっそう解剖学が楽しくなります!
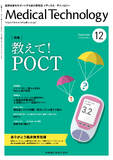
Medical Technology 48巻12号
教えて! POCT
教えて! POCT
2004 年にはじめてPOCT ガイドラインが発行され,以来,POCT は多様な発展を遂げてきました.迅速・簡便な操作で,検査結果を臨床に提供できることはPOCT の最大の特長であり,診療所や在宅医療,また災害現場など,多用なニーズがあることからも注目を集めています.そのようななか,編集部に「POCT について初心者でもわかるように,取り上げていただけないでしょうか?」との声が届きました.
そこでこのたび,POCT について読者の方からお寄せいただいた疑問や知りたい内容について,ご専門の先生方にご回答・解説をいただく特集をお届けします.みずからが検査者として使用する機会は少なくとも,検査のプロとして他職種の方達をサポート,運用し模範を示せるよう,本特集をご活用いただければ嬉しく思います.(編集部)

Medical Technology 48巻11号
検査室からみた生活習慣病-症例から学ぶ 病態と検査データの見方
検査室からみた生活習慣病-症例から学ぶ 病態と検査データの見方
生活習慣病は重篤な疾患の危険因子となり,身近でかつ重要な疾患群です.読者の皆様からは「生活習慣病に必要な検査とその結果の見方について教えてもらいたいです」,「検査結果を見た医師がどのように考え,診療・治療につなげていくのか知りたいです」といった声を頂戴しています.
そこで今回は,「検査室からみた生活習慣病」をテーマに,生活習慣病を有する各症例から検査データの読み解き方と診療の流れをご解説いただきます.第2 章は冒頭に症例を提示し解説,という流れになっておりますので,自分だったらどう考えるか,シミュレーションしながら読み進めていただければ幸いです.(編集部)

Medical Technology 48巻10号
着眼点を鍛える! 高齢者における細胞診
着眼点を鍛える! 高齢者における細胞診
今や日本は全人口の約28%を65 歳以上が占める超高齢社会となりましたが,高齢者を対象とした細胞診は,良悪性の判定が困難な細胞が出現したり,領域によって細胞観察時の注意点や思考プロセスが異なるなどの特徴があり,また典型像と異なる細胞像を呈することも,難しさを感じさせる原因となっています.
そこで本特集では,豊富なご経験をお持ちの先生方が高齢者の細胞診を行う際に何に着眼し,どのような思考プロセスで検査を行っているかご紹介いただきます.プロの視点を学びとり,ご自身の糧にしていただければと思います.(編集部)

検査と技術 Vol.49 No.1
2021年1月発行
-

総合リハビリテーション Vol.48 No.12
2020年12月発行
特集 障害者の加齢に伴う問題とその支援
特集 障害者の加齢に伴う問題とその支援 障害児者も加齢により,さまざまな成人の疾患への罹患率が増え,長期間障害をもって暮らしてきたことによる二次障害も頻度が増加します.そして家族や支援者の加齢や疾患といった変化にも対応しなければなりません.医療の進歩によって得られつつある障害児者の寿命の延伸が,ゆたかなものになるように,周囲や環境も支援方法や制度を変更していく必要があります.本特集では,さまざまな立場の方々から,障害児者の加齢に伴う問題とその支援についてご執筆いただきました.
