
看護理論家の業績と理論評価 第3版
看護理論の現在・そして未来へ。── 次代をひらくために実践知の体系化をめざす ──
欧米の31人の看護理論家の業績および理論の紹介、それぞれの理論の評価を解説する待望の第3版。今改訂では、新たに日本の看護学の礎を築いた先駆者たちも紹介。理論を学び、臨床に活かし、次代の看護科学をともに築くための必携書。

小児外科リファレンス

薬局ですぐに役立つ薬剤一覧ポケットブック
調剤、処方鑑査、服薬指導で使える便利な一覧と知っておきたい必須知識
「粉砕不可一覧」「一包化不可一覧」「疾患併用禁忌一覧」など,便利な薬の一覧が充実の57項目!わかりやすい解説も必読.調剤,処方鑑査,服薬指導の重要ポイントが学べます.ポケットに入れておきたい必携の1冊

症状から一発診断!
整形外科専門医はこう見立てる 第3版
好評書籍の改訂第3版。
患者の「主訴」「症状」から入り、外傷疾患や変性疾患までもカバー。一般診療の“武器”となる一冊です。
整形外科医はもちろんのこと、一般内科医、外科医をはじめ、柔道整復師やスポーツトレーナーの方々にもおすすめ。

本当に使える症候学の話をしよう とことんわかる病態のクリニカルロジック
●解剖・生理からひも解く病歴・身体所見の深い診かた
●患者の訴えを鵜呑みにしない「聞く」テクニック
●総合診療の目線で日々全身を診ている医師が教える新しい症候学
症状を手がかりに疾患や病態を探る症候学。しかし、実際の臨床ではシンプルに「この症状ならこの病気」とはいかないものです。そこで本書は、解剖学、生理学、組織学、免疫学などを駆使して症状をとらえ、判断に困ったときの考え方や現場で使える診かたをわかりやすくレクチャーします。
病態生理を掘り下げることで、これまでより深い病歴・身体所見の診かた、患者さんにポイントを突いた聞き方ができるようになります。
総合診療の目線で「全身を診ること」にこだわってきた医師が教える、これまでになかった病態推論。医師、薬剤師、看護師問わず、わかりやすく現場に役立つ1冊です!

もしも「死にたい」と言われたら 自殺リスクの評価と対応
「死にたい」とだれかに告げることは,「死にたいくらいつらい」ということ.だから,もしもこのつらさを少しでもやわらげることができるならば,「本当は生きたい」のである.「死にたい」という患者を前にして医療は何ができるのか,何をすべきなのか.自殺企図,自殺未遂患者の自殺リスクをどう評価して,どう対応すべきなのか.この難しいテーマに真っ向から取り組んできた筆者がこれまでの経験と知識を元に書き下ろした一冊.
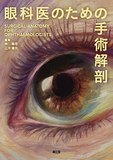
眼科医のための手術解剖
眼科手術全般において,低侵襲あるいは無駄のない合理的な手術を実現するためには「局所解剖の熟知」が必須である.本書は各専門領域のトップサージャンの視点から,手術解剖を究めるために必要な写真と数百枚に及ぶリアルな解剖図で満たした最高の指南書である.基本的なアプローチに加え,術野をみやすくする一工夫も掲載され,手術前に読むだけで自信をもたらしてくれる一冊.

摂食障害の認知行動療法
「摂食障害患者への認知行動療法」の実施やテクニックについて詳しく紹介。原因を問うよりも、病状を持続させているプロセスに注目し、まず摂食行動異常、そしてその背景にある精神病理についても扱っている。摂食障害患者にかかわる医師、臨床心理士にとって、日常臨床をより効果的に進めるための参考書。

ロジックで進めるリウマチ・膠原病診療
すぐれた若手リウマチ内科医・指導医として知られる著者が、その診療ロジックを惜しげもなく開陳した。プライマリ・ケアの場で一般医は、リウマチ・膠原病を「どう疑い」「どう追い詰める」べきなのか、治療薬を「何をもとに決定し、どう使用するのか」などの診療の基本を、著者ならではのロジック(思考経路)をもってわかりやすく示した。すべてのプライマリ・ケア医が読むべき「通読できるリウマチ・膠原病の教科書」の登場。

医学のあゆみ296巻6号
第1土曜特集
急性腹症の診療の質を上げる秘策
急性腹症の診療の質を上げる秘策
企画:真弓俊彦(地域医療機能推進機構中京病院ICU 診療部副院長,ICU 部長)
・7年ぶりに改訂された「急性腹症診療ガイドライン」のポイントをガイドライン作成メンバーが直々に解説するとともに,ガイドラインの内容とあわせておさえておきたい診療のコツがまとまった一冊.
・超音波検査,小児・高齢者の急性腹症,イレウス,腸閉塞などにおける“診療の質を上げる秘策”を各エキスパートたちがその豊富な経験をもとに伝授する.
・さらに,急性腹症における訴訟リスクを低減するための診療上の留意点も取り上げ,考察する.

皮膚科 膠原病
皮疹から全身を診る
チーム医療が求められる膠原病診療において,よりよい診療のために皮膚科医として知っておきたい知識を網羅した書.特異的な皮疹が学べる臨床写真を多く盛り込んでアトラス的な要素を充実させるとともに,近年臨床的意義が高まっている自己抗体を大きく取り上げた.他科における診療のポイント,病態解明研究の最新情報についても解説しており,膠原病の実態をより深く理解できる.

頭頸部がん薬物療法ハンドブック 改訂3版
頭頸部がん薬物療法に特化したマニュアルとして好評を博した書の改訂第3版.専門病院のスタッフのみならず,一般病院のスタッフにも役立つよう,頭頸部がんの薬物療法に特徴的な臨床上のコツや支持療法を平易にまとめている.今版では近年の新薬の導入を踏まえ,転移・再発がんに対する治療法を重点的に加えた.執筆陣には経験豊富な各エキスパートを集め,実際の現場での治療立案・実践および副作用管理に役立つ実践書である.

伝わる!真似できる!手術記録の描き方・活かし方 デジタルイラストで描くオペレコ入門 すぐに使えるイラストパーツ&WEB動画付 第2版
第1版の刊行から約4年が経過しましたが、以前と変わらず外科医の働く環境は大変多忙を極めており、手術記録を短時間かつより伝わるものとして記録する技術がより求められています。
本書では、手術記録に関する基礎的な知識はもとより、実際に真似でき、効率的かつ効果的な手術記録の書き方・活かし方について1冊に凝縮して提示しており、いままで絵をデジタルで描いたことがない方、またそもそも絵に苦手意識のある方でもツールの導入から、操作方法、線画、色付けと本書の内容に沿って実際に手を動かすことで簡単にマスターすることができます。
今回の改訂では、患者さんへの説明書式への応用、最近のオペレコを紹介するとともに、急速に普及しつつあるロボット手術に対応できるような「イラストパーツ」を追加しました。
ぜひ本書をきっかけにデジタルイラストに挑戦してみてください。

研修医・総合診療医のための
精神科ファーストタッチ
●コンパクトだけど精神科の悩みを解決できる1冊!
●向精神薬の選び方・心のケアのポイントがシンプルにわかる!
●「スタンダードな治療のながれは?」「向精神薬のリスクと限界は?」「副作用?それとも増悪?」一度でも悩んだことのある人必読!
精神疾患への向き合いかたに迷子になっているすべての研修医へ。せん妄や抑うつなどの精神症状を一度でも診たことがある人なら知っておきたい診断・治療のエッセンスをまとめました。重要なポイントにしぼって、スタンダードな治療のながれをぎゅっと解説。数値・画像でとらえづらい疾患・症状でも、パッと引いてすぐに実践できます。さらに、よく使われる向精神薬の適応症や適用外使用がサッと確認できる一覧表付き! コンパクトながら、疾患・薬・副作用を網羅的にカバーした万能な1冊です。

新 呼吸器専門医テキスト 改訂第2版
日本呼吸器学会編集による「呼吸器専門研修カリキュラム」に準拠したテキストの改訂版。2019年のカリキュラム改定に対応。総論では呼吸器の形態・機能、病態生理から症候、身体所見、各種検査、治療手技までを解説。各論では呼吸器科医に必要な各呼吸器疾患を解説。各項の冒頭には「到達目標」を提示し、巻末付録には専門医試験の過去問題を掲載している。専門医を目指す医師の自己学習のため、ならびに専門医取得者の知識更新に必携の一冊。

臨床・病理
胆道癌取扱い規約 第7版
8年ぶりとなる本改訂では、最新のUICC TNM分類第8版に準拠するとともに、病理ではWHO分類第5版の内容を反映。また、前版の第6版改訂の際に削除された項目から、臨床上必要な情報は改めて掲載した。さらに、胆管癌、胆嚢癌、乳頭部癌の3分類で記載内容が重複しないよう構成や記載順を変更したほか、ゲノム診断における病理標本処理方法の項目の新設、臨床所見と病理所見のチェックリストの掲載など、より使いやすい内容となることを目指した。胆道癌診療において必携の一冊。

内分泌専門医に絶対合格したい人のための問題集 第2版
専門医試験合格を目指す研修医/若手医師のための唯一無二の問題集、待望の新装改訂版です。
・気鋭の筆者が、自身の受験体験をもとに専門医試験の出題項目を総まとめ。
・一次試験(書類審査)でのサマリーの選び方や書き方のコツ、提出後のうっかりチェックもフォロー。二次試験(筆記試験)で問われる部位・疾患別の解説はもちろん、直前総仕上げもカバーしてくれる、専門医試験完全攻略のための問題集です。

整形外科 SURGICAL TECHNIQUE(サージカルテクニック) 2023年4号
2023年4号
特集: 踵骨・距骨骨折の手術治療
特集: 踵骨・距骨骨折の手術治療 整形外科領域の「手術」を徹底して取り上げる専門誌『整形外科サージカルテクニック』
教科書には載っていない手術のコツ、ピットフォール、リカバリー法が満載。各手術のエキスパートの技と知恵を凝縮した「手術が見える・わかる専門誌」です。
本誌で取り上げた手術動画を専用WEBページでチェックでき、誌面と動画でしっかり確認できます。
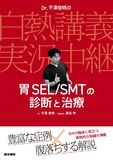
Dr. 平澤俊明の白熱講義実況中継 胃SEL/SMTの診断と治療
豊富な症例×腹落ちする解説で,胃SELの診断と治療の実践的な知識を習得できる一冊
胃SEL(subepithelial lesion)の診断と治療についての実践的な知識を体系的にわかりやすく解説.「豊富な症例」と日々の診療で生じる疑問点や初学者がつまずきがちなポイントに焦点を当てた「腹落ちする解説」を、工夫を凝らした「視覚的に理解しやすいレイアウト」と自然に引き込まれるような語り口かつ明快な「実況中継」形式で、読む人のわかりやすさにこだわってまとめ上げた、他に類を見ない一冊!

医療系 はじめまして!統計学
医療分野を目指す学生やさまざまな職種の医療従事者が、はじめて統計を学ぶことを想定した教科書。数式は少し、身近な具体例を日常用語で説明、簡単な統計用語やコンピュータ用語辞典付き、統計学的なプレゼンテーション能力も身に付けることをめざして書かれた。統計のはじめの1冊に最適。
