
3秒でわかる漢方ルール
複雑混沌とした漢方の世界にわずか3秒で合理的に理解できるルールをまとめました。今まで誰も書かなかった、Improbable(ありえない)本ができました。お楽しみください。

フレームワークで考える内科診断
もう鑑別診断で迷わない!直感や記憶力に頼らない、全く新しいアプローチ法
内科でよく遭遇する50の症例に関し、著者が組み立てた診断アプローチを行う上での考え方の枠組み=フレームワークを解説。鑑別診断に際し羅列的に診断名を挙げていくアプローチとは異なり、症例ごとに解剖学・生理学・症候学等に基づいた分類に従いポイントを提示。診断の過程をフローチャートを示しつつ順を追って解説。医学生や研修医が考え方の「型」を身につけるのに役立ち、ケースカンファレンスを行う指導医にも最適。各疾患ごとのフローチャートのみをまとめた別冊付き。

産婦人科ベッドサイドマニュアル 第8版
代々受け継がれ、磨かれてきた 産婦人科臨床必携マニュアル
産婦人科臨床必携との定評あるポケット判マニュアルが5年ぶりにアップデート。実臨床に徹して内容を精選、配列したことにより初版刊行から30年以上にわたり支持されてきた。臨床で困ったこと、不明な事態に遭遇したときに、本書を開けばほぼ間違いなく答えが得られる。病棟のみならず外来診療にも心強い味方。研修医にもベテラン臨床家にも、本書を迷わずおすすめする!

medicina Vol.62 No.4
2025年 04月号(増刊号)
特集 総合力で対応する Emergency/Intensive Care Medicine 内科医ができる初期治療:応援が来るまでにデキること
特集 総合力で対応する Emergency/Intensive Care Medicine 内科医ができる初期治療:応援が来るまでにデキること 内科診療に不可欠な情報をわかりやすくお届けする総合臨床誌。通常号では内科領域のさまざまなテーマを特集形式で取り上げるとともに、連載では注目のトピックスを掘り下げる。また、領域横断的なテーマの増刊号、増大号も発行。知識のアップデートと、技術のブラッシュアップに! (ISSN 0025-7699)
月刊、増刊号と増大号を含む年13冊

こういうことだったのか!!酸素療法
酸素療法はその仕組みを理解することが,うまく使いこなせるようになる近道である.苦手意識のある医師,看護師,臨床工学技士は必読.酸素療法が好きになる,新バイブル.

高齢者ERレジデントマニュアル
「成人と高齢者は鑑別が異なる。マネジメントも異なる。高齢者は評価に時間がかかる」――。そんな悩みを抱える若手医師に向けて、本書は1)成人との比較論でない高齢者の特徴、2)診断できなくても結局どうするか、3)高齢者でも短時間で評価が可能なテクニックを解説した。救急搬送が年間1万台のERで研修医と日々奮闘している筆者が「高齢救急患者特有の診療・マネジメント」のコツを余すところなく注ぎ込んだマニュアル。

小腸癌取扱い規約
本邦における小腸癌治療成績のさらなる向上に資する、という規約の基本理念を踏まえ、TNM分類第8版および他臓器の癌取扱い規約との整合性を重視して作成した。
TNM分類第8版と大腸癌取扱い規約第9版を参考とし、Treitz靭帯以下の小腸の解剖学的構造を考慮したが、領域リンパ節の定義、進行度分類はTNM分類と異なっている。
また、希少な病理画像を数多く掲載した。

やさしく学べる がん免疫療法のしくみ
がん治療にかかわる医師・メディカルスタッフが最も知りたい「がん免疫療法」の入門テキスト.なぜ効くのか? 副作用や課題は? 豊富な図とともにに,やさしく解説.

脳神経外科 周術期管理のすべて 第5版
第4版が2014年に刊行されてから5年が経とうとしている。その間の脳神経外科の進歩,ガイドラインの改訂,また脳神経外科を取り巻く環境の変化を踏まえて本書を改訂。また,「第I章 周術期における医療安全」では,「災害時の対策」の項を追加して,昨今頻発する災害に対して何をすべきかについて解説。
脳神経外科医をはじめ,周術期管理に携わるスタッフ必携の書籍である。
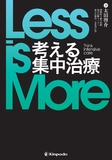
Less is More 考える集中治療
集中治療分野では「重症だから……」という理由だけで、詳細な病態や適応の評価もそこそこに、惰性的に、様々な薬剤投与、度重なる膨大な検査などが行われていることがあります。しかし、それは患者にとってデメリットでもあることを知っておきましょう。
ヨーロッパの集中治療医学会雑誌Intensive Care Medicineの「less is more」をもとに、日本の実情も踏まえながら、今後の医療の質を変えてみませんか?
――すべてのものは毒であり、毒でないものはない
パラケルスス(スイス人医師、1493~1541)
我々医療者の行為には、侵襲的なものや、効果効能が疑問視されているものも存在します。そして、それらはもれなくコストやマンパワーも必要とします。時にその有害性が命を脅かすことも稀ではありません。こと集中治療においては「重症だから」という理由だけで、詳細な病態や適応の評価もそこそこに、安易な薬剤投与や連日の検査などの医療的介入が行われることをよく目にします。しかし過度な医療行為は、パラケルススの言った通り「毒であり」、過ぎたるは及ばざるが如しであるということを肝に銘じなければなりません。すなわち、“less is more”な管理を行うことの価値を知る必要があります。そこで本書は、海外の集中治療系“Choosing Wisely”とヨーロッパの集中治療医学会雑誌『Intensive Care Medicine』の特集である“less is more”シリーズの内容を紹介しつつ、最近の知見を踏まえて、世界標準のシンプルかつスタンダードな管理を提唱することを目的として企画しました。
と、偉そうに書いていますが、正直に言うと、集中治療専門医として第一線で活躍されている先生方にはほぼ常識といえる内容です。ただ日本では集中治療専門医の数はまだまだ少なく、非専門医の先生が探り探りの集中治療を行っていることも多いと思います。研修医の先生においては、重症管理に精通して手取り足取り教えてくれる指導医がいないかもしれません。そんな先生方に向けて、本書から「ICUだからといって肩ひじ張らず、必要な介入をシンプルに行えばよい」というメッセージを感じてもらえればと思います。もちろん第一線の集中治療専門医の先生方にとっても、日頃のプラクティスを見直す機会となれば幸いです。また筆者自身もまだまだ勉強中の身でありますゆえ、本書を叩き台として忌憚なきご意見・ご指導をいただければと存じます。
“less is more”とは、シンプルなもののほうが、高度なものや複雑なものよりも優れている、という意味合いで使われる表現で、何かをやり過ぎてしまうことへの危惧がこの考え方の背景にあります。このフレーズは“God is in the details.”(神は細部に宿る)というモットーを掲げたことでも知られるドイツ人建築家のルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ(1886~1969)が遺した言葉とされています。多くのデザイナーがこの言葉にインスピレーションを受け、シンプルでありながら美しいものをデザインするという一つの表現が生まれたそうです。
医療においても同様で、余計なものが多すぎると本質的なものを見失ってしまう可能性があります。我々医療者も、洗練された患者プランを提案できるデザイナーとなり、真に重要なことに集中することが望まれます。
2021年8月
57年ぶりの東京オリンピックのかたわら、毎年変わらぬ蝉の声を聞きながら
静岡県立総合病院集中治療センター集中治療科/急変対応科
太田啓介

麻酔科レジデントマニュアル 第2版
麻酔科研修に行くならまずこの一冊! 麻酔の基本的な知識から臨床での心構え、実践で役立つテクニックまでを幅広くかつコンパクトにまとめたマニュアル、待望の全面改訂! 術中基本手技は豊富なイラストに加えて動画による解説も。麻酔科ローテートの中で経験する「集中治療」「ペインクリニック」「緩和ケア」についてもカバーしており、幅広い場面で役立つ内容となっている。
*「レジデントマニュアル」は株式会社医学書院の登録商標です。

救急医学2026年1月号
千の倉より母・子は宝
千の倉より母・子は宝 誰もが安全に安心して出産・子育てができる社会。そのためには、「宝」である母と子を救い守る医療体制が必要で、救急医療と周産期医療は、まさにその両輪だ。海外・国内の周産期救急・母体救命医療体制や各分野の事業・取り組みの実情を知り、視座を高めよう。

消化器外科2019年4月臨時増刊号
新 手術記録の書き方
新 手術記録の書き方 消化器外科64領域の最新術式の「手術記録」を掲載。
「手術記録」を正確かつ丁寧に記載することは、局所解剖や手術手順の理解にもつながります。
若気外科医から、ベテラン医師まで、手術手順確認の際に役立てていただきたい。
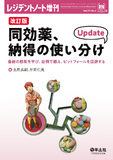
レジデントノート増刊 Vol.27 No.2
【特集】改訂版 同効薬、納得の使い分け Update
【特集】改訂版 同効薬、納得の使い分け Update
『なぜその処方を選ぶのか?』各分野のエキスパートが若手の視点に立って「同効薬の使い分けで研修医が知っておくべき基本や,1人で診療する際の処方の考え方」を概説!選択の根拠をしっかり学び,症例とピットフォールを通して上級医の思考プロセスを理解することで,現場での判断力を鍛えられる!薬剤情報を最新アップデート&新規項目の追加で,初版よりますます充実.どの診療科でも現場で即役立つ知識をこの一冊で!

≪Emer-Log 2021年春季増刊≫
救急の現場で役立つ検査値の知識を網羅!
救急の検査値これだけBOOK
【救急の現場で役立つ検査値の知識を網羅!】
救急医療・看護の実践に役立つ「検査」の知識が詰まった1冊!検査値の解釈に必要な基礎知識を全て押さえ、症例を通して、症状・所見から病態を推測し、検査の選択、検査結果の解釈までをまるごと理解!ウィズコロナ時代の救急外来の検査を解説するWeb動画付き!

小児消化管感染症診療ガイドライン2024
小児消化管感染症の治療法に関する9つのCQと,専門家による解説で構成.
CQはMinds 2020診療ガイドラインに準拠し,小児の感染性胃腸炎に対する非抗菌薬,抗菌薬の治療法について,特に抗菌薬では適正使用の観点も反映させ作成している.
解説では,疫学,診断,治療,予後,特殊な状況での感染症や予防,また臨床現場で役立つよう,小児用量についても可能な限り記載.小児の消化管感染症にかかわるすべての医師に必携の書.

この1冊で極める 不明熱の診断学
不明熱の不明率を下げるためのガイドブック
Commonな病態にもかかわらず,不明熱の診断は難しくそのストラテジーを詳しく記した書籍は少ない.本書は不明熱診療の基礎知識から,知っておくべきメジャー/マイナーな鑑別疾患,病歴からのアプローチ,身体所見のポイント,検査の組み立てと評価,症例検討と,あらゆる角度から診断に至る考え方を記した1冊.豊富な図表,臨床で役立つclinical pearlやエピソードを満載.不明熱で生じる皮疹写真集,不明熱の鑑別診断リスト等付録も充実.

内分泌代謝・糖尿病専門医のセルフスタディ230
内分泌代謝・糖尿病疾患に特化した230問題を収録.前版となる「内分泌代謝専門医のセルフスタディ230」発行から10年が経過し,主な診断基準・診断ガイドラインに対応し大幅に刷新.内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医にも対応.8つの分野ごとに問題と解説をまとめて掲載.各問題には3段階の難易度を示し,通常の索引の他に出題テーマから各問題にたどりつける問題索引を設けた.内分泌にかかわる臨床医必携のセルフスタディツールとなる1冊.

食道・胃・十二指腸ESDの基本とコツ
部位別・シチュエーション別の治療手技・戦略を伝授
上部消化管ESDの最強攻略本!必須知識やITナイフを中心とした基本手技,若手内視鏡医から集めた「現場での疑問」をエキスパートが解説.近年内視鏡治療が増えてきた十二指腸病変の治療戦略・考え方もカバー.

術式・手技とカテ前~中~後を見わたす
カテ室の見取図
看護をシンプルに“見える化”した「見取図シリーズ」第3弾!
全領域を網羅した血管系(6領域)+非血管系の59項目
カテーテル検査・治療の全体を見わたせる
医師、看護師、診療放射線技師、臨床工学技士でつくったメディカルスタッフのためのカテ事典です。
専門性の高い血管系・非血管系計59項目のカテーテル検査・治療について、「どのような検査・治療を行うのか」「検査・治療時における各メディカルスタッフの役割、注意点は何か」を簡潔に解説しています。
また、本書の冒頭ではカテ業務で使用するデバイスや薬剤、医療体制など、基礎知識をまとめています。
カテ室に配属されたばかりの新人の方、カテを学びなおしたいベテランの方、ケアのためにカテを知りたい病棟看護師など、カテにかかわるすべての方におすすめです。
