
小児内科52巻1号
【特集】母子感染症の必修知識―エキスパートに学び予防につなげる
【特集】母子感染症の必修知識―エキスパートに学び予防につなげる

小児外科52巻1号
【特集】小児外科領域における感染症―基礎編
【特集】小児外科領域における感染症―基礎編

周産期医学50巻1号
【特集】知っておきたい周産期にかかわる法律・制度
【特集】知っておきたい周産期にかかわる法律・制度

実験医学 Vol.38 No.13
2020年8月号
【特集】RAN翻訳と相分離で紐解く リピート病
【特集】RAN翻訳と相分離で紐解く リピート病 くり返し配列の異常伸長がなぜ神経・筋疾患につながるのか.「RAN翻訳」や「相分離」のキーワードで紐解かれる疾患共通のメカニズムに迫ります.他,マウス以外の疾患モデル生物の最新トレンドも紹介しています.

脳血流量は語る ―かくれた謎をひも解く―
脳の疾患や健康状態を表す脳血流量は,脳機能を支えるインフラである.それゆえ脳疾患の診断ツールにはなりえても,マイナーな存在であった.しかしイメージング技術の発展と共に,脳血流量には「揺らぎ」があることが判明.この揺らぎが,脳の神経細胞の活動領域に対応していることが分かってきた.寡黙と思われていた脳血流量が,実は脳の活動を雄弁に語っていた代弁者であった.本書はその語りから,脳の秘密をひも解いていく.

子どものあざ どう診て・どう治療するか
一昔前は「治療法がない」と言われていたあざも,今は治療可能なものもある.逆に「何もしない方がよい」とされていたものが,今では積極的に治療した方がよいというものもある.子どものあざ治療をライフワークにしている著者が,あざを色別にまとめ,予測される自然経過や合併症の有無,治療方法や治療時期を多くの写真と共にまとめた一冊.

≪Crosslink 理学療法学テキスト≫
日常生活活動学
理学療法学専門科目に対応したテキストシリーズ。
第1章では日常生活活動の概念や評価についての基礎知識を解説,第2〜6章では基本動作とヘルスケア,生活環境整備,身体活動量,代表的な疾患・障害における日常生活活動について解説し,基本的な内容から実践的な内容まで,1冊で学べる構成となっている。

プライマリケアにおける 喘息と合併症の管理
喘息を多様性疾患として捉え、合併症に配慮した診療の実際を解説!
◆吸入薬での薬物療法が奏功しない喘息において、治療成功のカギは合併症の管理にあります。
◆喘息を多様性疾患と捉え、合併症に配慮した薬の使い分け、指導管理など治療アプローチの実際を解説。
◆喘息患者を受け持つプライマリケア医・一般内科医必携の一冊。

非麻酔科医のための鎮静医療安全
医学シミュレーション学会鎮静委員会によるセミナー「院内多職種連携を基盤とした鎮静トレーニング」のエッセンスを凝縮!
◆最新の鎮静医療安全の世界基準(ASA-SED2018)に準拠し、診療科別の鎮静管理の実際も記載しました。
◆善意の医療行為としての「鎮静」を、医療事故につなげないために。
◆すべての職種・診療科に対する鎮静の基本を示した一冊。

日本内視鏡外科学会雑誌 Vol.25 No.4
2020年07月発行
-

LiSA Vol.27 No.7 2020
2020年7月号
徹底分析シリーズ:もう一度始めるTIVA/症例カンファレンス:睡眠薬依存症患者の婦人科手術/快人快説:最先端の研究テクノロジー紹介(9)疾患メタボロミクス
徹底分析シリーズ:もう一度始めるTIVA/症例カンファレンス:睡眠薬依存症患者の婦人科手術/快人快説:最先端の研究テクノロジー紹介(9)疾患メタボロミクス 徹底分析シリーズ:もう一度始めるTIVA
症例カンファレンス:睡眠薬依存症患者の婦人科手術
快人快説:最先端の研究テクノロジー紹介(9)疾患メタボロミクス

検査と技術 Vol.48 No.8
2020年08月発行
-

臨床整形外科 Vol.55 No.7
2020年07月発行
特集 脊椎手術-前方か後方か?
特集 脊椎手術-前方か後方か? -

胃と腸 Vol.55 No.8
2020年07月発行
主題 H. pylori未感染胃の上皮性腫瘍
主題 H. pylori未感染胃の上皮性腫瘍 -

レジデントノート Vol.22 No.7
医学情報を獲りに行け!
医学情報を獲りに行け! 医学情報は自ら考え取捨選択してこそ真の学びにつながる――臨床的疑問解決の考え方と,情報検索・整理ツールを使いこなすために知っておきたいそれぞれのメリット・デメリットや実践的な使い方,Tipsを紹介!

臨牀透析 Vol.36 No.7
2020年7月号
透析患者PAD の最前線
透析患者PAD の最前線
糖尿病の有無にかかわらず,慢性腎臓病は下肢末梢動脈疾患(PAD)の独立した危険因子である.透析患者は約33 万人いるが,そのうち約4 %が下肢切断を受けている.ひとたび大切断に至ると,その後1 年で約半数の患者が亡くなるという厳しい現実がある.(小林論文要旨より抜粋)

J-IDEO (ジェイ・イデオ) Vol.4 No.4
2020年7月号
【Special Topic】ASTの市中病院での進め方
【Special Topic】ASTの市中病院での進め方
今号のSpecial Topicは『ASTの市中病院での進め方』
AST(antimicrobial stewardship team,抗菌薬適正使用支援チーム)は,治療効果の向上,耐性菌出現の抑制,副作用の防止などを目指し抗菌薬適正使用を支援する,医師・薬剤師・看護師・臨床検査技師ら多職種からなるチームです.
市中病院でASTが活動するにあたり,理想と乖離したさまざまな制約や限界があるのが現実です.今号ではそのような理想と現実の間で折り合いをつけながらASTを成功・定着させる方法やコツをQ&A形式で解説します.

消化器外科2020年7月号
T4b大腸癌に対する腹腔鏡下手術;安全・確実に病変を取り除くために!
T4b大腸癌に対する腹腔鏡下手術;安全・確実に病変を取り除くために! T4b大腸癌に対する腹腔鏡下手術の際、剝離断端陽性となってしまったり、不要な臓器損傷を起こすことのない、他臓器浸潤の画像診断、腹腔鏡下手術の適応、術中のラインのとり方などについて、腹腔鏡下大腸手術のエキスパートがわかりやすく解説。

救急医学2020年7月号
ライフラインパニック!!;想定外に対応できるか!?
ライフラインパニック!!;想定外に対応できるか!? 停電、断水、ガス停止、システム障害、そして病院避難。あなたの施設では、その備えができていますか? 災害による想定外の“ライフラインパニック”を想定内にするために、過去の実体験からその対応ノウハウを学ぼう!
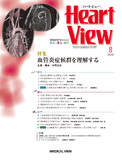
Heart View Vol.24 No.8
2020年8月号
【特集】血管炎症候群を理解する
【特集】血管炎症候群を理解する
