
職場不適応のサイン
ベテラン産業医が教える気づきと対応のコツ
「職場不適応」は社会問題化しており,多くの職場関係者や家族らが悩みうるテーマである.問題が起こる前に予防する,あるいは問題を早期に発見して対処することが望まれるが,その方法は手探りで行われているのが実情である.本書は40年以上,多くの相談を受けてきたベテラン産業医が,豊富な事例を交えて対応のコツをまとめた.

団塊世代“大死亡時代”の航海図 2040年―医療&介護のデッドライン
〔本書より〕「団塊の世代の大死亡時代が刻々と迫っている。筆者もその一員である団塊世代700万人が大量死亡するピークの2040年まであと20年」
「団塊世代の40万人が,2030~40年にかけて,死に場所難民になる可能性がでてきた。そもそも団塊の世代は,学生時代は管理社会に反抗してゲバ棒をもって暴れた世代だ。病室で点滴と鼻からチューブを入れられて,心電図の音を聞きながら死ぬのは真っ平ごめんだと考えている世代だ」
「団塊世代の在宅看取りの場を整えることは,実はその後の世代,特に団塊ジュニアが高齢者になったときの在宅ケアに大いに役立つ。そして同時に,これから始まるアジアの高齢化の先進モデルにもなるだろう」
★「2040年問題」──人口が減少する一方で団塊世代が平均寿命ラインを越え,現役1.5人が高齢者1人を支える超高齢化社会を迎えます。
★本書では,そんな時代の医療と介護はどうなるか,地域・医療機関・介護施設の役割はどう変化するのか,団塊世代の死に場所はどこになるか──を医療と介護のリアルな現場や海外の様々な取組みなどから,多角的に考察しています。
★2040年に向かう“潮流”に沿って,今後どのような地域・医療・介護の体制が構築されていくか,医療機関と介護施設は今後どの方向に舵を切るべきか──団塊世代“大死亡時代”の航海図を読み解くヒントがここにあります。

“リアル”なクリニック経営―300の鉄則
開業,財務管理,集患,採用,人事労務,職場活力,承継まで
★クリニック経営は,机上のプラン通りにいかないのが当たり前の世界です。開業時の事業計画の甘さ,想定患者数と現実の乖離,診療報酬の変化,地域の疾病構造の変化,競合クリニックの開設,スタッフの雇用問題,想定外の出費,資金繰りの悪化──等々,様々なギャップやアクシデントが生じます。
★プランを狂わせる“落とし穴”は,開業支援業者に勧められるままの事業計画,銀行からの過重融資,合い見積もりを取らない契約,納税や必要経費を考慮しない投資,費用対効果マイナスの広告,削ってはいけない人材コストの削減,スタッフの採用・教育の失敗──等々,無数に存在します。
★これが,経営入門書や経営セミナーでは見えてこないクリニック経営の“現実”です。本書では,これまで30年間で200以上のクリニックを経営改善に導いてきたプロフェッショナルの“リアルな経験知”を総まとめしています。
★その現実に基づく,失敗しない計画,騙されない契約,実効性ある業務改善,活力ある職場,優秀な人材育成──を実現する実践的な“クリニック経営の300の鉄則”。プランと現実との乖離が見えてきたら,ぜひ本書で手当てを。
300の鉄則(例)
■マニュアルどおりの開業では成功しなくなった。医療を取り巻く環境は変わった
■開業コンサルティングが無料であれば,その費用はどこか別のところにプラスされている
■「こんなことが起こるのか?」──成功への道は誰もが通る予想外の道?
■建築内装被や機械納入価格は業者や担当者によって異なる。適正価格を確かめる必要がある
■1日当たりの患者数と診療単価,診療限界患者数が事業計画の鍵となる
■後から払う税金,先に払う税金がある。自由に使える資金は意外と少ない
■金融投資より事業にプラスになる前向きな投資を。スタッフへの投資は最優先課題となる
■意見の押し付けでは退職者が増える。意欲をもたせることができれば予想以上に成長する
■病院とクリニックの受診目的の違いを知る。どの患者も自分にとってのオンリーワンを求めている
■広告やホームページに頼らなくても流行っているクリニックはいくらでもある
■患者から総合的に支持されなければ絶対に成功しない。何でもないと思うことが一番評判を落とす
■顧客管理で地域や患者ニーズに応えて診療を変化させることが増患・増収につながる

≪職場の難問Q&A≫
“働き方改革”の実践応用編 医療&介護の職場トラブルQ&A
労働環境・ハラスメント・給与・残業・メンタルヘルス──全120QA
★働き方改革関連法が2019年4月から順次施行され,5月にはパワハラ防止法が成立しました。医療機関や介護施設でも,労働環境や処遇の改善,ハラスメントの問題は重要課題としてクロードアップされています。
★本書は,医療機関と介護施設における,労働条件・残業・勤務評定・給与・休暇・退職・ハラスメント・職権の範囲・モラル・職場の活力・コミュニケーション・労災・メンタルヘルス・個人情報――など,スタッフ・職員が日頃疑問や不満に思っている120の諸問題をQ&Aでズバリ解決しています。
★本書は,最新の法制度に準拠したうえで『職場の難問Q&A』(旧書名)を大幅に見直し,新しいQ&Aも多数加えてリニューアルしたものです。
★「LCG医業福祉部会」は医療機関や介護施設を専門とした人事労務コンサルタントの全国組織。様々なトラブルを解決してきた経験豊富なプロフェッショナルが,最新の法律解釈と実践的な解決法をあまさず伝授します?
Q&A例
Q 残業が月60時間超で夜勤も10日以上。こうした長時間労働は法的に問題ないか?
Q 夜勤業務中の仮眠や申し送りの時間について賃金が払われていない。問題ないか?
Q 業績悪化を理由に一方的に給与が減額。事前説明のない減額は問題ないか?
Q パワハラと訴えられることが心配で注意や指導ができない。パワハラの判断基準は?
Q 上司の暴言などで,うつ病に罹患。パワハラによる労災として認められるか?
Q 職員が癌に罹患。就労継続のためには,どのような支援や配慮が必要か?
Q 未払い残業を労働基準監督署に申告したら守秘義務違反で解雇。許されるのか?
Q 職員に積極性ややる気が感じられない。職場風土を改善する良い方法はないか?
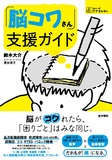
≪シリーズ ケアをひらく≫
「脳コワさん」支援ガイド
会話がうまくできない、雑踏が歩けない、突然キレる、すぐに疲れる……。病名や受傷経緯は違っていても、結局みんな「脳の情報処理」で苦しんでいる。高次脳機能障害の人も、発達障害の人も、認知症の人も、うつの人も、脳が「楽」になれば見えている世界が変わる。それが最高の治療であり、ケアであり、リハビリだ。疾患ごとの〈違い〉に着目する医学+〈同じ〉困りごとに着目する当事者学=「楽になる」を支える超実践的ガイド!
*「ケアをひらく」は株式会社医学書院の登録商標です。

はじめての基礎化学実験
大学の基礎化学実験で理解不足の知識を補える分かりやすい実験書!
本書は、大学教養および専門学校などで行われている基礎化学実験をイラストなどで視覚的に分かりやすく丁寧にまとめた実験書です。大学や専門学校では、高校までの実験器具よりもさらに多くの器具を扱うことになるため、安全に楽しく実験が行えるように配慮した内容としています。また、「この実験の目的は何か」を明確に示し、ただ実験をするだけではなく、その結果からどのような考察ができるのかを解説してありますので、大学初学年向けの教科書や参考書として活用できます。
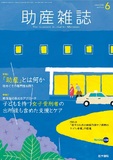
助産雑誌 Vol.74 No.6
2020年06月発行
特集1 「助産」とは何か 改めてその専門性を問う/特集2 助産師の新たなアプローチ 子どもを持つ女子受刑者の出所後も含めた支援とケア
特集1 「助産」とは何か 改めてその専門性を問う/特集2 助産師の新たなアプローチ 子どもを持つ女子受刑者の出所後も含めた支援とケア 医療現場では専門分野が細分化され,医療技術もめまぐるしく進歩しています。少子化,ハイリスク分娩の増加など,助産師を取り巻く状況も変化しています。また,多様な生き方や考え方が尊重される時代にあって,分娩や育児に対する女性の考え方はもちろん,支援の求め先も多様化しているでしょう。助産師は今,岐路に立っているとも言えます。その流れの中で,助産師のみに許された「助産」という専門性は,どのように発揮されているのでしょうか。そもそも助産の専門性とは,いったいどのようなものを言うのでしょうか。本特集では二つのテーマ「無痛分娩」と「産後ケア」を選び,対談を通して,答えを見つけるヒントを探していきたいと思います。

訪問看護と介護 Vol.25 No.6
2020年06月発行
特集 心不全在宅管理 ケアと治療をつなげる「翻訳」スキル
特集 心不全在宅管理 ケアと治療をつなげる「翻訳」スキル 心不全を抱えた療養者さんが、増えています。そして今後、ますます増えることが予測されています。個別性の高い「心不全」の治療とケア。それを的確に引き継ぎ、その人ならではの療養生活に落とし込んでいくには、本人を中心とした多職種チームによる有機的で細やかな動きと伝え合う力、つまり「翻訳する力」が求められます。 本特集では、在宅の現場における多職種チームを〝地域ハートチーム〟として捉え、訪問看護師が押さえておきたいケアと治療をつなげる「翻訳」のための知識・スキルをまとめます。

保健師ジャーナル Vol.76 No.6
2020年06月発行
特集 進むデータの利活用 現場の保健師の役割と機能を知る
特集 進むデータの利活用 現場の保健師の役割と機能を知る 情報通信技術(ICT)の発達により,保健現場には一層のデータの利活用が求められている。本特集では,保健師が利用可能なデータや,その活用の方法,質的データを含めた検討の重要性など,利活用の上での心構えについて,地域での取り組みとともに紹介する。
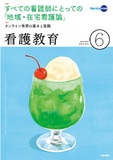
看護教育 Vol.61 No.6
2020年06月発行
特集 すべての看護師にとっての「地域・在宅看護論」
特集 すべての看護師にとっての「地域・在宅看護論」 今回の指定規則改正にて、統合分野「在宅看護論」から、基礎看護学に続く「地域・在宅看護論」へと変更されます。この変更は、単なる教育・科目内容の移動にとどまらず、「療養する人々」から「生活する人々」へと看護の対象そのもののとらえ方を転換した、看護基礎教育の大きな改革といえるでしょう。従来、「在宅看護論」は応用的な位置づけで、「専門」の教員が担当している教育機関が多かったと思います。しかし、今回の変更を受け、領域を問わずすべての教員が、在宅および地域を意識した教育に取り組むことが求められていると考えられます。本誌では2号にわたって特集を組み、この「地域・在宅看護論」の新たな枠組みを解説します。前編となる本号では、すべての看護師にとって「地域・在宅看護」の視点が求められる時代背景をあらためて考え直すとともに、より学年の早い段階から「地域・在宅看護論」を学ぶ授業内容を考えます。

病院 Vol.79 No.6
2020年06月発行
特集 できる事務長の育て方
特集 できる事務長の育て方 地域医療構想や働き方改革、直近では新型コロナウイルス感染症と、病院を巡る環境は激変している。こうした環境下でも伸びる病院には特長がある。経営状況を客観的に判断し、経営者と危機感を共有する「できる事務長」の存在である。事務長は、ヒト・モノ・カネ・情報を最大限に活用し、経営の根幹から細部に至るまで多岐にわたる課題に対処する、病院のキーパーソンである。本特集では、事務長の役割と求められるスキルを探り、その育成のあり方を追求したい。

臨床泌尿器科 Vol.74 No.6
2020年05月発行
特集 高齢患者の泌尿器疾患を診る 転ばぬ先の薬と手術
特集 高齢患者の泌尿器疾患を診る 転ばぬ先の薬と手術 -

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.92 No.7
2020年06月発行
特集 耳鼻咽喉科領域の外傷を診る! 初期対応から根治療法まで
特集 耳鼻咽喉科領域の外傷を診る! 初期対応から根治療法まで -

臨床婦人科産科 Vol.74 No.4
2020年05月発行(増刊号)
特集 産婦人科処方のすべて2020 症例に応じた実践マニュアル
特集 産婦人科処方のすべて2020 症例に応じた実践マニュアル -

胃と腸 Vol.55 No.6
2020年06月発行
主題 スキルス胃癌 病態と診断・治療の最前線
主題 スキルス胃癌 病態と診断・治療の最前線 -

公衆衛生 Vol.84 No.6
2020年06月発行
特集 次代の公衆衛生を展望する
特集 次代の公衆衛生を展望する -
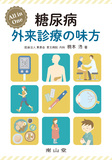
All in One 糖尿病 外来診療の味方
プライマリ・ケアの現場において,様々な疾患・患者に対応しなくてはならない医師に実用的な情報を提供すべく,糖尿病の基本や合併症から妊娠糖尿病や二次性糖尿病まで幅広くまとめた必携の一冊.著者の経験をもとにしたコラムも収載されており,糖尿病診療についてさらに知識を深められるものになっている.

臨床皮膚科 Vol.74 No.6
2020年05月発行
-

Gノート Vol.7 No.4
2020年6月号
【特集】現場で知っトク!歯と口腔の基礎知識
【特集】現場で知っトク!歯と口腔の基礎知識
う蝕・歯周病の機序は?義歯をしている患者の診療の注意点は?小児の歯の発達・おしゃぶりの是非は?歯科紹介のポイントは?口腔の解剖…など,医師に知っておいてほしい歯科・口腔外科領域の知識を簡単に解説!

臨牀消化器内科 Vol.35 No.6
2020年6月号
消化管疾患のER-診断と治療のポイント
消化管疾患のER-診断と治療のポイント
本特集は明日遭遇するかもしれない対応困難な症例を意識した内容になっています.出血点の同定が困難な下部消化管出血より、多くの治療法が開発された上部消化管出血の死亡率が高いことは、改めて消化管出血治療の難しさが伺えます.心窩部痛症例の造影CTで描出される心筋梗塞には度胆を抜かれます.
