
Journal of Internet of Medical Things Vol.2 No.1
2019年7月号
特集 IoMTのUP-TO-DATE
特集 IoMTのUP-TO-DATE
本誌『Journal of IoMT』は医療におけるIoT(IoMT)、AI、ロボティクスやそこから収集されるビッグデータならびに新しいテクノロジーへの挑戦をキーワードとして新しい情報発信を行います。

Journal of Internet of Medical Things Vol.1 No.1
2018年5月号
特集 IoMTの可能性と未来
特集 IoMTの可能性と未来
本誌『Journal of IoMT』は医療におけるIoT(IoMT)、AI、ロボティクスやそこから収集されるビッグデータならびに新しいテクノロジーへの挑戦をキーワードとして新しい情報発信を行います。

関節外科 基礎と臨床 Vol.39 No.6
2020年6月号
【特集】股関節領域の術前・術中支援技術 Up to date
【特集】股関節領域の術前・術中支援技術 Up to date

検査と技術 Vol.48 No.6
2020年06月発行
-

総合リハビリテーション Vol.48 No.5
2020年05月発行
特集 周術期のリハビリテーション診療 何を考え何を診て何をするのか
特集 周術期のリハビリテーション診療 何を考え何を診て何をするのか 手術治療では患者に大きな侵襲が加わるため,一定期間の安静・不動を強いることになり,これが合 併症につながる可能性があります.また,手術によっては安静・不動と無関係な合併症を生じることも あります.リハビリテーション診療はこれらの合併症の予防や治療だけでなく,患者の機能向上にも役 立ちます.そして周術期リハビリテーションは手術の対象となる疾患,手術内容を十分に理解してこそ 力を発揮すると考えられます.そこで,本特集では,周術期リハビリテーションを行うにあたり,何を 考えて何を診て何をするのかを解説していただきました.

臨床泌尿器科 Vol.74 No.5
2020年05月発行
特集 ここが変わった! 膀胱癌診療 新ガイドラインを読み解く
特集 ここが変わった! 膀胱癌診療 新ガイドラインを読み解く -

臨床皮膚科 Vol.74 No.5
2020年05月発行(増刊号)
特集 最近のトピックス2020
特集 最近のトピックス2020 -
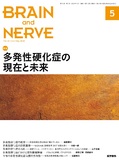
BRAIN and NERVE Vol.72 No.5
2020年05月発行
特集 多発性硬化症の現在と未来
特集 多発性硬化症の現在と未来 多発性硬化症(MS)は日本でも患者数が着実に増えており,疾患修飾薬として既に6剤 が使用可能となっている。しかし,欧米で使用可能となっている薬剤がすべて日本に上 陸している状況にはなく,診断・治療においてはいまだ大きな問題を抱えたままである。本特集では疫学,診断基準,画像,認知機能障害,治療という多角的な視点から,現時 点の最新知見をエキスパートに解説していただく。

ゆっくり発達している子どもが輝く遊びの処方箋
子どもの発達段階に応じた「遊び」で、子どもの心と身体がグンと伸びる!
「子どもの心と身体を発達させる遊び」を発達障害治療の専門家(作業療法士)が豊富なイラストでわかりやすく紹介。
お家で、療育現場で、教育現場で、明日から簡単にできる『遊びの処方箋』です。
こんな悩みにおススメ!
●集団行動が苦手な子ども(発達障害)が、友達と上手く遊べるようになるには?
●1人で行動することが苦手で不安な子ども(肢体不自由・精神運動発達遅滞)が、1人でできることを増やすには?
●ちょっと臆病で人見知りな子ども(精神運動発達遅滞)が、きちんとお話できるようになるには?
●じっとするのが苦手な子ども(発達障害)が、落ち着いて授業を受けられるようになるには?

作業療法が生きる地域リハビリテーションのすすめ
いのち輝く生活の支援を目指して
目次や推薦の辞にあるごとく、作業療法士ならではのリハサービスのメニューやコツが、実践をとおして示めされている。作業療法士であれば誰でもがこれだけのサービスを十分に提供できるものではないが、作業療法型の地域リハのモデルとして、とりわけ小規模型のモデルとして、経験をつめば、観察眼を澄ませば、地域や家族を理解すれば、地域に関わる資格のある作業療法士に対してのみでなく、スタッフのかたがた、ボランティア、行政のかたがたにも目標とすべきものが示されている。ここでは本書の出版に著者とともに尽力された鎌倉矩子氏の推薦の辞を引用して、紹介に変えたい。
「本書には訪問リハやデイサービスなど地域で作業療法を実践するためのノウハウが惜しげもなく述べられている。誰もが普通の生活の中で行う作業こそが、ひとの心と体をととのえ、鍛え、よろこばせるのだという認識。これこそが作業療法の源流の基盤であったことをあらためて思った。 ー推薦の辞(鎌倉矩子)より

リハビリテーション的障害論
そもそも障害ってなんだ
「障害」をいわゆるただのインペアメントと捉える専門職はもはやいないであろう。しかし、ともすれば機械的に関連づけて、その軽減のための技術の修練に専心する真面目なセラピストも少なくない。本書は「障害」がそのような物理的法則に規定されるものでなく、意思と感情と知性をもった人間特有のものであり、この問題に取り組むことは人間存在そのものの本質的考察と決して切り離すことができないものだとして、その本質的側面について考察する。例えば「障害」をつくっているのは、社会であり、環境であり、技術であると。その他、比較の対象とされること、あるいは告げるものとしての他者の存在、さらには「障害」の構造と関連づけて「障害」の外在性、内在性、全体性という面にも言及している。
セラピストとしての豊富な実践経験と当事者の方の実例や書物を例に挙げ、リハビリテーションとは何か、そもそも専門職はどうかかわるべきかについて提言する。

障害受容からの自由
あなたのあるがままに
行間から命懸けで生きている「当事者」たちの生身の声や共感が聞こえてくるような本です。
「障害受容」というテーマは従来リハビリテーションの研究者、医師、セラピスト、看護職、その他医療専門家の間で、リハビリテーションにおける究極の過程であり、「受容することで」当事者に価値の転換を促し、積極的にリハ訓練に取り組む契機となる、リハにおけるいわば目標として位置付けられてきました。しかし「障害」はひとり当事者のみの問題ではなく、家族、支援者(治療者を含む)さらには文化や宗教にも関わる多元的な問題であり、「受容」という課題は、それぞれの立場により大きく異なる複雑で輻輳的なものです。また専門家の用いる「障害受容」については当事者への「受容」の押し付け、圧力にもなりかねないことから、近年、特に専門家の用いる「障害受容」の言葉の使用法に対しての批判も少なからず提起されるようになってきています。
このような状況のなかで、「障害受容について/から考える研究会」を立ちあげ、本テーマにつき3年間、14回にわたって議論を重ねてきた、主としてリハ専門職の人たちが、当事者、家族、支援者の参加を得て、ともに生身で語りあった記録をもとに書籍化したものです。
「障害受容」の意味を考える中で「障害を生きること」の肯定こそが重要ではないかという結語に至った人たちによって編まれています。
どれもこれも深い内省に富んだ文章がならんでいますが、とりわけ感動するのは当事者や家族の方たちの命懸けで生きている、声や支援者の共感の声が聞こえてくるような文章が随所に散りばめられていることです。

作業療法はおもしろい
あるパイオニアOTのオリジナルな半生
鎌倉矩子さんという日本の作業療法の「今」になくてはならない貢献をした,パイオニアOTの半生をたどる評伝である.揺籃期にOTを志したものの,一時はそのことを後悔しながらもやがてその可能性に目覚めると,作業療法の実践に留まることなく,研究面でも,教育面でも,さらには倫理面でも先頭にたち,今日のプロフェッションとしての水準にまで到達するにいたった歩みを追っている.
元「クロワッサン」編集長である著者が徹底的に本人と,共に歩んだ人たちへのインタビューを行い,人びとの回想や証言の中から作業療法とは何か,作業療法のやりがいと面白さ,よい作業療法士になるために必要な態度など,珠玉の後輩へのメッセージを伝えている.

臨床雑誌外科 Vol.82 No.6
2020年5月号
消化器悪性腫瘍診療におけるガイドラインの功罪
消化器悪性腫瘍診療におけるガイドラインの功罪 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

各科スペシャリストが伝授 内科医が知っておくべき疾患102
一般内科医(ジェネラリスト)が遭遇し,診断または初期治療をする可能性のある境界領域の疾患について,各科のスペシャリストが実践的な診断方法・治療のコツなどを解説します。
掲載疾患数は,厳選した11診療科/102疾患。すべて見開き2ページで完結しています。

NEW 精神科研修ハンドブック
奈良県立医科大学の精神科チームが15年かけてつくりあげた渾身のマニュアル。修正に修正を重ね、2020年スタートの精神科臨床研修にふさわしいベストオブベスト! 白衣におさまるコンパクト版。効率的に最新情報をアップデートしたい先生方にもお勧めします。

画像診断 Vol.40 No.5(2020年4月号)
【特集】基礎から学ぶ肺癌の画像診断
【特集】基礎から学ぶ肺癌の画像診断 本特集では,日々進化していく肺癌診療について,日頃から少し気になっている所見や,いつもの画像診断に少し追記して解説を加えたい所見など,肺癌診療の基礎となる所見を中心にわかりやすく解説.

もう困らない 外来・病棟での腎臓のみかた
腎臓専門医であり総合内科医としての経験も豊富な著者が,一問一答形式で腎臓の臨床的な問題点を明確に示し,平易かつ丁寧に解説.非専門医が外来・病棟の現場で,「腎臓に何が起こっているのか.どう対応すればいいのか」を適切に判断できるようになることを目指した.簡潔ながらも,腎臓の知識の根幹である腎生理学的視点から説かれた本書は,実践的に使える深い知識を身にけることができる.明日からの診療に自信が付く1冊だ.

医療AIとディープラーニングシリーズ Pythonによる医用画像処理入門
医用画像処理・解析のためのPython入門 決定版!
医用画像の分野では画像診断支援の分野で大きな期待が寄せられ、今後人工知能が組み込まれたAI-PACS(画像保管管理システム)の普及が予想されています。こうした状況の中で最近注目されているプログラム言語であるPythonは初学者にも学びやすく、また画像処理や人工知能のためのパッケージが多く提供されています。これらを上手く使うことで様々なソフトウェア作成することができ、簡単な実験から臨床研究などへ幅広くPythonは適しています。
本書ではこれからPythonを学ぼうとする初学者からPythonを使いこなして画像処理から人工知能研究、さらにアプリケーション開発者まで、幅広く対応できる内容をまとめています。

臨牀透析 Vol.36 No.5
2020年5月号
近未来の透析医療
近未来の透析医療
近年は、AI技術が進歩し、血液浄化療法の管理にも取り入れられつつある。透析関連機器の進歩は目覚ましく、効率や安全性向上、小型化や操作簡便化などが図られている。どのような透析医療の未来が開けるのか、その展望をこの特集号でまとめた。
