
新型インフルエンザパンデミックに日本はいかに立ち向かってきたか
1918スペインインフルエンザから現在までの歩み
パンデミックが生じたその時,医療者は,行政は,社会は,それぞれどのような行動をとったのか.本書では,過去100年に生じた新型インフルエンザパンデミックをレビューした.さらに,現在も監視が続く鳥インフルエンザの状況や2009年以降の政策についても,最新事情が専門家により解説されている.パンデミックに備える上で必須の一冊.

医師・医学生のための人工知能入門
現状のAIは,囲碁の世界王者に勝てるのに東大には合格できない.それはなぜか.1980年代のニューロブームを体験した脳生理学者である著者が,脳と比較しながらAIの基礎・歴史から応用や展望まで解説.平易な語り口をたどるうち,AIと脳研究の新たなクロスオーバーが見えてくるはずだ.
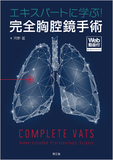
エキスパートに学ぶ!完全胸腔鏡手術[Web動画付]
患者に負担が少なく低侵襲の手術である完全胸腔鏡手術を25年以上にわたり一貫して行い、7,000例以上の豊富な手術件数を有する著者の渾身の一冊。手技の工夫やトラブルシューティングなどもふんだんに収載し、同手技を余すところなく披露。豊富な写真とWeb上で閲覧できる200分を超える動画で同手技をていねいに解説した。
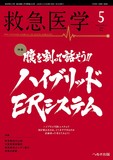
救急医学2020年5月号
腹を割って話そう!! ハイブリッドERシステム
腹を割って話そう!! ハイブリッドERシステム ハイブリッドERってそもそも何!? 経費は!? 外傷診療はどう変わる!? 外傷以外の活用は!? 教育はどうする!? ていうかホントに効果あるの!? ハイブリッドERの“光”も“闇”も、腹を割って話そう!!

別冊整形外科 No.77 鏡視下手術の進歩─小関節から脊椎まで
関節鏡視下手術における適応疾患の増加や手術手技の進歩は著しく、四肢の関節のみならず脊椎疾患の診断と治療にまで適応が広がっており、手術侵襲の少なさから整形外科においては治療の主流を占めるようになってきた。本特集号では手指の小関節から脊椎までさまざまな鏡視下手術の手術手技や術後成績、コツやピットフォールなどの最新情報を掲載した。

INTENSIVIST Vol.12 No.2 2020
2020年2号
特集:災害とICU
特集:災害とICU 特集:災害とICU

精神看護 Vol.23 No.3
2020年05月発行
特集 教えて先輩! 看護って何? 現場のどうしよう、困ったを解消する看護理論【退院に至る道】編
特集 教えて先輩! 看護って何? 現場のどうしよう、困ったを解消する看護理論【退院に至る道】編 この特集は、2019年3月号で掲載した漫画特集「教えて先輩! 看護って何? 現場のどうしよう、困ったを解消する看護理論」の続きの物語です。
[これまでの話]
40年近く長期入院中の若寺さん。担当になった私(新人看護師の鮎川桜子)は、生活がほとんど自立している若寺さんとどうかかわっていいのかわからず、とまどっていました。先輩の助言を受けながら少しずつ話ができるようになってきた私でしたが、ある時若寺さんから入院に至る経緯を聞いてその内容に圧倒されてしまい、「自分みたいな新人が何かをしてあげることなんてできない。つらいだけの退院に意味はない。若寺さんはこのまま入院していたほうが幸せなのでは?」と先輩看護師(高樹玲奈)に泣きながら相談しました。それを聞いた先輩は、私の涙に理解を示しつつも、“意味がある・意味がない”“幸せ・不幸せ”を他人が決めてはいけない、と諭してくれたのでした。
自分の観点に決めつけがあったことに気づいた私は、方法はまだわからないけれど、これからも若寺さんとかかわっていこうと思ったのでした。

嚥下医学 Vol.9 No.1
2020年1号
特集:サルコペニア・フレイルと嚥下障害
特集:サルコペニア・フレイルと嚥下障害 嚥下医療に携わるすべての専門職のための新雑誌。超高齢社会に入ったわが国においてますます重視される嚥下の問題に焦点を当て、動画配信サイトとの連携も図りながら、現場で役立つ有用な情報をわかりやすく提示・解説する。嚥下機能評価、嚥下障害の治療・ケア・リハビリテーションに関する原著論文や解説を多数提供。メディカルスタッフに親しみやすい連載も充実。本号は特集号として「サルコペニア・フレイルと嚥下障害」を企画。超高齢社会を迎え、サルコペニア・フレイルが話題となる一方で、高齢者の死因において誤嚥性肺炎の比率が高く、そのベースには嚥下障害が潜んでいる。ここではサルコペニア・フレイルと嚥下障害の密接な関係に焦点をあてて解説していく。

嚥下医学 Vol.8 No.2
2019年2号
嚥下医療に携わるすべての専門職のための新雑誌。超高齢社会に入ったわが国においてますます重視される嚥下の問題に焦点を当て、動画配信サイトとの連携も図りながら、現場で役立つ有用な情報をわかりやすく提示・解説する。
嚥下機能評価、嚥下障害の治療・ケア・リハビリテーションに関する原著論文や解説を多数提供。メディカルスタッフに親しみやすい連載も充実。

嚥下医学 Vol.8 No.1
2019年1号
特集:多職種から考える医療安全 小児・高齢者の誤嚥・窒息リスクの評価とその対応
特集:多職種から考える医療安全 小児・高齢者の誤嚥・窒息リスクの評価とその対応 嚥下医療に携わるすべての専門職のための新雑誌。超高齢社会に入ったわが国においてますます重視される嚥下の問題に焦点を当て、動画配信サイトとの連携も図りながら、現場で役立つ有用な情報をわかりやすく提示・解説する。嚥下機能評価、嚥下障害の治療・ケア・リハビリテーションに関する原著論文や解説を多数提供。メディカルスタッフに親しみやすい連載も充実。
本号は特集号として「多職種から考える医療安全」を企画。病院の医療安全管理部門による誤嚥・窒息への対策をはじめ、高齢者および乳幼児の誤嚥・窒息予防の取り組みについて、さまざまな専門職種の立場から解説する。

嚥下医学 Vol.7 No.2
2018年2号
嚥下医療に携わるすべての専門職のための新雑誌。超高齢社会に入ったわが国においてますます重視される嚥下の問題に焦点を当て、動画配信サイトとの連携も図りながら、現場で役立つ有用な情報をわかりやすく提示・解説する。
嚥下機能評価、嚥下障害の治療・ケア・リハビリテーションに関する原著論文や解説を多数提供。メディカルスタッフに親しみやすい連載も充実。

嚥下医学 Vol.7 No.1
2018年1号
特集:病態に基づく摂食嚥下訓練
特集:病態に基づく摂食嚥下訓練 嚥下医療に携わるすべての専門職のための新雑誌。超高齢社会に入ったわが国においてますます重視される嚥下の問題に焦点を当て、動画配信サイトとの連携も図りながら、現場で役立つ有用な情報をわかりやすく提示する。
本号は特集号として「病態に基づく摂食嚥下訓練」を企画。嚥下障害を呈するいくつかの疾患を取り上げ、それぞれの症状や病態に基づく評価や治療戦略・訓練プログラム・日常での対応等について、最新の臨床治験や具体的手技を含めて解説する。

嚥下医学 Vol.6 No.2
2017年2号
嚥下医療に携わるすべての専門職のための新雑誌。超高齢社会に入ったわが国においてますます重視される嚥下の問題をクローズアップし、動画配信サイトとの連携も図りながら、現場で役立つ有用な情報をわかりやすく提示・解説する。嚥下機能評価、嚥下障害の治療・ケア・リハビリテーションに関する原著論文や解説を多数提供。メディカルスタッフに親しみやすい連載も充実。

嚥下医学 Vol.6 No.1
2017年1号
特集:嚥下障害の早期発見と予防
特集:嚥下障害の早期発見と予防 嚥下医療に携わるすべての専門職のための新雑誌。超高齢社会に入ったわが国においてますます重視される嚥下の問題を正面から取り上げ、動画配信サイトとの連携も図りながら、現場で役立つ有用な情報をわかりやすく提示する。
本号は特集号として「嚥下障害の早期発見と予防」を企画。今後の嚥下障害対策に求められるチーム医療の取り組みとして、どの職種でも危険なサインを見逃さず適切な対応を行っていくための具体的な方法について解説していく。

最新ガイドライン準拠 消化器疾患 診断・治療指針
内科医が多く遭遇する一般的な腹部症状(腹痛,下痢,便秘,嘔吐,腹部膨満など)や重篤な消化器疾患につながる所見(急性腹症,吐血,下血,黄疸,体重減少など)について豊富な知識をもつことは,患者の診療と専門医へのコンサルタントに役立つ.

J-IDEO Vol.4 No.3 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ジャーナルトピック
2020年5月号
【Special Topic】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ジャーナルトピック 岩田健太郎
【Special Topic】新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ジャーナルトピック 岩田健太郎
編集主幹・岩田健太郎先生がCOVID-19に関する様々な論文の中から,診療や感染対策に役立ちそうと感じたものを選りすぐって紹介するジャーナルレビューです.また,感染対策のプロフェッショナル・坂本史衣先生の「泣く子も黙る感染対策」のテーマは,ずばり「新型コロナウイルス感染症の院内感染対策」.この他にもCOVID-19に関する記事を多数掲載.すべての医療者のお手元にお届けしたい1冊です.
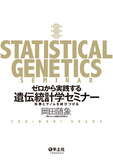
ゼロから実践する 遺伝統計学セミナー
疾患とゲノムを結びつける
論文で見たあのプロットが自分でも描ける!遺伝統計学の先端トピック,手法の特徴の理解から,Python・Rでの実習まで,手元のPCでワンストップで体験できる.ゲノムデータから発見を導く先端研究への招待.

実験医学増刊 Vol.38 No.7
【特集】疾患に挑むメカノバイオロジー
【特集】疾患に挑むメカノバイオロジー
生体内での力の刺激が疾患発症に寄与することが次々と発見され,新たな展開をみせるメカノバイオロジー.力学的視点から組織レベルでとらえた疾患や生命機能の姿から,治療法への展開までご紹介します.

楽しくわかる栄養学
「どうしてバランスのよい食事が大切なのか」「そもそも栄養とは何か」という栄養学の基本から,栄養アセスメント,経腸栄養など医療の現場で役立つ知識まで学べます.栄養の世界を知る第一歩として最適の教科書

ファーマナビゲーター DIC編【改訂版】
“Ebb Tide”のなかで
最近、日本は科学論文の数が減少傾向にある、というニュースが相次いだ。かつて10年前には、米国に次いで2位という輝かしい時代もあったが、現在はベスト10からも脱落している。わが国のサイエンスが“Ebb Tide、引き潮”状態であるということである。悲しいことだ。原因として思い当たる節は、第一に研究予算の削減であろう。“どうにかしたい”とは日本人なら誰しも思うことである。
“DIC-ology”というべき新潮流
このようなサイエンス退潮のなかで、頑張っている数少ない分野のひとつが、わが「DICの基礎と臨床の分野」であろう。私は本書を編集し、原稿を校正する過程で、この感を強くした。もちろん、DIC学の基盤をなす血液凝固学、血管生物学、感染症学、侵襲科学、免疫学などが世界的レベルで進歩していることの反映でもあるわけであるが、それらの下部領域をすくい上げ、編集し直して、応用・発展させて、“DIC学”、“DIC-ology”とも呼べる学域に止揚させたのは、わが国の基礎、臨床の医者、科学者の力量である。
New Tide:DIC-processingの底流に
この度5年ぶりに改訂することになった『ファーマナビゲーターDIC編』は、次の新しい潮流を予感させるものとなっている。次に取り込むべきは、制御閾値とレベルと場を逸脱した凝固・線溶系の暴走に引き続くプロセスの解明、あるいはその制御の学問の生誕であろう。換言すると“Tissue damage:Sensing, Control and Tolerance/Repair”ともいうべき領域である。
このDIC-ologyともいうべき領域にまで到達した成果が日常の臨床、研究に大いに資することを期待したい。そして、これが更なるジャンプの踏み台になり、さらに大きな潮流になることを心から祈念しながら、編集・校正した次第である。
(丸山征郎「序文」より抜粋)
