
嚥下医学 Vol.6 No.1
2017年1号
特集:嚥下障害の早期発見と予防
特集:嚥下障害の早期発見と予防 嚥下医療に携わるすべての専門職のための新雑誌。超高齢社会に入ったわが国においてますます重視される嚥下の問題を正面から取り上げ、動画配信サイトとの連携も図りながら、現場で役立つ有用な情報をわかりやすく提示する。
本号は特集号として「嚥下障害の早期発見と予防」を企画。今後の嚥下障害対策に求められるチーム医療の取り組みとして、どの職種でも危険なサインを見逃さず適切な対応を行っていくための具体的な方法について解説していく。

最新ガイドライン準拠 消化器疾患 診断・治療指針
内科医が多く遭遇する一般的な腹部症状(腹痛,下痢,便秘,嘔吐,腹部膨満など)や重篤な消化器疾患につながる所見(急性腹症,吐血,下血,黄疸,体重減少など)について豊富な知識をもつことは,患者の診療と専門医へのコンサルタントに役立つ.
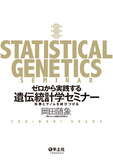
ゼロから実践する 遺伝統計学セミナー
疾患とゲノムを結びつける
論文で見たあのプロットが自分でも描ける!遺伝統計学の先端トピック,手法の特徴の理解から,Python・Rでの実習まで,手元のPCでワンストップで体験できる.ゲノムデータから発見を導く先端研究への招待.

実験医学増刊 Vol.38 No.7
【特集】疾患に挑むメカノバイオロジー
【特集】疾患に挑むメカノバイオロジー
生体内での力の刺激が疾患発症に寄与することが次々と発見され,新たな展開をみせるメカノバイオロジー.力学的視点から組織レベルでとらえた疾患や生命機能の姿から,治療法への展開までご紹介します.

楽しくわかる栄養学
「どうしてバランスのよい食事が大切なのか」「そもそも栄養とは何か」という栄養学の基本から,栄養アセスメント,経腸栄養など医療の現場で役立つ知識まで学べます.栄養の世界を知る第一歩として最適の教科書

ファーマナビゲーター DIC編【改訂版】
“Ebb Tide”のなかで
最近、日本は科学論文の数が減少傾向にある、というニュースが相次いだ。かつて10年前には、米国に次いで2位という輝かしい時代もあったが、現在はベスト10からも脱落している。わが国のサイエンスが“Ebb Tide、引き潮”状態であるということである。悲しいことだ。原因として思い当たる節は、第一に研究予算の削減であろう。“どうにかしたい”とは日本人なら誰しも思うことである。
“DIC-ology”というべき新潮流
このようなサイエンス退潮のなかで、頑張っている数少ない分野のひとつが、わが「DICの基礎と臨床の分野」であろう。私は本書を編集し、原稿を校正する過程で、この感を強くした。もちろん、DIC学の基盤をなす血液凝固学、血管生物学、感染症学、侵襲科学、免疫学などが世界的レベルで進歩していることの反映でもあるわけであるが、それらの下部領域をすくい上げ、編集し直して、応用・発展させて、“DIC学”、“DIC-ology”とも呼べる学域に止揚させたのは、わが国の基礎、臨床の医者、科学者の力量である。
New Tide:DIC-processingの底流に
この度5年ぶりに改訂することになった『ファーマナビゲーターDIC編』は、次の新しい潮流を予感させるものとなっている。次に取り込むべきは、制御閾値とレベルと場を逸脱した凝固・線溶系の暴走に引き続くプロセスの解明、あるいはその制御の学問の生誕であろう。換言すると“Tissue damage:Sensing, Control and Tolerance/Repair”ともいうべき領域である。
このDIC-ologyともいうべき領域にまで到達した成果が日常の臨床、研究に大いに資することを期待したい。そして、これが更なるジャンプの踏み台になり、さらに大きな潮流になることを心から祈念しながら、編集・校正した次第である。
(丸山征郎「序文」より抜粋)

LiSA 2020年別冊春号
2020のシェヘラザードたち
2020のシェヘラザードたち 2020のシェヘラザードたち

リハビリテーション職種のマネジメント
頼りない先輩、セミナー依存症、キャリアの不安・・・
利用者が増えない、スタッフが運営に協力しない、組織間が対立している・・・
リハビリテーション現場のその悩み、全てマネジメントで解決できます。
現場で起こりがちな課題やトラブル31場面(臨床編15場面、運営・経営編16場面)を臨場感たっぷりに漫画化!
解決するためのマネジメントの考え方や手法をピンポイントでわかりやすく解説。

地域リハビリテーションと私
“リハビリテーション”という言葉すら日本に定着していなかった時代、1人でも多くの障害者がその人らしい充実した人生を送れるよう、奔走した若い医師がいた。理想と情熱に燃えたこの医師は、やがて“地域リハビリテーションの父”となった。
日本のリハビリテーションを確固たるものにした医師・澤村誠志の半生と、共に駆け抜けた仲間たちの活躍を振り返り、超高齢化社会を迎える日本が真の福祉国家となる道を示す。

言葉の力、作業の力
自己を対象とした事例研究を読み解く
長年うつ症状に悩まされ,名医の治療を受診しつつも「言葉」による対話型の精神療法に限界を感じていた著者.ある日,なにげない作業を通して,自分の心が解き放された経験をきっかけに,「作業」をさらに深く理解したいと大学院での研究を思い立つ.その思いに突き動かされ,精神科作業療法の第一人者 山根寛教授を見出し,京都大学大学院の院生として作業療法の治療的機序の研究と,うつ病の当事者として,自身の体験を通して治療効果を確かめたい旨を山根教授に申し出る———————————.
本書は当事者である著者が作業療法士である山根寛教授の指導のもとで,作業療法を実際に体験し,自身を事例に研究,最後には学会にて発表するに至るまでの過程について,著者自身による記録と山根教授による解説によって記されている.著者がどのような体験をし,どのような作業の効用を感じていたのか.また,精神療法(言葉)と作業療法(作業)の持つ力やその相関性とはどのようなものなのかが凝縮された一冊となっている.
さらに,本書の巻末には主治医であり,わが国の精神医学界の泰斗笠原嘉医師も交えて著者,山根教授の鼎談にてそれぞれの思いを語り合っていただいた.
作業療法の本質,とりわけ当事者の体験を通してしか知ることができない,作業の持つ力やそのありかたを学ぶことのできる,わが国にはこれまでにない新しい形の精神科教本である.

頸損晩夏
創りつづけた頸髄損傷35年の生活の記録
著者は26年前に「明日を創る」という本を出版している.事故で頸髄損傷となり,首から下の機能を失いながらも,自宅に戻り,自立した日常生活が送れるようになるまでを描いたものだ.その表紙の装丁,イラストも口にくわえた電子ペンで息を使って自ら描き、本文もマウススティックで打ち込んで仕上げた.当時なんの福祉機器もなく,多くの頸損当事者が寝たきりのままの生活を強いられ,失意のどん底にとどまっている中にあって,彼の自立は奇跡にふさわしかった.著者がどのように自立の道を探っていったのか,その仕掛人となった支援者たちとの交流を克明に記録したその本は,当時,当事者,専門職を問わず全ての人々に広く感動を与えた.
それから26年の歳月が過ぎた.著者はその後も活動を続け,障がいを持つ人の社会参加,就労支援,政策提言をも行っている.いつの間にか支援される側から支援する側になっていたのだ.しかし,麻痺した手足は一度として動くことのないように,動くことのない社会的現実とも直面してきた.障がい者の内側にも,彼らを取り巻く外側にもバリアーは厳然と存在し,簡単には超えることはできない.本書は、受傷当時に支えあった仲間が再会し,奇跡の出会いからの日々を,それぞれが体験した26年を振り返り著した,明日障がいを持つかもしれない仲間たちへのアドバイスとメッセージである.

リハビリテーション職種のキャリア・デザイン
資格があっても仕事が無い?!
これからの将来、リハビリテーション職種=PT・OT・STの雇用は不安定になり、労働市場において極めて熾烈な競争を強いられることになります。近い将来に生じるPT・OTの過剰供給、地域包括ケアシステムの推進、高齢者数の増加の頭打ち、ロボットテクノロジーなどの技術革新、国家財政のひっ迫等が、リハビリテーション職種に熾烈な競争を強いる原因となります。
不確かな時代の中で、不安を感じているリハビリテーション職種の方は少なくありません。
「長い将来、この仕事をやっていけるのか?」
「将来に漫然とした不安がある」
「自分がやりたいことがみつからない・・・」
将来の自分を思い描けていますか?
現代は、全てのリハビリテーション職種にとってキャリア開発の視点が不可欠な時代といえます。
リハビリテーション職種を目指す学生・若手が自分に向き合い、自分の人生を切り開くためのキャリア・デザインの方法論をわかりやすく解説します。

エキスパートによる生殖領域の外科的手法
生殖内視鏡と不妊治療のコツ
生殖医療における外科手術や侵襲的検査は,身体的にはもちろん,精神的な苦痛を強く感じうる.本書では,内視鏡下手術や子宮鏡,精管造影の検査など,術者の技量で患者の満足度やQOLに大きな差異が出てしまうこれらの手法についてまとめた.執筆陣には,今まさに現場で活躍しているエキスパートを揃え,経験に裏付けされたコツと知識をできるだけ詳細に解説してもらった.明日からの手技が変わる,叡智が詰まったバイブルである.

日本排尿機能学会標準用語集 第1版
下部尿路機能およびその障害に関する標準用語集の最新版.International Continence Society (ICS,国際禁制学会)が出版した標準用語報告書のうちの主な3編に,International Children’s Continence Society (ICCS,国際小児禁制学会)の1編を加え,学会を代表するエキスパートたちが,これらに準拠して編集した.下部尿路機能障害の診療・研究に携わる本邦の専門家が,学術活動の場で使用できる共通言語を提供する.

≪ケアをひらく≫
誤作動する脳
「時間という一本のロープにたくさんの写真がぶら下がっている。それをたぐり寄せて思い出をつかもうとしても、私にはそのロープがない」――たとえば〈記憶障害〉という医学用語にこのリアリティはありません。ケアの拠り所となるのは、体験した世界を正確に表現したこうした言葉ではないでしょうか。本書は、「レビー小体型認知症」と診断された女性が、幻視、幻臭、幻聴など五感の変調を抱えながら達成した圧倒的な当事者研究です。*「ケアをひらく」は株式会社医学書院の登録商標です。
パンフレットはこちらから

リーダーのための育み合う人間力
自分も周りも大事にして元気な職場をつくる
現任リーダーは1人で抱えてがんばりすぎていませんか? 次世代リーダーは自分に務まるのかと不安を抱えていませんか? 変化の激しい時代は、能力が高く強いリーダーが1人いたところでどうにもなりません。求められるのは、各人が強みをいかしてリーダーシップを発揮できるようにしかけをつくり、仲間と一緒に育ち合う場をつくれるリーダー。そのために必要な人間力の育み合い方をトップマネジャー歴17年のオカンが伝えます。

看護管理 Vol.30 No.5
2020年05月発行
特集 今こそ再考したい事業継続計画(BCP) 地域医療とスタッフをどう護る?
特集 今こそ再考したい事業継続計画(BCP) 地域医療とスタッフをどう護る? 近年,甚大な自然災害が毎年のように発生しています。診療継続をはじめとする病院運営全体に支障を来した病院が多数発生した状況から,厚生労働省は全病院に対して初めて事業継続計画(BCP)の策定状況に関する調査を行いました。その結果,BCPが要件となっている災害拠点病院を除く一般病院では,策定が進んでいない状況が明らかになりました。現在,新型コロナウイルスの感染が拡大し,現在進行形で事業継続への対応が迫られています。診療機能や地域医療,そしてスタッフを護るため,多職種によるBCPの早期策定,あるいは見直しが求められています。本特集では,BCP策定の基本的な考え方と,各施設の取り組みを紹介します。

助産雑誌 Vol.74 No.5
2020年05月発行
特集 妊娠期からできる虐待防止の方策 「気になる妊婦」を見つけるための連携と支援
特集 妊娠期からできる虐待防止の方策 「気になる妊婦」を見つけるための連携と支援 昨今,世間では痛ましい虐待事件が多発しています。本来愛されるべき子どもが傷つけられ,果ては亡くなってしまうニュースを見るたび,こうした子どもたちを何とか救うことができたのでは?と思う方も多いのではないでしょうか。また,日常の業務を振り返ると,何となく「気になる」と思った妊婦はいませんでしたか? 確かに直感ではあるものの,何となくおかしいと感じる─こうした妊婦を早い段階で他職種につなぎ,連携をとって関わっていくことができれば,将来発生するリスク・事件を未然に防ぐことができると考えられます。本特集では,「気になる妊婦」や「特定妊婦」といった虐待リスクの高い妊婦への支援方法と実際を取り上げ,助産師が関われるタイミングで,虐待を未然に防ぐためにできることを考えます。

訪問看護と介護 Vol.25 No.5
2020年05月発行
特集 「喪失」に直面する人へのケア
特集 「喪失」に直面する人へのケア 「喪失」は、誰もが人生の中で幾度となく経験するものです。「老化や病気、障害によって心身の健康が損なわれる」「死別によって大切な人を失う」。在宅ケアの現場ではこのような形で喪失体験をもつ人と出会い、それに伴って生ずる悲嘆や葛藤に対するケアが求められることになります。「喪失に対するさまざまなケアこそが、在宅ケアである」。そう言っても過言ではないのかもしれません。本特集では、喪失とそれに対するケア(特にグリーフケア)という視点から、その意義と必要性を確認していきます。(企画協力)坂口 幸弘(関西学院大学人間福祉学部人間科学科教授)

保健師ジャーナル Vol.76 No.5
2020年05月発行
特集 母子保健の危機 援助職としての源流
特集 母子保健の危機 援助職としての源流 近年の児童虐待相談対応件数の増加や,虐待による子どもの死亡事件の発生が続いたことを踏まえ,2018年に「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」が設けられ,さらなる対策の強化が進められている。児童相談所と警察との全件情報共有の動きも広がる中,本特集では,「取り締まり」や「監視」ではない虐待防止につながる支援のあり方をさまざまな視点から紹介し,援助職として子どもの虐待防止にどのように取り組むべきかを考える。
