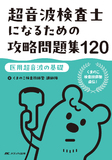
超音波検査士になるための攻略問題集120【医用超音波の基礎】
【試験問題にかかわる必須項目をすべて網羅!】
超音波検査士を目指す場合、医用超音波検査の基礎工学の試験問題は避けては通れない。本書は、試験問題の解き方、考え方、体験談、さらに臨床に役立つポイントなども含め、試験にも実際の診療にも役立つ情報をふんだんに盛り込む。難しいことを簡単に、わかりやすく解説する。

≪新OS NEXUS No.15≫
小児の骨折と手術[Web動画付]
No.15では,小児の四肢の各部位における外傷の全体像と特殊性,注意すべきポイントを解説したうえで,頻度,要度の高い,あるいは筆者が得意とする術式について写真やイラストを多用してわかりやすく解説。
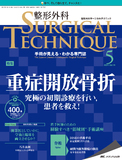
整形外科 SURGICAL TECHNIQUE(サージカルテクニック) 2021年5号
2021年5号
特集: 重症開放骨折 究極の初期診療を行い,患者を救え!
特集: 重症開放骨折 究極の初期診療を行い,患者を救え! 整形外科領域の「手術」を徹底して取り上げる専門誌『整形外科サージカルテクニック』
教科書には載っていない手術のコツ、ピットフォール、リカバリー法が満載。各手術のエキスパートの技と知恵を凝縮した「手術が見える・わかる専門誌」です。
本誌で取り上げた手術動画を専用WEBページでチェックでき、誌面と動画でしっかり確認できます。

皮膚科学 第11版
半世紀を経てもなお皮膚科医のバイブルとして信頼を得ている本書の6年ぶりの改訂版です。基本骨格を残しながらも、急速に進展し、変化する皮膚科学の現在を反映して、新たな著者陣を迎え、修正・追加を加えました。「パッと見て理解できる」ことではなく、幅広く記載された皮膚科学の真髄を精読し、丁寧に学びたい読者に捧げます。
序文
「皮膚科学」第11版は第10版以来6年を経てここに刊行されました。本書が1971年故上野賢一先生著の「小皮膚科書」として上梓されて半世紀、編者の1人が上野先生から本書を引き継いでからも20年近くを経ています。その間、世の中が大きく動き、自然科学、医学、皮膚科学も目まぐるしいほどに進歩しています。その動き、進捗に対応して、改版の度に少しずつ新知見を加えてよりよい教本を目指してきた次第です。しかし11版では著書から複数の編者による編集本に変更し、多くの章で新進気鋭の皮膚科臨床医、研究者に分担執筆をお願いしました。このような措置により我が国の皮膚科学の新しい側面、疾患概念の変化やcutting edge部分を含めて、その息吹を本書に取り込めたのではないか、また将来に亘って本書の意味合いを変革しつつ維持できるのではないかと考えております。その意味で11版が曲がり角を通過したように思います。ただ残念ながらここのところのコロナ禍やその他の事情により議論や準備が必ずしも十分とは言えず、多くの積み残しもございます。12版以降さらにこの方向性を先に進めて、本書にふさわしい新しい伝統を志向、構築したいと考えています。
本書は学部学生から、一般臨床医、皮膚科の臨床医、専門医ないし専門医を目指す諸氏等広い読者層に向けたものですが、皮膚科学の基礎とともに進歩の先端部分などを取り込みまして、皮膚科専門医にも十分対応できる教本とも思っています。本書第11版が意欲ある読者諸氏のお役に立つことができれば望外の喜びです。また前述の方針に従って鋭意編集作業をしましたが、内容などにやや凹凸や不備をお感じいただく向きがあるやと危惧しております。その際には是非その旨をご叱正いただければ幸いです。次版以降の改訂に向けての御教示、参考にと考えております。宜しくお願い致します。
階前梧葉已秋聲ですが、未覺池塘春草夢の心で参りたい、泉下の上野名誉教授にもお伝えできればと考えます。
ともあれ、本書が連綿として半世紀を経て、此の度その第11版を世に送り出せますことを慶び、また多々ご援助、ご教示いただいた多くの皮膚科医、研究者の方々に、また多大なご助力を賜った金芳堂、藤森祐介氏に深甚なる感謝の意を表する次第です。
2022年晩春
編者
大塚藤男
藤本学

骨折の機能解剖学的運動療法 その基礎から臨床まで 総論・上肢 第2版
2015年の初版から7年ぶりの改訂となる第2版.総論では骨折の運動療法を行うために必要な知識,各論では骨折後に必ずおこる組織の修復過程を基礎に、上肢,体幹,下肢ごとに疫学、整形外科的な治療の考え方、評価と治療について解説.主な改訂内容として、総論では近年話題のfascia、慢性疼痛のfear-avoidancemodelを加筆.また肩関節と手関節周辺骨折の運動療法について可能な限り詳細に修正と加筆を加えた待望の第2版の刊行.
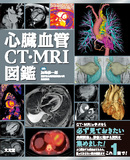
心臓血管CT・MRI図鑑
CT・MRIを学ぶなら必ず見ておきたい典型画像と,診断に繋がる所見を集めた.よく遭遇する疾患から知っておきたい稀少疾患までを網羅.さらに最先端の技術や,著者の経験からの診療のコツなどの豆知識も多数掲載.エキスパートが撮った数多くの美しい画像を見ることで,「図鑑」のように視覚的に学べる一冊となっている.

手 その機能と解剖
今迄に出版した各版をもう一度見直し、内容を統括し、その上で最近の知見を加えて第6版が作製された。
基本的な知識から治療の実践上知っておくべき手の機能と解剖の要点がまとめられている。この本を熟読して頂ければ、正常な手の進化の過程やその機能と解剖の知識を得られるばかりでなく、手の先天異常、損傷、病気などについてもある程度は学べるように配慮され、生きた手の機能と解剖が克明に説き明かされている。
また、多数の色刷りシェーマとカラー写真やX線写真で、明快に展開されているので、整形外科医、形成外科医はもちろん、ハンドセラピスト、理学療法士、作業療法士など幅広い読者層に対応する充実した内容を完備した。

レジデントのための 栄養管理基本マニュアル
NSTディレクターになるための必読書
レジデントやコメディカル向けに,栄養管理の実際をわかりやすく実践的に解説したポケットマニュアル.栄養アセスメントや病態別の栄養管理の実際などのほかに,「病院食とは?」といったベーシックな項目も取り入れ,これから栄養管理を始める人にも一から学べる内容となっている.NSTのメンバーを目指す医師,看護師,薬剤師,管理栄養士の必読書.

頭痛診療が劇的に変わる!
すぐに活かせるエキスパートの問診・診断・処方の考え方
よく出合う23症例をもとに,頭痛専門医の診断・治療の思考プロセスを丁寧に解説!「患者さんにどう聞いて診断する?処方はどう変えていく?」などの具体的なコツがわかるから診療に自信がつく!頭痛を診るすべての医師におすすめ

所見の書き方がまねできる
腹部超音波検査レポート実例集 改訂第2版
初学者,研修医をはじめ対象から支持されている,“腹部超音波検査レポートの実際の書き方”がよくわかる好評書が改訂.症例数が74から93とさらに充実.超音波画像とシェーマ(ガイドポスト)を見開きで見やすく構成.本書を“まねて”レポートを作成するうちに,病変に特徴的な所見の書き方のコツも自然に身につく.ケースファイル,所見用語リストとしても役立つ一冊.

状況設定問題“読み解き”レッスン
臨床実践のエキスパートが看護師国試「状況設定問題」の読み解き方を指南.
選択肢一つずつについて,臨床実践の知識を交えて解説することで,一つの状況設定問題から周辺知識を関連付けて学べる看護学生必携の1冊!
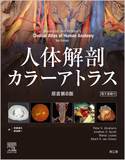
人体解剖カラーアトラス 原書第8版
本書に収載されている600点を超える人体の解剖標本のカラーアトラスは臨床面での有用性が高いと広く支持されている。これらにより人体のリアルを学ぶことができる。医療技術系養成課程で学ぶ学生にとっては必携の一冊。今版より電子書籍と動画へのアクセス権が付属し、より学習しやすくなった。
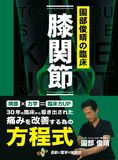
園部俊晴の臨床 膝関節
数多くのプロスポーツ選手や著名人が集まるコンディション・ラボの理学療法士、園部俊晴の初の単著がついに発売。
伝説の理学療法士、入谷誠の一番弟子としてスタートした30年の臨床の中で培った技術と知見を余すことなく詰め込んだ膝関節書籍の決定版。

「その」手術室外での鎮静・鎮痛 安全ですか
検査・処置や救急・集中治療の現場で欠かせない「鎮静と鎮痛」。適切な管理は患者の苦痛を和らげる一方、薬剤反応の差により重篤な合併症を招く危険を伴う。
本書は鎮静の基本概念から安全に行うための体制・機器・人員までを体系的に解説。さらに、各領域での安全な実践を専門家が解説するとともに、臨床で役立つチェックリストも巻末に収載した。
手術室外における鎮静の質と安全性を高めたい全ての医療者に必携の一冊!
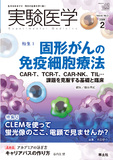
実験医学 Vol.44 No.3
2026年2月号
特集1:固形がんの免疫細胞療法 CAR-T、TCR-T、CAR-NK、TIL…課題を克服する基礎と臨床/特集2:CLEMを使って蛍光像のここ、電顕で見ませんか? 標的部位を精密に狙い超微構造を見る
特集1:固形がんの免疫細胞療法 CAR-T、TCR-T、CAR-NK、TIL…課題を克服する基礎と臨床/特集2:CLEMを使って蛍光像のここ、電顕で見ませんか? 標的部位を精密に狙い超微構造を見る
特集1:固形がんの壁を打ち破る! CAR-T細胞やTCR-T細胞,NK細胞,iPS技術など,多角的アプローチで弱点を克服し治療の限界を押し広げる「免疫細胞療法」の最前線に迫る/特集2:蛍光顕微鏡で捉えた現象を,電子顕微鏡の解像度でもう一度見る.研究の説得力を高める「光-電子相関顕微鏡法」への誘い

根拠ある治療の選択肢が増える!
運動器障害の多角的アプローチ[Web動画付]
典型症例から学ぶ運動療法・徒手療法・物理療法・装具療法の実践
臨床で携わる機会の多い代表的な運動器障害について,症例を提示したうえで運動療法,徒手療法,物理療法,補装具療法のエキスパートがそれぞれのアプローチ法を解説。
治療法が効果的であると判断し選択する際の根拠を「科学的根拠(エビデンス)」「機能解剖・生理学的観点」「臨床的観点(エキスパート・オピニオン)」に分類してわかりやすく示すとともに,治療内容を豊富な写真と動画を通じて具体的に紹介する。さらに「まとめ」では治療法を選ぶ際の参考にできるように,編者が各治療法の有用性についてコメントを記している。
多様な治療法に触れることで,治療の選択肢を増やせる一冊!

≪アスレティックトレーナー専門基礎科目テキスト 2≫
スポーツ科学概論
スポーツ科学に関する基礎的知識を解説した上で,その応用について,①競技に必要なアスレティックパフォーマンスと測定評価&向上の取り組み例,②外傷・障害予防への知識の応用,③健康管理(疲労回復、トレーニング負荷管理など),以上のような項目例を参考にスポーツ科学の知識を活かした実践的な応用例を解説,習得を目指した1冊.
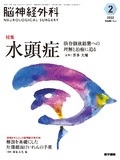
脳神経外科 Vol.50 No.2
2022年3月発行
水頭症─脳脊髄液動態への理解と治療に迫る
水頭症─脳脊髄液動態への理解と治療に迫る 雑誌『脳神経外科』は2021年1月よりリニューアルしました。「教科書の先を行く実践的知識」を切り口に、脳血管障害、脳腫瘍、脊椎脊髄、頭部外傷、機能外科、小児神経外科など各サブスペシャリティはもちろん、その枠を超えた横断テーマも広く特集します。専門分野・教育に精通し第一線で活躍する脳神経外科医を企画者・執筆者に迎え、診断・治療に不可欠な知識、手術に生きる手技や解剖を、豊富な図と写真を用いて解説します。さらに、脳神経外科領域の最新の話題を取り上げる「総説」、手術のトレンドを修得することのできる「解剖を中心とした脳神経手術手技」も掲載します。 (ISSN 0301-2603)

原発性免疫不全症候群 診療の手引き 改訂第2版
研究,診療の進歩が目覚ましい原発性免疫不全症候群から代表的かつ頻度の高い疾患を選び,診療の手引きとして疾患概要から診断基準,重症度分類,診療上注意すべき点,専門医への紹介までの対応など,診療の一助となる内容が満載.
各分野のエキスパートにより図表やフローチャートを用いながらわかりやすく解説され,最新の情報を網羅した臨床的・実践的な一冊となった.診察で重要な移行期ガイドラインも掲載している.

≪新OS NEXUS No.17≫
新しい上肢の手術[Web動画付]
No.17では,手指の人工関節手術,橈骨遠位端骨折の新しいプレート固定術など,手,肘,肩の「新しい」手技を中心に取り上げた。
