
臨床整形外科 Vol.61 No.1
2026年 01月号
特集 下垂足を極める 病態理解から治療戦略まで
特集 下垂足を極める 病態理解から治療戦略まで よりよい臨床・研究を目指す整形外科医の「うまくなりたい」「学びたい」に応える月刊誌。知らないままでいられないタイムリーなテーマに、トップランナーによる企画と多角的な解説で迫る「特集」。一流査読者による厳正審査を経た原著論文は「論述」「臨床経験」「症例報告」など、充実のラインナップ。2020年からスタートした大好評の増大号は選り抜いたテーマを通常号よりさらに深く掘り下げてお届け。毎号、整形外科医に “響く” 情報を多彩に発信する。 (ISSN 0557-0433)
月刊、増大号を含む年12冊

臨床に役立つ!病理診断のキホン教えます
良性・悪性はどうしてわかる? 病理医は何をみているの?臨床に活かす病理の基本的な見かたを初学者レベルでやさしく解説.診断プロセスを実感できるケーススタディ,病理レポートを読むのに役立つ専門用語など必読!
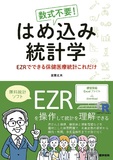
数式不要! はめ込み統計学
EZRでできる保健医療統計これだけ
無料統計ソフトEZRを使って始める
保健医療統計!
保健医療の現場で実際に統計を「使える」ことを目指し,数式を使用せずに解説した実用統計書。運動習慣と糖尿病,喫煙と肺がんなどを題材にした練習問題を基に,無料統計ソフトEZRを操作しながら理解できる。名義変数の解析から,連続変数の解析,傾向・相関の解析,多変量解析,生存期間の比較までを解説。これから統計を使いたい方に最適の一冊。

見てわかる
がん薬物療法における曝露対策 第2版
薬学的基礎知識にはじまり、抗がん薬の調製・投与、投与後の体液やリネン類の取り扱い、スピル時・曝露時の対応などを看護業務の流れに沿って解説。CSTD(閉鎖式薬物移送システム)やPPE(個人防護具)の選択肢とその特徴をさらに充実、CSTDを用いた局所投与などの新項目も追加。曝露を防ぐための手技やケア方法が写真・イラスト・web動画でひとめで“わかる”。
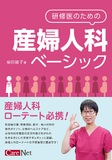
研修医のための産婦人科ベーシック
ありそうでなかった研修医必読の1冊が誕生しました!
初期臨床研修の必修科目である産婦人科の要点をギュギュっと凝縮。指導、執筆経験も豊富な柴田綾子先生がCareNeTV「臨床研修サポートプログラム」での講演をベースに執筆しているので、講義の実況中継さながらの生き生きとした文体になっており、あなたを飽きさせません。実際の研修の場における注意点などの超実践的なアドバイスも満載。研修前の予習として目を通すのはもちろん、研修後のまとめにも最適です。限られたローテート期間をより充実としたものとするためにぜひご活用ください。産婦人科の知識を確認したいベテランの先生にもお勧めです。
※本書はCareNeTV臨床研修サポートプログラム「研修医のための産婦人科ベーシック」を基に執筆されたものです。

INTENSIVIST Vol.9 No.3 2017
2017年3号
特集:中毒
特集:中毒
中毒はありふれていて,その大部分は集中治療を必要とせず,後遺症を残さず治療可能と考えられています。しかし一方で,ごく少数の重症患者では集中治療を必要とし,対症療法にとどまらない中毒原因に応じた特異な治療が必要となる場合があります。そこで本特集では,薬物の体内動態を中心とした薬理学的知識,中毒を疑った場合に症状や症候から鑑別するアプローチといった集中治療医が今ひとつ苦手とする分野の基礎的事項について触れ,特に集中治療が必要な中毒についてはエビデンスを踏まえた解説を行います。また,各章は臨床疑問(clinical questions)に答える形式としております。

見逃してはいけない小児救急
小児救急は軽症の頻度が圧倒的に高いため、緊急度の高い疾患への配慮を忘れやすく、診断エラーに繋がりやすい状況があります。本書では、小児救急でよくある診断エラーやピットフォールを共有し、症例の振り返りを通してポイントや解決法を紹介しています。
本書の対象は、小児の救急外来での診断・判断に関わる方です。経験を積み知識が増えれば、診断エラーがなくなるわけではありません。初学者からベテランまで、それぞれ違った視点で、学びがあるのではないかと考えています。また、救急外来で働く看護師、診療放射線技師、臨床検査技師など、直接、診断・判断をしなくても、チームとして診断エラーを減らすために、本書の内容は役立つと思います。
患者さんを通して学びながら、本書が読者の皆さんのそれぞれに合った診断の仕方、鑑別疾患の肉づけをするためのきっかけづくりになれば幸いです。
推薦文
~すべてのシーンの小児診療に彩りを加える良書~
著者の鉄原先生とは10年来の付き合いになる。彼の様々な長所をあげていくと与えられた字数が足りなくなるので、私の一押しポイントに絞ると、学ぶことが好き、教育が好き、Mr.Childrenが好き、そして、君が好き。である。
実際、シミュレーショントレーニングでみせる愛情あふれるファシリテーションは素晴らしい。私のファシリテーションの半分はテツハラでできている。あなたも一度は彼のコースを経験すべきと思う。
これは、そんな鉄原先生の編集によるすべての小児医療従事者が読むべき本である。他書にはみられない特徴的な強みは2つある。1つは編集方針、もう1つは広い読者対象である。
まず、1つ目は、違う視点を許容する編集方針である。「あなた」が経験した喉頭蓋炎と、「わたし」が経験した喉頭蓋炎のプレゼンテーションは違うはずである。同じ疾患を記述しても、著者によって強調するところが変わる。それを通して、より多面的全面的に疾患の理解が進む。そのように仕掛けられている。編者の「君が好き」が読者だけでなくすべての著者に向けられている。
2つ目は、誰が読んでも学びがあることである。本書は、失敗症例を振り返って、みずから改善点をみつけるという、診断エラー学の入門書として有用である。それだけではなく、初期研修医や学生は、総論部分でABCDEから始まる小児救急医療の基本を守ることが学べる。症例検討が中心の中盤では、総合診療医であっても初診では診断しきれないような困難症例が並び、後半は、ベテラン小児医が苦手な外傷・熱中症などの外因性疾患のシンプルな指針が示されている。小児救急医療を学ぶという「終わりなき旅」を最初から最後までガイドするのが本書である。
色んな異論があっていい、医学の深海にともにゆこう。そんなてっちゃんの励ましの言葉が頭にひびく。てっちゃんの出世作を予約して読もう! どう読むのかは、君の好きなようにして!
2022年5月
こだま小児科
児玉和彦
推薦文
子どもの「困った」に本気で向き合いたい君へのギフト
小児科医になった理由を若手の先生との面談で聞くと、子どもと家族に「何か貢献したい」が動機の方が圧倒的に多いです。「見逃してはいけない小児救急」(以下、本書)には「何かしたい」にとてもシンプルに答えてくれる参考書です。すなわち子どもの不調(困った)と病気の関連に気づくセンスとそれに対応できるスキルのノウハウが詰まっています。本書の通読をお勧めします。
ところが、小児科医はそこで終わってはいけません。子どもの不調(困った)の原因に病気が隠れている可能性があること、そして病気に気づければ、その不調(困った)が改善できること、だから、勇気を持って医療にアクセスしてもらうことが実は大事なのです。ですので、小児科医はそのための行動をし続ける必要性があります。何かの病気かもしれない、でもこんなことで受診をして良いのだろうか? 何しに来たと思われないかと、非医療者の方は心配されています。なんかおかしいな、普段と違うなと思ったら、安心のために受診できるようなハードとソフトの両面で小児救急医療の充実が必要です。もし読者の方の地域でそのような準備がなければ、鉄原先生やお近くの本書の執筆者に連絡し、講演や教育回診やカンファレンスなどしてもらってください。「病気じゃない、軽くて良かった」と安心してもらい笑顔で帰宅してもらうことに喜びを見出し、何か引っかかることがあれば、専門医療への引き継ぎや入院適応の決定を日々高精度で行い、子どもたちと家族のハッピーを実現しましょう。
困っている子どもたちと家族に優しく対応し、システマティックに診療し、子どもたちのライフ(命・人生)を繋いでいく、それが小児救急医療です。本書ではその小児救急医マインドの一端に触れることができます。本書が小児医療を担う若手小児科医や小児医療関係者へのギフトである所以です。ギフトですがご購入はご自身で 笑。
2022年5月
兵庫県立こども病院感染症内科
笠井正志
序文
『見逃してはいけない小児救急』に、ようこそいらっしゃいました。あえて「見逃したくて」診療をしている人はいないと思います。しかし、忙しかったり、疲れたり、落ち込んだり……、いろいろな事情があって無意識的に「軽く考えてしまったり・・・・・」「考えられなくなってしまったりして『見逃しに至る』」ことがあると思います。読者の皆さんの中に、夜、自分が救急外来で診た患者さんが、翌日、違う診断で入院していることを、上級医にそっと耳打ちされたことはありませんか? 後で振り返ってみたら、「なんであの時、そんなことしたんだろう?」とか「運が悪かっただけだと信じたい」とか、思ったことはありませんか?
例えば、胸痛が主訴で胸膜炎と思っていたら肺塞栓だったこと、また、パニックで暴れていたので精神科にコンサルトしたが辺縁系脳炎だったこと、転落して受診し全身診察して帰宅してもらったが、再来時の診察で大腿骨骨折と判明したこと。いずれも僕が診させていただいた患者さんです。診断エラーは、患者さん、ご家族、そして、診断に関わったすべての人たちに、ダメージを与えてしまいます。しかし人は、エラーをする生き物です。
では、どうすれば診断エラーを減らすことができるのでしょうか。「診断エラーをしないこと」と「正確な診断をすること」は表裏です。ゆえに、本書の第1章の総論では、まず「小児の救急外来での臨床推論」から始まります。小児の救急外来の初診で、正確な診断・・をつけることは不可能なことが多いです。診断名を無理やりつけるのではなく、最善の判断・・をすることが大事です。次に、「小児救急での診断エラー」に続きます。そして、診断エラーを減らし最善の判断を行う方法の1つとして「ABCDEの診かたのコツ」を紹介します。これはPALS(Pediatric Advanced Life Support)で学ぶ重症小児に対するアプローチですが、すべての患者さんに対して応用して使えます。緊急度を評価する際に活用してみてください。最後に、すべての小児に潜んでいる虐待について考えていきます。
第2章の各論では、まず「あるある」のピットフォール症例や悩ましい症例を紹介します。次に、振り返りをもとに、どのようにアプローチすれば、エラーを避け、より良い判断ができるかを記載しています。診断エラーの症例であっても、決して珍しい症例ではなく、よくあるピットフォールですので、明日出会う患者さんかもしれません。また、鑑別疾患の表をつけています。優先順位をつけて鑑別を挙げるために有用だと考えます。
各論を読んでいただく際、診断名を当てるのではなく、診断の過程・・を一緒に考えていただければと思います。また各論では、直観的思考でエラーが起こり、分析的思考で振り返るという形式にしていますが、ここで示した診断過程や鑑別疾患は、唯一の正解ではありません。限られた時間で行う診療の中で短い時間で診断(判断)できる直観的思考は多くの場合有用です。患者さんを通して学びながら、本書が読者の皆さんのそれぞれに合った診断の仕方、鑑別疾患の肉づけをするためのきっかけづくりになれば幸いです。
本書の対象は、小児の救急外来での診断・判断に関わる方です。診断エラーのところで詳しく述べますが、経験を積み知識が増えれば、診断エラーがなくなるわけではありません。初学者からベテランまで、それぞれ違った視点で、学びがあるのではないかと考えています。また、救急外来で働く看護師、診療放射線技師、臨床検査技師など、直接、診断・判断をしなくても、チームとして診断エラーを減らすために、本書の内容は役立つと思います。
執筆いただいた先生方は、臨床が何より大好きで、教育にも情熱的で、脂が乗りに乗った僕の尊敬する小児救急医たちです。読者の皆さんが、現場で悩み、暗闇の中にいるように感じた時に、本書で光を射すことができれば幸いです。最後に、温かく僕の背中を押してくださる金芳堂編集部の西堀智子さん、河原生典さん、全国のたくさんの仲間たち、そして、学びと元気を与えてくださる患者さんたちに、最大級の感謝を。
本書が「こどもたちと家族のHAPPY」につながることを願って
令和4年5月
鉄原健一

スパルタ病理塾
あなたの臨床を変える!病理標本の読み方
病理を読まないなんて、もったいない! 病理標本を読み解き、病態を理解できれば、臨床が変わります。「普段戦っている相手(=疾患)の本質」がわかり、「病理診断のプロセス」がわかる、臨床と病理をつなぐ1冊。「病理に詳しい臨床医になりたい!」を“診断屋”が叶えます。
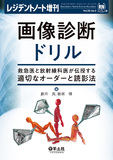
レジデントノート増刊 Vol.22 No.2
【特集】画像診断ドリル
【特集】画像診断ドリル
救急医と放射線科医が画像診断の極意を伝授!放射線科医が出題するドリル形式の症例問題と救急医が求める画像検査の適切なオーダーの仕方,救急で知っておくべきポイントを掲載!両方の知識と見解を1冊で学ぶ!

Q&Aでわかる 初心者のための小児のてんかん・けいれん
小児のてんかん・けいれん診療において若手医師が実際に抱いた様々な疑問に対して,臨床の最前線で活躍する専門家たちが的確に解説.複雑で難解な症候群分類や発作分類などを明快に解き,また,執筆者の経験や本音を記載した「私の一言」では,教科書やガイドラインの記述通りとは限らない実際の現場での雰囲気を伝えている,小児てんかん・けいれんに対する苦手意識を軽減する助けとなる一冊.

胃と腸 Vol.59 No.12
2024年 12月号
主題 回盲部・虫垂病変の診断
主題 回盲部・虫垂病変の診断 消化管の形態診断学を中心とした専門誌。毎月の特集では最新の知見を取り上げ、内科、外科、病理の連携により、治療につながる診断学の向上をめざす。症例報告も含め、消化管関連疾患の美麗なX線・内視鏡写真と病理写真を提示。希少疾患も最新の画像で深く学べる。年2回増大号を発行。 (ISSN 0536-2180)
月刊、増大号2冊を含む年12冊
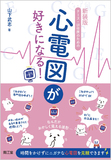
新装版 ナース・研修医のための心電図が好きになる!
研修医、看護師、検査技師など、これから心電図を学ぶ人、心電図でつまずいた人に向けて大好評を博したベストセラーが、装いを新たに一層見やすく、読みやすくなって帰ってきた!不整脈・心電図判読の名人である著者が、モニター心電図だけでなく12誘導心電図も含めて、病棟における実践的な観点をわかりやすく解説。この1冊で“時間をかけずに心電図が好きになる”こと間違いなし。

こんなときどうする ペースメーカプログラミングのキモ!
ペースメーカは新規植込み,交換を含め年間約6万台が患者に植え込まれている。各社よりさまざまな機種が出ているが,搭載される機能も複雑化している。ペースメーカの普及に伴い,他施設で植え込まれた患者を診察・治療するケースも増えているため,医療スタッフは自施設使用のペースメーカのみならず各社のペースメーカ・プログラミングについての基本知識を押さえておく必要がある。また外来フォロー時に問題が起きた場合には,原因特定のうえ,適切な設定に変更する必要が出てくる。
本書では医師,臨床工学技士など関連する医療スタッフが頻度の高い緊急対応やトラブルシューティングも含め,患者の状況に応じた対応・設定について,慌てず対応できるノウハウを提供する書籍である。
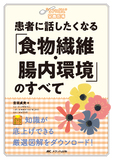
≪“ちょい足し”栄養指導≫
患者に話したくなる「食物繊維・腸内環境」のすべて
【ちまたで話題の栄養情報をスッキリ解説!】「体をととのえる」といわれる食物繊維と腸内環境について、知っているようで知らなかった基礎知識から、栄養ケアに活用できる最新情報まで紹介。「今」知りたいトレンドを“ちょい足し”した適切な栄養食事指導で、患者の心をつかむ。

さぁレーザー治療をはじめよう! 2023
皮膚科・形成外科のための保険診療と美容皮膚
難しいレーザーのしくみについては説明ナシ。あくまでも「どう使って治療してゆくか」に絞り、実用書として編集されています。レーザーの導入や照射の基本だけでなく、POINTやワザ・禁忌・生涯を通じた治療などが詳細に述べられ、レーザー治療を始めるのに必携の1冊となっています。
説明はビジュアルに、イラスト・平易な文章・動画によってなされ、初学者に親切な内容になっているのが人気の理由ではないでしょうか。

はじめて学ぶ小児血液・腫瘍疾患 改訂第2版
―To Do&Not to Doで理解する―
外来や救急の現場で血液・腫瘍疾患を見逃さない!
専門性が高く,診断が難しい小児血液・腫瘍疾患の「すべきこと」「してはいけないこと」をスペシャリストがわかりやすく伝授.診断,対応,専門医への紹介や患児・保護者への説明のポイント,治療後の外来対応まで,知っておきたい知識が詰まった入門書となっており,現場ですぐに活かせます.
プライマリケアに携わる医師,小児の血液・腫瘍疾患をはじめて学ぶ方に必携の1冊!

手術書をレビューする!
一般消化器外科手術 達人へのSuccess Road
若き消化器外科医が抱く,19種の一般消化器外科手術に対する152個の悩みを取り上げ,解決のために押さえておくべき知識とスキルについて,先人たちの業績(過去の論文や手術書)をレビューし,豊富なイラストと丁寧な解説でコーチングする「一般消化器外科の手術手技ガイド」。【悩みの背景分析→術式の簡単な概要→解剖学の解説→手術書レビューによる術式解説→まとめ】という流れで構成し,各項目最後のまとめとして,手術成功のために必要な知識や注意点を箇条書きで簡潔に記載した「指南書」をもれなく掲載。押さえどころが一目でわかるようになっている。先人の知恵と経験を要領よく盗んで効率よく知識・スキルを習得でき,より実践に活かせる1冊。

かかりつけ医のための甲状腺疾患治療ガイド
ガイドラインに沿った甲状腺診療の普及に向けて
専門外なので,どのような検査をすればよいかわからない・・.そんな声におこたえし,甲状腺疾患の診断から治療,管理までをわかりやすく解説した“かかりつけ医”のための書籍です.
日常臨床で甲状腺疾患を疑い,必要な検査をして治療につなげられるよう,甲状腺機能検査や抗体検査など診断に必要な検査の理解,治療法の選択肢,選択基準,治療の終了の中止時期と方法,経過観察の対象,治療中での検査法とその時期,投与薬剤の相互作用や副作用,適正投与のための投与量の決定,抗甲状腺薬の副作用対処法などが書かれ,コンパクトながら盛りだくさんの内容です.

スタンダード検査血液学 第4版Web動画付
●WHO分類改訂第4版(2017)に沿ってアップデートした,ロングセラー好評書の第4版!
●認定血液検査技師,認定骨髄検査技師を目指す技師のためのテキストが,待望の改訂!
●第4版では,WHO分類改訂第4版(2017)に伴い,「第V章 検査結果の評価」造血器腫瘍の項目を中心に変更.その他の章についても最新の情報に基づき全体的にアップデートした.
●付録のWeb動画では,末梢血液検査分野と骨髄検査分野について収載.

高齢者ERレジデントマニュアル
「成人と高齢者は鑑別が異なる。マネジメントも異なる。高齢者は評価に時間がかかる」――。そんな悩みを抱える若手医師に向けて、本書は1)成人との比較論でない高齢者の特徴、2)診断できなくても結局どうするか、3)高齢者でも短時間で評価が可能なテクニックを解説した。救急搬送が年間1万台のERで研修医と日々奮闘している筆者が「高齢救急患者特有の診療・マネジメント」のコツを余すところなく注ぎ込んだマニュアル。
