
全国柔道整復学校協会監修教科書 解剖学 第2版
●2色刷りで図表や大切なポイントの把握が容易になった全面改訂第2版!
●人体の構造と機能を臨床に結びつけて理解できるように編集した(公社)全国柔道整復学校協会教科ガイドライン,国試出題基準にもとづくテキスト.用語を改訂し解剖図を理解しやすいように全編を2色刷りとし柔道整復師業務に役立つよう特に運動系(骨・関節と靱帯・筋)に力点がおかれているのが特徴.

産婦人科の実際 Vol.74 No.7
2025年7月号
「ADC時代」の到来―チソツマブ ベドチン,そしてその先へ
「ADC時代」の到来―チソツマブ ベドチン,そしてその先へ
がん治療の世界では今,抗体薬物複合体(ADC)が注目を集めています。日本では先日,子宮頸癌に対するチソツマブ ベドチンが保険承認されました。また,乳癌や消化器癌で劇的な効果を示し国内外で薬事承認を受けているトラスツズマブ デルクステカンは,生殖器の悪性腫瘍にも高い抗腫瘍効果を示し,来春には日本でも保険承認になると予想されます。さらに,卵巣癌に対するミルベツクシマブ ソラブタンシンはすでに米国FDAで承認されており,日本でも承認に向けた臨床試験が進行中です。本号では,産婦人科医が知っておくべきADCの基礎から最新の臨床応用,特有の有害事象までわかりやすく解説いただきました。

耳鼻咽喉・頭頸部手術アトラス[下巻] 第2版
第一線の執筆陣による手術アトラスの定本、待望の改訂版。耳科、鼻科と関連領域を扱った上巻に続き、下巻では口腔・咽喉頭、頭頸部の手術を網羅。手術の流れに沿い、手技上のポイントをわかりやすく解説する。正確な臨床解剖に基づく多数のイラストにより手術を立体的に理解することができる。術前の注意点やピットフォールなど、安全・確実に手術を完遂するための要点も記載。

臨床雑誌外科 Vol.87 No.5
2025年4月増刊号
消化器外科手術術中・術後トラブルシューティング 私ならこうする!
消化器外科手術術中・術後トラブルシューティング 私ならこうする! 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。
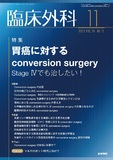
臨床外科 Vol.78 No.12
2023年 11月号
特集 胃癌に対するconversion surgery Stage IVでも治したい!
特集 胃癌に対するconversion surgery Stage IVでも治したい! 一般外科・消化器外科を中心とした外科総合誌。手術で本当に役立つ臨床解剖の知識や達人の手術テクニックを、大きい判型とカラー写真でのビジュアルな誌面で解説。術中・術後のトラブル対処法、集学的治療・周術期管理法の最新情報など、臨床に根ざした“外科医が最も知りたいこと”に迫る。手技を中心にweb動画も好評配信中。 (ISSN 0386-9857)
月刊、増刊号を含む年13冊

臨床外科 Vol.76 No.7
2021年7月発行
特集 若手外科医のための食道手術ハンドブック 良性から悪性まで〔特別付録Web動画付き〕
特集 若手外科医のための食道手術ハンドブック 良性から悪性まで〔特別付録Web動画付き〕 -

ハーバード大学テキスト心臓病の病態生理 第4版
学生が知りたいこと、教官が教えたいことが詰め込まれた正統派テキスト、オールカラーの最新版
ハーバード大学の医学生と循環器内科の教官が共同で作り上げたテキスト、オールカラーに生まれ変わった第4版。心臓の解剖から、生理、病態生理、心臓病の基礎知識、薬物に関してまとめ、心疾患発症のメカニズムを明解に基本から解説する。内容のアップデートに伴い、日本の実情に照らし合わせながら訳や訳注の見直しを徹底。今版でも正しい理解につながるべく、訳者の教育的配慮と熱意がこめられた一冊。
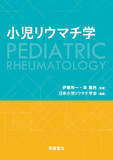
小児リウマチ学
現在の小児リウマチ学を網羅した,小児リウマチ専門医,小児科医から医学系・看護系学生の必携書。〔内容〕関節炎等小児リウマチ性疾患/全身性リウマチ性疾患/血管炎症候群/自己炎症性症候群/慢性疼痛性疾患/治療薬・治療法/社会環境
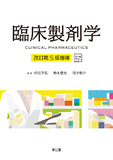
臨床製剤学[電子版付] 改訂第5版増補
製剤に関する内容を基礎から臨床まで一貫して解説した教科書.基礎物理化学・剤形に加え,病院・薬局製剤,注射剤の調整など臨床で必要な内容まで幅広く解説.剤形や製剤機械は実際の写真を掲載し,初めて学ぶ学生でも内容をイメージしやすいよう工夫した.今回の増補では改訂第5版の内容を一部更新したたうえで,電子版付とした.第十八改正日本薬局方に対応.

胆道がん・膵がん・膵NET薬物療法クリニカルガイド
胆道がん・膵がん・膵NET(神経内分泌腫瘍)における薬物療法は,日々新たな展開を見せている.新薬の登場により治療選択肢は広がったが,薬剤の使い分けや副作用対策など,臨床現場では複雑な判断が求められる.本書は,最新薬剤の特徴と適応,副作用への対応はもちろんのこと支持療法,精神・栄養管理にも言及し,現場での実践に直結する知識を提供する.治療に迷う医療者にとって,信頼できる指針となる一冊.
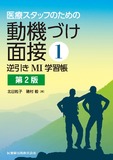
医療スタッフのための 動機づけ面接1 逆引きMI学習帳 第2版
注目の動機づけ面接法(MI)をわかりやすく紹介!
●生活習慣の改善に効果的なカウンセリング技法として注目される「動機づけ面接(Motivational interviewing;MI)」を豊富な面談事例を用いてわかりやすく解説.
●MI学習を通して「人柄が穏やかになる」「自他への優しさが増す」「自己理解が促進される」「専門家としての自己効力感が向上する」「メタ認知が進展する」などの変化を実感.
●臨床家であるあなたが変われば,あなたの周りもそして目のまえの相手も変わります!

集学的治療 脳神経外科手術×放射線治療
【放射線治療が分かると手術がうまくいく!】脳神経外科で行われるあらゆる手術で、前後に定位放射線治療を行う機会が増え、その重要性が増している。ただ実際には、一過性膨大を合併症と誤解したり、再発と放射線壊死の鑑別ができないといった課題が山積している。脳神経外科手術/放射線治療のエキスパートそれぞれが放射線治療前後の正しいアプローチ、観察方法について詳述し相互理解を促進する画期的な1冊。

てんかん専門医ガイドブック 改訂第2版
2017年の国際抗てんかん連盟の分類に依拠し,概念や分類,病因,診断,検査,治療などの総論から,新生児から高齢者までの各年代別の重要なてんかんや遺伝子研究結果に基づく特殊てんかんの最新知識,外科治療などを解説した各論,さらには妊娠,運転,生活支援についても具体的に紹介.
てんかん専門医に必要な知識をできるだけ偏らず,かつ過不足なく編集.さらに過去の専門医試験50問を厳選し解説も収載した,専門医試験を受験する医師のみならず,てんかん診療にかかわるすべての医師必携のガイドブックです.

That's 形成外科 第一集
本書は,カタチ全般何でも治す形成外科の啓蒙書である!! マンガで味わう「わかる!」の快感。こんな形成外科の教科書が欲しかった! 山本健人先生(「外科医けいゆう」京都大学消化管外科)激奨! Xフォロワー3万人,絵を描く美容&形成外科医まさるの形成外科推し活の書,爆誕! 肉球せんせいの「オマケ漫画」と,雑誌「形成外科」好評連載分も併せて収載しました。

≪整形外科看護2022年秋季増刊≫
整形外科の疾患・手術・ケア
【3ステップで知りたいことにすぐアクセス!】
できる整形外科ナースは、ポイントを絞って理解していた!この本で医師が厳選した疾患や患者さんの特徴、手術の目的、ケアで注意すべきところをおさえれば、大事なことがするっと理解できる。疾患・手術・ケアごとに解説しているので、見たいとこだけ見られるのも便利。

腎生検病理診断取扱い規約
本書は腎臓病の分類を病因論から理解するため、日本腎生検レジストリーの新分類に沿って編集した。また、診断の標準化のために診断アルゴリズムなどを用いて診断過程を明瞭化し、国際腎病理協会による最新の病変の定義と診断フォーマット、国際分類を掲載した。病理組織標本から抽出した多くの所見を病理診断として統合し、病態を解釈することで、腎臓病を全身病としてとらえ臨床の現場に生きた情報として還元できるようになる。

「尺度」を使った看護研究のキホンとコツ 第2版
看護研究の精度を上げ、かつスピードアップも実現する「尺度」の使い方を徹底解説
尺度とは何か、既存の尺度からどのような視点で選べばよいのか、尺度を使ってどのように調査・分析したらよいのかなど、尺度を使って看護研究に取り組むための“キホンとコツ”をまとめた好評書籍、待望の改訂版!
第2版では、Web調査の方法や本書の活用事例などを追加し、より読みやすくブラッシュアップしました。

大腸ポリープ診療ガイドライン2020 改訂第2版
日本消化器病学会編集による診療ガイドライン。Mindsの作成マニュアルに準拠し、臨床上の疑問をCQ(clinical question)、BQ(background question)、FRQ(future research question)に分けて記載。CQではエビデンスレベルと推奨の強さを提示。大腸ポリープ診療における、疫学、スクリーニング検査、病態・定義・分類、診断、治療、偶発症と治療後のサーベイランス等について、エビデンスに基づき現時点の標準的な指針を示す。

対話と承認のケア 増補版
ナラティヴが生み出す世界
ナラティヴ・アプローチ探求の金字塔『対話と承認のケア』の増補版!
多くの方に愛読されている『対話と承認のケア──ナラティヴが生み出す世界』の増補版。補遺(ほい)にて、ナラティヴ・アプローチの有効性とこれからの展望を初版から一歩進めて解説。巻末には索引が付き利便性もアップ。研究職のみならず、臨床の医療職にも有用な1冊となって再登場!

看護展望2026年2月号
新人看護師のリアリティショックを防ぐ―教育現場と臨床現場での支援と実践
【特集】
新人看護師のリアリティショックを防ぐ―教育現場と臨床現場での支援と実践
新人看護師が理想と現実のギャップに直面し、とまどいや無力感を抱く「リアリティショック」は、離職や燃え尽きの一因として長年指摘されてきました。その背景には、教育課程での学びと臨床現場で求められる実践力との間に生じる認識や経験のずれ、そして配属初期のサポート体制の不十分さなどがあります。
本特集では、教育現場・臨床現場それぞれが担う役割を整理し、リアリティショックを未然に防ぐ支援のあり方を探ります。教育課程での「現場を意識した支援・アプローチ」や、臨床現場での「配属初期支援」「OJT・Off-JTの工夫」など、実践例を交えて具体的に紹介し、新人看護師が安心して成長できる環境を整えるために、教育と臨床の現場がどのように連携すべきかを考えます。
