
公衆衛生 Vol.84 No.10
2020年10月発行
特集 SNSで防ぐ災害関連死 「Society 5.0」時代のリーダーになる!
特集 SNSで防ぐ災害関連死 「Society 5.0」時代のリーダーになる! -

寝ころんで読む金匱要略
最も有名な漢方の古典は『傷寒論』ですが,学習が進むに従って急性疾患を重視する『傷寒論』だけではなく,実際に漢方薬を処方する機会の多い慢性疾患についてまとめられた『金匱要略』の理解も必要となってきます.本書では,『傷寒論』以上に難解と言われる『金匱要略』を可能なかぎり平易に解説することを目指した古典ガイドブックです.
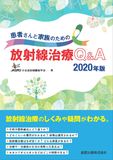
患者さんと家族のための放射線治療Q&A 2020年版
放射線治療は、手術や薬物療法と並ぶ主要ながんの治療法の一つで、保険適用されるがんも増えています。2015年版からの改訂に際し、進歩が著しい機器や治療法はもちろん、「放射線皮膚炎」「被ばくの影響」「セカンドオピニオン」といった患者さんが気になるトピックも充実させました。また、複雑な放射線治療のしくみや実際の治療なども具体的にイメージできるようにイラストを70点以上追加・刷新しました。

救急医学2020年9月号
症例から考える重症外傷診療;あなたならどうする⁉
症例から考える重症外傷診療;あなたならどうする⁉ 重症度判断、輸液・輸血戦略、止血法の選択、銃創・爆傷診療…重症外傷診療の“悩みどころ”について、第一線の救急医・施設ではどのように考え・判断しているのか、症例ベースに徹底解説!

臨床画像 Vol.36 No.10
2020年10月号
【特集】透析患者の画像診断
【特集】透析患者の画像診断
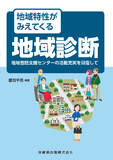
地域特性がみえてくる地域診断 地域包括支援センターの活動充実を目指して
●確かなデータに基づく地域特性の把握は,安心して住み続けることのできる地域づくりの第一歩!
●「地域包括ケアシステム」では,高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるために,医療,介護,福祉サービスが一体化して提供される地域づくりが求められている.
●システムの中核を担う地域包括支援センターの職員が一丸となって「地域診断」を活用すれば,より地域特性や実態を反映させた地域づくりが可能となる.
●地域診断を通じて,地域包括支援センターがどのようにして地域づくりを行っていったのかについて,実際の地域包括支援センターの活動をもとにした事例を紹介する.

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.92 No.11
2020年10月発行
特集 Voiceを診る 音声障害を知ろう!〔特別付録Web動画〕
特集 Voiceを診る 音声障害を知ろう!〔特別付録Web動画〕 編集室より:本号では関連する動画を配信しています。ぜひご覧ください。
※ 配信・閲覧期限:発行後3年間
※ ファイルは予告なしに変更・修正,または配信を停止する場合もございます。あらかじめご了承ください。

The Liver Cancer Journal Vol.11 No.2
2019年10月号
座談会 分子機序に基づく肝癌の治療
座談会 分子機序に基づく肝癌の治療
肝癌に関する最新の研究動向から実地診療におけるノウハウまで,研究者・臨床家の叡智を結集して,質の高い最新情報を提供する日本初の肝癌に特化した学術専門雑誌。

The Liver Cancer Journal Vol.11 No.1
2019年3月号
座談会 肝癌モデルの展望
座談会 肝癌モデルの展望
肝癌に関する最新の研究動向から実地診療におけるノウハウまで,研究者・臨床家の叡智を結集して,質の高い最新情報を提供する日本初の肝癌に特化した学術専門雑誌。
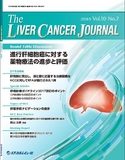
The Liver Cancer Journal Vol.10 No.2
2018年9月号
座談会 進行肝細胞癌に対する薬物療法の進歩と評価
座談会 進行肝細胞癌に対する薬物療法の進歩と評価
肝癌に関する最新の研究動向から実地診療におけるノウハウまで,研究者・臨床家の叡智を結集して,質の高い最新情報を提供する日本初の肝癌に特化した学術専門雑誌。
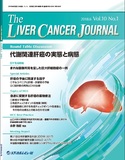
The Liver Cancer Journal Vol.10 No.1
2018年6月号
座談会 代謝関連肝癌の実態と病態
座談会 代謝関連肝癌の実態と病態
肝癌に関する最新の研究動向から実地診療におけるノウハウまで,研究者・臨床家の叡智を結集して,質の高い最新情報を提供する日本初の肝癌に特化した学術専門雑誌。
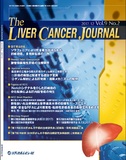
The Liver Cancer Journal Vol.9 No.2
2017年12月号
座談会 脈管侵襲陽性肝癌の治療限界
座談会 脈管侵襲陽性肝癌の治療限界
肝癌に関する最新の研究動向から実地診療におけるノウハウまで,研究者・臨床家の叡智を結集して,質の高い最新情報を提供する日本初の肝癌に特化した学術専門雑誌。
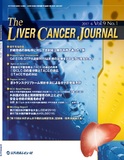
The Liver Cancer Journal Vol.9 No.1
2017年6月号
座談会 Gd-EOB-DTPA造影MRIは肝癌の診療をどのように変えたか?
座談会 Gd-EOB-DTPA造影MRIは肝癌の診療をどのように変えたか?
肝癌に関する最新の研究動向から実地診療におけるノウハウまで,研究者・臨床家の叡智を結集して,質の高い最新情報を提供する日本初の肝癌に特化した学術専門雑誌。

乳房超音波診断ガイドライン 改訂第4版
用語の定義、検査法、判定法等の標準化のため刊行され改訂を重ねている、乳房超音波診断における指針を示す定本。今改訂では、WHO分類・日本乳癌学会分類の改訂を反映して病理の記載をアップデート。また、エラストグラフィやドプラ法、造影超音波の評価等を充実させた。検診と精査における診断上の考えかたの違いをより明快に記載し、日常診療においてさらに使いやすい内容となっている。

腎と透析88巻3号
【特集】Cl-:電解質のクイーン
【特集】Cl-:電解質のクイーン

消化器内視鏡32巻3号
【特集】胆膵内視鏡治療におけるトラブルシューティング
【特集】胆膵内視鏡治療におけるトラブルシューティング

小児内科52巻3号
【特集】小児神経学―現在から未来へ
【特集】小児神経学―現在から未来へ

小児外科52巻3号
【特集】小児外科における多診療科連携
【特集】小児外科における多診療科連携

周産期医学50巻3号
【特集】周産期医療と細菌叢
【特集】周産期医療と細菌叢

JOHNS36巻3号
【特集】日常診療に活かせるアレルギーの知識
【特集】日常診療に活かせるアレルギーの知識
