
J-COSMO Vol.1 No.5
2019年12月号
【Special Topic】私の一冊
【Special Topic】私の一冊 臨床医の世界に新たなCommon Senseを提供する『J-COSMO(ジェイ・コスモ)』1巻5号.
ジェネラリスト・スペシャリストの垣根を越えて,すべての臨床医を応援する連載中心の医学雑誌です.
今回のSpecial Topicでは,編集委員がそれぞれの「私の一冊」を紹介します.
登場するのは,様々なジャンルからチョイスされた珠玉の著作ばかり.年末年始のお供にいかがでしょうか.
今号開始の新連載は「チーフレジデント養成講座」(野木真将,小杉俊介)です!

臨牀透析 Vol.35 No.13
2019年12月号
緊急特集「長期にわたる停電・断水への対策―大型台風による広域災害」特集「透析生活をサポートする-各職種ができることと限界」
緊急特集「長期にわたる停電・断水への対策―大型台風による広域災害」特集「透析生活をサポートする-各職種ができることと限界」
緊急企画では,ライフラインおよび情報連絡網の確保,電子カルテや患者情報の管理,各透析治療における対処法,昨年の台風24 号による広域停電の経験などを取り上げ,実際に災害を経験されたエキスパートの先生方に執筆いただき,これまで想定していなかった風水害によるライフラインの長期途絶に対し,透析施設としてどう対処すればよいのかをお書きいただきました.
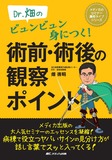
≪メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ≫
Dr.畑のビュンビュン身につく! 術前・術後の観察ポイント
【大人気セミナーを本でも楽しめる!】
メディカ出版の人気セミナー1日分のエッセンスを、話し言葉そのままに読みやすく再現! 外科ドクターがナースに看てほしいポイントをやさしく解説する。手術患者のリスクから万全の準備をする力、異常を察知し予防する力がつき、経過観察でよいのか緊急連絡が必要な状況かの判断にもう迷わない、臨床判断能力upに役立つ一冊。
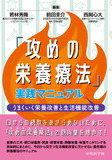
「攻めの栄養療法」実践マニュアル
うまくいく栄養改善と生活機能改善
「口からの摂取をあきらめない」ための、「攻めの栄養療法」=体重(主に筋肉量)を増やす栄養療法を実践するために必要な、食事の工夫・経口栄養剤・間食・経管栄養・静脈栄養・栄養モニタリングを具体的にまとめた,病棟だけでなく外来担当医師にも知る必要性がある栄養療法の今日から使える臨床で役立つマニュアル.
糖尿病・CKD・認知症・経済的ゆとりがないなど,ケース別対処法も紹介.
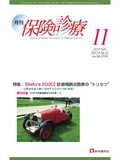
月刊/保険診療 2019年11月号
特集/Before 2020 診療報酬点数表の“トリセツ”~点数表を最大限に活用するための360°解説~
特集/Before 2020 診療報酬点数表の“トリセツ”~点数表を最大限に活用するための360°解説~
Part1 診療報酬点数表360°解説…①診療報酬の決定方法と改定時の情報入手方法,②診療報酬の評価体系,③点数表の特徴と構造,④点数表の読み解き方と最適な使い方,⑤「My点数表」の作り方,⑥診療報酬の変遷と2020年改定――などを総まとめします。
Part2 【座談会】点数表を最大限に活用する…点数表をどう習得するか,どう読み解くか,どう活用するか,2020年改定をどう読むか――など,点数表に精通したプロフェッショナルの知識とスキルを凝縮した座談会。
Part3 【事例】診療報酬点数表の活用事例…レセプトの査定減点事例や請求もれ事例,施設基準の検討事例,DPC事例,保険外併用療養費,医療と介護の給付調整――などの事例につき,診療報酬点数表・DPC点数表・薬価基準・介護単位数表を活用して解決する工程とノウハウをわかりやすく解説します。
連載特集 2020年診療報酬改定を読み解く3…中医協・入院医療等の調査・評価分科会の山本修一氏(千葉大学医学部附属病院長)に,改定の重点課題と議論の方向性を伺います。

訪問看護と介護 Vol.24 No.12
2019年12月発行
特集 どうすりゃいいんだ、横綱級困難ケース 何が、誰が「困難」にしていたのか
特集 どうすりゃいいんだ、横綱級困難ケース 何が、誰が「困難」にしていたのか 医学書院から発行された書籍『精神疾患をもつ人を、病院でない所で支援するときにまず読む本-“横綱級”困難ケースにしないための技と型』(小瀬古伸幸著)が反響を呼んでいます。「くり返し要求してくる」「要求がエスカレートしていく」「頻回に電話してくる」「こだわりが強く怒りっぽくクレームが多い」「家族関係の不和(虐待的な関係性)を抱えている」-。横綱級困難ケースとは、疾患の重症度ではなく、こうした本人またはその家族との対人関係的な困難さにより、一筋縄ではいかないケースを指した言葉。……誰しも思い当たるものがあるのではないでしょうか?今号は、そんな横綱級困難ケースを考えます。困難さを生む要因は何なのか。誰が困難にしてしまっているのか。現場の試行錯誤の足跡とともに、くじけず、適切な対応で乗り越えていくためのヒントを紹介します。
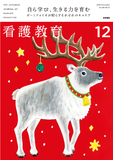
看護教育 Vol.60 No.12
2019年12月発行
特集 自ら学び、生きる力を育む ポートフォリオが照らすそれぞれのキャリア
特集 自ら学び、生きる力を育む ポートフォリオが照らすそれぞれのキャリア アクティブ・ラーニング、教育のICT化など、世界的に教育に大きな変革がうたわれています。そこには、一斉授業による、すべての学生へ同質の教育を実施するあり方への見直しが通底しています。価値観や働き方がさらに多様化していく時代において、自らで目標を定め、個々人で学びながら生きていく力が求められています。現在、そうした個人の学びを支えるものとして、初等・中等・高等すべての教育において、ポートフォリオに注目が集まっています。これまでも、看護基礎教育では、さまざまな形でポートフォリオが活用されてきました。今特集ではあらためて、個々の学びを支えるポートフォリオの教育的意義を確認し、豊かな実践例をご紹介します。

理学療法ジャーナル Vol.53 No.12
2019年12月発行
特集 装具の臨床
特集 装具の臨床 理学療法士が,個々の装具名称・特徴と適応・構造などの装具一般について学ぶのは,装具学であ る.装具を用いる個々の疾患の病態や治療は,別の臨床医学科目で学ぶ.しかし理学療法の臨床では 別々の知識としてではなく,患者さんの病態と数ある装具をマッチさせ治療戦略にどう生かすかが求 められる.在宅・地域では,装具は患者さんの生活の道具であり環境やライフスタイルとも関連が深 い.本特集では,病院から生活領域まで,理学療法士が装具をどう捉えどのようにかかわるのか,現 状と可能性・課題を考える.

臨床婦人科産科 Vol.73 No.12
2019年12月発行
今月の臨床 産婦人科領域で話題の新技術 時代の潮流に乗り遅れないための羅針盤
今月の臨床 産婦人科領域で話題の新技術 時代の潮流に乗り遅れないための羅針盤 -

臨床整形外科 Vol.54 No.12
2019年12月発行
誌上シンポジウム 患者の満足度を高める関節リウマチ手術
誌上シンポジウム 患者の満足度を高める関節リウマチ手術 -

臨床外科 Vol.74 No.13
2019年12月発行
特集 見せます!できる外科医のオペ記事 肝胆膵高度技能医は手術をこう描く
特集 見せます!できる外科医のオペ記事 肝胆膵高度技能医は手術をこう描く 手術記事を書くことは外科医の日常業務の一つであるが,同時に外科医教育の要諦の一つである.誰でも若いときには2~3時間かけて手術書や先輩の手術記事を参考にしながら夜中まで書いたものである.現在では,以前に比べると手術記事はだいぶ簡素化されていると聞く.しかし領域によっては,専門医受験に手書きの手術記事が必要な分野もある.本特集では,日本肝胆膵外科学会高度技能専門医を取得したまさに脂の乗った若手外科医,指導医による手術記事を特集した.手書きもあればiPadで書かれたものもある.要はいいとこ取りで自分のスタイルを確立してほしい.手術記事を書くのに要した時間は自分を裏切らない.本特集が専門医をめざす若手外科医の役に立てば幸いである.

BRAIN and NERVE Vol.71 No.12
2019年12月発行
特集 小脳と大脳 Masao Itoのレガシー
特集 小脳と大脳 Masao Itoのレガシー 2018年12月18日,伊藤正男先生が永眠された。伊藤先生は小脳の「長期抑圧」などを発見 したことで知られるが,小脳研究にとどまることなく,小脳と大脳の関連性にも言及され, 国内外の研究機関の設立に携わるなど,さまざまな方面に多大な業績を遺された。これらの レガシーを紐解くことは今後の神経科学・脳科学の課題を明らかにするのではないだろうか。 次の時代のブレークスルーを生み出すきっかけとなることを祈念して本特集号を贈る。

総合診療 Vol.29 No.12
2019年12月発行
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療
特集 困っている“あなた”に届く 認知症診療 医師にとって認知症診療は、治療している実感が持ちにくく、また診るときのコツや患者さんへの言葉かけもよくわからず、無力感や苦手意識を感じてしまいがちなテーマと言えるでしょう。本特集では、どうすれば「患者さんに届く」診療ができるのか(=診療・マネジメントがうまくいくか)、具体的なCaseを提示してどんな診療や対応を行えばよいのかを考えながら、“あなた”(=患者さん、そして読者のあなた)に届く認知症診療のノウハウと最新トピックスをお届けします!

生体の科学 Vol.70 No.6
2019年12月発行
特集 科学と芸術の接点
特集 科学と芸術の接点 -

PT・OTのための画像評価に基づく疾患別ケーススタディ
これだけは知っておきたい画像の基礎知識と画像評価に基づく臨床判断の具体的なポイントがわかる !
・実際の画像から得られる情報を簡潔に解説
・過去のPT・OT国家試験の出題傾向を見据えた画像評価のポイントを提示
・運動器系疾患、神経系疾患、内部疾患のカテゴリに大別し、臨床でたびたび遭遇する疾患を厳選
・画像所見に基づく担当医の症例解説(「病態」「治療」「画像をみるポイント」「予後予測」)が示され、各病期におけるセラピストの介入(「評価」「課題」「目標」「プログラム」「臨床判断」「経過」「連携のポイント」「今後の課題・反省点」)を詳述
・各病期における理学療法経過・作業療法経過を併記したわかりやすい紙面構成
医療関連職種がそれぞれの立場で症例を追った"臨床の現実”と、画像情報に基づく臨床判断のケーススタディが詰まった1冊 !

Modern Physician Vol.39 No.12
2019年12月号
【今月のアプローチ】ざっくり学ぶ身近な発達障害(症)
【今月のアプローチ】ざっくり学ぶ身近な発達障害(症)
発達障害(症)の概念・診断は変化している。
本号では発達障害(症)の生物学的背景から最新治療までを網羅。
ADHDとASDへの臨床介入ポイント
ADHDの新薬物療法は必読。

INTESTINE Vol.23 No.6
2019年11・12月号
全身性疾患における腸管病変-腸管ベーチェット病とその鑑別疾患
全身性疾患における腸管病変-腸管ベーチェット病とその鑑別疾患
全身性疾患において腸管病変を把握することは診断のみならず予後予測と治療方針の決定に重要である.腸管ベーチェット病の診断はベーチェット病患者の予後予測と治療方針の決定に大きく影響する.(序説より抜粋)
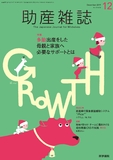
助産雑誌 Vol.73 No.12
2019年12月発行
特集 多胎出産をした母親と家族へ必要なサポートとは
特集 多胎出産をした母親と家族へ必要なサポートとは 三つ子を出産した母親が一人の児を殺めてしまった事件で,2019年3月,執行猶予無しの実刑判決が下されたというニュースが話題となりました。この事件をきっかけに,多胎出産をした母親と家族への支援の必要性について,さまざまな議論がなされたと思います。しかし一方で,多胎出産と育児への支援や,地域でのケア体制などがなかなか周知されておらず,本当に支援を必要としている母親と家族に届いていないのが実情です。本特集では,多胎の妊婦,多胎児を出産した母親に対するケア・支援を行っている団体,施設の取り組みを紹介し,追いつめられる母親と家族を一人でも救うために,助産師をはじめとする専門職ができる支援やケアについて考えます。

日本整形外科学会診療ガイドライン
脊柱靱帯骨化症診療ガイドライン2019
脊柱靱帯の骨化により脊柱管が狭小化し脊髄症や神経根症などを引き起こす頚椎後縦靱帯骨化症・胸椎後縦靱帯骨化症・胸椎黄色靱帯骨化症を包括した最新のガイドライン。近年の基礎・臨床両面の新しい知見を反映して作成され、エビデンスに立脚し、患者の希望や日本の医療制度に即した診療指針を提供する一冊。

Heart View Vol.23 No.13
2019年12月号
【特集】心筋症のいまを識る!
【特集】心筋症のいまを識る!
