
総合リハビリテーション Vol.47 No.9
2019年09月発行
特集 回復期リハビリテーション病棟退院後の戦略 生活機能の向上をめざして
特集 回復期リハビリテーション病棟退院後の戦略 生活機能の向上をめざして 日本のリハビリテーションの特徴の 1 つとして,比較的長期の入院リハビリテーションにより達成さ れる高い機能・日常生活動作(activities of daily living;ADL)の達成が挙げられます.その一方,回復期 リハビリテーション病院退院後にその機能・ADL を維持することができない,難しいという不安を患者 が感じていることも指摘されています.そこで今回は,回復期リハビリテーション病院退院後に,機能 や能力を高く保つ,もしくは在宅でさらに改善させていくために,入院中から何を行うべきか,外来診 療や在宅サービスとどう連携していくかなどについて,それぞれの立場からご解説いただきました.

日本内視鏡外科学会雑誌 Vol.24 No.5
2019年09月発行
-

Modern Physician Vol.39 No.9
2019年9月号
【今月のアプローチ】処置・検査のための安全な鎮痛・鎮静管理
【今月のアプローチ】処置・検査のための安全な鎮痛・鎮静管理 2018年に米国麻酔学会が公表したガイドラインに準拠し、各診療科における安全な鎮痛・鎮静管理のポイントを解説。患者への苦痛を減らしより安全な処置・検査へ

最新 糖尿病診療のエビデンス 改訂版
EBM(根拠に基づいた医療)の考え方に基づき、2型糖尿病の薬物治療や生活習慣改善に関する最新の知見を紹介。
EBM(Evidence-Based Medicine)界の若手ホープである著者が、日々の糖尿病診療で生じる臨床的な疑問について、最新のエビデンスと診療ガイドラインをひもときながら、わかりやすく解説します。
『日経メディカル Online』で好評を博した連載(臨床講座)をベースに、初版を2015年に発行。今回は、2019年6月までに発表された大規模臨床試験の結果や新しい糖尿病診断基準、診療ガイドラインの紹介を加え、全面刷新しました。
SGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬がなぜ今、注目されているのか、包括的なリスク管理はどの程度の意義があるのか、糖質制限の長期的な評価など、臨床現場で役立つ数々のトピックスを、EBMの切り口で明快に解説。
研修医や糖尿病を専門としていない全ての臨床医を中心に、糖尿病診療指導士や看護師、管理栄養士、薬剤師など、糖尿病患者の治療・指導に携わる全ての医療専門職と、製薬会社のMR(医薬情報担当者)を主たる読者対象としています。

フローチャートによるトリアージ実践マニュアル
その時、薬剤師はどのように判断するか
既刊「薬剤師のためのトリアージ実践ガイド」の応用編。 本書は、来局者の病状を適切に把握し、病院を受診したほうがいいのか、あるいはOTC薬(一般薬)によるセルフメディケーションでいいのかを、判断するためのノウハウをわかりやすく解説します。 「どのように思考すれば、患者にフィットするトリアージシステムになるか?」、「いかにして、医師の診断理論を薬剤師用に翻訳するか?」にポイントをおき、「問診と視診で重症度と緊急度を判断する方法」がフローチャートでわかる構成となっています。これからの薬局薬剤師に求められる「患者をみる力」と「トリアージ」の能力を養う実践的マニュアルです。

≪京大人気講義シリーズ≫
健康・医療の情報を読み解く 第2版
健康情報学への招待
京都大学で著者が受け持つ人気講義「健康情報学」を活字化。ビッグデータの時代、あふれる情報との上手な付き合い方とは?疫学やEBMの考え方をもとに、身近な実例の紹介を通じて健康や医療の情報の読み解き方をわかりやすく解説します。 本書の知識を応用すれば、膨大なデータから各種の健康・医療情報を適切に利用し、意思決定や問題解決、コミュニケーションに役立てることができるようになります。

臨床放射線 Vol.64 No.4
2019年4月臨時増刊号
【特集】乳癌の診断と治療
【特集】乳癌の診断と治療 診断編では各モダリティの読影ポイントを詳説し,治療編では化学療法から外科療法,放射線療法まで解説!超音波画像などはWEB動画とも連動!
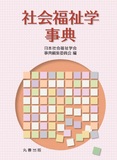
社会福祉学事典
社会福祉という領域は、超「少子高齢社会」の現代日本では、市場の関心も高く、教育や保健医療などと並んで、脱工業社会時代のリーディング・インダストリーとしてその存在意義をますます大きくしています。 本書は、この社会福祉を実際に手がけていく上で必要な予備知識や方法上のガイドライン、イシュー(論点・争点)までを網羅し、実務レベルでさまざまに社会福祉に関わる人びとが、現場に即して活用できるように構成された中項目事典です。

臨床場面でわかる!くすりの知識 改訂第2版
ナースが出会う14の場面,134の疑問
くすりに関する14の臨床場面とそこから生まれる134の疑問をもとに、看護に活かせるくすりの知識を解説する好評書の改訂版。多くのナースが直面する「現場の疑問」を、イラスト・薬剤写真を豊富に用いて、ていねいに掘り下げやさしく解説。禁忌事項・必須知識に重要度のランクづけがあるためメリハリをつけて理解できる。改訂にあたり、薬剤や手技、機器の情報をすべてアップデートした。読んで楽しい、持ってて安心の「明日失敗しない」ための実践書!

LiSA Vol.26 No.9 2019
2019年9月号
徹底分析シリーズ:補助循環/症例カンファレンス:抗血小板療法中透析患者のY-graft置換術/快人快説:呼吸のモニタリング
徹底分析シリーズ:補助循環/症例カンファレンス:抗血小板療法中透析患者のY-graft置換術/快人快説:呼吸のモニタリング 徹底分析シリーズ:補助循環
症例カンファレンス:抗血小板療法中透析患者のY-graft置換術
快人快説:呼吸のモニタリング

臨床放射線 Vol.61 No.11
2016年10月臨時増刊号
【特集】Multi-Organ Disease 臓器からアプローチする全身疾患
【特集】Multi-Organ Disease 臓器からアプローチする全身疾患 障害が多臓器にまたがる疾患・病態・合併症・感染症について,読影ポイントを解説しています。
希少疾患も含め多くの全身性疾患を取り上げており,日常診療のために読影室に備えておきたい1冊です。

臨床放射線 Vol.62 No.11
2017年10月臨時増刊号
【特集】泌尿器の画像診断と放射線治療
【特集】泌尿器の画像診断と放射線治療 泌尿器疾患の診断・治療方針決定・治療効果判定において,画像検査は重要な役割を担っています。
各疾患の画像所見を解説する各論に重点を置き,核医学(6項目)と放射線治療(9項目)についても取り上げています。

作業療法の話をしよう
作業の力に気づくための歴史・理論・実践
「作業療法」とはいったい何だろう。本書は、作業療法学生や新人作業療法士を中心に、経験のある作業療法士、そして作業療法を知りたい方々に向けて、これまで偉人たちが紡ぎ上げてきた作業療法の歴史を踏まえたうえで、現代から将来への作業療法のビジョンを明確に提示する。作業療法らしい物語25篇、さらには日本の作業療法を創り上げた作業療法士による座談会も収載。作業の力に気づき、作業療法の魅力を発信したくなる1冊。

日本腎不全看護学会誌 Vol.21 No.2
2018年09月発行
-
- 一般社団法人日本腎不全看護学会編集・刊行の学会誌。本号は、実践報告1本、委員会報告3本、DLN事例報告1本を掲載

精神看護 Vol.22 No.5
2019年09月発行
特集 感情・関係・状況を可視化できるグラフィックレコーディングのインパクト なぜこのツールは希望を生み出すのか
特集 感情・関係・状況を可視化できるグラフィックレコーディングのインパクト なぜこのツールは希望を生み出すのか ホワイトボードに描くという光景は、べてるの家が始めた「当事者研究」と切り離せないものです。最近「メタ認知」という言葉をよく聞きますが、メタ認知は、本人にとっての現実を一緒にながめてくれる、もう1人の仲間がいて、初めて発生するのかもしれないということです。1人でトレーニングできるようなものではなくて、外在化は2人から起きる、というのが、べてるの家のホワイトボードの実践が教えてくれたことかなと思っています。本日は、そんな大事なホワイトボードの役割が、グラフィックレコーディングを学ぶことによって補完・強化されるのではないかという期待をもって、このカンファレンスを開きました。このスキルをみんなで学び、高めるための会にできればと思います。よろしくお願いいたします。

看護教育 Vol.60 No.9
2019年09月発行
特集 看護教育における効果的なOSCEの実施
特集 看護教育における効果的なOSCEの実施 シミュレーション教育は、技能を身につけるために有用です。特に、失敗が許されない臨床とは異なり、失敗から学ぶことができる利点があります。また、看護領域によっては、実習で受け持つ機会が少ない対象の看護をすることもできるでしょう。一方で、学生同士や顔見知りを対象とした学習の場合、リアリティに欠けたり、評価基準を一定に保つのがむずかしいといった課題もあります。そこで、模擬患者などを利用して臨床能力の客観的評価を行うのがOSCEです。医師・歯科医師・薬剤師などの養成課程(6年制)においては、臨床実習に進む前にOSCEに合格することが求められます。看護基礎教育においても授業にOSCEを導入している施設は増えていますが、制度として規定されたものではないため、その内容や取り組みはまちまちです。今回の特集では、大学や専門学校での取り組みを紹介するとともに、看護師に求められる臨床能力について確認することで、OSCEをより一層効果的なものにする方法を考えます。

検査と技術 Vol.47 No.10
2019年10月発行
-
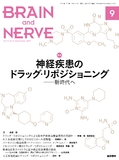
BRAIN and NERVE Vol.71 No.9
2019年09月発行
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング 新時代へ
特集 神経疾患のドラッグ・リポジショニング 新時代へ ドラッグ・リポジショニング(DR)の手法と2004年の薬事法改正により,ア カデミアによる新薬開発が可能となった。現在の医師主導治験ではほとんど がこの手法を用いており,偶然に予想外のものを発見することから始まり, 近年ではiPS細胞や人工知能を用いた革新的な手法が登場している。神経疾 患におけるDRの新時代とも言える現状を,創薬の最前線から報告する。

発達心理学
健やかで幸せな発達をめざして
発達心理学は、人間が受精してから死に至るまでの心理学の諸問題を研究する学問です。 本書では、QOL(quality of life:生活の質、人生の質)を追求することをテーマに、前半では、発達に関わる問題=性の問題、いじめ・不登校・ひきこもり、心の病(精神医学的問題)、自殺、発達のつまづき、虐待・トラウマ、激変するメディア環境と、近年興味関心をひいているトピック・課題を中心に取り上げます。 後半では胎児期、新生児期、乳児期、幼児期、児童期、青年期、成人期前期、成人期後期、高齢期について年代順にそれぞれの専門家が解説します。

研究的思考法
想いを伝える技術
思考を整理し アカデミックに書く ! 話す !
あらゆるコミュニケーションに役立つ 伝えるための思考法
研究上の作法を利用して、自分の考えをクリアーに伝える方法を解説した書。学術文書の基本であるパラグラフ・ライティングの作法に基づき、「最初に意見・主張を示し、後に根拠を述べる」スタイルで伝える意義を解説。さらに、研究法の観点から「根拠となるデータを正しく吟味する方法」を紹介。レポートや論文の文書作成、プレゼンのスライド作成などに対応できる思考法・表現技法を学ぶことができる。つまずきやすいポイントは、例文を使って丁寧に解説。「自分の意見がなぜか人に伝わらない」と感じている人にとって、文章力・プレゼン力アップの第一歩を後押ししてくれる。
