
服部安子が応える! 認知症ケアの真髄
・認知症ケアに関するあらゆる場面・疑問をピックアップし,全5章97項目のQ&A形式で解説
・現場で30余年にわたり積み上げた,著者のゆるぎない信念と圧倒的な経験から紡ぎ出される珠玉のアドバイスの数々。かつて、これほどの認知症ケアのための手引き書があったでしょうか?
・認知症の医療・介護に携わる全ての方々に読んでいただきたい、これこそ真のバイブル!

臨床泌尿器科 Vol.73 No.10
2019年09月発行
特集 腎移植臨床の進歩 集学的治療における泌尿器科医の役割を再考する
特集 腎移植臨床の進歩 集学的治療における泌尿器科医の役割を再考する -

臨床皮膚科 Vol.73 No.10
2019年09月発行
-

精神医学 Vol.61 No.9
2019年09月発行
特集 高齢者の精神科救急・急性期医療
特集 高齢者の精神科救急・急性期医療 -

循環器ジャーナル Vol.67 No.4
2019年10月発行
特集 冠動脈疾患のリスク管理のフロントライン
特集 冠動脈疾患のリスク管理のフロントライン -

胃と腸 Vol.54 No.10
2019年10月発行
主題 知っておきたい特殊な食道腫瘍・腫瘍様病変
主題 知っておきたい特殊な食道腫瘍・腫瘍様病変 -

公衆衛生 Vol.83 No.10
2019年10月発行
特集 摂食障害の理解と対応
特集 摂食障害の理解と対応 -
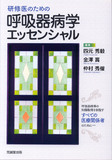
研修医のための呼吸器病学エッセンシャル

オンコロジークリニカルガイド
肺癌化学療法 第2版
肺癌のKey Drugsやエビデンスレベルの高い薬物療法の最新知見をコンパクトに解説.また,国内外の大規模臨床試験や米国臨床腫瘍学会ASCOなどの情報も盛り込んだ.本分野の第一線で活躍する医師がポイントを体系的にわかりやすく整理.肺癌領域のプロフェッショナルを目指す医療従事者に必携の書.

実験医学 Vol.37 No.16
2019年10月号
【特集】AIとがん研究 その妥当性、有効性
【特集】AIとがん研究 その妥当性、有効性 AIによるビッグデータ解析でがんの本質を見抜く!ゲノム・細胞画像・医用画像・文献情報などの解析にAI技術を用いた最新の実例をご紹介.研究に,診断に,AIを取り入れようか迷っている方必見です.

臨床雑誌内科 Vol.124 No.3
2019年9月増大号
内科医に求められる他科の知識
内科医に求められる他科の知識 1958年創刊。日常診療に直結したテーマを、毎号"特集"として掲載。特集の内容は、実地医家にすぐに役立つように構成。座談会では、特集で話題になっているものを取り上げ、かつわかりやすく解説。

臨床雑誌外科 Vol.81 No.10
2019年9月号
Innovativeな大腸癌診断・治療
Innovativeな大腸癌診断・治療 1937年創刊。外科領域の月刊誌では、いちばん長い歴史と伝統を誇る。毎号特集形式で、外科領域全般にかかわるup to dateなテーマを選び最先端の情報を充実した執筆陣により分かりやすい内容で提供。一般外科医にとって必要な知識をテーマした連載が3~4篇、また投稿論文も多数掲載し、充実した誌面を構成。

臨牀消化器内科 Vol.34 No.11
2019年10月号
胃癌診療2019-現状と課題
胃癌診療2019-現状と課題
胃癌は,本邦におけるがん対策において,最重要がん種の一つである.しかし,若年者,壮年者におけるH.pylori 感染率の急激な低下に伴い,すでに胃癌罹患数,死亡数は減少に転じている.
胃癌対策においては,高齢者胃癌にいかに対峙し,生活の質をも意識した,さらなる死亡数減少を目指していくかが大きな課題と考えられる.
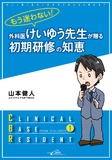
もう迷わない!外科医けいゆう先生が贈る初期研修の知恵
けいゆう先生のペンネームで知られ、SNSやウェブメディアの連載などで活躍中の山本健人先生が、医学生や研修医向けに書き下ろしたのが本書です。編集部の人間が読んでも「なるほど! 」と唸る、さすがの切り口の文章が満載。消化器外科医の日常を通し、「初期研修で学ぶべきこと」が余すことなく伝えられています。これから初期研修を受ける医師にとっては必携の書となるでしょう。本書が贈る「知恵」が初期研修を実りあるものにしてくれると確信しております。
以下、本書「はじめに」より
若手医師が勉強法やキャリアについて情報収集したいと思った時、アクセスできる情報ソースは意外に限られています。インターネットで検索したり、書店に行って本を探したりしても、自分に役立つ情報はなかなか見つけにくいものです。私は、こうした問題意識を常に持ってキャリアを歩む中で、できるだけ多くの後輩に自分の学んだことを伝えたい、と考え続けてきました。 (中略) 確かにここに書いたのは、一介の若手外科医の私見に過ぎないでしょう。しかし私はこの書籍に、これまで自分が医師として、外科医として、毎日頭をひねって考えてきたことの全てを書きました。読んでいただければ、「今すぐにでも実践したい」と思うことがきっとたくさんあると思います。もしそう思ったら、この本を閉じた瞬間から、動き始めてください。あなたのこれからの人生で、今日が一番若い日です。

診断推論 奥義伝授
◆臨床経験を積んでいけば、直感的に診断名がひらめくことは増えていきます。しかし、どうしても分析的・系統的なアプローチが必要な場面もでてきます。非特異的な訴え…なじみのない訴え…複数の箇所に出現している所見…。そんなとき、「どう推論を組み立てて」いけばいいのか?
◆その悩みにお答えします!すでに一般的になっている「診断推論」の弱点を補強、疑問を掘り下げて、野口善令先生が解説していきます!
◆本書では「直感を鍛える」「推論を深化させる」を大きなテーマとしています。無意識で働く「直感」をどう鍛えるのか?その方法も、もちろん紹介しております。ぜひ本書で、一歩進んだ「上級編」の診断推論を始めてください!

食品衛生学 改訂第2版
改正食品衛生法に対応して改訂!食品衛生関連の法律・制度から食中毒・有害物質の科学的な知識までわかりやすく解説!国試対策はもちろん食品衛生監視員・食品衛生管理者養成校の教科書としても役立つ1冊.

関節リウマチ看護ガイドブック
共同意思決定をめざしたトータルケアの実践
病態・診察・治療等の基本知識から,現場を熟知したエキスパートによる実践的ケアのポイントまで,エビデンスにもとづいたRA看護のエッセンスを新書サイズに凝縮.患者さん視点のチーム医療実践に必須の一冊です.

詳述!学べる・使える 水・電解質・酸塩基平衡異常Q&A事典
水電解質・酸塩基平衡異常の臨床に関する発表された“すべての論文・書籍等をすべて知る”,つまり,徹底した先行研究検討を行い,水電解質・酸塩基平衡異常の臨床に関する教科書的とされる知識の正確度について再検討を行っている著者が,腎生理学の解説書と,診断・治療アルゴリズムが主体となっている従来の水電解質・酸塩基平衡異常の臨床の解説書との橋渡しを行うことを目的に執筆。テーマを徹底的に細分化して記述しているため,効率的に必要な情報にアクセスできます。

運動器エコー指南書
運動器のプロフェッショナルに贈るエコー指南書
エコーによる病態の理解と、エコーガイド下注射、ハイドロリリースの手技について詳しく解説しました。
【動画40本収録】
執筆者:
髙橋 周 東あおば整形外科
松崎正史 ソニックジャパン株式会社
服部惣一 亀田メディカルセンター・スポーツ医学科
宮武和馬 横浜市立大学附属病院整形外科
中島祐子 広島大学運動器超音波医学
中瀬順介 金沢大学整形外科
笹原 潤 帝京大学スポーツ医科学センター
林 典雄 運動器機能解剖学研究所
山口睦弘 株式会社ソノジー
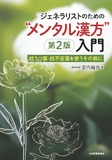
“メンタル漢方”入門 第2版
向精神薬を出す前に、漢方薬という選択肢を考えてみませんか?
◆漢方ビギナーの先生方に贈る、“メンタル漢方”入門書です。
◆抑うつ、不安、不眠、認知症BPSD、身体化障害に使える漢方処方を紹介。生薬の作用を知ることで、処方の意味や使い分けがわかるようになります。
◆軽度の精神症状の初期治療として、向精神薬の補助として、漢方薬を上手に使いこなしましょう!
