
臨牀消化器内科 Vol.34 No.11
2019年10月号
胃癌診療2019-現状と課題
胃癌診療2019-現状と課題
胃癌は,本邦におけるがん対策において,最重要がん種の一つである.しかし,若年者,壮年者におけるH.pylori 感染率の急激な低下に伴い,すでに胃癌罹患数,死亡数は減少に転じている.
胃癌対策においては,高齢者胃癌にいかに対峙し,生活の質をも意識した,さらなる死亡数減少を目指していくかが大きな課題と考えられる.
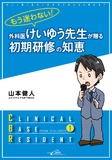
もう迷わない!外科医けいゆう先生が贈る初期研修の知恵
けいゆう先生のペンネームで知られ、SNSやウェブメディアの連載などで活躍中の山本健人先生が、医学生や研修医向けに書き下ろしたのが本書です。編集部の人間が読んでも「なるほど! 」と唸る、さすがの切り口の文章が満載。消化器外科医の日常を通し、「初期研修で学ぶべきこと」が余すことなく伝えられています。これから初期研修を受ける医師にとっては必携の書となるでしょう。本書が贈る「知恵」が初期研修を実りあるものにしてくれると確信しております。
以下、本書「はじめに」より
若手医師が勉強法やキャリアについて情報収集したいと思った時、アクセスできる情報ソースは意外に限られています。インターネットで検索したり、書店に行って本を探したりしても、自分に役立つ情報はなかなか見つけにくいものです。私は、こうした問題意識を常に持ってキャリアを歩む中で、できるだけ多くの後輩に自分の学んだことを伝えたい、と考え続けてきました。 (中略) 確かにここに書いたのは、一介の若手外科医の私見に過ぎないでしょう。しかし私はこの書籍に、これまで自分が医師として、外科医として、毎日頭をひねって考えてきたことの全てを書きました。読んでいただければ、「今すぐにでも実践したい」と思うことがきっとたくさんあると思います。もしそう思ったら、この本を閉じた瞬間から、動き始めてください。あなたのこれからの人生で、今日が一番若い日です。

診断推論 奥義伝授
◆臨床経験を積んでいけば、直感的に診断名がひらめくことは増えていきます。しかし、どうしても分析的・系統的なアプローチが必要な場面もでてきます。非特異的な訴え…なじみのない訴え…複数の箇所に出現している所見…。そんなとき、「どう推論を組み立てて」いけばいいのか?
◆その悩みにお答えします!すでに一般的になっている「診断推論」の弱点を補強、疑問を掘り下げて、野口善令先生が解説していきます!
◆本書では「直感を鍛える」「推論を深化させる」を大きなテーマとしています。無意識で働く「直感」をどう鍛えるのか?その方法も、もちろん紹介しております。ぜひ本書で、一歩進んだ「上級編」の診断推論を始めてください!

食品衛生学 改訂第2版
改正食品衛生法に対応して改訂!食品衛生関連の法律・制度から食中毒・有害物質の科学的な知識までわかりやすく解説!国試対策はもちろん食品衛生監視員・食品衛生管理者養成校の教科書としても役立つ1冊.

関節リウマチ看護ガイドブック
共同意思決定をめざしたトータルケアの実践
病態・診察・治療等の基本知識から,現場を熟知したエキスパートによる実践的ケアのポイントまで,エビデンスにもとづいたRA看護のエッセンスを新書サイズに凝縮.患者さん視点のチーム医療実践に必須の一冊です.

詳述!学べる・使える 水・電解質・酸塩基平衡異常Q&A事典
水電解質・酸塩基平衡異常の臨床に関する発表された“すべての論文・書籍等をすべて知る”,つまり,徹底した先行研究検討を行い,水電解質・酸塩基平衡異常の臨床に関する教科書的とされる知識の正確度について再検討を行っている著者が,腎生理学の解説書と,診断・治療アルゴリズムが主体となっている従来の水電解質・酸塩基平衡異常の臨床の解説書との橋渡しを行うことを目的に執筆。テーマを徹底的に細分化して記述しているため,効率的に必要な情報にアクセスできます。

運動器エコー指南書
運動器のプロフェッショナルに贈るエコー指南書
エコーによる病態の理解と、エコーガイド下注射、ハイドロリリースの手技について詳しく解説しました。
【動画40本収録】
執筆者:
髙橋 周 東あおば整形外科
松崎正史 ソニックジャパン株式会社
服部惣一 亀田メディカルセンター・スポーツ医学科
宮武和馬 横浜市立大学附属病院整形外科
中島祐子 広島大学運動器超音波医学
中瀬順介 金沢大学整形外科
笹原 潤 帝京大学スポーツ医科学センター
林 典雄 運動器機能解剖学研究所
山口睦弘 株式会社ソノジー
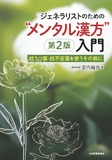
“メンタル漢方”入門 第2版
向精神薬を出す前に、漢方薬という選択肢を考えてみませんか?
◆漢方ビギナーの先生方に贈る、“メンタル漢方”入門書です。
◆抑うつ、不安、不眠、認知症BPSD、身体化障害に使える漢方処方を紹介。生薬の作用を知ることで、処方の意味や使い分けがわかるようになります。
◆軽度の精神症状の初期治療として、向精神薬の補助として、漢方薬を上手に使いこなしましょう!

月刊/保険診療 2019年8月号
特集/医療機関の“心理学&言葉術”~心を読む洞察力,心を動かす表現力~
特集/医療機関の“心理学&言葉術”~心を読む洞察力,心を動かす表現力~
Part1 医療に応用できる心理学入門…心理学にはどのような学説・精神分析法・カウンセリング方法があるか,人の性格や気質はどう分類できるか,心理学を医療現場でいかに応用するか――などについて,その初歩からわかりやすく解説した入門編。
Part2 【座談会】医療機関の“心理学&言葉術”を考える…病院・クリニックの様々な人間関係(患者対医療者,医療者対医療者)において,①特に注意すべき心理構造・言葉表現,②心理学的アプローチによる医療現場・医療機能の最適化ーーを検討する座談会。
Part3 医療現場の“心理学・言葉術”ケーススタディ12…①場面別ケース(受付・会計・診察・病棟・手術等,会議・交渉・教育等),②対人別ケース(患者,上司・同僚・部下,多職種スタッフーーにおいて,その心理分析と言葉表現のメソッドを悪例・好例によるケーススタディで実践的に解説
第50回診療報酬請求事務能力認定試験〔医科〕:問題と解説…7月実施試験の解説・解答。

DELTAプログラムによるせん妄対策
多職種で取り組む予防,対応,情報共有
せん妄!? かもしれないと思ったときのケアで、その後が変わる。DELTAプログラムを用いた、せん妄の早期発見、重症化予防へのケアを解説した実践書

Gノート増刊 Vol.6 No.6
【特集】なめたらアカン風邪診療 あなたのいつもの診療、見られてますよ!
【特集】なめたらアカン風邪診療 あなたのいつもの診療、見られてますよ! “せき・はな・のど”などの病型ごとのアプローチや,風邪に似ているが風邪ではない致死的な“地雷疾患”の見極め方を丁寧に解説.コモンな疾患と侮って足をすくわれないための診かた・考え方が身につく一冊!

看護研究 Vol.52 No.4
2019年08月発行(増刊号)
特集 臨床実践を研究につなげる
特集 臨床実践を研究につなげる -

総合リハビリテーション Vol.47 No.9
2019年09月発行
特集 回復期リハビリテーション病棟退院後の戦略 生活機能の向上をめざして
特集 回復期リハビリテーション病棟退院後の戦略 生活機能の向上をめざして 日本のリハビリテーションの特徴の 1 つとして,比較的長期の入院リハビリテーションにより達成さ れる高い機能・日常生活動作(activities of daily living;ADL)の達成が挙げられます.その一方,回復期 リハビリテーション病院退院後にその機能・ADL を維持することができない,難しいという不安を患者 が感じていることも指摘されています.そこで今回は,回復期リハビリテーション病院退院後に,機能 や能力を高く保つ,もしくは在宅でさらに改善させていくために,入院中から何を行うべきか,外来診 療や在宅サービスとどう連携していくかなどについて,それぞれの立場からご解説いただきました.

日本内視鏡外科学会雑誌 Vol.24 No.5
2019年09月発行
-

肘実践講座 よくわかる野球肘 離断性骨軟骨炎
長年野球肘検診の活動に携わっている徳島大学整形外科グループを中心に野球肘のエキスパートを執筆陣に迎え、『離断性骨軟骨炎』にテーマをあてた待望の一冊!
野球肘検診が国的に広まりを見せている中、検診現場から見た予防・早期発見・治療の重要性を啓発し、離断性骨軟骨炎の歴史、病態論、画像診断、保存治療から手術、早期発見や予防にいたるまで網羅した、医療関係者はもちろん全国の野球指導者、保護者にとっても「よくわかる」充実した内容となっています。

Modern Physician Vol.39 No.9
2019年9月号
【今月のアプローチ】処置・検査のための安全な鎮痛・鎮静管理
【今月のアプローチ】処置・検査のための安全な鎮痛・鎮静管理 2018年に米国麻酔学会が公表したガイドラインに準拠し、各診療科における安全な鎮痛・鎮静管理のポイントを解説。患者への苦痛を減らしより安全な処置・検査へ

最新 糖尿病診療のエビデンス 改訂版
EBM(根拠に基づいた医療)の考え方に基づき、2型糖尿病の薬物治療や生活習慣改善に関する最新の知見を紹介。
EBM(Evidence-Based Medicine)界の若手ホープである著者が、日々の糖尿病診療で生じる臨床的な疑問について、最新のエビデンスと診療ガイドラインをひもときながら、わかりやすく解説します。
『日経メディカル Online』で好評を博した連載(臨床講座)をベースに、初版を2015年に発行。今回は、2019年6月までに発表された大規模臨床試験の結果や新しい糖尿病診断基準、診療ガイドラインの紹介を加え、全面刷新しました。
SGLT2阻害薬やGLP-1受容体作動薬がなぜ今、注目されているのか、包括的なリスク管理はどの程度の意義があるのか、糖質制限の長期的な評価など、臨床現場で役立つ数々のトピックスを、EBMの切り口で明快に解説。
研修医や糖尿病を専門としていない全ての臨床医を中心に、糖尿病診療指導士や看護師、管理栄養士、薬剤師など、糖尿病患者の治療・指導に携わる全ての医療専門職と、製薬会社のMR(医薬情報担当者)を主たる読者対象としています。

フローチャートによるトリアージ実践マニュアル
その時、薬剤師はどのように判断するか
既刊「薬剤師のためのトリアージ実践ガイド」の応用編。 本書は、来局者の病状を適切に把握し、病院を受診したほうがいいのか、あるいはOTC薬(一般薬)によるセルフメディケーションでいいのかを、判断するためのノウハウをわかりやすく解説します。 「どのように思考すれば、患者にフィットするトリアージシステムになるか?」、「いかにして、医師の診断理論を薬剤師用に翻訳するか?」にポイントをおき、「問診と視診で重症度と緊急度を判断する方法」がフローチャートでわかる構成となっています。これからの薬局薬剤師に求められる「患者をみる力」と「トリアージ」の能力を養う実践的マニュアルです。

≪京大人気講義シリーズ≫
健康・医療の情報を読み解く 第2版
健康情報学への招待
京都大学で著者が受け持つ人気講義「健康情報学」を活字化。ビッグデータの時代、あふれる情報との上手な付き合い方とは?疫学やEBMの考え方をもとに、身近な実例の紹介を通じて健康や医療の情報の読み解き方をわかりやすく解説します。 本書の知識を応用すれば、膨大なデータから各種の健康・医療情報を適切に利用し、意思決定や問題解決、コミュニケーションに役立てることができるようになります。

臨床放射線 Vol.64 No.4
2019年4月臨時増刊号
【特集】乳癌の診断と治療
【特集】乳癌の診断と治療 診断編では各モダリティの読影ポイントを詳説し,治療編では化学療法から外科療法,放射線療法まで解説!超音波画像などはWEB動画とも連動!
