
≪サイエンス・パレット 26≫
サイエンス・パレット026 幹細胞と再生医療
この分野で日本をリードしてきた著者が、多能性幹細胞の特徴、倫理問題の本質、世界の状況、そして治療や創薬への応用について、いま私たちに必要な知識を提供します。基礎研究で得られた知見を実際の治療につなげるにはどのような技術やプロセスが必要か、実用化への道筋がわかるのが本書の特長です。
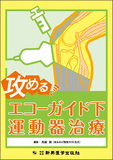
攻める!エコーガイド下運動器治療
令和の時代は「まず、レントゲン」から「まず、エコー」へ!
運動器疾患は骨以外に主病変がある場合が圧倒的に多く、単純X線写真では診断できないために、初期に適切な処置がなされず放置されてきた。しかし、エコーを用いることで、運動器構成体をリアルタイムで観察することができ、かつその場で精度の高い治療を行うことができる。本書では、必要な走査技術、エコーガイド下注射のコツや注意点を運動器疾患ごとに分けて解説した。目の前にいる患者さんが訴える痛みに対し、的確で積極的な「攻め」のアプローチができ、治療効果が飛躍的に向上する!
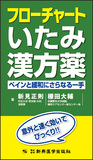
ペインと緩和にさらなる一手
フローチャートいたみ漢方薬
これからの時代は二刀流! 漢方を上手につかいこなして患者満足度をアップしよう!
デジタル化できない痛みの訴えに漢方がマッチ! 判然としない痛みに困ったとき、漢方薬が役に立ちます。最初から当てようと思わずに患者さんと一緒に順次試してみましょう。困ったときにすぐ処方できる本シリーズで、漢方処方を今すぐスタートしよう。

症例検討で身につける
脳卒中の理学療法
エキスパートPTによる20症例の臨床推論と効果的なリハプログラム
代表的な20症例を厳選し,急性期,回復期,生活期に分けて解説.症例報告の形で各期ごとに重要な病態・症状,介入方法や結果がまとめられ,エキスパートPTの理学療法が学べる.臨床力を伸ばす74の能力養成問題付き!

実験医学増刊 Vol.37 No.12
【特集】ミトコンドリアと疾患・老化
【特集】ミトコンドリアと疾患・老化 真核細胞の中で、融合と分裂を繰り返しながら妖しく動くミトコンドリア。エネルギー工場としての役割を超え、細胞高次機能のプラットフォームとして次々と明らかになる側面と、その破綻による疾患をご紹介します。

臨牀消化器内科 Vol.34 No.10
2019年9月号
消化器ステント留置
消化器ステント留置
消化器のステント治療が進歩・普及している.消化器の広い領域で,悪性疾患・良性疾患に対してステント留置が行われている.ステントは狭窄・閉塞の解除だけではなく,瘻孔閉鎖や内腔減圧の目的にも用いられる.

整形・災害外科 Vol.59 No.6
2016年5月臨時増刊号
【特集】スポーツ整形外科 最新の治療
【特集】スポーツ整形外科 最新の治療 臨床医に必要な脊椎・脊髄疾患の基礎的知識から最新知識まで広く網羅

整形・災害外科 Vol.60 No.5
2017年4月臨時増刊号
【特集】脊椎・脊髄疾患のニューロサイエンス
【特集】脊椎・脊髄疾患のニューロサイエンス スポーツ整形外科の最新情報をアップデート

整形・災害外科 Vol.62 No.5
2019年4月臨時増刊号
【特集】脊椎脊髄外科の最近の進歩
【特集】脊椎脊髄外科の最近の進歩 最新の治療法をわかりやすく紹介!

がん看護 Vol.24 No.7
2019年9-10月
いま必要ながん看護
いま必要ながん看護 がんの医学・医療的知識から経過別看護、症状別看護、検査・治療・処置別看護、さらにはサイコオンコロジーにいたるまで、臨床に役立つさまざまなテーマをわかりやすく解説し、最新の知見を提供。施設内看護から訪問・在宅・地域看護まで、看護の場と領域に特有な問題をとりあげ、検討・解説。告知、インフォームド・コンセント、生命倫理、グリーフワークといった、患者・家族をとりまく今日の諸課題についても積極的にアプローチし、問題の深化をはかるべく、意見交流の場としての役割も果たす。

抗てんかん薬TDM標準化ガイドライン 2018
抗てんかん薬の効果と副作用の発現には個人差が大きい。そのため、日常臨床における治療薬物モニタリング(TDM)が投与計画を決定するうえで重要な手段となり、各種抗てんかん薬の薬物動態に基づいたTDMを行う必要がある。本書では11種類の抗てんかん薬について、TDMの標準的な手法が薬剤別にまとめられた。TDMに携わる薬剤師や臨床検査技師、TDMをオーダーする医師必携のガイドラインである。

保健師ジャーナル Vol.75 No.9
2019年09月発行
特集 若年性認知症者と家族の理解と支援
特集 若年性認知症者と家族の理解と支援 若年性認知症には,家庭内の経済的な問題や家族関係の再構築,多重介護,相談・支援体制の未整備など,高齢者の認知症とは異なる課題がある。改正社会福祉法では包括的支援体制の構築を市町村の努力義務としているが,これらの課題を抱える若年性認知症者とその家族に対する支援が十分に進んでいるとは言えない。本特集では,疫学調査や先進的な取り組みからその現状を紹介し,支援や共生の糸口を探る。

理学療法ジャーナル Vol.53 No.9
2019年09月発行
特集 栄養を学ぶ 学際と実際
特集 栄養を学ぶ 学際と実際 管理栄養士でもないのになぜ理学療法士が栄養のことを知らねばならないのだろうか.知らなければならないとしても,何をどこまで理解しておかなければならないのか.近年,栄養と理学療法の関係が注目されるなかで,新たな「理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則」では,栄養学の基礎が必修化され,すべての理学療法士が栄養学を学ぶ必要性が示された.本号では特に栄養学の周辺学問領域についても理解を深め,養成学で栄養学を学んでいない理学療法士でも本特集を読むことによって,より効果的な理学療法を実践できるようになることを期待して企画した.

臨床皮膚科 Vol.73 No.9
2019年08月発行
-

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 Vol.91 No.10
2019年09月発行
特集 嚥下障害を診る! プロに学ぶ実践スキル
特集 嚥下障害を診る! プロに学ぶ実践スキル -

臨床眼科 Vol.73 No.9
2019年09月発行
特集 第72回 日本臨床眼科学会講演集[7]
特集 第72回 日本臨床眼科学会講演集[7] -

臨床外科 Vol.74 No.9
2019年09月発行
特集 膵・消化管神経内分泌腫瘍 診断・治療の基本と最新動向〔特別付録Web動画付き〕
特集 膵・消化管神経内分泌腫瘍 診断・治療の基本と最新動向〔特別付録Web動画付き〕 本誌で前回,膵・消化管神経内分泌腫瘍についての特集企画を掲載したのは2015年4月号であったが,この4年間でこの疾患に対する社会的認知度が急上昇し,病態に対する理解が深まってきた.2015年に診療ガイドラインの第1版が出版され,WHO分類は2017年に膵NETの新分類が発表され,2019年に消化管NETの新分類が発表された.略称も,高分化の腫瘍(NET)と低分化の癌(NEC)を合わせてNENと呼称されるようになっている.また,診療ガイドラインの第2版も2019年に出版される予定であり,本領域への期待が高まっている.これらの流れを踏まえ,本特集では,膵・消化管神経内分泌腫瘍について,基本事項をおさえるとともに,この数年の変化,最新の動向をエキスパートの執筆者にご解説いただいた.

精神医学 Vol.61 No.8
2019年08月発行
特集 光と精神医学
特集 光と精神医学 -

胃と腸 Vol.54 No.9
2019年08月発行
主題 消化管X線造影検査のすべて 撮影手技の実際と読影のポイント
主題 消化管X線造影検査のすべて 撮影手技の実際と読影のポイント -

公衆衛生 Vol.83 No.9
2019年09月発行
特集 ヘルスサービスリサーチ サービスの効率と質の向上へ
特集 ヘルスサービスリサーチ サービスの効率と質の向上へ -
