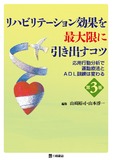
リハビリテーション効果を最大限に引き出すコツ 第3版
応用行動分析で運動療法とADL訓練は変わる!
質の高いリハを提供したいなら ! 遭遇率の高い症例や困難事例にこそ、応用行動分析学を ! 改善事例を豊富に掲載 !
4刷りを重ねた好評本の第3版。大きな改訂点としては、読者に関心が高い応用行動分析を用いた事例集の章を大幅に差し替え、現場で遭遇することの多い重度片麻痺症例や高次脳機能障害における効果事例、さらに難渋することの多い重度認知症例を多く掲載している。
また応用行動分析学をリハに取り入れるうえで欠かせない筋力や関節可動域、バランス能力等の基準値や筋肉トレーニングの効果についてのデータ等、最新の研究報告を追加した。筆者らが積み上げてきた応用行動分析学を応用したリハビリ効果事例を、明日からの現場にぜひ役立ててほしい。

力学で読み解くからだの動き
動作理解のための基礎バイオメカニクス
基礎バイオメカニクスの教科書としても、自習書としても最適な入門書
本書は、バイオメカニクスや運動制御の専門書・専門雑誌を理解できるレベルに達することおよび臨床で役立つ基礎バイオメカニクスの知識を身に付けることを意図した入門書です。
力学的理解を段階的に進めるために、次の学習段階に進むための道筋を示しているので、力をイメージすることからはじめて、静力学の考え方、力を含めない運動解析法(キネマティクス)、直線運動の動力学、流体力学、回転運動の動力学、多関節運動の動力学へと、スモールステップで段階的に学ぶことができます。
教科書としても、自習書としても使えるよう、一つひとつの事柄を、数式だけでなく、わかりやすい図と言葉で丁寧に説明しています。
本文の内容を理解しやすくする数学的な基礎事項を説明した「付録」付き。

スポーツ傷害 予防と治療のための体幹モーターコントロール
体幹筋機能の向上は、スポーツおける障害予防や、治療時のリハビリテーションに非常に有効であるとされ、近年高い注目を浴びている。
本書は、その体幹機能のなかでも腰椎や四肢の活動において重要な機能を果たすモーターコントロール機能に着目し、その向上を図るための様々なエクササイズやトレーニングを医学的な根拠(エビデンス)に基づいて行うための具体的な方法を写真や豊富な図表を用いてわかりやすく解説している。

日めくり麻酔科エビデンスアップデート2
~1日1つ,3カ月で100の知見を得る~

産科医のための無痛分娩講座

Modern Physician Vol.39 No.8
2019年8月号
【今月のアプローチ】読むと得する!アレルギー診療の重要トリビア
【今月のアプローチ】読むと得する!アレルギー診療の重要トリビア 治療がうまくいかないとき、このトリビアが役に立ちます。全身的・全人生的なトータル・アプローチを行うための知恵がワンランク上のアレルギー診療を可能にします。
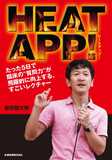
HEATAPP!
たった5日で臨床の“質問力”が飛躍的に向上する、すごいレクチャー
2017年5月.神戸大学医学部4年生に行われた感染症チュートリアル5日間は、学生たちにとって、想定外の展開をみせることになる。講師の岩田健太郎氏は「医療に必要なのは質問に答える能力ではなく、問いを立てる力である」と説く。よい質問の仕方とは、本質の問題解決とは何か。インタラクティブに行われるレクチャーのなかで、その臨床マインドは長足の進歩を遂げる。5日間:全22セッション、至極の名講義がいま甦る!

≪YORi-SOU がんナーシング2019年別冊≫
改訂2版 がん疼痛治療の薬-オピオイド鎮痛薬・非オピオイド鎮痛薬・鎮痛補助薬・オピオイドの副作用対症療法薬-はや調べノート
【がん疼痛治療薬の最新情報をピックアップ!】
がん疼痛治療の柱である「オピオイド鎮痛薬」「非オピオイド鎮痛薬」「鎮痛補助薬」「オピオイドによる副作用の対症療法薬」の最新情報がこの1冊に!使いやすいと大好評のミニブックは、最低限押さえておきたい内容に絞って薬の特徴が載っており、患者説明などにすぐに使える内容になっている。

保険審査委員による “保険診療&請求”ガイドライン
電子カルテ&レセプト──最適化のための26章
★「保険診療」のルールとその範囲,「保険審査」「指導」の実際,「診療報酬点数表」の構造──を明快に解説。類書にありがちな概論や法規の羅列ではなく,「保険診療&請求」のノウハウを個別具体的な診療・請求事例で実践的に解説した“ガイドライン”全26章‼
★実際の診療・請求事例ごとに保険審査・指導のポイント──なぜ査定減点・指導されるのか,何をどう改めればよいのか──を具体的に解説。点数表だけでは判断のつかないポイントも,確かな医学的根拠や実際の審査規定に基づいて明快な解釈を示しています。
★支払基金医療顧問(保険審査委員)を務め,医療現場と審査・指導現場を熟知した著者が,実際に保険審査に関わってきた経験知と医学・法制度のエビデンスに基づいて書き下ろした,日本で唯一の実践的な「保険診療ガイドライン」と呼べる,稀有にして貴重なる1冊‼
★医師や看護師のための「保険診療入門書」として,医事部門のための「保険請求マニュアル」として,医療機関の全スタッフに必須の1冊。医師研修,医事研修,看護師研修等のテキストとしても最適です‼
【CONTENTS】
【総論:保険診療の基本】(第1章~第5章)
国民皆保険制度は医療者のためになっているか?/新時代の診療体系/電子カルテとレセプトの連動は療担規則に従順か?/レセ審査をパスするために保険医はどんな点に注意すべきか?/審査機関と厚生局の関係と指導のポイント
【各論:保険請求の項目別留意点】(第6章~第25章)
初・再診料/入院基本料・特定入院料/DPC/医学管理料/在宅/検体検査/生体検査/画像診断/投薬/注射/リハビリテーション/精神科専門療法/処置/手術/輸血/麻酔/病理診断/放射線治療/老健施設入所者診療料/不定愁訴と検査

≪シリーズ生命倫理学 10≫
救急医療
救急医療においては、一般医療と比較して患者、医療者の双方に、時間的にも精神的にも余裕のない状況にあることが多く、現場では、専門診療科だけではなく、診療科各職種の協業とさまざまなスタッフによるチーム医療が要となります。 本巻では、さまざまな状況下で短時間に適切な医療が求められる救急医療について、現場の観点からその特徴、倫理的な視点、考え方を解説しています。

≪シリーズ生命倫理学 9≫
精神科医療
精神医学分野が伝統的に倫理問題への関心が薄かったといわれる理由、また精神医学の濫用の実例として、ナチス・ドイツや旧ソビエト連邦の歴史とともに、現代の精神科医療が直面する多様な倫理的課題などを取り上げ、日本の一般精神科医療の現状を、臨床と研究におけるインフォームド・コンセントと守秘義務、強制治療と人権、最新の神経科学を応用した治療の可能性と限界といった多方面から提示し、専門家への実践的指針ばかりでなく一般読者にも資する内容を目指した。さまざまな論者の観点から今後の精神科医療の在り方を提示する。

≪シリーズ生命倫理学 8≫
高齢者・難病患者・障害者の医療福祉
本巻「シリーズ生命倫理学 第8巻 高齢者・難病患者・障害者の医療福祉」では、高齢者や障害者といった社会福祉で大きなテーマとなる分野を扱います。医療が「治す」ことを目標にするなら、高齢者や障害者はその対象から外れていきかねません。高齢ゆえの衰えにはもはや「治せない」部分が多いし、障害は「根治はできないから長く付き合って飼いならしていく」という宿命を背負うものと言えます。難病とて、「治し難い」から難病と呼ばれるのであって、その実態は障害に近く、ここでは、「治す」医療ばかりではなく、「機能を維持する、機能低下の速度を遅くする、代替手段を見つけてそれを使いやすくする」医療が求められます。そしてその医療は、限られた健康状態でも心健やかに暮らすための福祉的支援と連携するものとなるでしょう。本巻では、このように「高齢者・難病患者・障害者」に関しては、「医療」単独ではなく「医療福祉」という統合的な問題意識で生命倫理的な議論も深めていく必要があるという立場から論じてゆきます。

≪シリーズ生命倫理学 7≫
周産期・新生児・小児医療
本巻「シリーズ生命倫理学 第7巻 周産期・新生児・小児医療」では、妊婦、胎児から、新生児、小児にいたる患者への倫理的問題を医学、法学、倫理学の面から解説します。 周産期医療・新生児医療・小児医療における倫理的特徴を医学的側面・法的側面から解説し、出生前診断や胎児治療、予後不良児への対応の倫理的考察から児童虐待や障害児へのサポート等の問題までを考察します。

12人のクライエントが教えてくれる作業療法をするうえで大切なこと
たくさんの気づきや教訓がつまった、何度も読み返したくなる本
『作業療法ジャーナル』に連載の人気コラム「ひとをおもう」を加筆、書籍化。
本書では、筆者らが過去に経験したクライエントとのエピソードをコラムとして掲載し、一つひとつのエピソードを通して得た気づきや学びについて解説。
紹介する12のエピソードは臨床家の作業療法士が、臨床場面で必ずや遭遇する出来事を厳選。
本書は、作業療法士が過去に経験したエピソードや今後経験するエピソードを言語化し、クライエントとの相互交流の中で選択・調整される実践の一助となるであろう。

月刊/保険診療 2019年6月号
特集 経験知の“銀行”――事務長の仕事術~事務長24時間365日の全メソッド~
特集 経験知の“銀行”――事務長の仕事術~事務長24時間365日の全メソッド~ Part1 事務長の仕事24時間365日…病院・クリニックの組織運営を取り仕切る事務長という仕事のノウハウとディテールを,事務長界の第一人者2人に取材して紹介します。
Part2 【座談会】10年後に向けた医療機関改革の戦略構想…数々の院内改革を成功させてきた4人の改革派事務長が,①これまでどのように改革してきたか,②今後の自院の戦略とビジョンをどう構築していくか――について多角的に検討する“戦略会議”。
Part3 医療機関改革の“経験知”――7人の事務長に聞く…全国の病院・クリニックで着実に実績を上げてきた実力派事務長7人に,①自身の仕事術,②院内改革の経験知(成功体験・失敗体験),③現在から10年後に向けた課題と解決策――等の話を聞きます。
■■■連載■■■
厚生関連資料/審査機関統計資料
月間NEWSダイジェスト
介護保険/医学・臨床/医療事故NEWS
めーるBOX
■エッセイ・評論
NEWS縦断「医療機関への訪日外国人受入れ」/武藤正樹
こうして医療機関を変えてきた!「地方極小病院と公立病院改革の波」/大野毎子
プロの先読み・深読み・裏読みの技術「救急搬送入院増と看護必要度」/工藤高
医療界の不都合な真実「医療の公共性は? 都立病院独法化を考える」/本田宏
大人なのに走る「第16話 誰がために仕事する」/大佐戸達也
■医事・法制度・経営管理
病院&クリニック経営100問100答「クリニック経営を向上させるデータ活用術」/小松大介
医療事務Openフォーラム「人事制度評価入力アプリケーションの開発と活用」/森孝之
医事課にお邪魔/公立昭和病院
■臨床知識
カルテ・レセプトの原風景【せん妄】原因不明の意識の消失と混濁/鹿島健,武田匤弘
■請求事務
実践DPC請求Navi/須貝和則
パーフェクト・レセプトの探求/株式会社ソラスト・坂井田晃
レセプト点検の“名探偵”/野中義哲
点数算定実践講座/圓山研介(協力:青木俊之)
保険診療オールラウンドQA
読者相談室/杉本恵申
休載:ことば座

現場で使う!! 熱中症ポケットマニュアル
本邦初の「熱中症」ポケットマニュアル.
前半部分は,介護施設の職員,学校関係者・教師,マスコミ関係者,スポーツコーチ,種々の安全管理担当者などの医療従事者以外でも活用できるチェックリストとなっており,熱中症に関する基本的な知識や重要事項,知っておかねばならないポイントが一目でわかる.
後半部分は,各チェックリストに対応した解説パートとなっており,チェックリストの根拠や熱中症の疫学,メカニズムなどを学ぶことができる.

医療者のための熱中症対策Q&A
熱中症はどうして起こる?
乳幼児や高齢者に必要な対策は?
屋外活動や運動を制限する基準はあるの?
もはや日本の「国民病」とも言える熱中症
2018年の猛暑を踏まえ、現場で迷う対応の疑問に専門家が答えます!
◆熱中症が起こるメカニズムや患者の年代・シチュエーション別の対策、予防・治療・予後の管理方法、持病を持つ患者さんへの対応、リスク管理など、熱中症対策の要点を各領域の専門家がエビデンスをもって解説します。医療者が必要とする診療情報に加え、患者さんの正しい理解を促す予防指導・情報発信にも役立つ内容を多数盛り込みました。
◆「熱中症はなぜ起こるのか?」「どんな危険があるのか?」といった基礎的な知識から、「高齢者施設で注意する点は?」「学校の屋外行事を中止する基準は?」「熱中症は労災になるのか?」など個別具体的な状況への対応まで、場面ごとに必要な対策とその根拠となる考え方をQ&A形式で解説しています。
◆2020年に国内で開催されるオリンピックなど大規模なスポーツイベントも念頭に、スポーツ分野では競技別の特徴や学校での部活動、あるいは観戦時のリスク、大会やイベント開催に伴う注意点など、熱中症とスポーツの関わりについても解説しています。
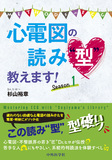
心電図の読み“型”教えます! Season 1
ケアネットの人気web連載「Dr.ヒロのドキドキ心電図マスター」待望の書籍化.
ライトで明快な語り口はそのままに,大幅に加筆し書籍としても読み応えのある1冊に仕上がった.
何度も心電図の壁にぶつかりながらも,己の力で超えてきた著者だからこそ見いだせた,系統的な心電図判読法を伝授.
既存の心電図教育に一石を投じるこの型破りな読み“型”は,壁を超えるための強大な武器となる.挫折を繰り返した人にこそ,おすすめしたい一冊.

≪Crosslink 理学療法学テキスト≫
地域理学療法学
理学療法学専門科目に対応し,講義・実習・臨床まで広く長く活用できる新テキスト。
各巻は,単なる丸暗記するための知識ではなく,なぜその評価法・治療法を選ぶのか,もしくは選んではいけないのか(禁忌)など根拠を示しながら,臨床につなげられるよう具体的に解説。平易な表現を用いながらも詳しく記述した本文と,図表を多用した紙面で理解しやすい構成となっている。
各見出しごとに「POINT」を設けて重要事項をまとめ,どこに重点を置いて学習すべきか,一目でわかるようになっている。また,さまざまな角度からの情報を盛り込んだ囲み記事も充実。巻末には症例検討や実習で役立つ「症例集」をまとめて掲載し,国家試験合格を最終目標とするだけでなく,臨床実習やその先の臨床の場でも活用できるつくりとなっている。
本巻「地域理学療法学」では,総論で地域理学療法の特徴や基礎知識について記載し,各論で地域理学療法の実際,個別支援の技術,地域づくりの技術について解説している。

歩行再建
歩行の理解とトレーニング
臨床が変わる ! 歩行のリハビリテーション決定版 !
歩行障害のある人を目の前にしたとき、多くの場合、一番に目が向くのは機能障害だろう。
機能改善を目的に、多くは関節拘縮や筋力低下に対する関節可動域改善や筋力トレーニングを実施するだろう。
これらのトレーニングの目的は、歩行の異常を生じさせる原因を改善することにある。
しかし、これらはあくまで二次的な機能障害であり、活動制限の主体である歩行そのものを対象としている介入ではない。歩行運動を改善するためには、「どのように歩くべきか」という歩き方そのものを指導する再教育が重要になる。そのためには、歩行とは「どのような運動であるか?」を熟知していなければ、効果的なトレーニングを提示することは困難である。
本書では、歩行運動の意味やトレーニング手段を力学的背景と制御の考えに基づき、多数のビジュアルを用いて詳細に解説。さらに、歩行再建のための次世代技術として注目されているロボットを利用したトレーニングについても紹介。
歩行の疑問をすっきり解決する1冊 !
